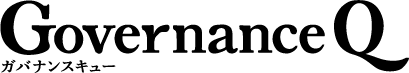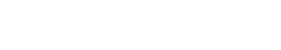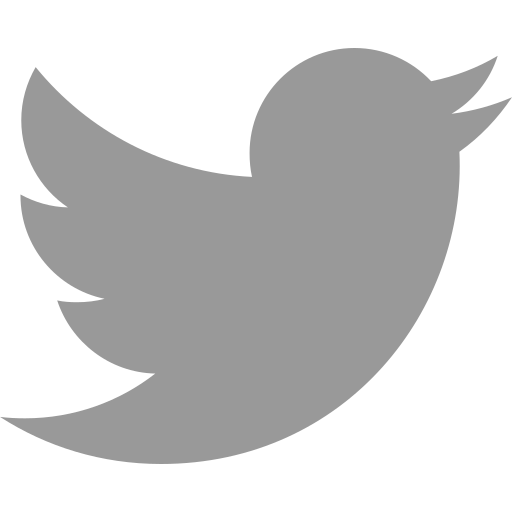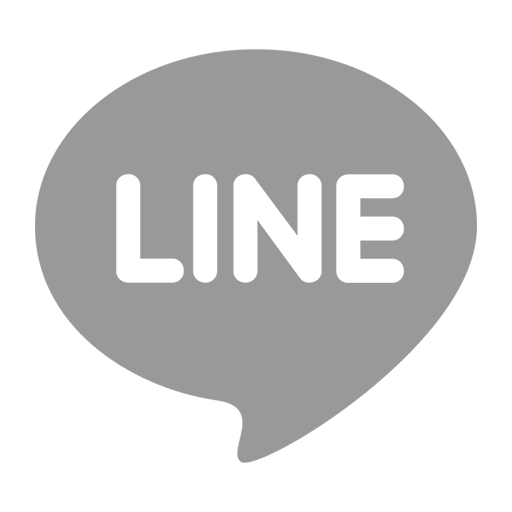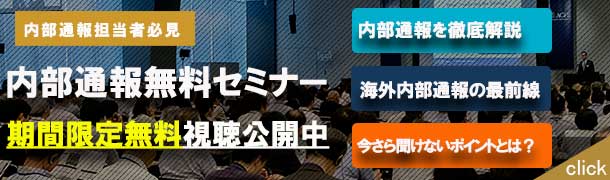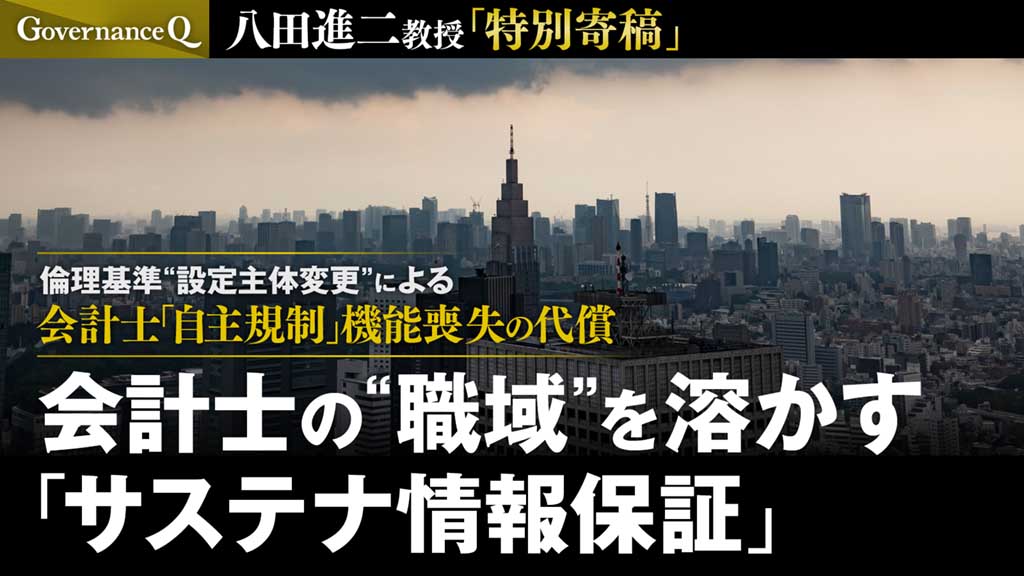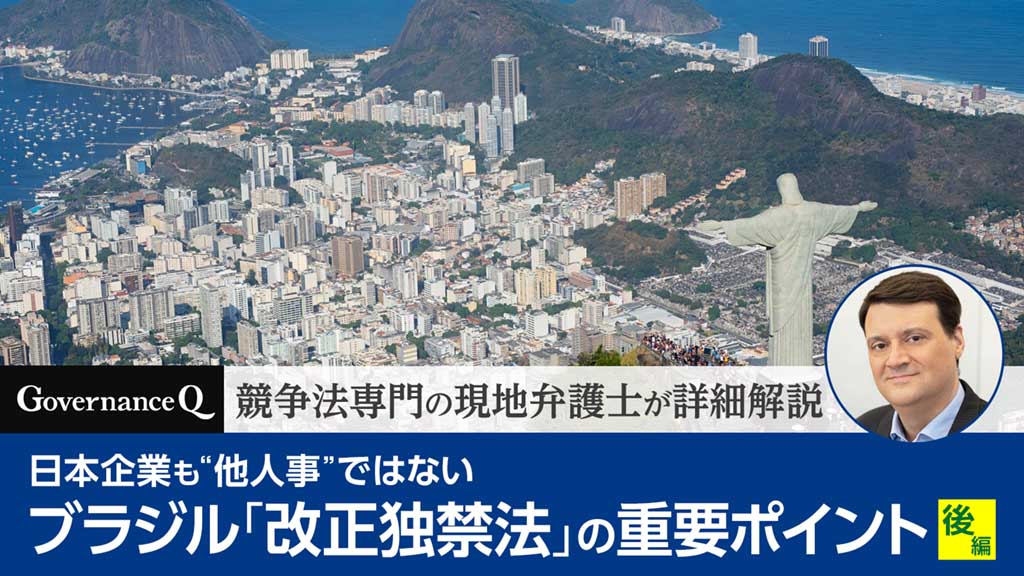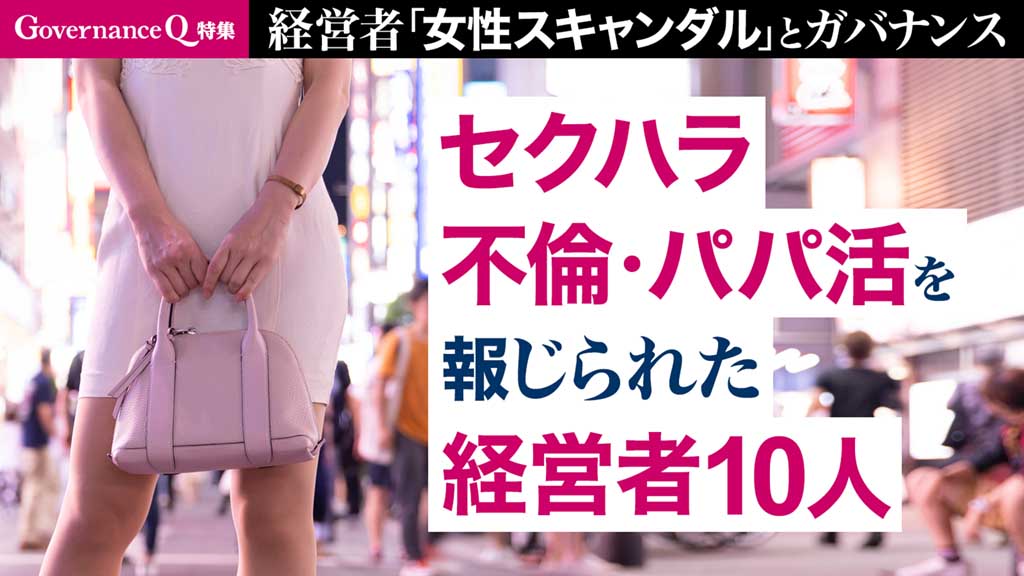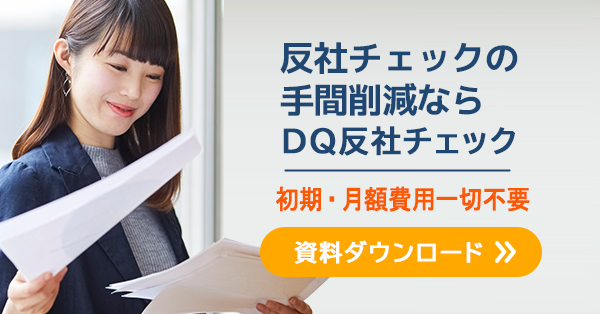第9回【冨山和彦×八田進二#1】企業の新陳代謝を拒んだ日本の「失われた30年」

八田進二・青山学院大学名誉教授が各界の注目人物と「ガバナンス」をテーマに縦横無尽に語り合う大型対談企画。シリーズ第9回目のゲストは、日本共創プラットフォーム(JPiX)社長の冨山和彦氏。金融再生プログラムの一環として、政府肝いりで立ち上げられた産業再生機構でCOO(最高執行責任者)に就任、機構解散後は経営共創基盤(IGPI)を創業し、多くの企業再生支援やベンチャー企業投資を手掛けている。一方、複数の企業で社外取締役を務め、昨年2022年には日本取締役協会会長にも就任。さらには金融庁・東証の「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」委員も務めるなど、日本のガバナンスをリードしてきた。そんな冨山氏が考えるガバナンス論とは――。
決して“特殊事例”ではなかったカネボウ事件
八田進二 冨山さんと言えば、何と言っても産業再生機構です。1990年代末期の金融危機で、日本の信用秩序が壊滅的な打撃を受け、企業倒産が相次ぐ中、官製ファンドの再生機構が誕生したのが2003年。今から20年前です。冨山さんは設立から関わられたわけですが、手掛けられた案件の中で最も印象深い案件は何でしょうか。
冨山和彦 やはり、カネボウですね。カネボウは当時相次いで破綻した日本企業の象徴だと思うんです。
八田 巨額の粉飾が発覚して監査を担当していた中央青山監査法人が解散に追い込まれ、「日本版エンロン事件」と言われました。再生機構はカネボウには途中から関与したんでしたね?
冨山 そうです。当初は花王に化粧品事業を譲渡することで再建を図ろうとしましたが、労働組合の反対で頓挫してしまい、我々にデューデリジェンスの依頼が来たというのがとっかかりでした。
「よくもまあ、あそこまでいろいろやったな」というのが第一印象。不正会計的な行為は10年以上にわたって行われていて、手口も多岐にわたっていて。事業の実態として帳尻が合わなくなっているので、とりあえず会社として存続できるように帳簿をいじっている。あんな操作を長期間続けることができたということ自体が異常です。
八田 金融機関もあの決算書で資金を貸していたわけですよね?
冨山 半分、目を瞑っていたというのが実態でしょう。一言で言えば、ガバナンスが全く機能してない。役員以下、従業員も銀行も、みんな共犯者になってましたね。
八田 カネボウの粉飾が発覚した当時、財界人たちは口をそろえて「あれは特殊な事例だ」と盛んに言っていましたね。
冨山 ええ。あのときはすべて長年トップに君臨していた伊藤淳二さん(元社長・会長、日本航空元会長)一人の責任みたいに説明する人が結構いたのですが、全然そんなことはなかった。中身を調べれば調べるほど、彼に帰着するものがあまりなくて、“ムラ”の調和を最優先する空気が社内を支配していたことが分かりました。
「何でこんな事業やめないのか?」「何でこんな間違った意思決定しているのか?」などと追及してくと、別に誰が命令しているわけでもなく、何となく決まっていっている。理詰めで考えたら結論は明白なのに、声を上げてムラ社会の調和を乱すようなヤツはとにかく排除する。その意味では見て見ぬフリをした金融機関や監査をやっていた会計士も共犯だと思いましたね。カネボウは財界の人たちが言うような「特殊な事例」じゃなくて、ムラ社会的な空気が社内を支配し、調和を乱す者を排除するから正しい判断ができないという点では、日本企業に共通していると言えるでしょう。
八田 そうですね。1990年代末期の金融危機の時は、ある日、金融機関が突然死のごとく破綻したように見えても、実際には突然でも何でもなくて、病巣の進行を察知しなければいけなかった監査がほとんど機能していなかったということなんですよね。監査法人は共犯とまでは言わないまでも完全に同胞であり、われわれ会計および監査論学者も、当時の会計監査のあり方について適切に意見を言っていたかという点については忸怩たる思いがあります。
冨山 消極的に幇助したというような感じですか。
八田 そうかもしれません。ただ、当時は監査法人にも日本公認会計士協会にもさほど危機感はなく、財界と同様、カネボウはレアケースだと捉えていました。ただ、アメリカでは2001年暮れにエンロン、翌2002年7月にワールドコムが破綻して、同月中にSOX法(企業改革法)が制定されます。それを受けて日本でも内部統制の議論が始まり、2006年に誕生する金融商品取引法に内部統制報告制度が盛り込まれるわけですが、カネボウの粉飾事件はその内部統制の議論をやっている真っ只中で発覚したというのに、ですよ。

ピックアップ
-
 【会計士「自主規制」機能喪失#2】監督当局の手に落ちた”会計プロフェッション”の倫理基準…
【会計士「自主規制」機能喪失#2】監督当局の手に落ちた”会計プロフェッション”の倫理基準…(#1から続く)会計士を“閉鎖的社会における専門家集団”のように扱い、プロフェッションとしての自主規制を有名無実化させようとする国際会計士倫…
-
 【会計士「自主規制」機能喪失#1】会計士の“職域”を溶かす「サステナ情報保証」という外圧…
【会計士「自主規制」機能喪失#1】会計士の“職域”を溶かす「サステナ情報保証」という外圧…《過度な節税指南に待った 会計士倫理の国際組織が新基準 議長「企業の評判にリスク」》――。日本経済新聞(6月27日付朝刊)にこんなタイトルの…
-
 ブラジル「改正独禁法」解説《後編》現地弁護士が教える改正のポイント…
ブラジル「改正独禁法」解説《後編》現地弁護士が教える改正のポイント…レオポルド・パゴット(Leopoldo Pagotto):弁護士(ブラジル在住) (前編から続く)ブラジルにおける競争法の最新事情について、…
-
 【経営者と女性スキャンダル#5】醜聞が明るみに出た“マル恥”企業トップ10人…
【経営者と女性スキャンダル#5】醜聞が明るみに出た“マル恥”企業トップ10人…(特集#1、#2、#3、#4から続く)「愛人を持つことは男の甲斐性」などと言われた時代もあったようだが、いまやそれは大昔の話。「コーポレート…
-
 今さらの「政策保有株削減」に経営改革は期待できるか【ガバナンス時評#19】…
今さらの「政策保有株削減」に経営改革は期待できるか【ガバナンス時評#19】…八田進二:青山学院大学名誉教授 3月末までに開示された東証プライム上場企業のコーポレートガバナンス報告書を集計したあずさ監査法人によると、プ…
-
 ブラジル「改正独禁法」解説《前編》現地弁護士が教える改正のポイント…
ブラジル「改正独禁法」解説《前編》現地弁護士が教える改正のポイント…レオポルド・パゴット(Leopoldo Pagotto):弁護士(ブラジル在住) 今回は、ブラジルにおける競争法の最新事情をお伝えしたい。著…