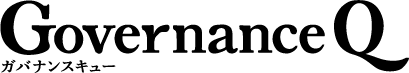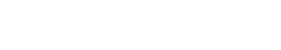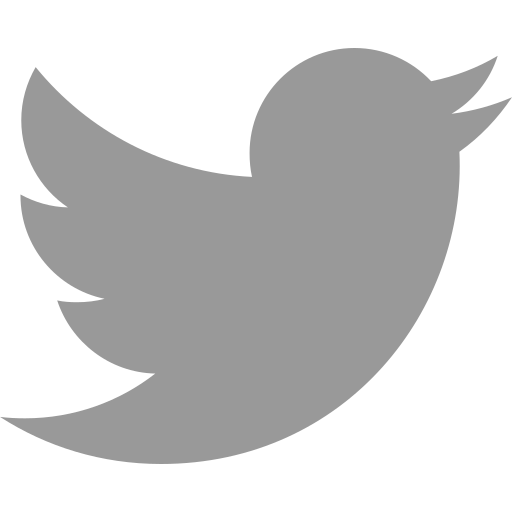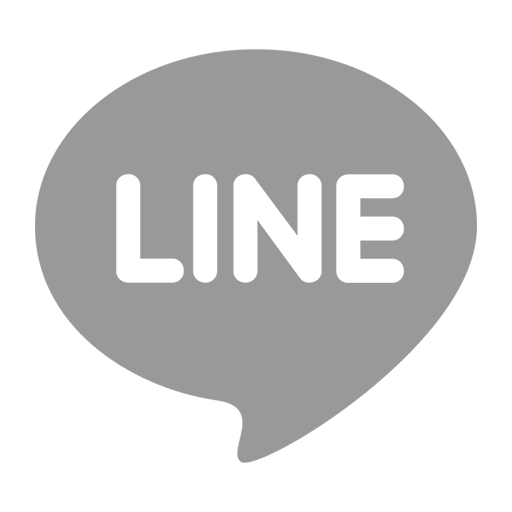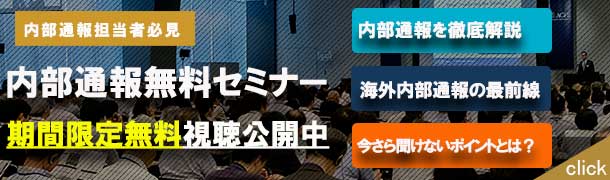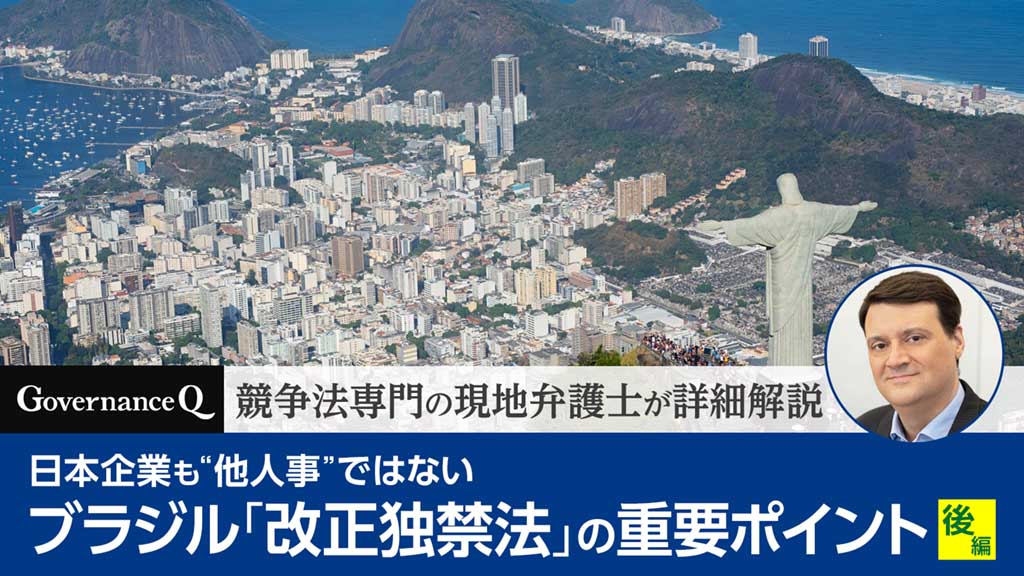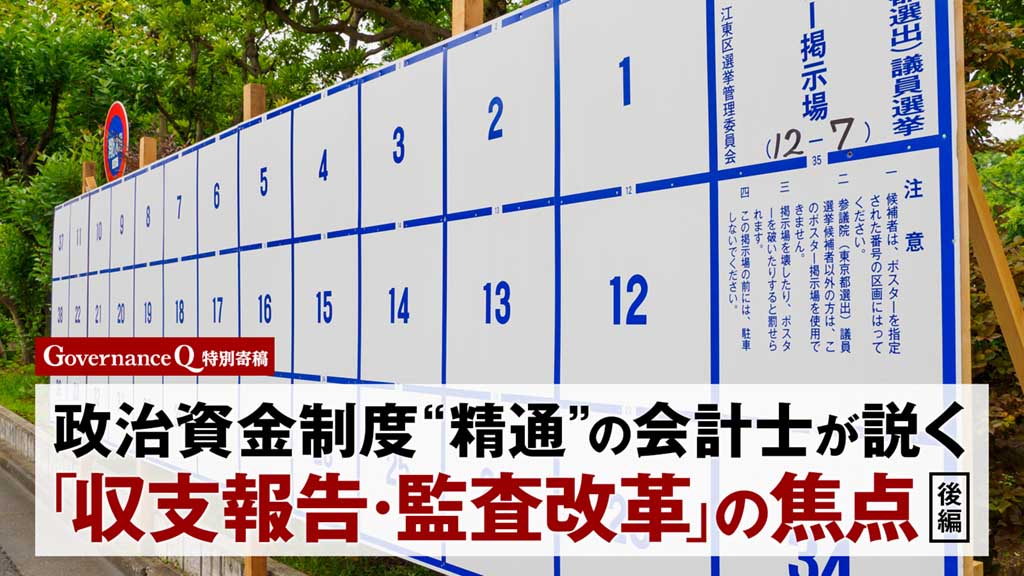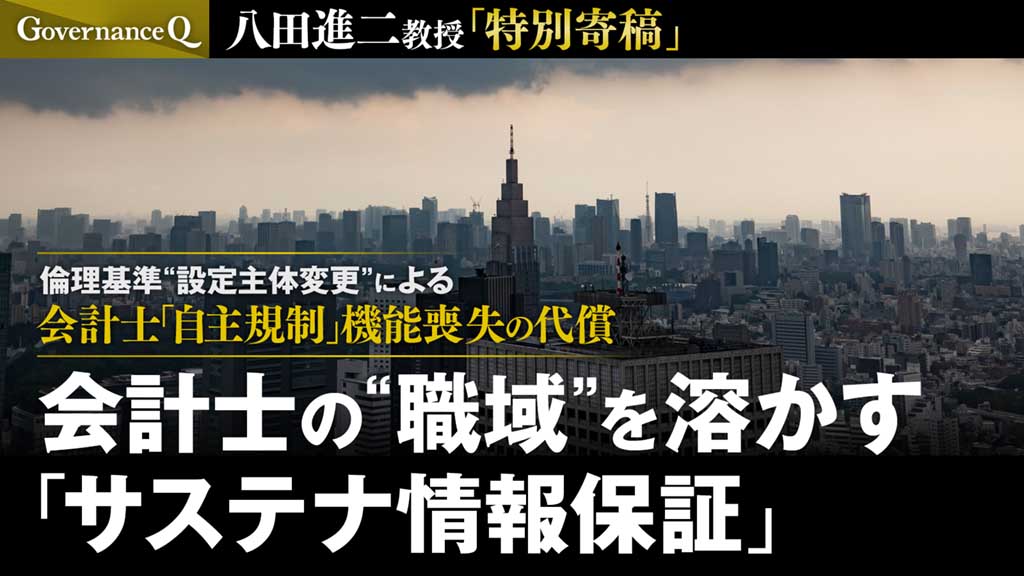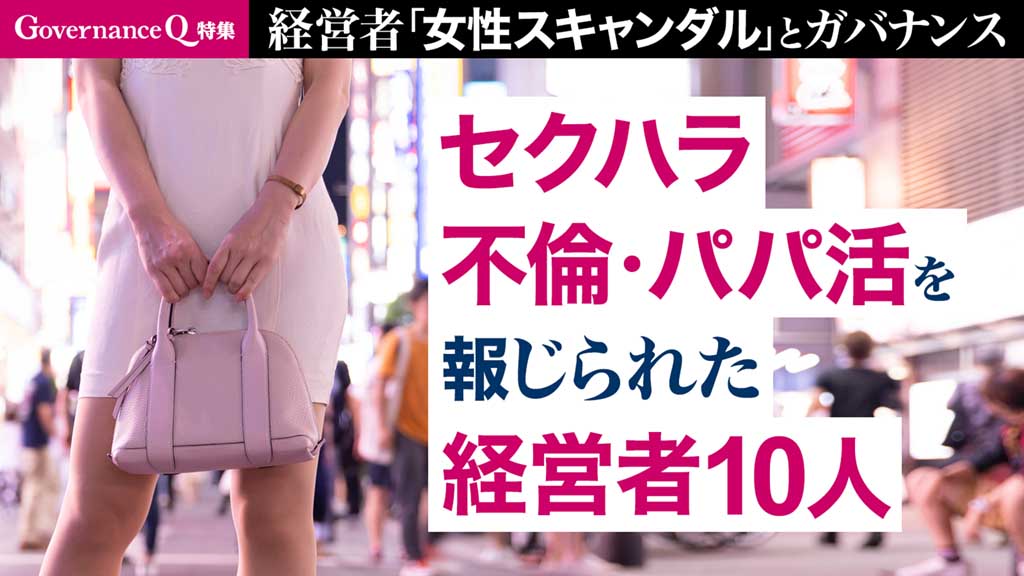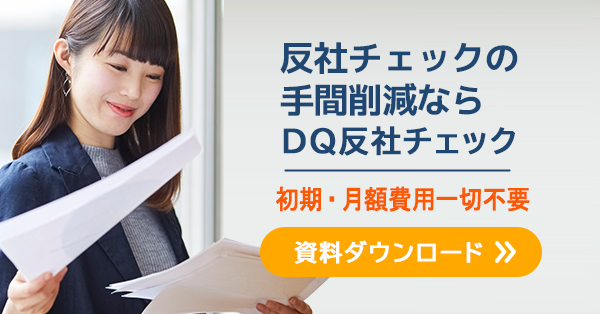企業犯罪学から見る「品質不正」の真因【白石賢・東京都立大学教授】前編

大企業における品質不正が後を絶たない。いまやわが国特有の企業不祥事の様相すら呈している問題だが、その真因はどこにあるのか。企業犯罪研究を専門とし、日本経済新聞で「企業の不祥事と倫理」(やさしい経済学)シリーズを連載した東京都立大学の白石賢教授に聞いた。インタビュー前編。
*
私は、主に行政法を行動経済学的に見るというアプローチで企業・組織の不祥事を考えています。「行動法と経済学」と言いまして、経済学に心理学を入れて法を分析します。過去には行政法の中の刑事罰(経済刑法)を扱った本に寄稿する機会も頂いたことがありますが、刑事法の世界においては行政処分は研究の対象外というのが一般的です。
しかし、企業犯罪を経済学的に考えれば、行政処分も刑事罰も「企業に対する不利益な処分=制裁」という意味では大きな違いはありません。ただし、刑事罰を会社に科す場合は、制裁を個人に科した上で、「両罰規定」で会社に制裁を科すという形になります。一方、業務改善命令のような行政処分は基本的には会社に課されるという違いがあります。
例えば、中古車販売大手ビッグモーターの店舗前で街路樹が伐採されるなどした事案では、本社勤務の男性が刑法の器物損壊の疑いで逮捕されました。刑法だけですと、会社側に刑事罰を科すことができないので、警察は道路法の両罰規定を使って、法人としてのビッグモーターを書類送検しました(2024年3月、不起訴処分)。
とはいえ、会社全体のコーポレートガバナンスを立て直すという視点で見れば、ビッグモーターの保険代理店登録を2023年11月末で取り消した金融庁の行政処分のほうが道路法による刑事罰より明らかに効果的だったと考えられます。このように企業に対する制裁の効果を捉えるのが、私が専門とする法と経済学的な思考です。もちろん、行政処分を何回受けても不祥事を繰り返す企業があることも事実ですが。
日本企業における不正の2パターン
大手上場企業を含む企業による不正や不祥事は後を絶ちません。原因はさまざまですが、最近の不祥事のうち社内で長年にわたり不正が習慣化していたものには2つのパターンがあるように思えます。
ひとつは、経営陣からの暗黙の指示のようなものが考えられる場合。例えば、東芝の粉飾決算の時は、トップをはじめとする経営層から「チャレンジ」などと言われて現場が会計不正を行っているようなものです。 “上”からの暗黙の指示やノルマに応えなければならなくなり、“下”が止むに止まれず不正に手を染めてしまうというタイプで、ビッグモーターのケースもこれに該当するかもしれません。つまり、トップダウン型の不正と言えます。
もうひとつのパターンは、認証試験不正問題を起こしたダイハツ工業のようなケースです。こちらも納期をめぐるプレッシャーはありましたが、上司の直接的な関与はなく、現場の社員が「これぐらいは大丈夫だろう」と考えて不正を行ってきたというものです。敢えて言うならば、ボトムアップ型の不正でしょう。
トップダウン、ボトムアップ型ともに、コンプライアンスに詳しい郷原信郎弁護士は「カビ型」の不正と指摘されています。組織の中で長期間にわたって恒常化し広がりをもっている不正行為で、品質不正や検査不正はその典型例だと言えます。
さらに、このようなカビ型不正をめぐって、誰も「おかしい」と声を上げる人がいない、あるいは、言えるような状態になっていないということが第三者委員会の調査報告書などでよく指摘されています。そして、これが日本企業の企業風土として、「不正の温床」になっていると言われています。
一方、同じ検査不正でも海外では様相が異なっています。技術的な面での違いもなくはありませんが、例えば、フォルクスワーゲン(VW)が排ガス規制を逃れるためディーゼル車に不正ソフトを搭載していた問題(2015年)では、検査不正を行っていたのは日本のような品質管理部門の現場担当者ではなく、VW内のトップクラスのエンジニアたちでした。しかも、彼らが排出量を過少に報告するソフトを主体的に開発していました。上層部の確信犯的な不正行為だったと言え、日本的な「カビ型」の不正とは異なります。
また、日本企業の品質不正の温床のひとつとして、基本的に自社で製造したものを自社で検査するという点が挙げられます。監督官庁などによる外部機関の検査ではなく、自分で検査して自分でOKを出すという仕組みになっているのです。だから、同じような品質不正が同じ業界の別の会社や同様の仕組みの製造業で発生するのです。外部機関による検査のキャパシティーの問題もありますが、そういう内部検査の仕組みである以上、不正の芽を完全に摘み取ることは出来ません。しかし、外部の抜き打ち検査を増やしたり、誰がいつどのように改竄したのかが追跡できる検査システムを導入したりすれば、不正は減っていくのではないでしょうか。
ピックアップ
-
 【会計士「自主規制」機能喪失#2】監督当局の手に落ちた”会計プロフェッション”の倫理基準…
【会計士「自主規制」機能喪失#2】監督当局の手に落ちた”会計プロフェッション”の倫理基準…(#1から続く)会計士を“閉鎖的社会における専門家集団”のように扱い、プロフェッションとしての自主規制を有名無実化させようとする国際会計士倫…
-
 【会計士「自主規制」機能喪失#1】会計士の“職域”を溶かす「サステナ情報保証」という外圧…
【会計士「自主規制」機能喪失#1】会計士の“職域”を溶かす「サステナ情報保証」という外圧…《過度な節税指南に待った 会計士倫理の国際組織が新基準 議長「企業の評判にリスク」》――。日本経済新聞(6月27日付朝刊)にこんなタイトルの…
-
 ブラジル「改正独禁法」解説《後編》現地弁護士が教える改正のポイント…
ブラジル「改正独禁法」解説《後編》現地弁護士が教える改正のポイント…レオポルド・パゴット(Leopoldo Pagotto):弁護士(ブラジル在住) (前編から続く)ブラジルにおける競争法の最新事情について、…
-
 【経営者と女性スキャンダル#5】醜聞が明るみに出た“マル恥”企業トップ10人…
【経営者と女性スキャンダル#5】醜聞が明るみに出た“マル恥”企業トップ10人…(特集#1、#2、#3、#4から続く)「愛人を持つことは男の甲斐性」などと言われた時代もあったようだが、いまやそれは大昔の話。「コーポレート…
-
 今さらの「政策保有株削減」に経営改革は期待できるか【ガバナンス時評#19】…
今さらの「政策保有株削減」に経営改革は期待できるか【ガバナンス時評#19】…八田進二:青山学院大学名誉教授 3月末までに開示された東証プライム上場企業のコーポレートガバナンス報告書を集計したあずさ監査法人によると、プ…
-
 ブラジル「改正独禁法」解説《前編》現地弁護士が教える改正のポイント…
ブラジル「改正独禁法」解説《前編》現地弁護士が教える改正のポイント…レオポルド・パゴット(Leopoldo Pagotto):弁護士(ブラジル在住) 今回は、ブラジルにおける競争法の最新事情をお伝えしたい。著…