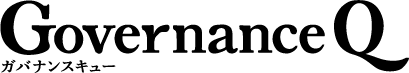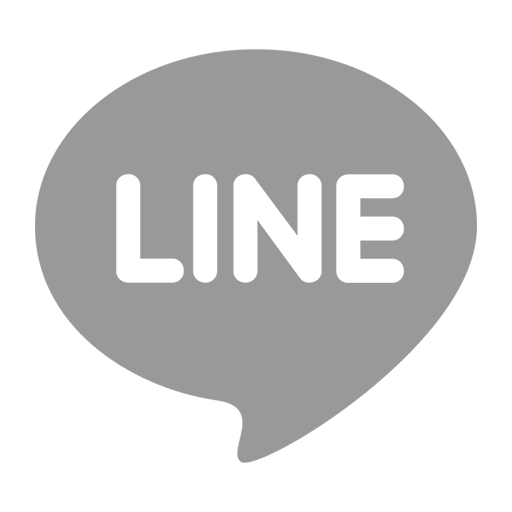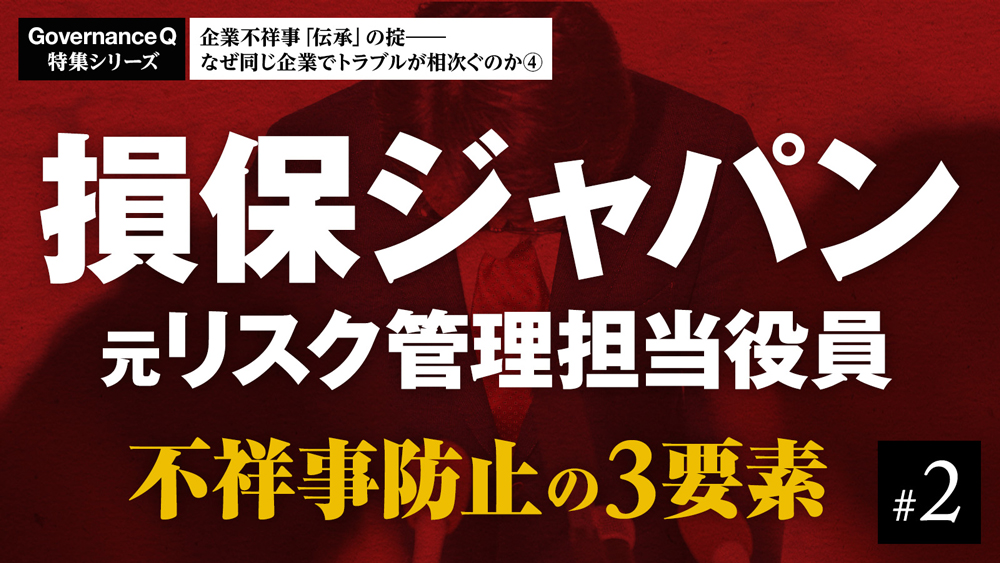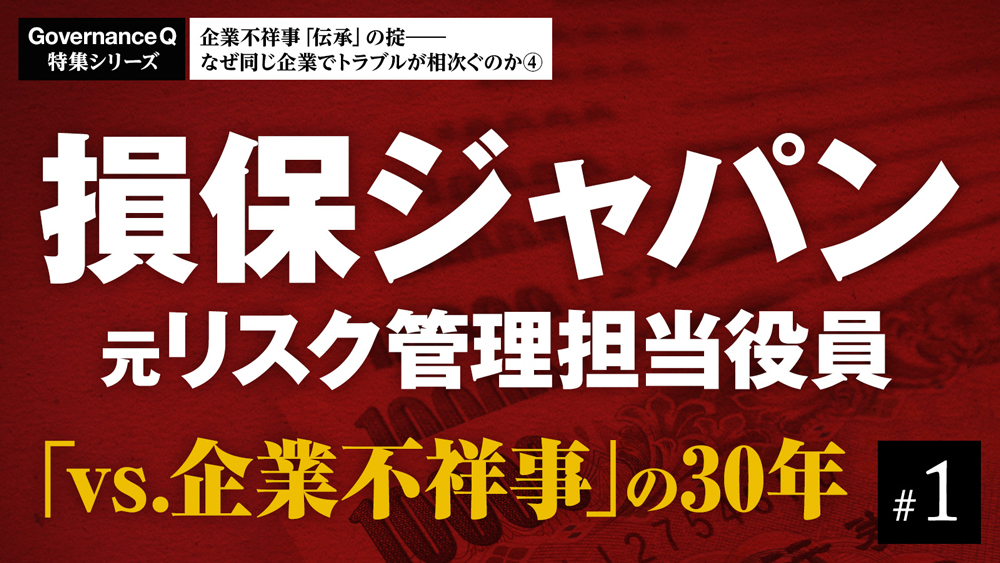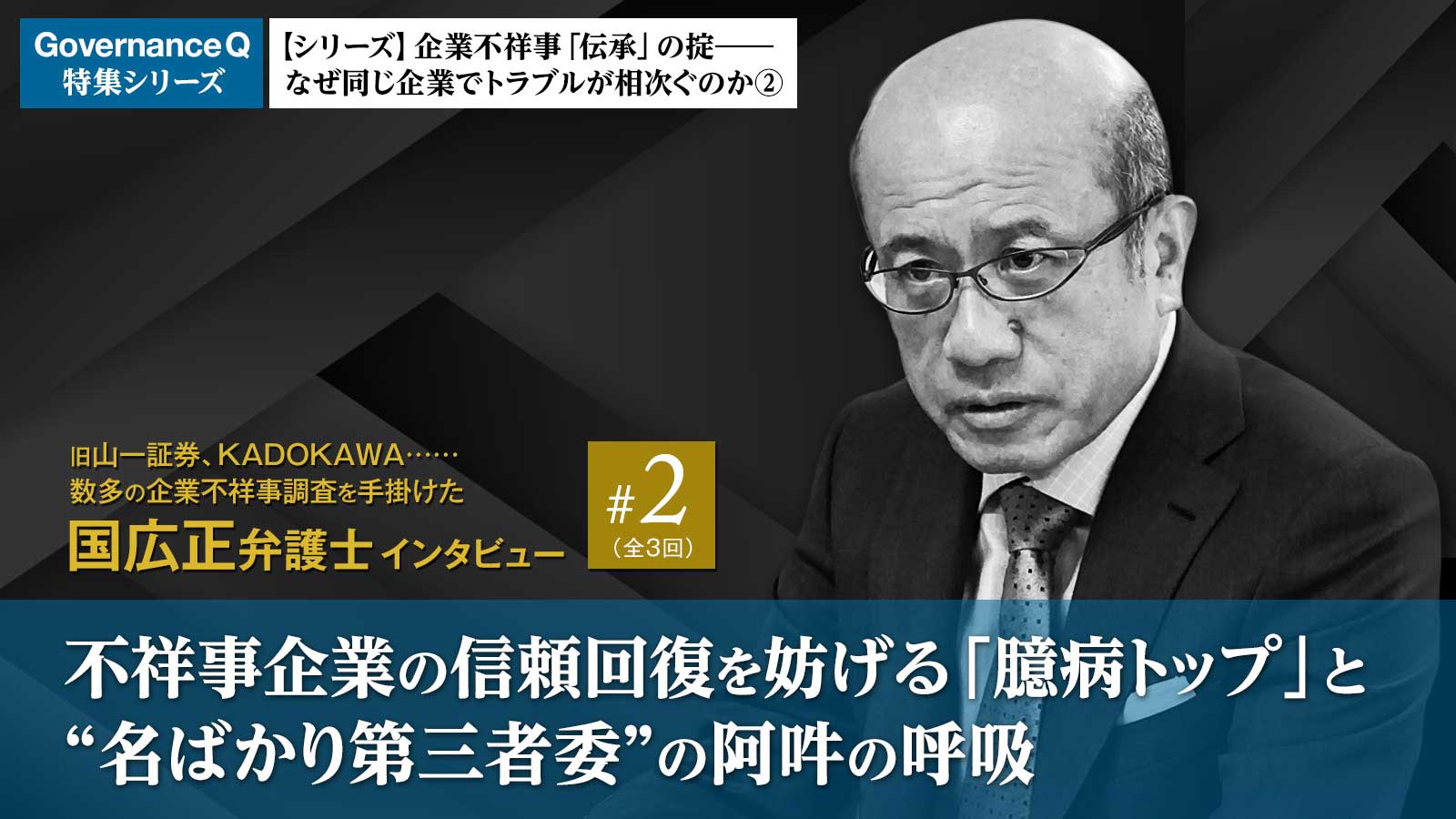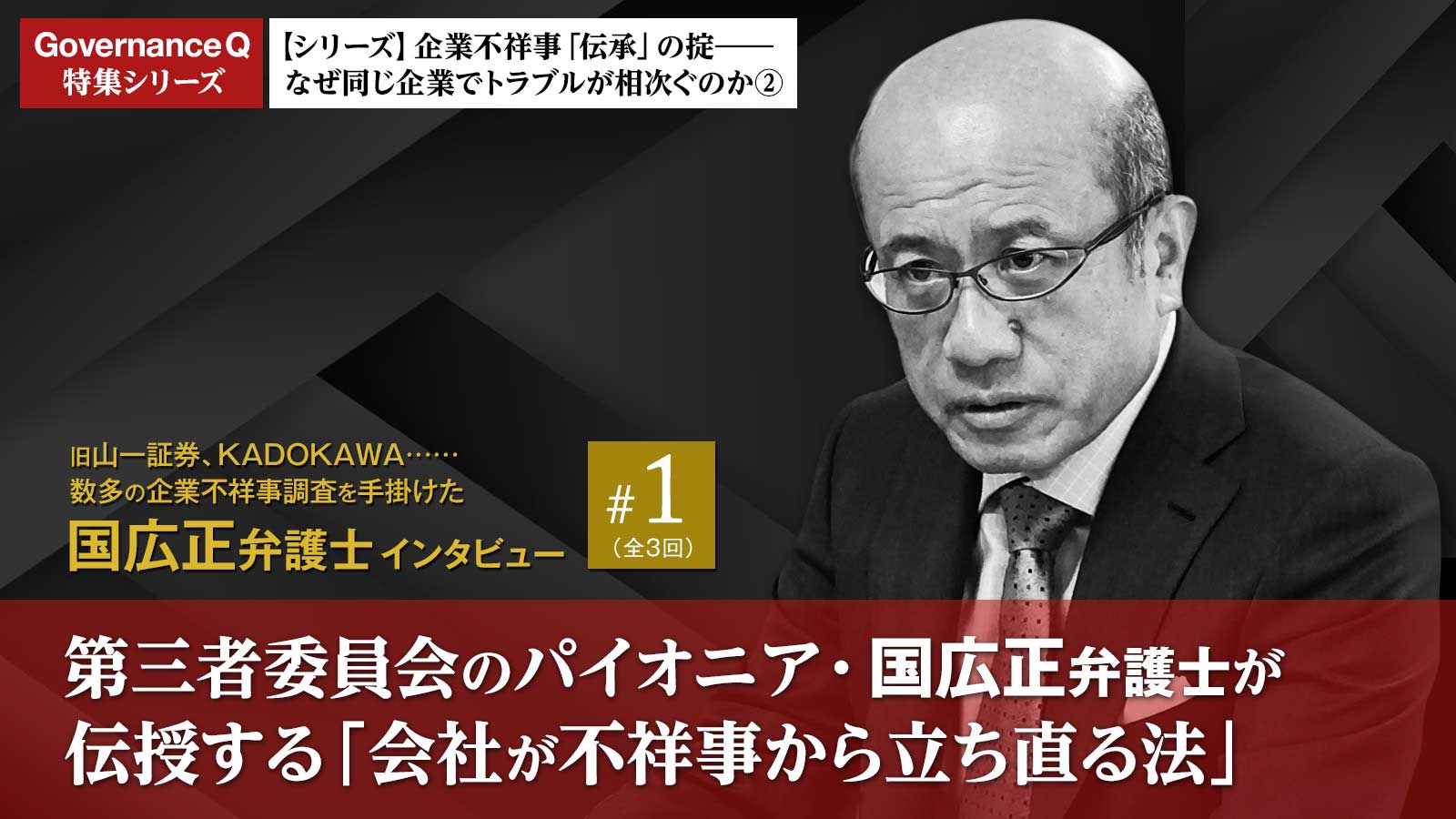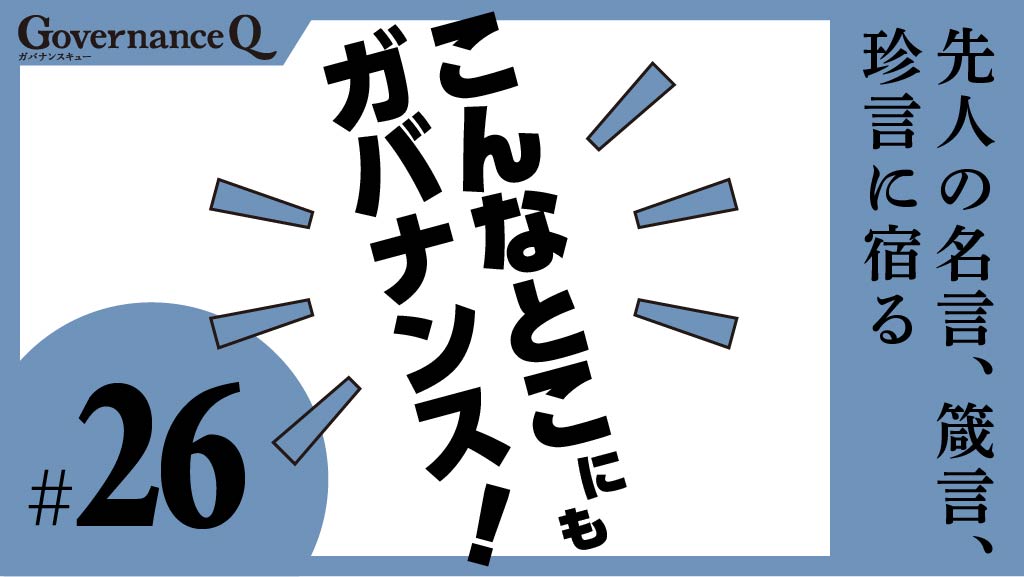【国広正弁護士#3】不祥事企業が公共財「第三者委員会調査報告書」で蘇るために
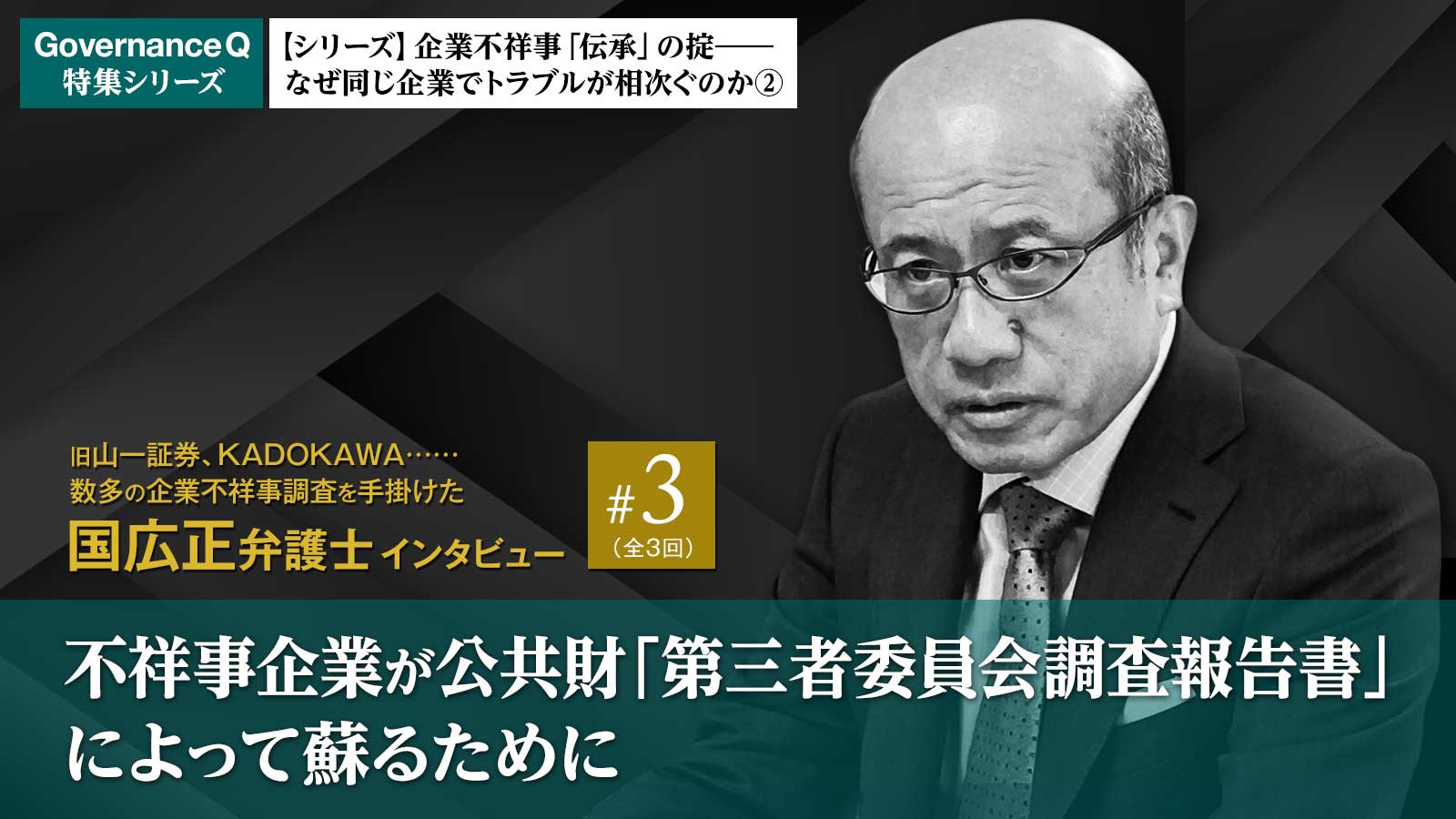
日本企業の不祥事・不正が後を絶たない。それどころか、同じ企業が何度も問題を繰り返すケースすら相次ぐ。そんなモラルハザードの核心には何があるのか――を探るシリーズ第2段の最終回#3記事では「第三者委員会」制度をリードしてきた國廣正弁護士が、不祥事企業が蘇生するために、どのような調査が必要なのか、その実務の姿とあるべき方向性を示す。第三者委調査を生かすも殺すも、経営者に懸かっているのだ――。
不祥事企業が報酬を払う「第三者委員会」に独立性はないのか
#1記事と#2記事では、不祥事企業の信頼回復のための方策と「第三者委員会」の効用、そして、近年跋扈している「名ばかり第三者委」がいかに信頼回復を妨げ得るかについて指摘してきましたが、第三者委をめぐっては、「第三者委の報酬はその会社が払っているから独立性を担保できない」という素朴な議論が根強く存在しているのも事実です。しかし、考えていただきたい。報酬を払っているのは本当は誰なのか――と。
結論を先に言うと、それはステークホルダーにほかならないのです。社長をはじめとする経営トップのポケットマネーではありません。それは株主のお金であるし、その会社の従業員が働いて稼いだお金であるし、取引先との取引で生まれたお金でもあり、ユーザーや消費者が商品を購入したことによって支払ったお金でもある。ですから、第三者委の“真の依頼者”は誰かというと、世の中、あるいは世間が実質的な依頼者なのです。世の中のために不祥事企業の病巣を特定して、それを世の中に説明することが第三者委の仕事ですから、世の中に調査報告書を公表するという形で還元する、そういう対価関係にあります。
その対価関係を理解していない人たちが「会社から金をもらって、きちんとした調査が出来るわけがない」と言うわけです。確かに、経営陣の意向を窺ってばかりの不良第三者委員会はその通りかもしれません。しかし、本来の第三者委はオール・ステークホルダーからコストをいただいて、そして成果は公表という形でオール・ステークホルダーにお返しする。そのような意味で、第三者委報告書は“公共財”ですから、「公表」することが必須なのです。会社は“社会の公器”であるということが前提であって、経営者の私有物ではありません。会社から報酬をもらって会社の責任を追及できるわけがないという議論は、そもそも「会社は誰のものか」がわかってない人たちの議論です。社長が主導して第三者委を設置することが現実には多いですが、社長は便宜的な依頼者に過ぎない。
ところで、“便宜的な依頼者”と言える社長には2つのパターンがあります。第1は、不祥事企業の社長が問題の鎮静化を図るべく、深く考えずに第三者委員会に依頼して、不良第三者委員会に丸投げされてしまうケース。第2はむしろ、社長の腹が座っていて、不祥事が起きてしまった以上、会社を良くするために第三者委に徹底的に調査してほしいと依頼するケース。後者の場合はとても良い報告書が出来上がります。ただし、これではどちらのケースに転ぶかは、社長の属人的な問題如何ということになってしまいます。では、どうすべきなのか。
私たちが推奨しているのは、会社のステークホルダーの代表である独立社外取締役および社外監査役がしっかりと主導して第三者委員会を設置することです。社長のキャラクターや個性といった属人性ということではなく、制度的にステークホルダーの代表である社外役員が第三者委を組成する、あるいは選ぶというやり方が会社法的にも、あるべき方向であろうと考えています。しかし、現実問題として、社外役員みんなが、真の意味で独立した存在であるのかという問題は依然として残るでしょう。
取締役会が本当に執行に対する監視機能を果たすようなものになれば、不祥事が発生した場合、第三者委員会ではなく、取締役会による徹底した調査が行われるのが本来の姿と言えます。その意味では第三者委は過渡的な制度と言える。だた、「あるべき論」ばかりが先行して、安易に第三者委を廃止してしまうと、企業不祥事が繰り返される状況に戻ってしまう可能性もある。むしろ、それは不祥事の真相究明を求めない経営者こそ、利することになりかねません。ですので、当面の間は、第三者委が果たす役割はなくならないでしょう。
膨大な時間とコストを求める「第三者委員会」の実務
ところで、第三者委員会を設置するには相応の費用がかかります。しかも、その多くは作業時間や拘束時間に応じて報酬が決まるタイムチャージ制が一般的です。成功報酬制にしてしまうと、何を以って成功とするのかという問題が発生します。場合によっては、依頼者である企業側の意に沿った報告書なら高額報酬がもらえるといった「名ばかり第三者委員会」の温床になる可能性すらあります。企業不祥事を深く調査するためには膨大な時間と能力がかかりますから、一定のコストがかかるのは仕方がない。費用をかければいいという話ではありませんが、ボランティアでやってくれと言われても、徹底した調査など出来ないことも確かなのです。
現実問題としては、第三者委員会で最もコストがかかるのは、デジタルフォレンジック調査です。デジタルフォレンジックとは、コンピュータや記録媒体に含まれたデータを調査・解析する手法ですが、現在、第三者委の調査には必須の事項となっています。たとえば、不祥事を起こした企業内で不祥事が発覚するまでにやり取りされたメールが何通あるかを考えてみてください。何億通あるか、わかりません。もちろん、調査対象を絞り込んでいくことになりますが、比較的数が少ない調査でも数百万規模はあるものです。全てのメールを読むのは不可能ですから、キーワードや人物で絞り込んでいく。あるいは、重要なメールが消去された可能性もありますから、それを復元する作業もしなければならない。そうなりますと、デジタルフォレンジックの専門業者に依頼しないわけにいかないわけですが、実はそれには相当なコストがかかります。
例えば500万通のメールを1万通ぐらいまで絞り込んでいくわけですが、最後はその1万通を解読するしかないのです。優秀な業者の場合、最初から第三者委員会に参画してもらい、われわれが何を調べようとしているのかを詳しく伝えます。関係者をピックアップし、キーワード検索で1万通くらいまで絞り込んで、業者がそれをデータ的に読み込んでいきます。その中から例えば数百通、なんとなく重要そうなメールが炙り出されてきます。そして、その数百通を弁護士をはじめとする委員が読むわけです。数百通の中から、例えば何通目のメールがなんとなく怪しい感じがするとなると、CCの付いた人物のメールを新たに検索し直します。また、メールには添付ファイルが付いている場合もありますから、パスワードでこじ開けることもある。こういった地道な作業の繰り返しなのです。
ファクトに謙虚である「第三者委員会調査」が紡ぐ不祥事企業の“正史”
このように、第三者委員会の調査は、事実を淡々と掘り起こしていく作業の連続です。当然ながら、初動で仮説を立てないわけではありませんが、あらかじめストーリーを作ってそれに事実を当てはめて報告書を書くというようなことはしません。少なくとも、きちんとした第三者委はそうです。ファクトに謙虚でなければいけないので、そこは真摯に誠実に事実に向き合います。事実に謙虚である以上、「第三者委で徹底的に調査をしたが、怪しい事実はなかった」という報告書もあり得るわけです。第三者委で調査したから必ず“有罪”にしなきゃいけないとか、必ず悪者を見つけないといけないとか、そういったことはあり得ない。あくまでも事実が最優先です。その意味で第三者委は「事実調査委員会」なのです。そして、重要なのは不祥事の原因にどう迫れるか――。事実に基づいて原因論にまでどのように洞察を加えるかは、その第三者委の分析力が問われるところです。
不祥事を繰り返す企業に特徴的なのは、本当は企業風土自体に問題があるにもかかわらず、不祥事のたびに “チェックリスト”を新たに作って現場に押し付けて疲弊させるばかりの積み重ね型のコンプライアンスを行っていることです。不祥事が起きる土壌、企業風土自体を変えようとせず、ルールなどで現場を縛ることを繰り返している印象があります。むしろ、ルールを減らす代わりに、大事な「プリンシプル」(原理原則)、自分の会社は何のために存在しているのかという根本から考え直したほうがいい。ルールばかりが多い会社では、社員が自分の頭で考えなくなります。現場はチェックリストをチェックすることに日々のエネルギーの大部分を奪われることになり、「これって、何かおかしくないか?」といった危機管理の感覚のようなものが劣化していきます。リスクを感知するセンスが摩耗する上に、やる気が失せ、良い仕事ができなくなるという悪循環に陥ります。
不祥事を起こした企業が、その経験や教訓を自分たちの後進にいかに伝えていくかという問題は、第三者委員会の報告書がその企業内でどのように扱われるかということと関連すると思います。報告書は公表して終わりではなく、その企業にとっては本来、スタートにならなければいけないわけです。優れた第三者委報告書が出ると、その企業は自分たちの体質なり組織の根っこの部分、自分たちではわからなかったものが「見える化」されます。そこには、不祥事を起こす根本原因を克服するためには何が必要か、大事なヒントがあります。その第三者委報告書で“真因”とされたものをどうやって克服するか、その再発防止がなされることによって企業が良くなっていくわけです。
第三者委員会のあるべき将来像は、執行の監視役である取締役会、とりわけ社外役員がステークホルダーの代表としての役割を果たせるようになれば、その機能に昇華されることでしょう。しかし、現実にはなかなか難しいのも事実です。そればかりか、社外取締役や社外監査役が不祥事を起こした経営陣の“防波堤”になってしまうケースすら見受けられる。企業の“真の歴史”を紡ぐうえでも、当面は第三者委員会が果たすべき役割は非常に大きいものだと私は考えています。
【シリーズ記事】
ピックアップ
-
 福沢桃介「私の口は信頼できぬ。なぜかというと、私には一定の主義がない」の巻【こんなとこにもガバナンス…
福沢桃介「私の口は信頼できぬ。なぜかというと、私には一定の主義がない」の巻【こんなとこにもガバナンス…栗下直也:コラムニスト「こんなとこにもガバナンス!」とは(連載概要ページ) 「私の口は信頼できぬ。なぜかというと、私には一定の主義がない」福…
-
 【11/22(金)15時 無料ウェビナー】医薬品の品質不正《品質不正とガバナンスの最前線・連続ウェビ…
【11/22(金)15時 無料ウェビナー】医薬品の品質不正《品質不正とガバナンスの最前線・連続ウェビ…本誌「Governance Q」と日本公認不正検査士協会(ACFE JAPAN)共催無料連続ウェビナー「品質不正とガバナンスの最前線:公認不…
-
 大谷翔平を嵌めた「水原一平」はアメリカでどんな施設に収監される?【海外法務リスク#4】…
大谷翔平を嵌めた「水原一平」はアメリカでどんな施設に収監される?【海外法務リスク#4】…有吉功一:ジャーナリスト、元時事通信社記者 (前回までの記事はこちらから)米メジャーリーグ、大谷翔平選手の専属通訳を務めた水原一平氏(39)…
-
 三菱UFJアセットマネジメントが「選任反対」した取締役・監査役リスト#1《1000~3000番台企業…
三菱UFJアセットマネジメントが「選任反対」した取締役・監査役リスト#1《1000~3000番台企業…後藤逸郎:ジャーナリスト + Governance Q特集班 上場企業のコーポレートガバナンスへの注目が俄然高まる中、機関投資家が株主総会で…
-
 King Gnuの「IKAROS」と、経営判断原則の要諦【遠藤元一弁護士の「ガバンス&ロー」#3】…
King Gnuの「IKAROS」と、経営判断原則の要諦【遠藤元一弁護士の「ガバンス&ロー」#3】…遠藤元一:弁護士(東京霞ヶ関法律事務所) ギリシャ神話「イカロス」に見る経営者の“勇気”と“傲慢” 2023年11月末にリリースされたKin…
-
 《最終回》米司法省 棄却でも残る「起訴の烙印」を消す“不条理な闘い”【逆転の「国際手配3000日」#…
《最終回》米司法省 棄却でも残る「起訴の烙印」を消す“不条理な闘い”【逆転の「国際手配3000日」#…有吉功一:ジャーナリスト、元時事通信社記者【関連特集】日本企業を襲う「海外法務リスク」の戦慄 はこちら (前回までの記事【米司法省が訴追した…