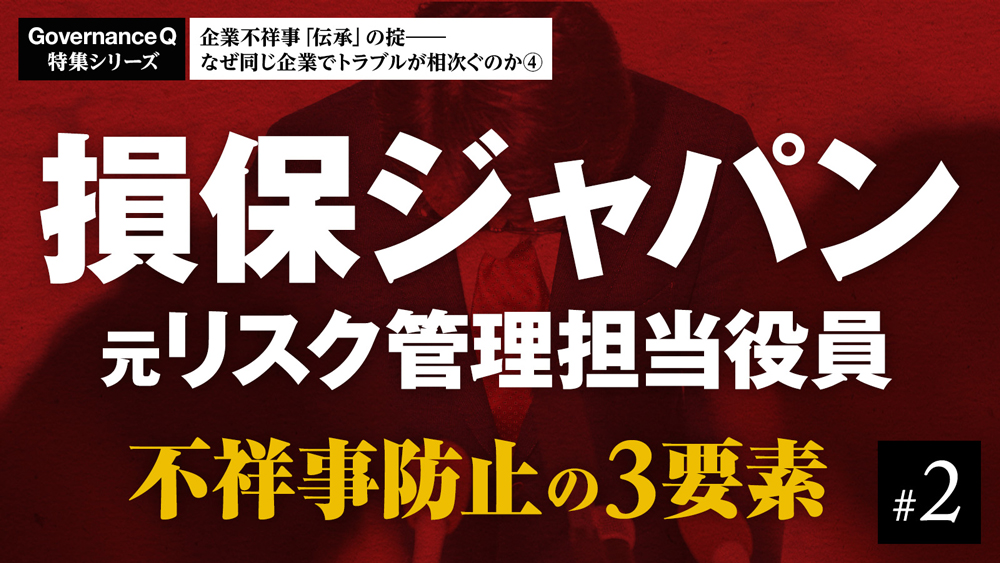【実効性向上の要素①】経営者の真剣度合い
(#1から続く)不祥事防止あるいは再発防止を検討するときに必要な要素が3つあります。
第1は、経営者の真剣度合いです。経営者が過去の企業不祥事から学ぶ姿勢があるかどうか。不祥事を他人事として受け止めず、常に他社で起こった不幸な事件が自社では起こらないか、似たような業務形態はないかなど、目配りを怠らない経営者のもとでは組織のリスク耐性は強靭になります。
不吉なこと、忌まわしいことが「ウチでは起こらないよね」「起こっていないはずだ」と思いたくなる心情は理解できますが、当然ながら、それは単なる気休めでしかありません。それどころか、必ず同じ(ような)ことが起き得ると考えたほうがいい。
不祥事から学ばない経営者は、今は平気な顔して他社の不祥事を非難していても、いざ、自分が同じ不祥事の状況に追い込まれたら、「きっとあなたも同じことやりますよ」というのが、実は私が言いたいことなのです。だから、自分の会社では、幸いにして不祥事は起きなかったけれども、これを“他山の石”として学ぶことは、とても大事なことなのです。それをどこまで真剣にやるか、そこにかかっています。
【実効性向上の要素②】不祥事原因の“深掘り”はできているか
第2は、少し技術的なことになりますが、不祥事の原因の深掘りができているかどうか。ある会社で不正が起きました、その原因はこうです――という事例があった際、その不祥事を起こした当事者の企業でさえも原因の深掘りがほとんどできてないことは往々にしてあります。
どういうことかと言うと、現在、不祥事が起きると、著名な法律事務所を中心に調査委員会が設置され、調査報告書が出されます。その内容、意外と”ワンパターン”になっているのです。大方の調査報告書の原因分析は、従業員のコンプライアンス意識の希薄さ、そこから始まります。それに付け足しのように、やれ、経営資源が足りなかったとか、やれ、不正をチェックする仕組みがなかったとか、やれ、下の声が上に届かなかったとか、報告書を読んでも結局は何が本質的な原因なのかよくわからないものが、実に多いのです。
私自身、いろいろな会社から相談を受けますが、たとえば、労災事故が立て続けに起きている会社があるとします。半年の間に6回も労災事故が発生した会社の担当者が、「何が原因か意見してもらいたい」と言うので、ざっと資料を見せてもらいました。そこにはルール通りに仕事をしてないとか、マニュアルに書いてある通りに作業をしてないとか、そういったことを原因として記述しているものが多いわけです。そうなると、対策は「マニュアルを徹底する」ということになりますし、実際に資料にもそう書かれている。
では、なぜ労災事故に遭った社員はルール通りにしなかったのか。その業務を遂行する能力そのものがなかったのかもしれないし、もともとルールに反感を持っていて、「こんなマニュアル通りにやったら進まない。もっと省略してやったらいい」という“近道行動”をとる人間であったかもしれない。あるいは、完全にルールはわかったうえで悪意を持ってルールを破る人間かもしれない。
そうすると、理解ができてないからルール通りにできなかったということと、理解はしているが、わざとやらなかった、または悪意でやらなかったということとは切り分けて考えなければなりません。「マニュアル通りに仕事をしなかった」と一口に言っても、対策はおのおの違ってくるはずなのです。ところが、十把一絡げに「マニュアルを徹底する」という整理で簡単に片付けてしまうと、再発防止の実効性は覚束なくなります。
一方、経営側の問題としては、マニュアルの出来映えの問題があります。マニュアルそのものが存在しなかったということもあるでしょう。また、あったとしても内容が不十分、内容は十分だったが、社員に周知徹底されていなかったケースも考えられます。さらに、マニュアルでの要求事項のレベルが高すぎて実行するのが非常に困難という場合は、マニュアル自体が投げ捨てられるに決まっているわけです。あるいは、マニュアルを実行しようとすれば、どれだけのコストと時間がかかるのかわからないというマニュアルもあります。
そういうふうに考えていくと、同じマニュアルを見ていない、読んでなかったと言っても、さらに「なぜ」「なぜ」を繰り返して、深掘りしていかないと問題が解明できない場合があるのです。そういうことをよく考えていかないと、対策を誤ります。
マニュアルで特に気をつけないといけないのは、本社の人が作成するマニュアルは現場の仕事や意見を反映していないことが多く、実務上使い勝手が悪いというのが一般的ということです。先の労災の相談事例でも、当のマニュアルを見せてもらうと、私は労災の専門家ではありませんが、そのハンデを考慮しても、マニュアル全体が何を言わんとしているのか、よくわからないのです。時には、書かれている日本語そのものが理解不能というときすらあります。極論すると、マニュアルを理解するためのマニュアルが必要になる。マニュアルがその現場で実際に働く人の目線に即して書かれていないわけです。現場での困難を経験した人が書いていない。あるいは、初めてその作業に従事する人の立場で書かれていない。
また、マニュアルの中で特定の部分については「別の資料参照」というものが結構あります。しかも、その別の資料をどこで見つけるべきかも、よくわからないケースも多い。ようやく探したら、膨大な量の資料だったりします。だから、私は「このマニュアル一発で全部完結させてください」「範囲が広くても、このマニュアルさえ読めば80パーセントは理解できる程度のものを作らないと、現場ではマニュアルとして使い物になりませんよ」とアドバイスしています。