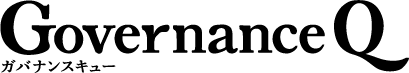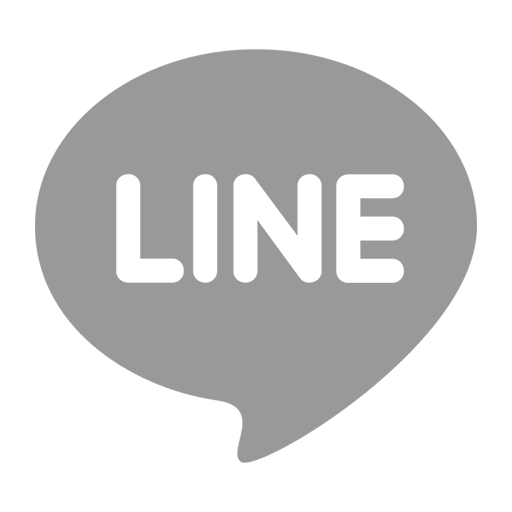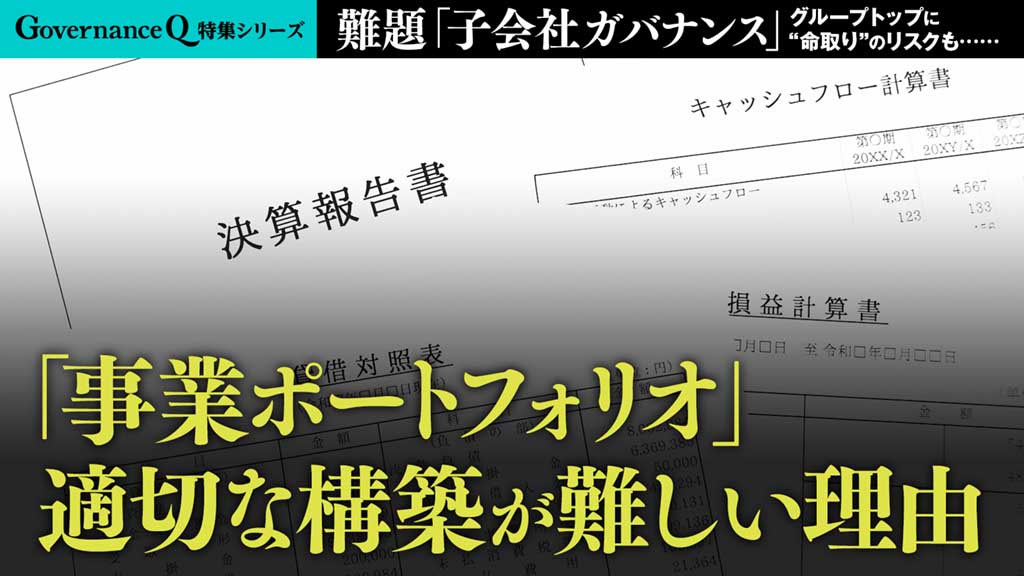第5回【佐々木清隆×八田進二#1】「平成経済事件史」を駆け抜けた金融官僚人生

プロフェッショナル会計学が専門でガバナンス界の論客、八田進二・青山学院大学名誉教授が各界の注目人物とガバナンスをテーマに縦横無尽に語り合う大型対談企画。シリーズ第5回のゲストは、36年間に及ぶ官僚人生の大半を“問題企業”の監視と不正の摘発、再発防止策の政策立案に努めた元金融庁総合政策局長・佐々木清隆氏である。1990年代末に端を発する外資系証券会社の不正行為、カネボウ、オリンパス、ライブドアに村上ファンド、東芝の粉飾事件……。あらゆる経済事件に携わり、「平成経済事件史」を体現する経歴を持つ。そんな佐々木氏が語るコーポレートガバナンス論とは――。
“問題企業処断”の原点は1990年代末の「金融危機」
八田進二 私の中では佐々木清隆さんと言うと、数々の経済事件において当局側で最前線に立った人、そして、「刑事告発」というものすごく高いハードルを超えなければ実現しなかった問題企業の処罰に、比較的ハードルが低い行政処分で迅速に対応していく道を開いた人……そういうイメージを持っています。そんな佐々木さんの“原点”は何でしょうか?
佐々木清隆 やはり1990年代末の金融危機ですね。1998年6月に金融庁の前身である金融監督庁が発足した際、いわゆる「財金分離」政策(旧大蔵省が所管していた財政と金融の2分野を分割する政策)によって、「大蔵省大臣官房金融検査部」という部署がそっくり金融監督庁に移管されました。私は前年の1997年からその金融検査部で都市銀行などの検査を担当していましたので、金融監督庁に籍を移す形になったのです。
八田 不良債権問題を機に大蔵省が、長年、護送船団方式で金融機関を指導し、“箸の上げ下げにまで口を出す”と言われた裁量行政と決別した時期ですね。
佐々木 私はOECD(経済協力開発機構)への出向で1993年からフランス・パリに行っていたのですが、1997年7月に帰国して金融検査部総括補佐になって4カ月後に三洋証券、北海道拓殖銀行、山一証券が破綻しました。1998年になると、事態はより深刻化し、同年秋の日本長期信用銀行、日本債券信用銀行の国有化へつながっていく。金融システム自体が揺らぐという未曾有の危機に直面し、より透明性が高い手法が必要になるなかで、私自身は銀行の不良債権の実態を把握するための検査計画の立案と実施に取り組む業務に従事していました。
八田 よく覚えているのは、イギリスの『フィナンシャル・タイムズ』の社説です。タイトルは「不思議の国ニッポン」。直近の財務情報は黒字で、監査法人も無限定適正意見を付けているのに、その数カ月後には何の前触れもなく、いきなり破綻してしまう。この批判には2つの側面があって、ひとつは日本の監査は単なる儀式に過ぎないのではないかという点。もうひとつは、そもそも貸倒リスクに対する引当基準は一体どうなっているんだという点でした。
佐々木 金融機関が破綻してみたら、その実、債務超過だったというのは、要は貸倒リスクに対する引当が不十分だから起きるわけですからね。
八田 ただ、私はあの当時の日本の会計基準はかなり税法に引っ張られていた印象を持っています。
佐々木 ご指摘のとおり、当時は「貸倒れ」が確定していない、引当段階で税務上損金処理できる範囲は極めて限定的で、当時の会計基準も税法に引っ張られ、有税でも積極的に引当を積む基準になっていたかというと、そうではありませんでした。世界は急速に資産も負債も簿価ではなく時価で把握する流れになっているなかで、日本はその潮流に乗り遅れた感がありました。自己査定における引当基準については、多くの通達を出して対応しましたが、なかなか追いつかなかったというのが実態です。

八田 監査の信頼性についてはどういうお考えでしたか。
佐々木 問題意識は持っていました。金融機関はとてつもない金額の不良債権を抱えているのに、会計監査では金融機関と監査法人の間で充分な議論がなされていない。それは今、八田先生が指摘された、当時の会計基準、そして、その会計基準に紐づいている監査基準の問題でもあったのですが、1998年~99年頃のわれわれは、金融機関の不良債権の実態把握だけでも精一杯で、監査の問題に踏み込む余裕はなかったというのが正直なところです。金融庁として監査法人を検査の対象とする制度もありませんでしたし……。ただ、旧検査局内では、監査の信頼性向上に取り組む必要性は認識していました。
八田 当時はコーポレートガバナンスの議論もなされていなかったでしょう?
佐々木 引当不足の問題というのは、突き詰めて言えば、信用リスクに対する経営者の認識の問題であり、その根幹にあるのはコーポレートガバナンスの欠如なんですよね。もちろん、当時はまだ「コーポレートガバナンス」という言葉は普及していませんでしたが、1999年に策定した金融検査マニュアルは、アメリカのCOSO(トレッドウエイ委員会支援組織委員会)の概念を基本にしていて、従来との最大の違いは「自己責任原則」を取り入れた点でした。
経営陣のリーダーシップの下で、それぞれの規模や特性に応じて内部規定を作成し、業務の健全性、適切性を確保しなさいと。検査では、それが出来ているかどうかを見ますよ、という趣旨のものであり、これこそまさにコーポレートガバナンスの考え方です。日本のコーポレートガバナンスの歴史において、「金融検査マニュアル」は先駆的な存在という自負はあります。
「カネボウ事件」で中央青山監査法人“解体”の厳罰
八田 金融機関が一足先に金融検査マニュアルによってコーポレートガバナンスの構築を求められたのに対し、一般事業会社においてもコーポレートガバナンスは必要なんだということが日本で理解され始めるのは、もう少しあとのことですよね?
佐々木 そうですね。
八田 アメリカでエンロン事件が起きたのが2001年の暮れ。ワールドコムの破綻が2002年7月です。いずれも会計不正を監査人が見落として証券市場を大混乱に陥れたわけですが、監査先進国のアメリカで、一般事業会社でとんでもない会計不正が起きたということは、早晩、同じことが日本でも起きるはず。だから、日本も対応しなくてはいけない――。そう考えて、私自身、学界においても積極的に問題を提起したのですが、当初はまったく相手にされませんでしたよ。
佐々木 実は私、エンロンやワールドコムが破綻したときはIMF(国際通貨基金)に派遣されていてワシントンD.C.にいまして……。だから、日本国内でどうとらえられていたのかは知らないのですが、エンロン事件から半年足らず、ワールドコムの倒産直後にアメリカではSOX法(サーペインズ=オックスりー法)が制定され、事業会社および監査法人に対する内部統制の確立が義務化されました。さすがにアメリカは対応が速いと思ったことを記憶しています。日本も当然、その流れになるだろうと思っていました。

八田 アメリカではエンロン事件で国際ネットワークの会計事務所であるアーサー・アンダーセンが消滅しましたが、その後に同じことが日本でも起きました。カネボウ巨額粉飾事件が2004年10月に発生し、当時の5大監査法人の一角をなす中央青山監査法人が2007年7月に解散に追い込まれます。このあたりから、佐々木さんはまさに当局側の当事者ですね。
佐々木 金融庁がカネボウの旧経営陣に対する刑事告発を行ったのが2005年7月。ちょうど私がワシントンD.C.から帰国して証券取引等監視委員会(SESC)の事務局の特別調査課長として着任したときでした。すでに調査は粗方済んでいて、実際、旧経営陣の刑事告発はもう手続きをとるだけ。「中央青山をどうするのか?」というのが議論の中心でした。
八田 結論として金融庁は、カネボウの監査を担当していた中央青山の会計士たちを粉飾の共犯として刑事告発しました。1990年代末の金融危機のとき、監査法人はまったくお咎めなしでしたから、当局の姿勢が大きく転換した印象を強く持ちましたね。
佐々木 金融危機のときも、監査法人が何らの責任を問われなくても良いのかという議論はあるにはあったのですが、当局も手が足りないし、迅速に対応する制度自体もないということで、実際には何も出来なかった。しかし、カネボウについては、これだけの巨額粉飾決算事件に対し、「今、やらずして、いつやるんだ!」というムードになっていました。
八田 アメリカでアーサー・アンダーセンが刑事告発されたことの影響もあったのでは?
佐々木 それは確かにあります。アメリカでアーサー・アンダーセンが刑事告発されていなかったら、カネボウであそこまでのことは出来なかったと思います。。
八田 会計士個人が刑事告発されただけでなく、監査法人自体も2006年に業務停止に追い込まれたわけですが、個人的にはあの処分には少々思うところがあるんです。というのも、中央青山を完全に業務停止にしてしまったでしょう。その結果、中央青山はその時点ですべての監査契約を破棄しなければならなくなった。
そして、カネボウの粉飾とは何の関係も問題もない、中央青山に監査を依頼していた事業会社が、いきなり監査をしてくれる監査法人を失ってしまい、かなりの混乱が発生しました。とりあえず7月末、8月末までに有価証券報告書を提出しなければならない会社の監査業務は継続できる措置がとられましたが、期中で監査法人が変わる、それも突然にという事態は、やはり粉飾とは無関係の健全な事業会社に、かなりの負担をかけるものだったと思います。
佐々木 確かにそのような批判はありましたが、監査法人の問題とともに監査法人ともたれ合いにあった事業会社にも緊張感を持ってもらううえでもやむを得なかったと考えます。
八田進二教授の「佐々木清隆氏との対談を終えて」
佐々木清隆氏は、ピンクのネクタイにカラーシャツ、そしてベリーショートの髪形がトレードマークになっており、国内外の市場関係者の誰もが知るところとなっている。2016年に、金融庁からの要請で、米国の会計・監査制度の監視機関である公開会社会計監視委員会(PCAOB)の委員長を訪ね、米国の監査事情を聴取した折、開口一番、「ピンクネクタイの彼は元気か?」と質問されたほどである。同氏は、そうしたファッションだけでなく、金融行政とりわけ監査法人監査の信頼性向上に向けて、注目を浴びる多くの提言を発し続けてきたのである。
なかでも、公認会計士・監査審査会事務局長時代、監査法人に対する品質モニタリング検査結果については、被監査会社の監査役等に対して報告しかつ十分な説明をするといった実務対応を推進されたのである。これは、従来、「ブラックボックス」だと揶揄され続けてきた監査業界にとって、画期的な改革であり、かつ、より透明性を高める経緯ともなったということで、監査の信頼性向上に対して大いに貢献したものと評することができる。併せて、監査人と監査役等とのコミュニケーションを促進させることにもなったといえる。
また、金融機関を取り巻く監査制度のさらなる強化に向けては、外部監査、内部監査および監査役等監査の「三様監査」を前提に、金融機関に対する当局の検査を加えて、「四様監査」の連携といった斬新な提言をされたのである。これも、それぞれの監査担当者にとっては、自身の監査業務の質向上に対して意識を高める契機ともなったといえる。
このように、佐々木氏は、官僚としては異質とも思われるように、それぞれの持ち場において、多くの軋轢を克服しつつも、常に革新的ないしは先駆的な提言や取り組みを実践されてきたことには敬意を表する次第である。今回の対談においても、そうした取り組みの一端を伺うことができた。

【ガバナンス熱血対談 第5回】佐々木清隆×八田進二シリーズ記事
ピックアップ
-
 【子会社ガバナンス#4】加登豊名古屋商科大学教授が語る「子会社業績向上の秘策」…
【子会社ガバナンス#4】加登豊名古屋商科大学教授が語る「子会社業績向上の秘策」…(#3から続く)今回の#4では、経営学者で現在、名古屋商科大学大学院マネジメント研究科で教授を務める加登豊氏をインタビュー。日本の企業グルー…
-
 【子会社ガバナンス#3】「親会社からの天下り」人事が子会社の成長を阻害する…
【子会社ガバナンス#3】「親会社からの天下り」人事が子会社の成長を阻害する…#1、#2では実例を引き合いに出して、子会社のコーポレートガバナンスが機能不全に陥り、ひいてはグループ全体のガバナンスを阻害しかねない状況を…
-
 【子会社ガバナンス#2】適切な事業ポートフォリオの構築が難しい理由…
【子会社ガバナンス#2】適切な事業ポートフォリオの構築が難しい理由…#1では大手企業の不動産子会社を例に、子会社のガバナンス不全があわや不祥事を生み出しかねない危険性を伝えた。続く#2では、新設子会社、あるい…
-
 【子会社ガバナンス#1】大企業の「不動産子会社」で不祥事が起きた背景…
【子会社ガバナンス#1】大企業の「不動産子会社」で不祥事が起きた背景…子会社・関連会社までを含めたグループ全体のコーポレートガバナンスが求められる大手企業。一方、大手企業グループには必ずと言っていいほど、不動産…
-
 「リスク情報収集」を自動化する最適なネット検索ツールとは…
「リスク情報収集」を自動化する最適なネット検索ツールとは…(前編から続く)リスク情報の収集には、時として正確性よりもスピードが求められる。その際、ネット上の情報をいかに集めるかが、勝負の分かれ目とな…
-
 企業担当者を悩ます「リスク情報収集」の死角…
企業担当者を悩ます「リスク情報収集」の死角…「仕事とはいえ、パソコンに向かい合ってネット上で関係先のリスク情報をチェックするのは、身心ともに疲れ果ててしまう」――。あるメーカーで与信管…