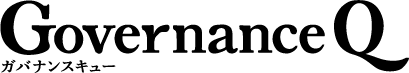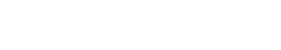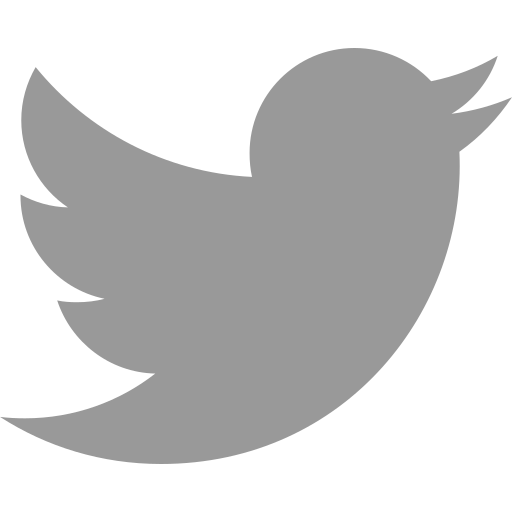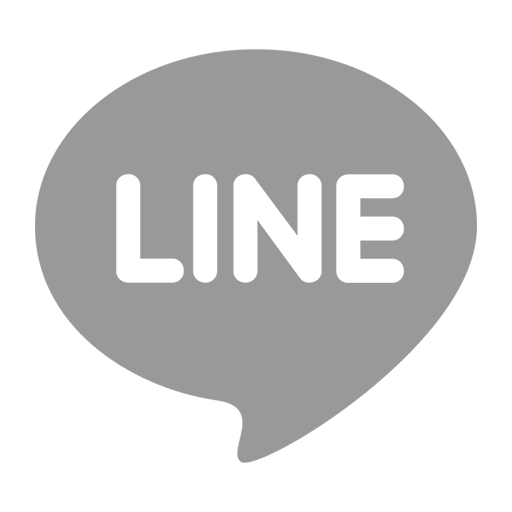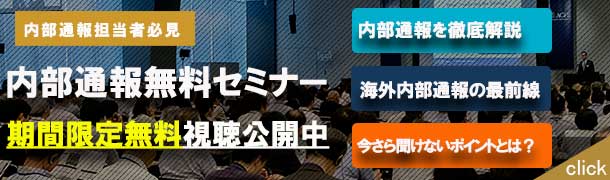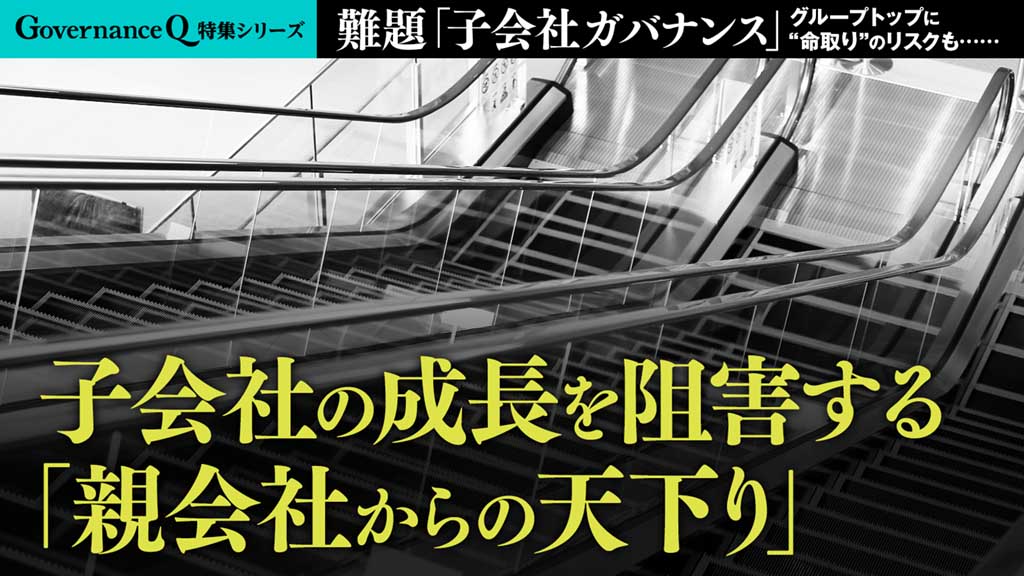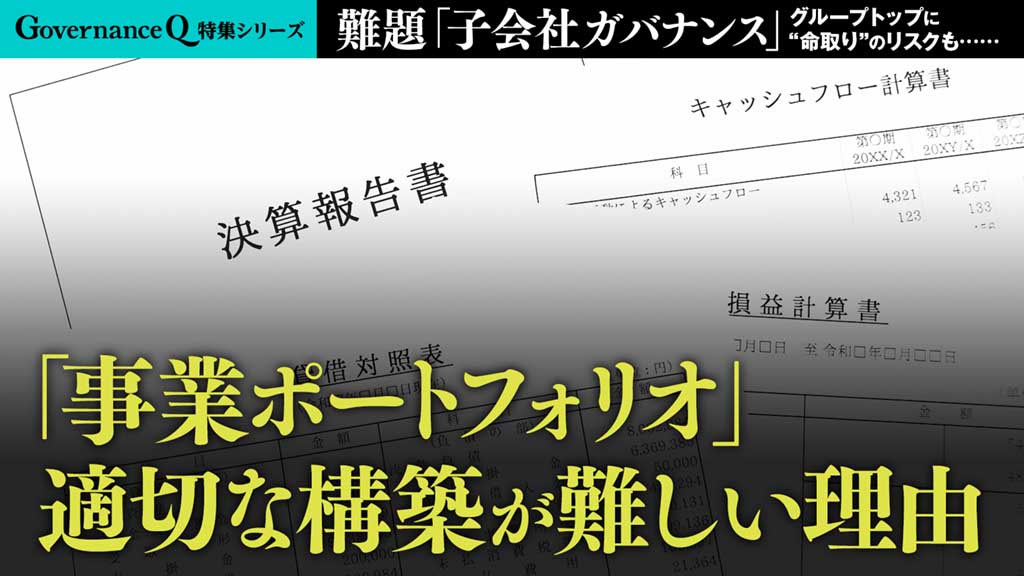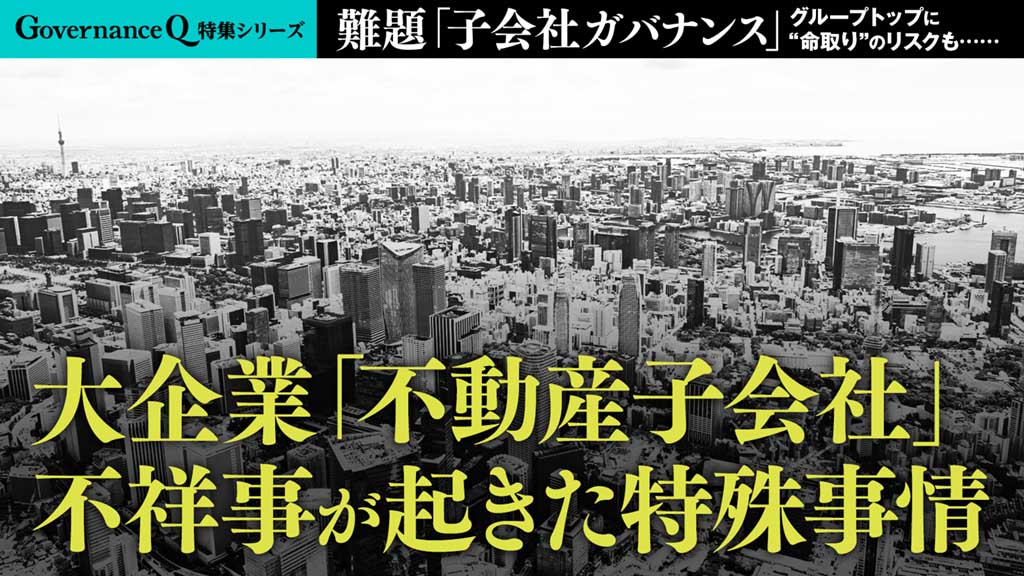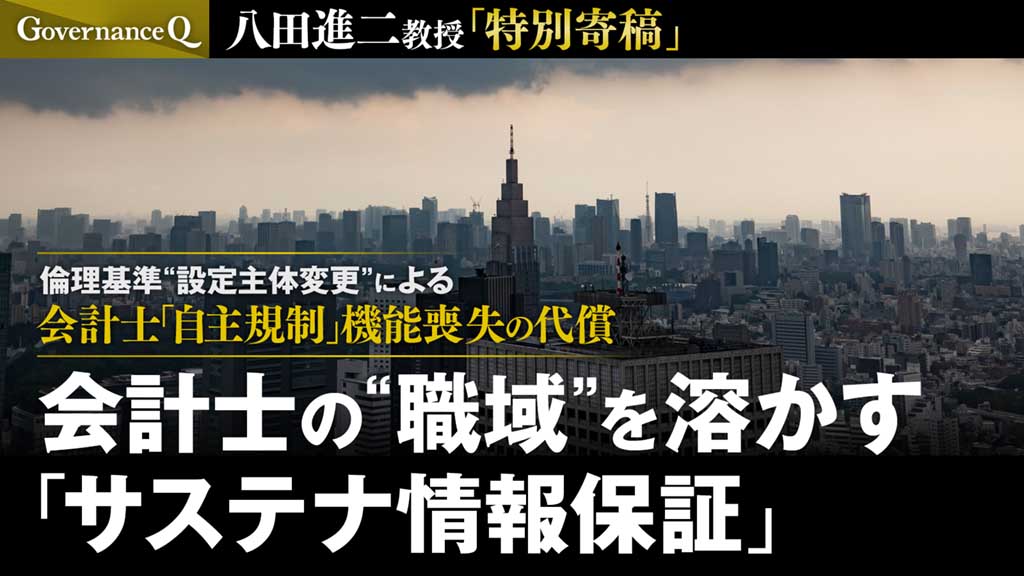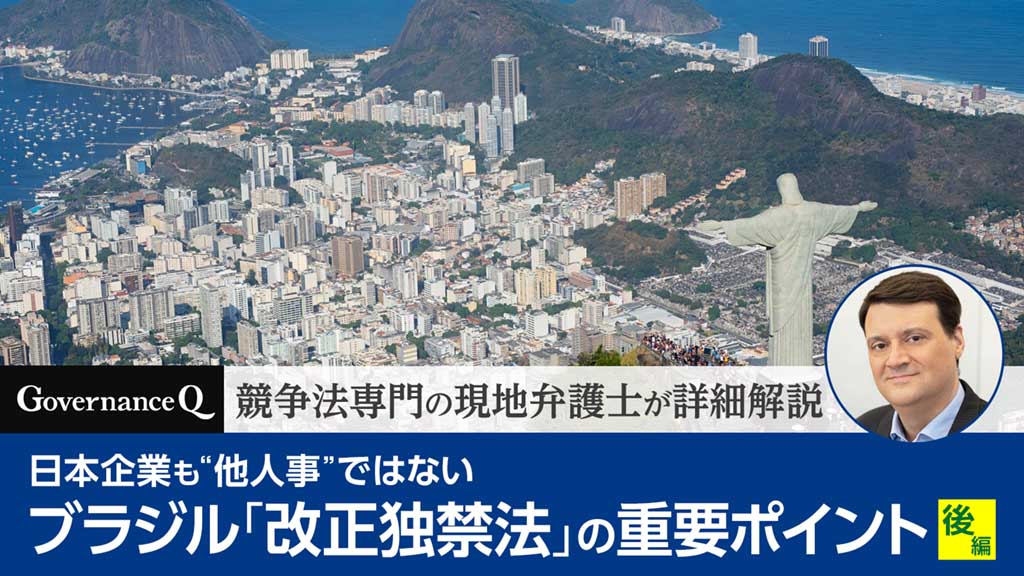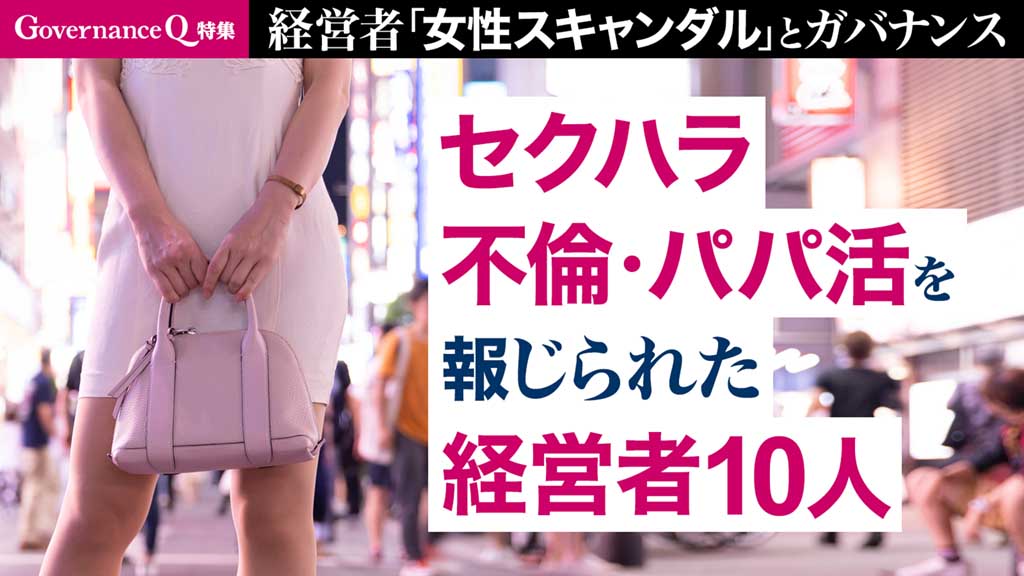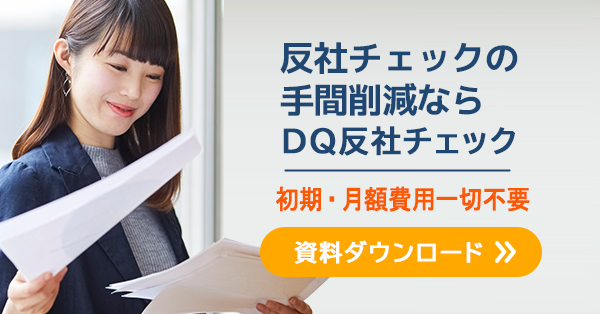【子会社ガバナンス#4】加登豊名古屋商科大学教授が語る「子会社業績向上の秘策」
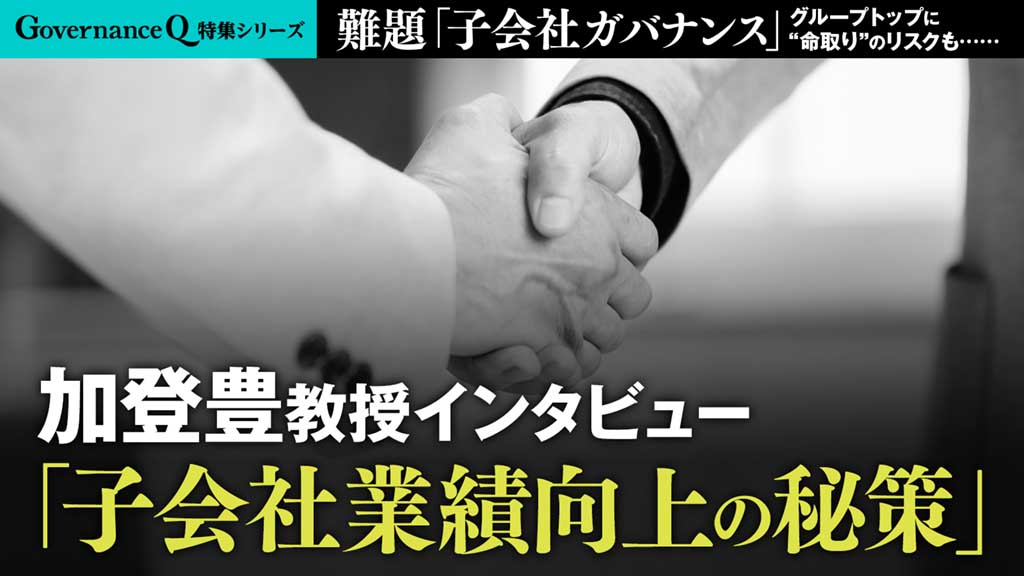
(#3から続く)今回の#4では、経営学者で現在、名古屋商科大学大学院マネジメント研究科で教授を務める加登豊氏をインタビュー。日本の企業グループにおける子会社の地位は低く、そのグループ構造は戦後一貫して変わって来なかったという加登教授。しかし、子会社は大過なく運営されていればいいという時代は終わった今、子会社ガバナンスに求められるものとは……。
「連単倍率」の低い日本の企業グループ
企業が子会社および関連会社(以下、「子会社」と総称)を所有する目的は、本来、子会社が成長して連結業績の向上に貢献してもらうことです。
子会社の貢献度を計る指標が「連単倍率」です。貢献度が高ければ連単倍率は1より大きくなりますが、日本では、上場企業でも1に近い企業がたくさんあり、マイナスの企業まである。総じて、子会社がグループ全体の連結決算に貢献していないのです。
【連単倍率】グループ全体の連結決算に占める親会社の単独決算の割合を表し、売り上げ、純利益等で算出する。例えば連結売り上げが1億円、単独売り上げが8000万円の場合は1.25。子会社・関連会社群の売り上げが大きいほど数値は大きくなり、貢献度が高いことになる。
子会社の成長を促す施策はいろいろありますが、そもそも、子会社のガバナンスを機能させることは大変難しい。親会社は支配権を持っていますが、管理が過ぎれば子会社は委縮し、自由を失って成長が阻まれます。しかし放任すれば、子会社は勝手なことをして、時として不祥事の発生につながりかねません。また、親会社と子会社の利益が相反する場合もあり、ガバナンスの観点から、親会社の子会社に対する経営介入については慎重な対応が求められます。
ひとつ、例を挙げましょう。
ある非上場企業A社が、旧財閥系企業B社を買収しました。A社の買収は、B社が持つ技術の獲得を目的としたものでした。技術は製品化途上にあり、いわば“先物買い”です。
A社は買収を決めた時、B社に対する特段の介入は考えていませんでした。買収後、B社は価値のある技術を製品化して、業績が上がると想定していたのです。しかしB社は旧財閥系でプライドが高く、買収されたという意識は芽生えませんでした。社名も変更せず、業績向上に向けた自発的な努力も行わなかったのです。買収後2年が過ぎても変わらず、A社は、テコ入れを検討せざるを得なくなりました。とはいえ、テコ入れの程度や方法如何ではB社の反発を招いて人材が流出するリスクもあり、簡単ではなかったそうです。
日本企業では成功しなかった「シェアードサービス」
近年、日本の企業が導入した制度や仕組みの是非も、改めて検討するべきでしょう。
子会社の問題で言えば、かつて持て囃された「シェアードサービス」事業が挙げられます。各グループ企業に点在する管理部門やIT部門を1つの子会社に集約して、効率を高めるとともに、専門家集団としてグループ外の取引を増やし、連結業績に貢献しようという構想です。
これは米ゼネラル・エレクトリック(GE)が経理部門の合理化を図るために導入したと言われていますが、日本では成功しませんでした。
理由のひとつは、人員削減が容易ではなかったこと。グループ10社が各管理部門に10人ずつスタッフを抱えていた場合、1つの子会社に集約すると100人になります。当然、そのままでは効率化が図れないため、業務が重複する人員を整理する必要が発生します。しかし日本ではリストラが難しく、効率化が図れませんでした。
もうひとつは、社員のモチベーション低下です。親会社に入社してIT部門に配属されたのに、シェアードサービスのために、新設された「情報サービス子会社」に移籍されたうえ、給料も下がる。移籍した社員のモチベーションは下がります。
原因は他にもありますが、シェアードサービスが日本で失敗したのは、子会社の成長を本気で考えたのではなく、親会社の単体発想による経費削減策でしかなかったからです。
“失われた30年”の間に、日本の企業が導入した制度や仕組みの多くは、低迷をさらに長期化させたものが少なくありません。シェアードサービスのように、欧米から輸入した制度や仕組みは大変多く、日本の企業に合わなかったという面があります。それを含めて、子会社の問題であれば、真に成長を促すものなのか、検討し直すべきでしょう。
ピックアップ
-
 【会計士「自主規制」機能喪失#2】監督当局の手に落ちた”会計プロフェッション”の倫理基準…
【会計士「自主規制」機能喪失#2】監督当局の手に落ちた”会計プロフェッション”の倫理基準…(#1から続く)会計士を“閉鎖的社会における専門家集団”のように扱い、プロフェッションとしての自主規制を有名無実化させようとする国際会計士倫…
-
 【会計士「自主規制」機能喪失#1】会計士の“職域”を溶かす「サステナ情報保証」という外圧…
【会計士「自主規制」機能喪失#1】会計士の“職域”を溶かす「サステナ情報保証」という外圧…《過度な節税指南に待った 会計士倫理の国際組織が新基準 議長「企業の評判にリスク」》――。日本経済新聞(6月27日付朝刊)にこんなタイトルの…
-
 ブラジル「改正独禁法」解説《後編》現地弁護士が教える改正のポイント…
ブラジル「改正独禁法」解説《後編》現地弁護士が教える改正のポイント…レオポルド・パゴット(Leopoldo Pagotto):弁護士(ブラジル在住) (前編から続く)ブラジルにおける競争法の最新事情について、…
-
 【経営者と女性スキャンダル#5】醜聞が明るみに出た“マル恥”企業トップ10人…
【経営者と女性スキャンダル#5】醜聞が明るみに出た“マル恥”企業トップ10人…(特集#1、#2、#3、#4から続く)「愛人を持つことは男の甲斐性」などと言われた時代もあったようだが、いまやそれは大昔の話。「コーポレート…
-
 今さらの「政策保有株削減」に経営改革は期待できるか【ガバナンス時評#19】…
今さらの「政策保有株削減」に経営改革は期待できるか【ガバナンス時評#19】…八田進二:青山学院大学名誉教授 3月末までに開示された東証プライム上場企業のコーポレートガバナンス報告書を集計したあずさ監査法人によると、プ…
-
 ブラジル「改正独禁法」解説《前編》現地弁護士が教える改正のポイント…
ブラジル「改正独禁法」解説《前編》現地弁護士が教える改正のポイント…レオポルド・パゴット(Leopoldo Pagotto):弁護士(ブラジル在住) 今回は、ブラジルにおける競争法の最新事情をお伝えしたい。著…