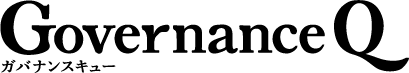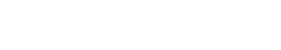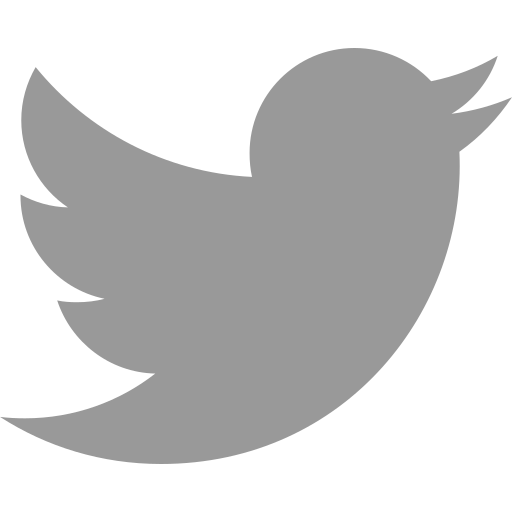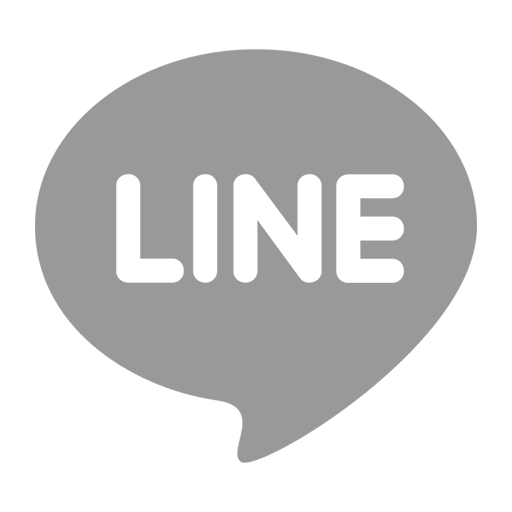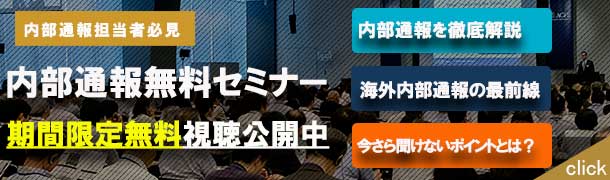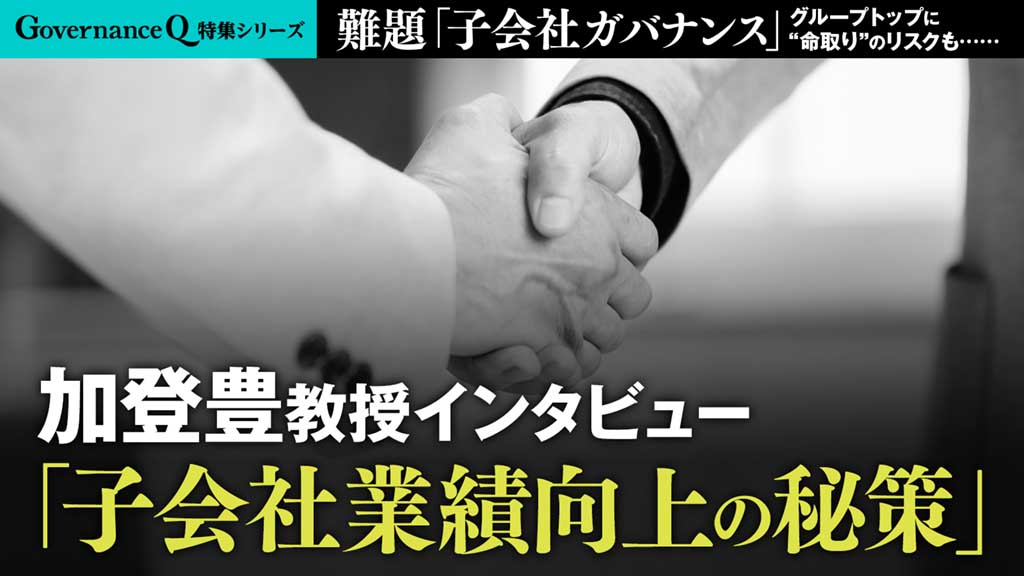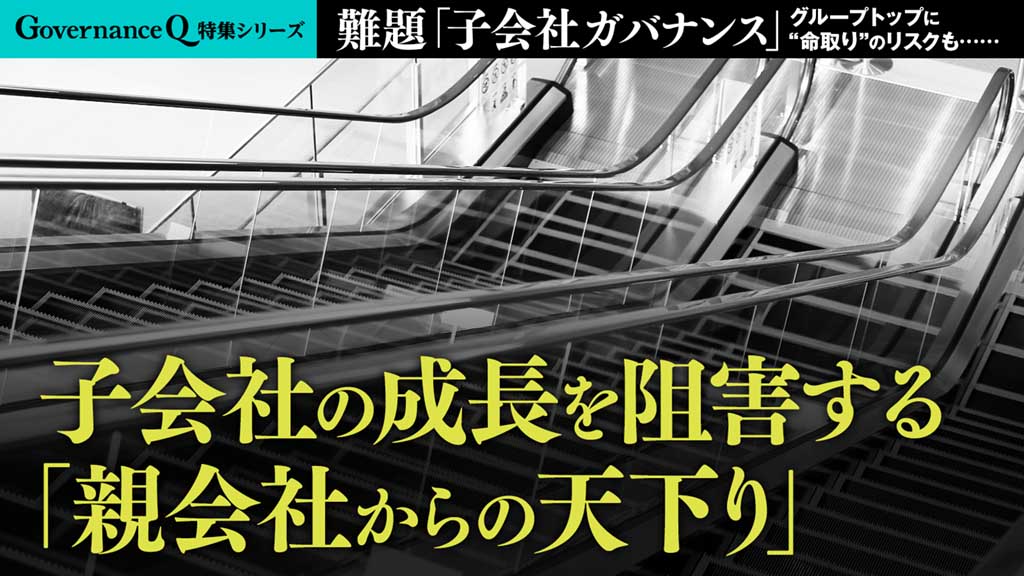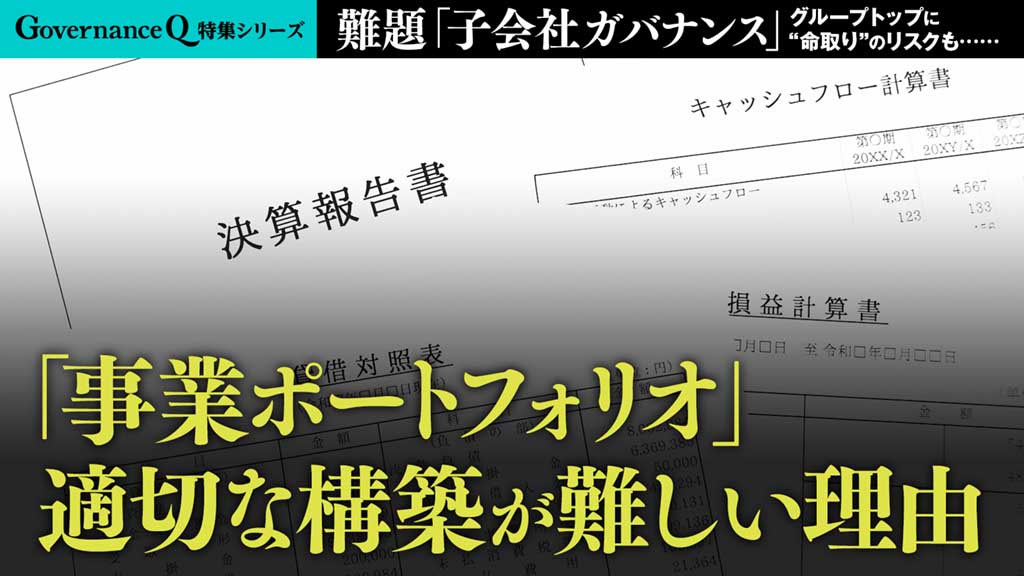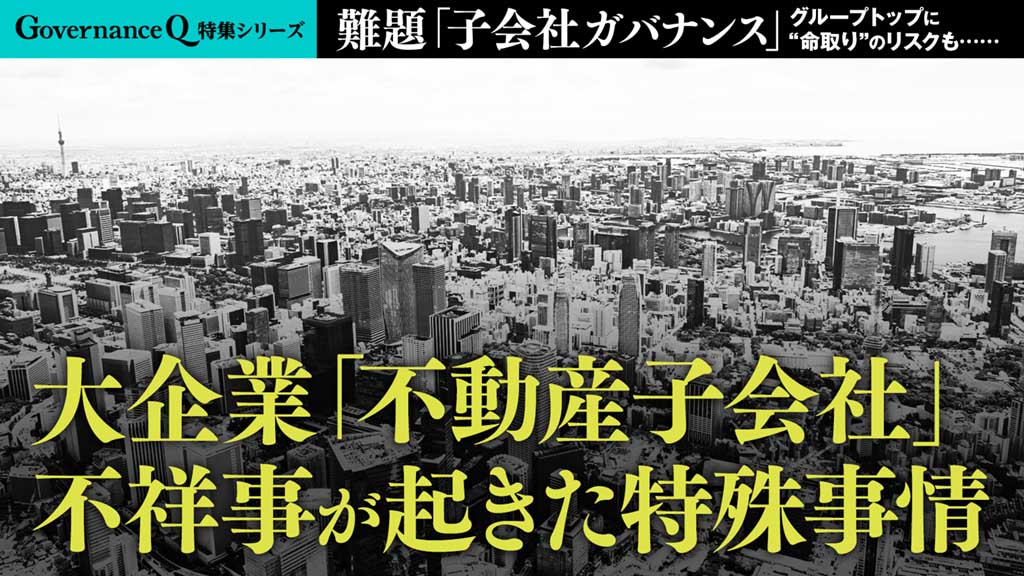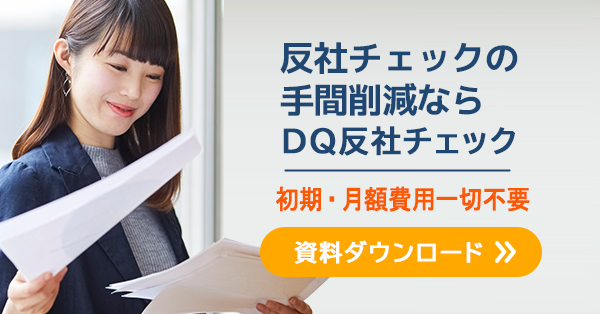第4回【佐藤隆文×八田進二#4】会社と経営者に求められる“4つの力”とインテグリティ

(第4回#3から続く)プロフェッショナル会計学が専門でガバナンス界の論客、八田進二・青山学院大学名誉教授が各界の注目人物とガバナンスをテーマに縦横無尽に語る大型対談連載。シリーズ第4回のゲストは金融庁長官、そして東京証券取引所自主規制法人(現・日本取引所自主規制法人)理事長を務めた佐藤隆文氏。最終回の#4記事では、多様化する企業不祥事をタイプ別に整理すると同時に、いかに不祥事と立ち向かうか、経営者、そして会社そのものに求められる“力”を示す。
多様化する「ガバナンス不全」と「企業不祥事」
八田進二 (#3から続く)ところで、ひと口に「ガバナンス」というと、かつては上場会社の問題として議論されていましたが、近年は非営利組織、公益法人、学校法人、地方公共団体など、ありとあらゆる組織の問題として議論されるようになりました。不祥事の定義も多様化しています。犯罪行為や法令違反だけでなく、社会的ないし倫理的に批判を浴びるような行為も今や不祥事の範疇です。
佐藤隆文 本当にそうですね。上場会社だけで見ても、現象面での類型、原因やメカニズム、検証の方法など、いずれも非常に多様化していると感じます。
たとえば現象面で言うと、検査偽装や検査データの改竄、製品の性能偽装、欠陥製品の出荷とか、横浜の傾斜マンション問題(2015年)や北海道・札幌のビルでの鉄骨の精度不良問題(2023年3月)も含めて、広い意味での製造現場で起こる不祥事。このほか、粉飾決算や不正会計、代金の水増し請求、不正な資金の授受、横領、会社経費の私的流用といったお金まわりの不祥事。社会ルール違反ですと、競争入札における談合とか、優越的地位の濫用、著作権侵害、個人情報の流出、反社会的勢力対応のぬるさ、劣悪な労働環境の放置や海外子会社の管理不行き届き、などがある。インサイダー取引や相場操縦は、市場ルール違反とお金まわりの不正が重なります。
多種多様な形態の現象が起きるのは、さまざまな要素が複雑に絡み合ってのことではあるのですが、ガバナンスの構造に着目してみると、ざっくり言って、内部統制の欠落、資質に欠けるのに強大な権力を持つトップの存在、それゆえに生まれる取り巻きのイエスマンたちの跋扈、あるいは強大な権力者はいない代わりに、現場重視という美名のもとに経営層が経営管理能力を発揮することを放棄していたり、現場の各部署の主張を調整する統轄機能がなかったりと……さまざまなパターンがありますね。

八田 ご指摘のような多種多様な不祥事や会社ぐるみの不祥事がある一方で、経営者が全く事態を把握していなかったというケースもよくありますね。
佐藤 そのあたりは経営者と現場との間の認識のズレ、価値観のズレという括りで整理できると思いますね。一番恥ずかしいのは、経営者自身が自分の会社の事業実態をよくわかっていないというケースです。現場の実態が経営陣に伝わらず情報の目詰まりが起きているのに、社長は上手く行っていると思い込んでいる事例が見受けられます。また、近年のビジネスでは、委託・受託、元請け・下請け、アウトソーシングといった重層的な責任移転と契約関係で事業が成り立っている事業運営が増えています。この場合、経営中枢がその実態を把握できていないと、それぞれのプレーヤーが責任範囲を自分の直接の契約関係までにとどめ安易に限定してしまう。結果として最終顧客への配慮に思いが至らない、サプライチェーンの一角で起きた問題を「他人事」と位置づけてしまうというパターンがあるでしょう。
八田 “結論ありき”で起こる不祥事もありますね。
佐藤 おっしゃるとおりです。実現したい結果を先に決めて目の前にある事実を軽視するのですから、発想が完全に転倒してしまっている。製造業で相次いだ検査偽装・データ改竄もそうですし、経営層が主導する粉飾決算などもその典型です。
八田 製品の納期順守のために検査データを改竄するというのも、転倒した発想の最たるものですね。
佐藤 その点で言うと、不祥事企業においては「優先順位の取り違え」という共通要因も頻繁に見受けられますよね。目の前のディールを実現したいから必要なリーガルチェックや品質検査を省くなんていうのは、その例ですね。もっとも、リーガルチェックや品質検査の手続きを踏みつつも形式だけでいい加減にやっていると、不可侵のボーダーラインを無自覚なうちに超えてしまうということが起きます。
八田 受注最優先で談合をしたり、反社に毅然とした対応をしないで済ませようとしたりするのもそうですね。経営者の説明責任からの逃避というのもあるでしょう。
佐藤 不祥事を、ひとつ別の次元から見ると、アカウンタビリティ(説明責任)の欠落、という特徴で共通しているような気がします。経営者に分析能力、実態把握能力、説明能力がないために、対外向けの説明から逃れようとして、結果的に不正や隠蔽を重ねてしまう。説明責任を意識した緊張感ある業務運営からの乖離ですね。同時に、会社を構成する従業員レベルでも、事なかれ主義と保身のために見て見ぬふりをするという誘惑が働くケースはなお多いでしょう。会社の中で命じられた自分の仕事だけこなしていればいい、平穏な日常が最優先だ、という意識が蔓延してしまうと、内部通報制度ができていても実効的に機能することは難しくなるでしょう。
ピックアップ
-
 【子会社ガバナンス#4】加登豊名古屋商科大学教授が語る「子会社業績向上の秘策」…
【子会社ガバナンス#4】加登豊名古屋商科大学教授が語る「子会社業績向上の秘策」…(#3から続く)今回の#4では、経営学者で現在、名古屋商科大学大学院マネジメント研究科で教授を務める加登豊氏をインタビュー。日本の企業グルー…
-
 【子会社ガバナンス#3】「親会社からの天下り」人事が子会社の成長を阻害する…
【子会社ガバナンス#3】「親会社からの天下り」人事が子会社の成長を阻害する…#1、#2では実例を引き合いに出して、子会社のコーポレートガバナンスが機能不全に陥り、ひいてはグループ全体のガバナンスを阻害しかねない状況を…
-
 【子会社ガバナンス#2】適切な事業ポートフォリオの構築が難しい理由…
【子会社ガバナンス#2】適切な事業ポートフォリオの構築が難しい理由…#1では大手企業の不動産子会社を例に、子会社のガバナンス不全があわや不祥事を生み出しかねない危険性を伝えた。続く#2では、新設子会社、あるい…
-
 【子会社ガバナンス#1】大企業の「不動産子会社」で不祥事が起きた背景…
【子会社ガバナンス#1】大企業の「不動産子会社」で不祥事が起きた背景…子会社・関連会社までを含めたグループ全体のコーポレートガバナンスが求められる大手企業。一方、大手企業グループには必ずと言っていいほど、不動産…
-
 「リスク情報収集」を自動化する最適なネット検索ツールとは…
「リスク情報収集」を自動化する最適なネット検索ツールとは…(前編から続く)リスク情報の収集には、時として正確性よりもスピードが求められる。その際、ネット上の情報をいかに集めるかが、勝負の分かれ目とな…
-
 企業担当者を悩ます「リスク情報収集」の死角…
企業担当者を悩ます「リスク情報収集」の死角…「仕事とはいえ、パソコンに向かい合ってネット上で関係先のリスク情報をチェックするのは、身心ともに疲れ果ててしまう」――。あるメーカーで与信管…