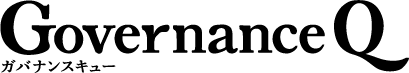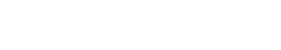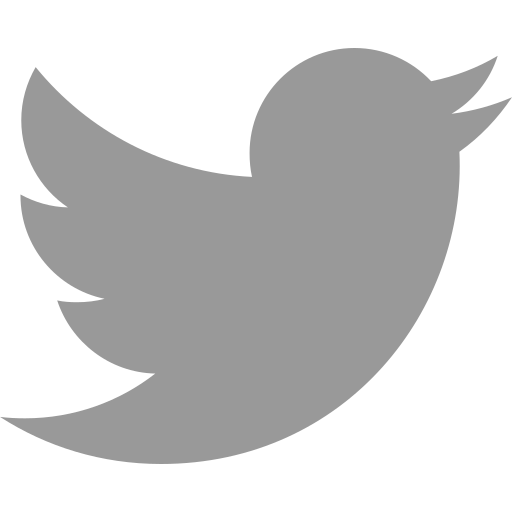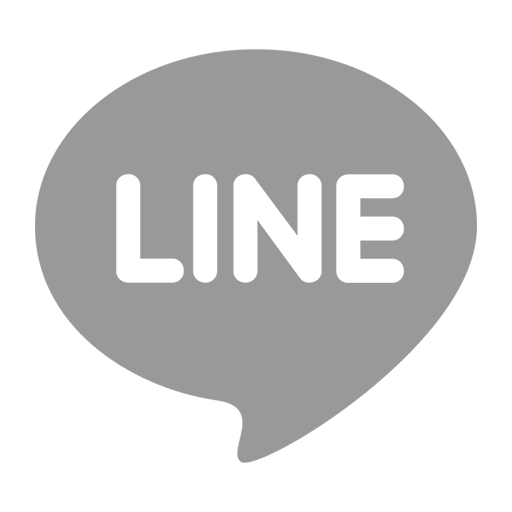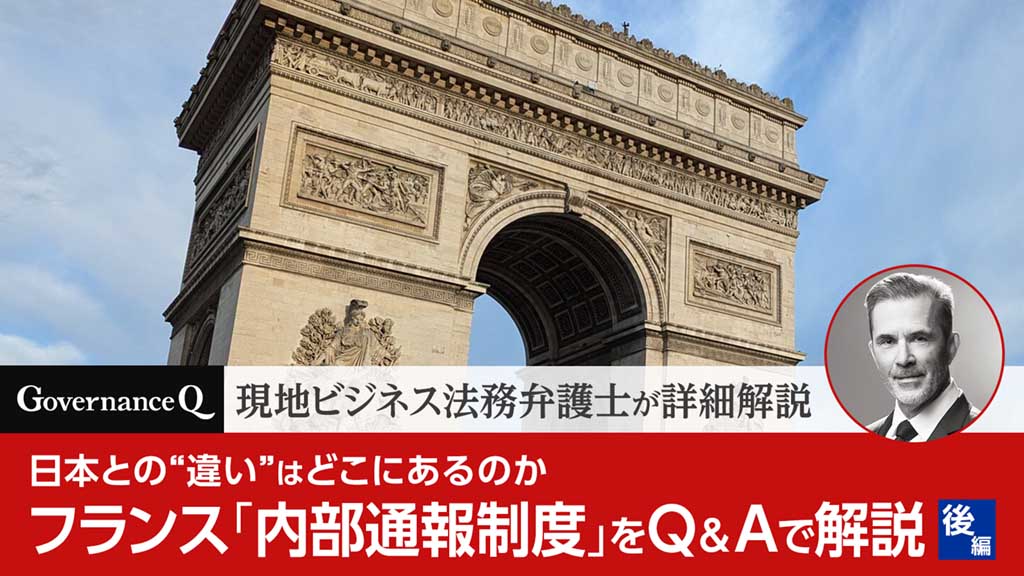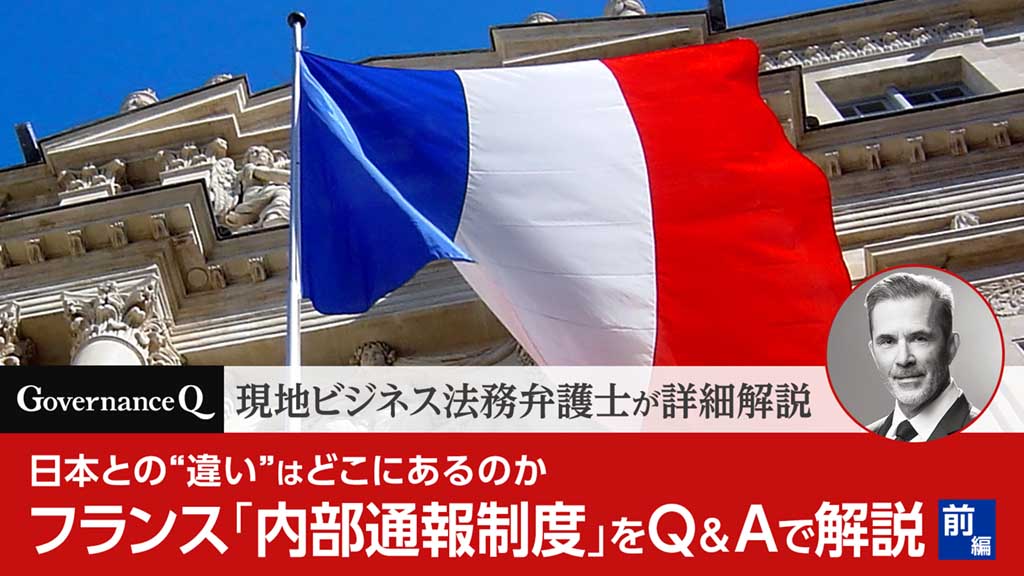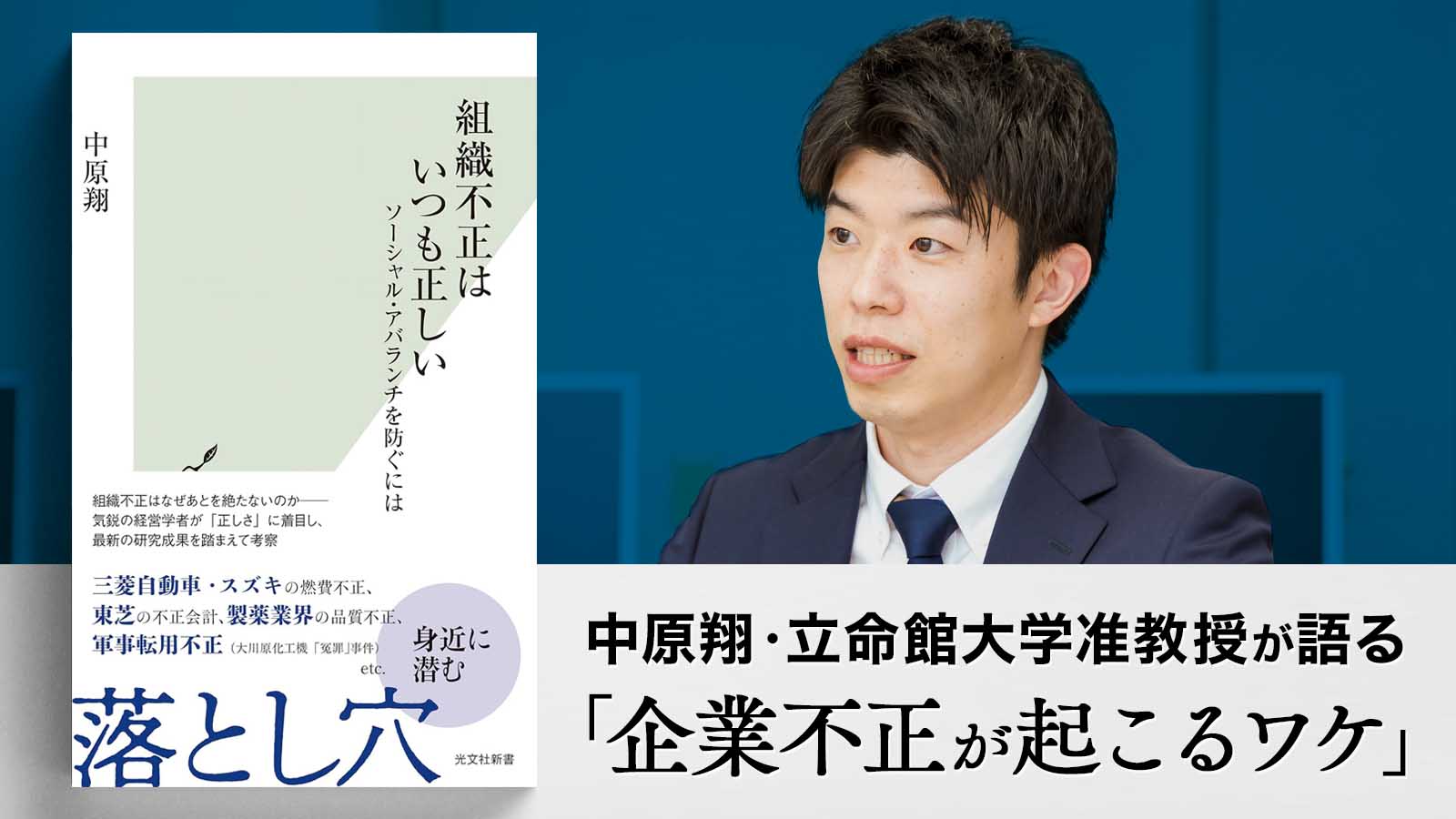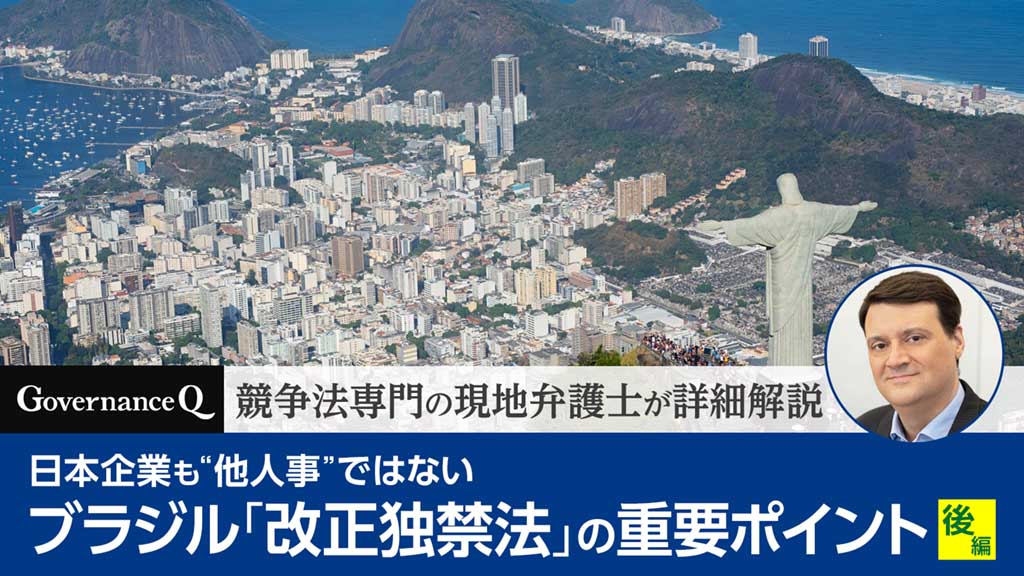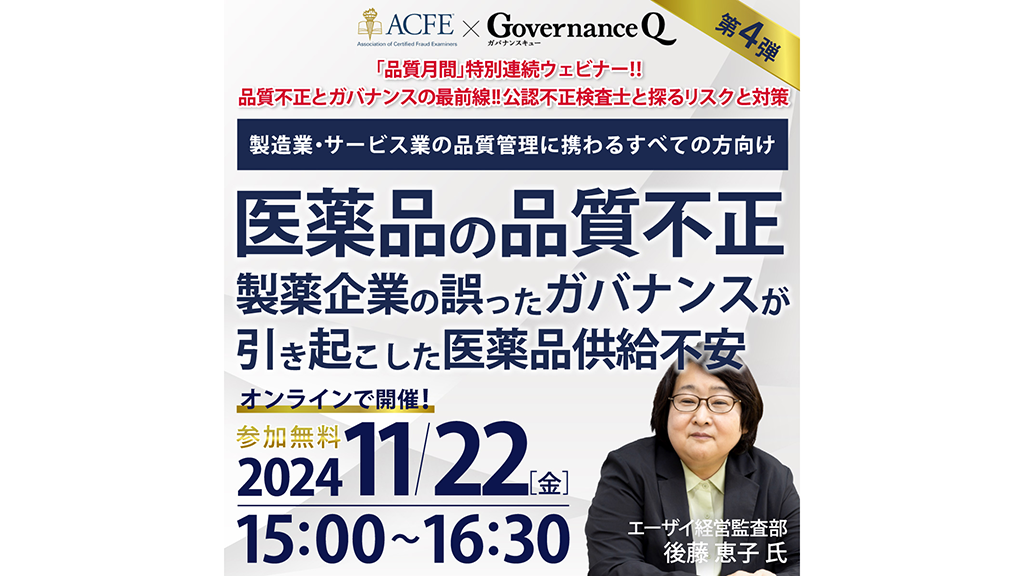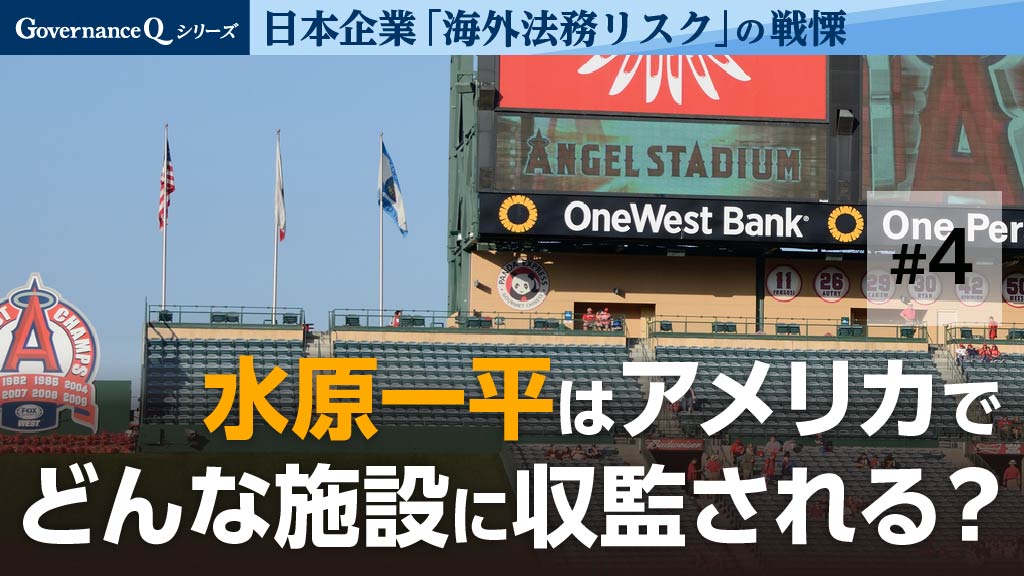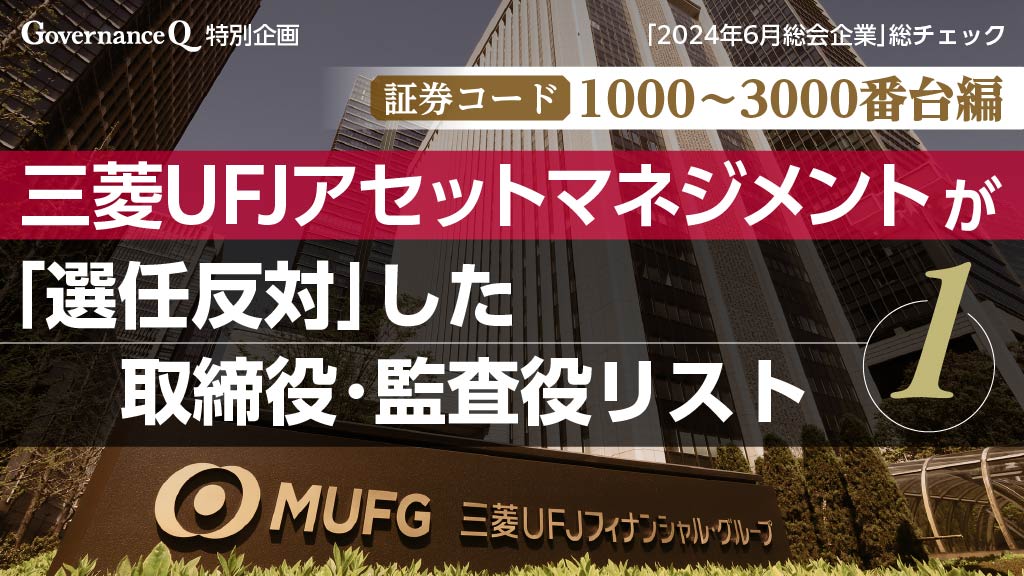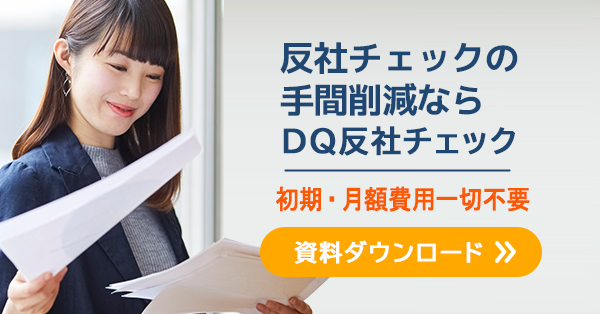日本企業“基本給が増えない”驚愕の根拠―「福利厚生、充実しています」の甘い罠
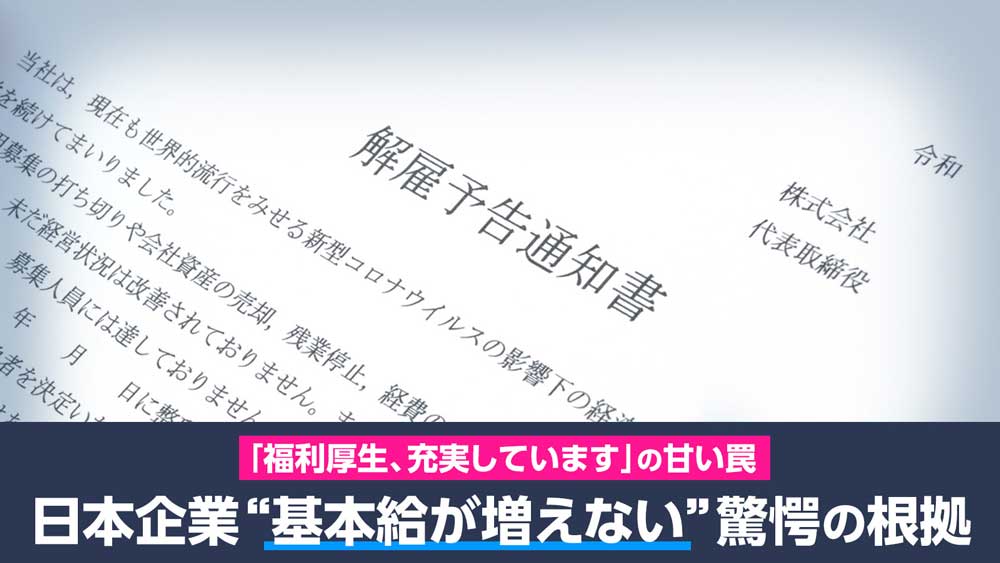
従業員が会社と定めたルールのもとで、そのルールに則って働くことは、高次のコーポレートガバナンスを云々する以前に、企業経営の基本中の基本である。しかし、こと、従業員が退社する段になると、こうした企業経営の基本に綻びが現れることになる。
不祥事の発覚が相次ぐ中古車販売大手のビッグモーターでは、『日刊自動車新聞』などによると、今年2023年1~3月末のわずか3カ月の間で全社員5000人超に対し、約1000人が退社したことが判明している。大量退職の舞台裏で、個々にどのような遣り取りがあったのかは不明ながら、各人なりに壮絶なものがあったことは想像に難くない。
ただ、ひとつ言えることは、コーポレートガバナンスの機能が回復し得ない企業については、従業員は「退職」するという形でしか、意思表示の余地がないということの証左でもあるということだ。
アメリカ流「at-will雇用」がない日本の労働市場
そうした退職の一形態に「解雇」がある。もっとも、日本にもアメリカにも、雇用を維持し労働者を守るルールが存在している。そして、日米両国ともに、企業の存続なくして労働者の雇用を守れないことから、一定条件のもとに解雇することも認められている。しかし、労働市場の柔軟性を重視し解雇ルールが明確に定められているアメリカに対して、日本は長期的な雇用関係を重視し、労働者の雇用安定を保障しようとしてきた。
アメリカの労働法では、「at-will(アットウィル)雇用」(随意雇用)と呼ばれる制度があり、これは特定の契約に基づかない限り、企業は事前通知なしに従業員を解雇することが可能であり、同様に従業員も自由に退職することが出来る。どちらかが契約を終了させたいと通知すれば、at will契約ということで、いつでも任意のタイミングで契約を終了させることになる。ただし例外があり、一部の従業員は特定の条件下でのみ解雇が可能な雇用契約を結んでいることがあったり、大規模なリストラを行う企業は、従業員に対して予告期間を設けるか、またはその期間分の給与を支払うことが求められることがある。
アメリカと比較して日本では、従業員を自由に解雇することは出来ない。労働契約法第16条に基づき、解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者を辞めさせることは出来ないのだ。
ピックアップ
-
 【11/22(金)15時 無料ウェビナー】医薬品の品質不正《品質不正とガバナンスの最前線・連続ウェビ…
【11/22(金)15時 無料ウェビナー】医薬品の品質不正《品質不正とガバナンスの最前線・連続ウェビ…本誌「Governance Q」と日本公認不正検査士協会(ACFE JAPAN)共催無料連続ウェビナー「品質不正とガバナンスの最前線:公認不…
-
 【2024年10月21日「適時開示ピックアップ」】エスポア、ハワイアンズ、ホープ、ペイクラウド、TB…
【2024年10月21日「適時開示ピックアップ」】エスポア、ハワイアンズ、ホープ、ペイクラウド、TB…週明け10月21日月曜日の東京株式市場は反落した。前日から27円安い3万8954円で引けた。大きな取引材料がなかったものとみられる。21日の…
-
 大谷翔平を嵌めた「水原一平」はアメリカでどんな施設に収監される?【海外法務リスク#4】…
大谷翔平を嵌めた「水原一平」はアメリカでどんな施設に収監される?【海外法務リスク#4】…有吉功一:ジャーナリスト、元時事通信社記者 (前回までの記事はこちらから)米メジャーリーグ、大谷翔平選手の専属通訳を務めた水原一平氏(39)…
-
 三菱UFJアセットマネジメントが「選任反対」した取締役・監査役リスト#1《1000~3000番台企業…
三菱UFJアセットマネジメントが「選任反対」した取締役・監査役リスト#1《1000~3000番台企業…後藤逸郎:ジャーナリスト + Governance Q特集班 上場企業のコーポレートガバナンスへの注目が俄然高まる中、機関投資家が株主総会で…
-
 King Gnuの「IKAROS」と、経営判断原則の要諦【遠藤元一弁護士の「ガバンス&ロー」#3】…
King Gnuの「IKAROS」と、経営判断原則の要諦【遠藤元一弁護士の「ガバンス&ロー」#3】…遠藤元一:弁護士(東京霞ヶ関法律事務所) ギリシャ神話「イカロス」に見る経営者の“勇気”と“傲慢” 2023年11月末にリリースされたKin…
-
 《最終回》米司法省 棄却でも残る「起訴の烙印」を消す“不条理な闘い”【逆転の「国際手配3000日」#…
《最終回》米司法省 棄却でも残る「起訴の烙印」を消す“不条理な闘い”【逆転の「国際手配3000日」#…有吉功一:ジャーナリスト、元時事通信社記者【関連特集】日本企業を襲う「海外法務リスク」の戦慄 はこちら (前回までの記事【米司法省が訴追した…