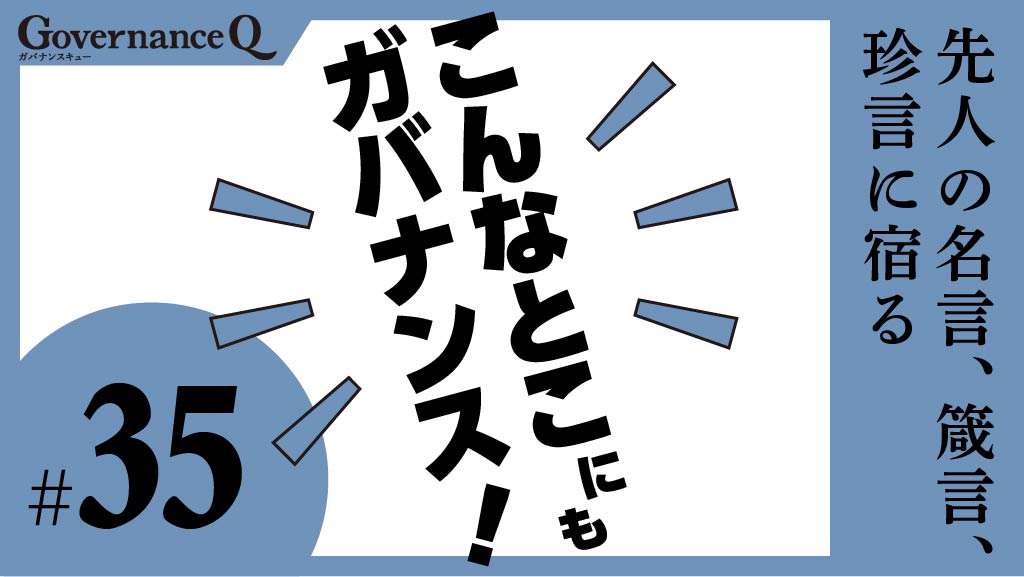栗下直也:コラムニスト
「こんなとこにもガバナンス!」とは(連載概要ページ)
「縁の下の力持ちになることを厭うな。人のためによかれと願う心を常に持てよ」
前島密(まえじま・ひそか、明治時代の官僚)1835~1919年。明治維新後に民部省、大蔵省に勤務。1870年、郵便制度の調査のため渡英し、翌年、帰国後に官営の郵便事業を始めたほか、郵便為替、郵便貯金など郵政3事業の基礎を確立。切手などの用語も定め、「郵便」「切手」などの名称を定めた。明治14年(1881年)の政変で下野し、立憲改進党の結成に参加する。晩年は実業界でも活躍した。
77年間にわたり「1円切手の顔」であり続ける
「官僚的」という言葉がネガティブな意味で使われるになったのはいつからだろうか。「昔の官僚は違った。官僚も経営者マインドを持つべきだ」という声も耳にするが、その際に「昔の官僚」の例として名前が挙がるひとりが「郵便の父」と呼ばれた前島密だろう。
元幕臣だった前島は、明治新政府で民部省の改正掛として大車輪の活躍を見せる。官僚の立場でありながら、起業家精神はそこらの経営者よりも旺盛で、駅制改革や陸・海運の振興、鉄道の計画、新聞事業の育成など、インフラを急ピッチで整備した。そうした中で最大の功績が郵便制度の確立だ。
過疎地にも同一料金で郵送し、切手に信用力を与えるためには官営しかないと判断し、尻込みする政府高官を懸命に説得した。近年はインターネット通販の拡大などで物流の大切さが改めてクローズアップされているが、その基礎を築いたのが前島だった。
郵政事業にとって前島の取り組みがどれほど大きかったかは、前島の写真が使われている1円切手のデザインが物語る。1947年から唯一デザインに変更がない切手である。前島は知名度がありながらもその人物像は浮かびにくい。目立たずとも欠かせない切手のような存在ともいえる。
信頼を失う前に思い出したい前島の言葉
「縁の下の力持ちになることを厭うな。人のためによかれと願う心を常に持てよ」を企業経営で考えると、顧客満足をいかに高めるかに行き着く。あらゆるサービスの原点だ。組織運営がうまくいかなくなっているときは、いつのまにかこの原点を見失っているはずだ。人も組織もいったん失った信頼を回復するのは簡単ではない。
(毎週水曜日連載、#36に続く)