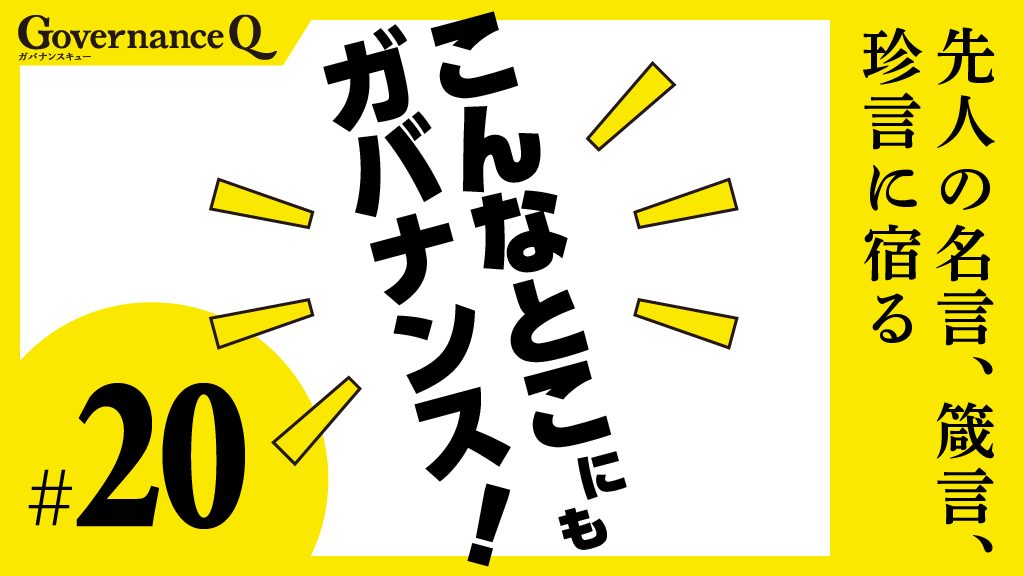栗下直也:コラムニスト
「こんなとこにもガバナンス!」とは(連載概要ページ)
「苦労したと言われるけど、血の小便が出るまで苦労されましたか」
松下幸之助(まつした・こうのすけ、日本の経営者)
1894~1989年。和歌山県に農家の三男として生まれ、尋常小学校を中退して働く。1910年、大阪電灯(現関西電力)に入社。17年、改良ソケットを考案する。18年松下電気器具製作所を創業、35年に松下電器産業(現パナソニック)に改組する。事業部制、連盟店制など独自の経営で「経営の神様」と呼ばれた。
松下電器の命運を分けた「伝説の熱海会談」
1964年、東京オリンピック後の日本経済は景気の過熱に対する金融引き締めで、不況の波に呑み込まれた。家電業界も例外ではなく、松下電器産業(現パナソニック)の販売会社や代理店の多くが赤字経営に苦しんでいた。
この状況を打開するため、会長の松下幸之助は全国の販売会社・代理店の社長たちを熱海に集めた。後に「伝説の熱海会談」と呼ばれるこの会合では激しい議論が交わされた。販売会社や代理店は松下電器の製品が悪いと不満を述べ、松下電器は販売する側の経営が悪いと指摘し、議論は平行線をたどった。
冒頭の言葉は「全財産と全精神を打ち込んで松下製品を売っている。こんなに苦労しているのに、儲からないのは、あなたの責任と違いますか」と追及された時に幸之助が放った一言だ。この言葉は、単なる叱責ではない。覚悟と責任を問う、厳しくも温かい問いかけだった。
お互いにあとがなかった。幸之助は何時間かけても話し合おうと決めていた。
会合は予定の2日間では収まらず、3日目まで延長された。それでも苦情は止まらなかった。松下への不満が噴出し続けた。
幸之助が認めた「松下電器が悪かった」
これらの批判に真摯に耳を傾けたていた幸之助は壇上に立ち、驚くべき発言をした。
「結局は松下電器が悪かった。この一語に尽きると思います」
と、自社の責任を認めたのだ。さらに、30年前に電球事業で苦労した思い出を語り、販売会社への感謝の念を示した。 幸之助の率直な謝罪と感謝の言葉は会場の攻撃的な空気を一変させた。会場の半数以上がハンカチで目を拭いていた。
熱海会談は代理店網との一体感を生み出した場としてパナソニックの社史に名を残すが、何か特別な一手を打ったわけではない。対話の場を設けて、相手の立場になって耳を傾ける。非があればトップ自ら非を認め、謝罪する勇気を持つ。そうした経営者としての現場主義が信頼関係を強固にした。
ちなみに、幸之助は熱海の会合前日に会場で入念に設営をチェックした。すべての参会者の顔がしっかり見えるように椅子を少しずつずらさせたという。そうした細やかな心配りが、熱海会談を“伝説”に昇華させたのかもしれない。
(月・水・金連載、#21に続く)