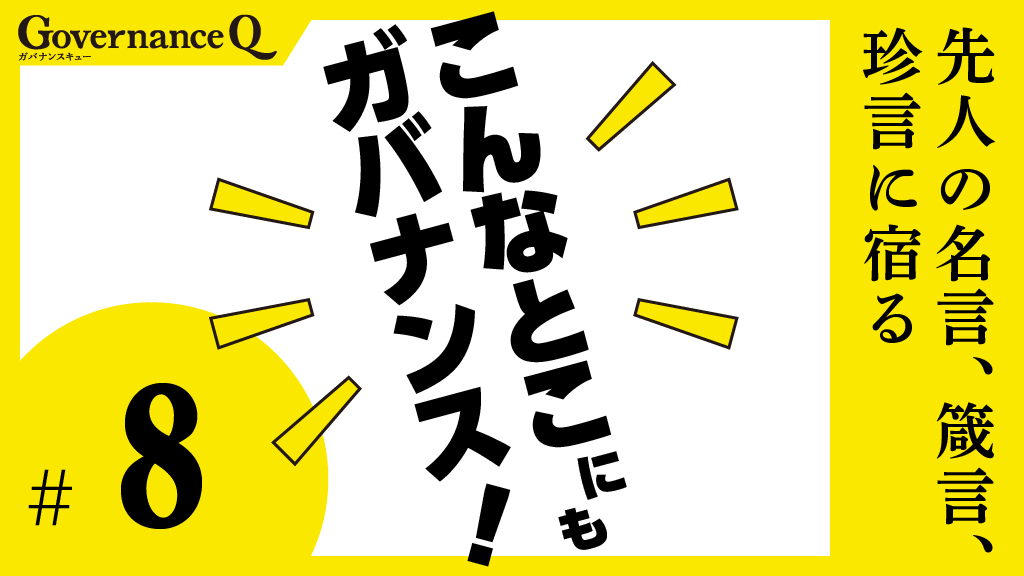栗下直也:コラムニスト
「こんなとこにもガバナンス!」とは(連載概要ページ)
「人はただ自分のしたいことをしないで、嫌だと思うことをすれば、身をもつことができる」
武田信玄(たけだ・しんげん、戦国時代の武将)
1521~1573年。武田信虎の長男。父を駿府(静岡市)の今川氏のもとへ追放して甲斐(山梨県)の国主となる。信濃(長野県)の諏訪、伊那などを攻略し、川中島で越後(新潟県)の上杉謙信と数度にわたって戦った「川中島の合戦」は広く知られる。駿河(静岡県)をも支配し、北条氏と和議を結んだのち1572年に京都を目指して軍を進める。徳川家康を三方原(浜松市)で破るが、翌年、病没した。幼名は勝千代、名は晴信。
「悪い結果には必ず原因がある」戦国最強武将の考え方
武田信玄は誰もが知る武将のひとりだろう。「戦国最強」とも呼ばれ、「戦の天才」の上杉謙信と互角に戦い、織田信長も正面衝突を避け続けた。
なぜそれほど強かったのか。彼の戦に対する思想が詰まった言葉がある。
「まさか負けはすまいと思える戦に負けたり、滅びはしないだろうと思える家が滅びたりするのを、人びとは天命だという。だが、わしは天命だとは思わぬ。それはみな、やり方が悪いためだと思うのだ。つね日ごろのやり方さえよくすれば、負けるはずがなかろう。だから、つねにわが家の作法は猥りがましきことのないように、道理にそむかぬようにと気づかうのである」
戦国時代も現代も「毎日コツコツ積み重ね」が大事
つまり、日頃からやることをひとつずつ、こつこつとやっていれば足元を救われることはないというわけだ。信玄は「万事小さいことからつぎつぎに組み立て、のちには大きなことも成る。逆に大きいことから小さいことへ及ぶというのはしにくいものだ」とも語っている。
そして、小さなことに取り組むにはとにかくズルいことをせずに改めるところを改めてルールをつくって、それを守ればいいという。
冒頭の言葉は、信玄が部下に説いた大名の組織づくりの心得のひとつだ。
いつの時代も組織づくりには奇策は通用しない。規模が大きくなればなるほど、基礎固めが大切になる。こつこつと小さいことから、嫌なことを避けずに取り組むしかない。
(月・水・金連載、#9に続く)