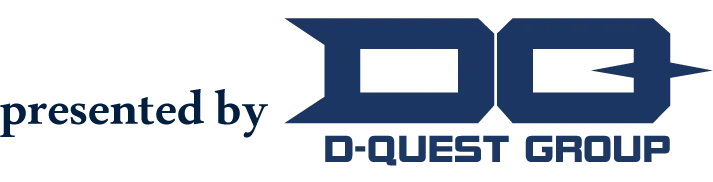プロフェッショナル会計学が専門でガバナンス界の論客、八田進二青山学院大学名誉教授が各界の注目人物とガバナンスをテーマに語り尽くす大型対談連載。記念すべき第1シリーズのゲストは、野村証券副社長、産業再生機構社長、日本取引所グループ(JPX)CEO(最高経営責任者)、そして日本野球機構(NPB)会長を務めた斉藤惇氏。バブル崩壊と金融不祥事、不良債権処理、証券市場改革……平成から令和に至る日本経済激動の時代を駆け抜けた斉藤氏が、八田教授とコーポレートガバナンスの過去・現在・未来を語り尽くす。果たして「ガバナンス敗戦」の先に日本企業、そして日本経済の復活はあるのか――。
アメリカの株価停滞が生んだ「企業価値向上」の発想

八田進二 「ガバナンス」という言葉は、今やありとあらゆる組織や機関で多用されるようになりましたが、先駆的だったのは株式会社におけるコーポレートガバナンスの議論でした。2015年3月に金融庁と東京証券取引所が共同でコーポレートガバナンス・コードの原案を発表しましたが、そのときにリーダーシップをとったのが、ほかならぬ、当時の東証社長であり日本取引所グループのCEOでもあった斉藤さんでした。そこで、この対談シリーズを始めるに際して、どうしても第1回目は斉藤さんにご登場いただきたかったのです。
斉藤惇 それは買い被りだと思いますが、光栄ですね(笑)。
八田 よくガバナンスというと、不正とか不祥事を防止するための仕組みなど、後ろ向きのイメージを持たれがちですが、そもそもの意図は違うんですよね。企業の価値、競争力を高めるための仕組みですから、不正や不祥事の防止はそのうちの一部でしかない。実際、斉藤さんにとってのガバナンスとは何でしょう?
斉藤 実は、私は幸運なことに、ガバナンスという概念がアメリカで現実に適用され始めた瞬間に立ち会っているんですよ。私は野村証券時代、1972年に大阪の堺支店からニューヨーク支店に転勤になりましてね。1979年にいったん帰国し、もう一度1982年から1985年までニューヨークで勤務したので、トータル10年ほどアメリカにいたんですが、私が最初に赴任した当時はちょうどベトナム戦争が終わりかけの頃で、アメリカはけっこう荒んでいたんです。
着任翌年には第1次オイルショック。ダウ平均株価も500ドルから1000ドルくらいの水準を行ったり来たり。一般庶民の感覚としては、新天地を求めてアメリカ大陸にやってきた曾祖父母の頃は貧しかったけれど、親の代はそれなりに豊かな暮らしをしているし、自分たちの生活もまずまず。でも、孫や曾孫の時代になったらどうなんだろうと。ちょうど日本経済が急成長しており、日本企業がアメリカにも進出してきていたので、自分たちの子孫は日本人に使われてるんじゃないか……。そんな不安を漠然と抱えていましたね。そして、みんなの関心事が「年金」でした。
八田 そういえば、当時のアメリカでは年金の運用失敗がかなり表面化していましたね。年金はちゃんともらえるのだろうか、という不安ですか。
斉藤 そうです。米国株は1960年代に急上昇し、オイルショックを境に1970年代は暴落、運用に失敗した運用会社の責任者がブラジルに逃げちゃったり、そもそも詐欺だったなんて話もあったりで。それで連邦議員の中から「年金の運用をもっとしっかりとやらなきゃいけない」という声が上がってくるんです。米労働省も動いて、非常に厳格な年金の運用ルールを作り上げてしまうんですよ。
八田 エリサ法(従業員退職所得保障法、1974年制定)ですね。
斉藤 そうです。企業年金の運用者に対し、委託者のために最善を尽くすことを義務付け、怠ったら罰則を科すという法律です。フィデューシャリー・デューティー、つまり、信任を受けた者が履行すべき義務(受託者責任)という考え方が柱になっていました。

八田 そういうところがアメリカのすごいところですね。
斉藤 私もそう思いますよ。私は運用会社に日本株のセールスに行くのが仕事だったんですが、いつも通っていたモルガン・スタンレー系の運用会社の事務所に行ったら、突然、もぬけの殻になってたんですよ。その運用会社のオフィスは証券会社の事務所の一角を間借りしていたので、モルスタの人にどうしたのか聞いたら、「連中は引っ越した」と。証券会社と運用会社は系列でも同居したらダメという法律ができたからだ、って言うんです。
つまり、運用会社は系列の証券会社に株式の売買を発注するわけですが、壁を隔てて隣接していたら、証券会社に有利な運用をする、不正の温床になる、というわけです。だからエリサ法ができた当初は、運用会社が系列の証券会社に発注できる株式の量も、確か、全体の3分の1程度に制限されていたはずです。
八田 当局から独立性を担保させられたわけですね。当時はカルパース(カリフォルニア州職員退職年金基金)とか、カレッジ・リタイアメント(大学教員の年金基金)でも運用難に陥っていたのではありませんか。
斉藤 米国株が低調でしたからね。そうなると、売買手数料にも厳しい目が向けられるようになるわけで、そこで出てきた発想が「企業価値の向上」です。それまでは値上がりしそうな株に次々と乗り換えていくのが株式運用の王道でした。しかし、それじゃあ、売買手数料が嵩んでしまう。株式市場が好調だったら売買手数料くらいは値上がりの中で吸収できたけれど、株価が上がらなくなったらそうもいかない。さらに取引によるマーケットインパクト問題(自らの売買行動によって生じる取引価格の変動問題)も重大視されだした。そこで、株主は同じ会社の株式を持ったままでも株価が上がるように、経営者に「企業価値を向上させろ」というプレッシャーをかけるようになっていくわけです。
黙って株を買っているだけだった年金が、投資先の企業に対し、経営や戦略についていろいろ注文を付けるようになったのは、運用成績を上げられなくなった年金のファンドマネージャーが企業価値を上げるのに必死になり出したからなんですね。そうなると、経営者をウォッチ、監視するという発想になる。それが「コーポレートガバナンス」という概念の原点だというのが私の理解です。

日本の異様な株主総会とアメリカの“CEOのクビが飛ぶ”株主総会
八田 日本経済新聞の連載「私の履歴書」(2017年10月掲載)に書いておられますが、野村をお辞めになる少し前、経団連のガバナンス視察団の団長として渡米されているんですね。1994年でしたか。
斉藤 そう、1994年です。経団連の中に「コーポレート・ガバナンス委員会」というのが発足しまして、当時、日本興業銀行(現みずほ銀行)の頭取だった黒澤洋さんが委員長で、私が副委員長。「コーポレートガバナンスとは何ぞや?」ということで、アメリカに見に行って来いと。私たち以外はソニーや日立製作所、新日鉄(現日本製鉄)、三菱商事などの法務部の人たちがメンバーで、商事法務がとりまとめ役を買って出てくれまして、主にアメリカの株主総会を見てまわりました。
八田 ずいぶん日本の株主総会とは勝手が違ったんじゃありませんか。
斉藤 ご存知の通り、何しろ当時の日本企業の株主総会は最前列に総会屋が陣取って、野党総会屋が社長に罵声を浴びせたかと思えば、与党総会屋が「異議なし!」と応酬する。そんな異様な雰囲気でしたからね。翻って、アメリカの総会は“お祭り”みたいな祝祭的なムードでしたが、その実、株主の関心は経営者が企業価値を上げているかどうかの一点。企業価値が上がっていなければ、CEOはクビです。
八田 そういえば、名経営者として知られたGM(ゼネラルモーターズ)会長のロジャー・スミスも総会で株主から緊急動議を出されてクビになりましたね。
斉藤 ビッグ3は日本車に陵駕されて業績が悪化していましたから。企業価値の向上といえば、年金はかつては上場企業株しか買ってはいけなかったんですが、規制緩和で未上場株も買えるようになると、西海岸のシリコンバレーの未上場銘柄に年金が資金を入れるようになる。それでIT産業が育ち、年金の運用パフォーマンスも上がっていった。本当にアメリカはすごい国だなとつくづく思いましたね。
八田 斉藤さんは企業人として一番多感な30代にアメリカでそういう貴重な体験をしておられるから、本物のガバナンスが自然と身についている。だからこそ、コーポレートガバナンスをご自身のライフワークだと言えるんですね。私はオリックスの宮内さん(宮内義彦シニアチェアマン、元会長)も、本物のガバナンス論者だと思っています。宮内さんも若い頃にアメリカに留学して本場を見てきているからなのでしょうね。
斉藤 経営に外部の視点を取り入れるということは、企業を鍛え、経済全体のためになる。そう確信するようになったのは、アメリカでの経験ゆえであることは間違いありません。

八田進二教授の「斉藤惇氏との対談を終えて」
「Governance Q」の企画、第1弾で斉藤惇氏をお迎えして、ご自身の体験に基づく先駆的なガバナンス論について、久しぶりに多くの示唆に富むお話を伺うことが出来た。
斉藤氏との出会いは、産業再生機構社長の重責を離れられた直後であり、その後、東京証券取引所社長にご就任後は、わが国の会計・監査制度に関する多くの議論をさせていただきながら、公私ともに大変親しくさせていただいている。いつお会いしても、的を射た厳しいご指摘をされる一方、常に温厚な笑顔を絶やさず、取り巻きの多くの関係者の心を惹きつけてしまう度量の広さに心底、感服するのである。
斉藤氏は、『日本経済新聞』の「私の履歴書」(2017年10月)でも吐露されるように、ご自身が描いたわけでもない人生を変遷されているが、それも「天命である」として受け入れ、常に、時代の節目での重責を担い、かつ、最大の成果を残してこられたのである。そして、その際のキーワードこそ、「コーポ―レートガバナンス改革」であったと捉えることが出来るのである。それは、野村証券時代に、2度にわたる米国での市場関係者との関わりの中で、「投資家保護」を重視する米国市場では、外部の視線を取り入れることで企業は鍛えられ、経済全体のためになるということを実体験で修得されたのである。それこそまさに、今日、わが国で議論の喧しいコーポ―レートガバナンス論の原点に至る課題ともいえるのである。
斉藤氏が「コーポ―レートガバナンスはライフワークと言えるテーマだ」と述べていることからも首肯しうるように、ガバナンス議論には終わりがない。それどころか、社会の変革や時代の変遷、そして国際化の動向等、様々な外部の環境要因も加味しながら、時代を先取りするような洗練されたガバナンス論が展開されていくことが不可欠であることを実感したのである。今回の斉藤氏との対談では、そこでのヒントを提供してくれているのではないだろうか。
読者諸氏には是非とも第2回目以降もご期待いただきたい。