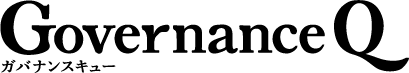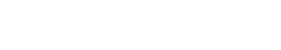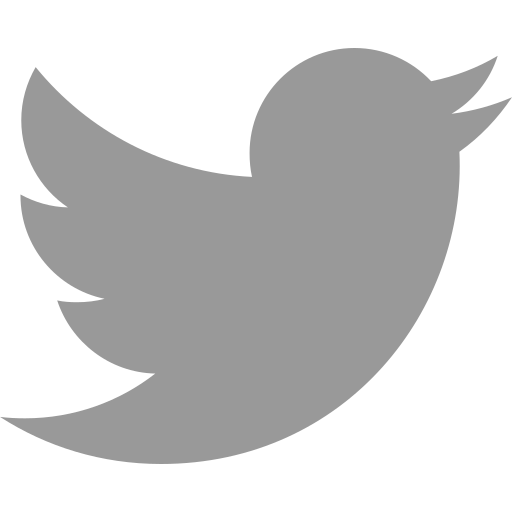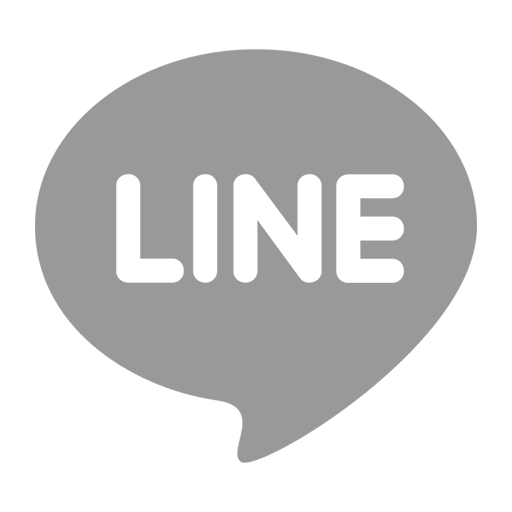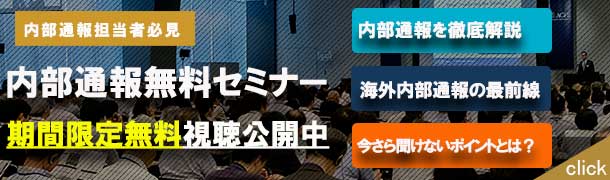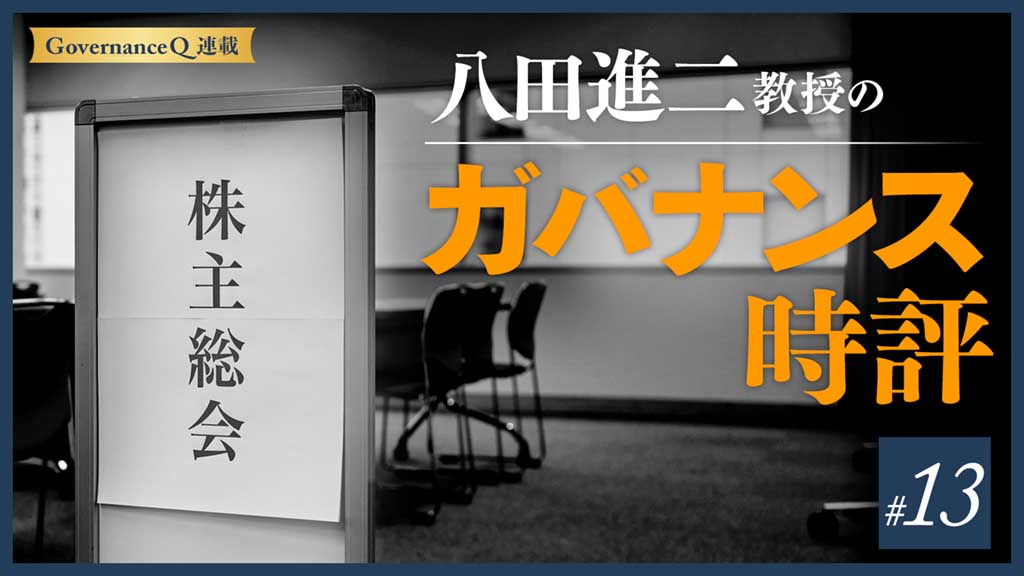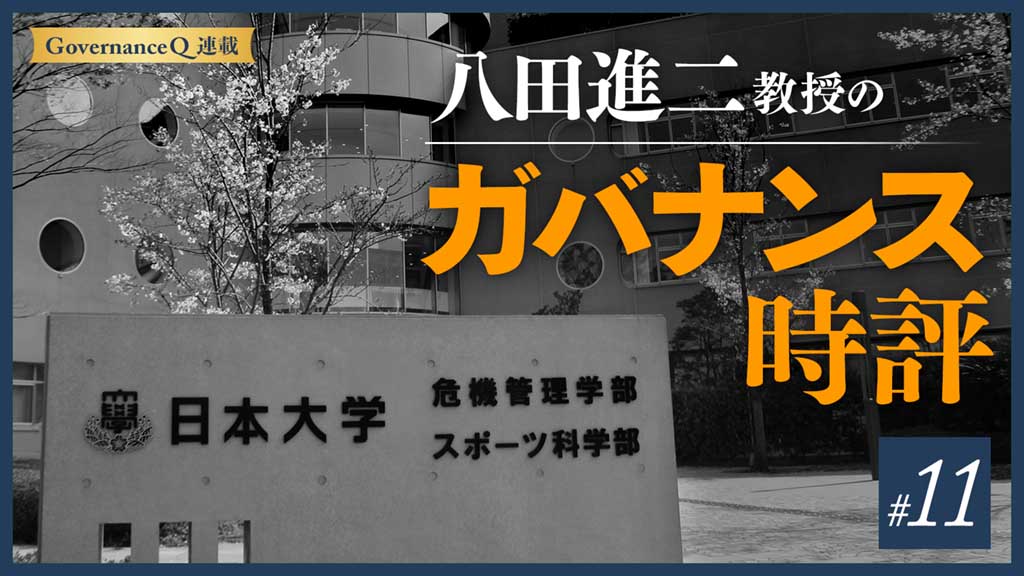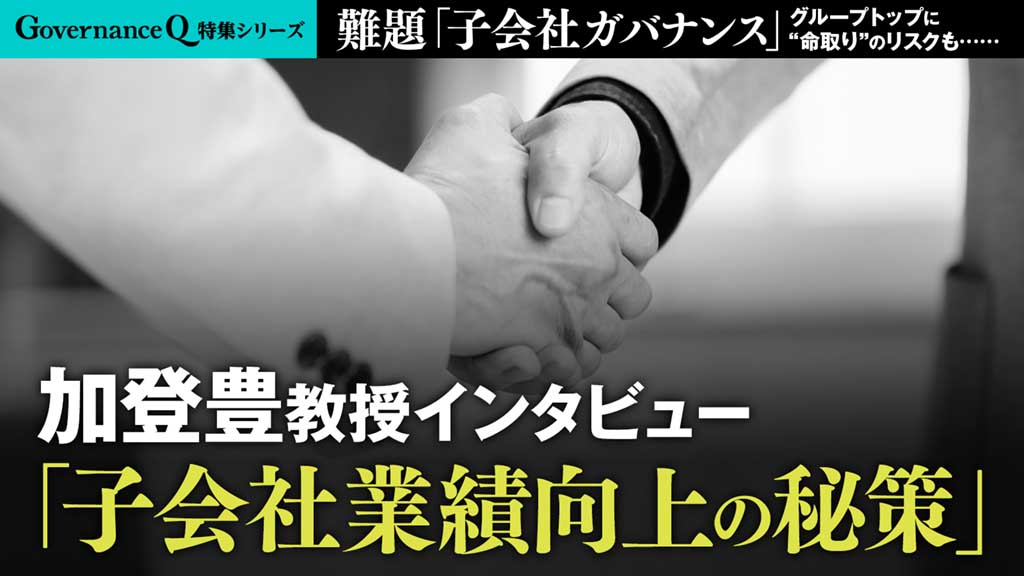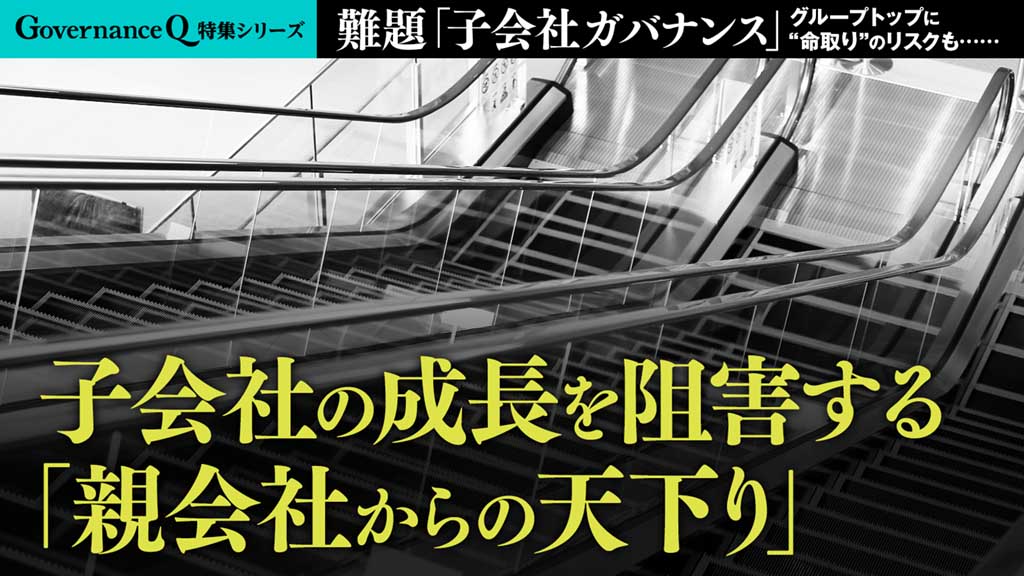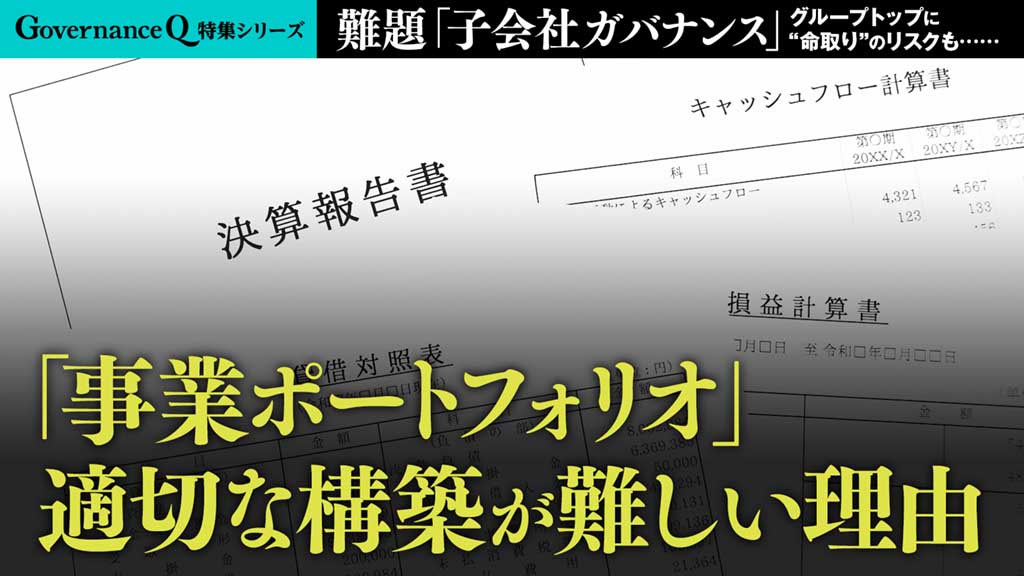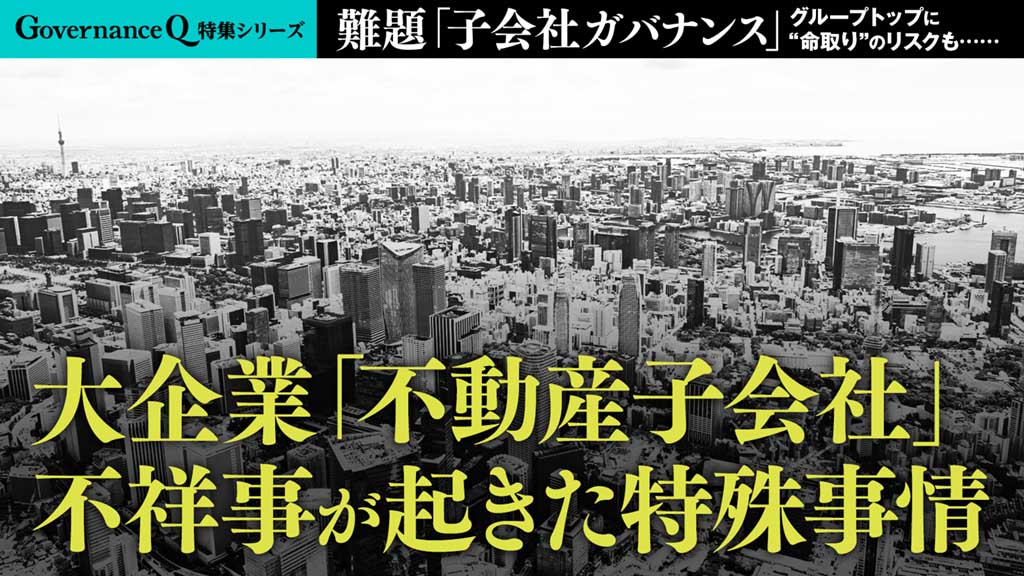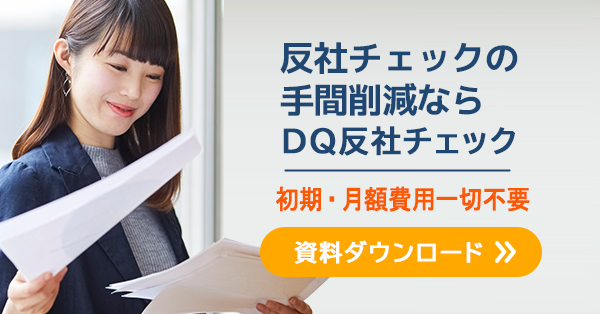なぜ今、ガバナンスを議論しなければならないのか?【ガバナンス時評#1】

自動車保険の保険料水増しなど数々の疑惑が報じられている、中古車販売大手のビッグモーター。コロナワクチン接種業務にかかる委託費の過大請求で社長が辞任に追い込まれた、大手旅行代理店の近畿日本ツーリスト。そして学生の大麻・覚醒剤所持が発覚した超マンモス校の、日本大学……。
この3カ月余りの間でも、企業や大学といった大組織による不祥事が相次いでいる。いずれも記者会見を開き、なぜこうした事態に至ったか、今後、どのように改善していくかなどを責任ある立場の人間が(時に弁解がましく)語っているが、こうした不祥事で必ず問われるのが「ガバナンス」である。
今回、「Governance Q」編集部からの依頼により、その時々の大組織をめぐる時事問題(多くは企業不祥事などの問題になろうが)を取り上げながら、「ガバナンス」という視座で私なりの見方を発信する機会を得た。そこでまずは「ガバナンスとは何なのか?」「なぜ会計・監査の研究者である私がガバナンスを語っているのか?」から説明し、連載の補助線を引いてみたい。
米国COSOが画期となった「内部統制」議論
私は大学院修士時代に公認会計士の2次試験に合格して実務家の道を歩み出した一方、監査理論や国際会計、さらには、あるべき監査人の資質に関しても研究してみたいと思い、博士課程に進むことを決心した。ただ、当時は企業会計や証券市場における議論は、基準や規則を理解して適用するということに終始しており、その役割を担う会計専門職業人の資質や適格性、さらには“職業倫理”の問題を解明することは、学問に馴染まないとの考えが支配的だった。
それから半世紀近く、そのような学問観は大きく変化した。そして私自身、会計・監査の研究者の立場から、ガバナンスについても国内外の事例を踏まえて調査、研究、そして提言を行ってきた。
だが、令和の世にあっても、この「ガバナンス」の必要性や意味合いが、日本ではいまだ真に理解されていないようだ。日本ではガバナンスという言葉は往々にして、株式会社を念頭に置いて「コーポレートガバナンス」と称されることが多い。それは「企業統治」と訳されるが、時に「企業の内部統制」と混同され、その意味を捉えきれていない企業人もいまだいるように思われる。しかも、頑迷な経営者は、ともすれば内部統制を「会社の上層部が末端社員を統制するために行うもの」と誤解している節すらある。
たとえば、ビッグモーターについてはどうか。幹部が社員に対しパワハラのごとき圧力をかけて、成績を上げるためなら法律は二の次、といった体質までもが発覚している。しかし、ビッグモーターの経営陣はこうした社員への指導こそが、「内部統制を利かせる」ことだと勘違いしていたのではないか。
あるいは日本大学のケースでは、学生の大麻・覚醒剤所持が発覚した時点ですぐ警察に通報するのではなく、日大OBの警察官に連絡を取り対策を相談していたという。これなども「内部で問題を封じ込めて表沙汰にせず、組織を守ることこそが内部統制である」と思い込んでいたのではないかとの疑念が浮かぶ。
当然ながら、この両者に内部統制は元より、ガバナンスへの理解が決定的に欠如していたことは言うまでもない。だが本来、ガバナンスとは組織の発展と繁栄を目指し、組織としての方向性を打ち出すことに主眼が置かれている。つまり、発展と繁栄を阻害する要因を排除し、そうした環境を整えることがガバナンスの基本的な考え方なのである。
企業不祥事や今日語られるガバナンスを知るうえで、指摘しておかなければならない“枠組み”に、1987年にアメリカで発足した「COSO」(コソ)という組織がある。COSOとは、トレッドウェイ委員会組織委員会(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)の略称だ。
アメリカでは1970年代から80年代前半にかけて、金融機関を含む上場企業の不祥事や経営破綻が大きな社会・政治問題となり、そのなかには会計不正に端を発するものもあった。結果、当該企業のみならず、監査を担う会計士への不信も高まっていた。こうした事態に対処するため、1985年に米国公認会計士協会(AICPA)は、米国会計学会(AAA)、財務担当経営者協会(現・国際財務担当経営者協会、FEI)、内部監査人協会(IIA)、全米会計人協会(現・米国管理会計士協会、IMA)に働きかけ、「不正な財務報告全米委員会」を組織した。
初代委員長の名前を冠して「トレッドウェイ委員会」と呼ばれたこの組織は、不正な財務報告を防止・発見する枠組みと対策についての検討を行ったのち、1987年に「不正な財務報告」と題するレポートを公表。長年、アメリカの動きを注視し、タイムラグを経て日本でも同様の問題が起こることを予感していた私は、49に及ぶ改善項目を勧告した同報告書の内容を、是が非でも日本に紹介したいと考えた。
一方、この時点では積み残しになっていた、内部統制に関する統合的な枠組みを構築するために発足したのが、先述のCOSOである。そして、私が1987年の「不正な財務報告」レポートを翻訳している間の1992年に発表されたのが、COSOの内部統制報告書と呼ばれる「内部統制――統合的枠組み」だった。
ピックアップ
-
 【子会社ガバナンス#4】加登豊名古屋商科大学教授が語る「子会社業績向上の秘策」…
【子会社ガバナンス#4】加登豊名古屋商科大学教授が語る「子会社業績向上の秘策」…(#3から続く)今回の#4では、経営学者で現在、名古屋商科大学大学院マネジメント研究科で教授を務める加登豊氏をインタビュー。日本の企業グルー…
-
 【子会社ガバナンス#3】「親会社からの天下り」人事が子会社の成長を阻害する…
【子会社ガバナンス#3】「親会社からの天下り」人事が子会社の成長を阻害する…#1、#2では実例を引き合いに出して、子会社のコーポレートガバナンスが機能不全に陥り、ひいてはグループ全体のガバナンスを阻害しかねない状況を…
-
 【子会社ガバナンス#2】適切な事業ポートフォリオの構築が難しい理由…
【子会社ガバナンス#2】適切な事業ポートフォリオの構築が難しい理由…#1では大手企業の不動産子会社を例に、子会社のガバナンス不全があわや不祥事を生み出しかねない危険性を伝えた。続く#2では、新設子会社、あるい…
-
 【子会社ガバナンス#1】大企業の「不動産子会社」で不祥事が起きた背景…
【子会社ガバナンス#1】大企業の「不動産子会社」で不祥事が起きた背景…子会社・関連会社までを含めたグループ全体のコーポレートガバナンスが求められる大手企業。一方、大手企業グループには必ずと言っていいほど、不動産…
-
 「リスク情報収集」を自動化する最適なネット検索ツールとは…
「リスク情報収集」を自動化する最適なネット検索ツールとは…(前編から続く)リスク情報の収集には、時として正確性よりもスピードが求められる。その際、ネット上の情報をいかに集めるかが、勝負の分かれ目とな…
-
 企業担当者を悩ます「リスク情報収集」の死角…
企業担当者を悩ます「リスク情報収集」の死角…「仕事とはいえ、パソコンに向かい合ってネット上で関係先のリスク情報をチェックするのは、身心ともに疲れ果ててしまう」――。あるメーカーで与信管…