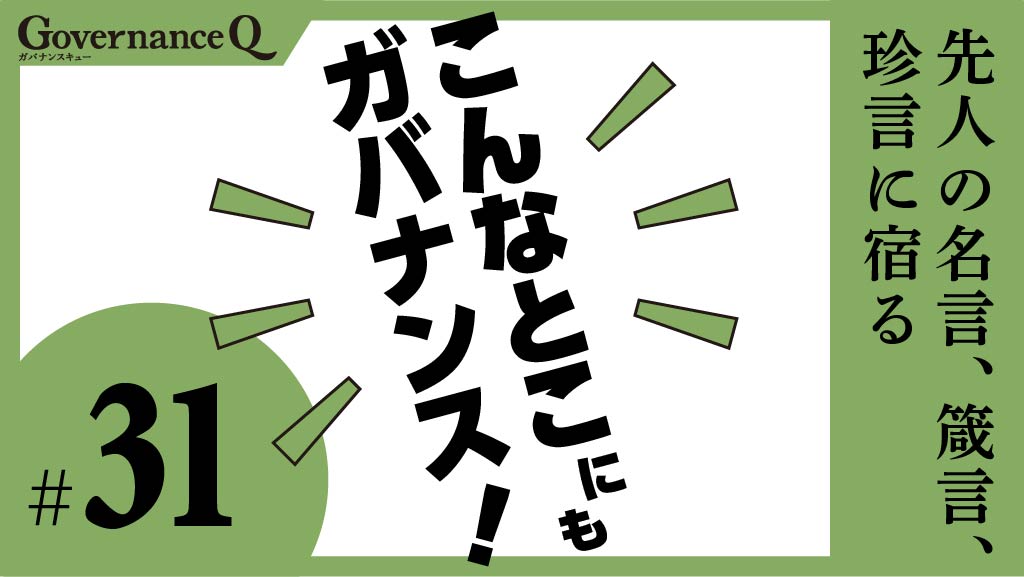栗下直也:コラムニスト
「こんなとこにもガバナンス!」とは(連載概要ページ)
「三人言いて虎を成す」
韓非(かんぴ、中国戦国時代の思想家)紀元前280?~紀元前233年。中国、戦国時代最末期の法家思想家。荀子に学ぶ。個人の徳に社会を任せるのでなく、信賞必罰を明文化した制度・法での矯正を説き、秦の始皇帝に絶賛される。のち、秦に使者として赴いたが、奸計にあって毒殺された。著作は、彼の名に託せられた『韓非子』55篇 が現存する。「矛盾」や「逆鱗に触れる」などの成語の出典としても知られる。
事実無根でも大勢が騒げば「真実」と勘違いする
『韓非子』は徹底した合理主義と冷徹非情な思想が貫かれている。その合理性は多くの為政者を惹きつけ、中国の国家統治の根底を貫いているといっても言い過ぎではない。秦の始皇帝や三国時代の蜀の軍師だった諸葛孔明、最近では習近平国家主席が演説に引用している。
「三人言いて虎を成す」は『韓非子』にある。戦争に敗れて、人質として他国に向かう大臣が去り際に国王に釘をさすために語った例え話だ。
大臣が「もし、誰か1人の人が町の中に虎がいるといったら、国王はそれを信じますか」と尋ねると、国王からは「信じない」と答えが返ってきた。次に、「では、2人が町に虎がいるといったらそれを信じますか」と聞くと、国王は「半信半疑だが、疑うだろうな」と答えた。それを受けて、最後に「では、3人が町に虎がいるといったら信じますか」と問いかけると、国王は「信じる」と答えた。
ここで大臣はため息をつきながら、こう忠告した。「町の中に虎は出ません。ただ、事実無根の話でも、多くの人が騒ぎ立てると、虚構でも真実のようになってしまいます。私がいなくなれば、私を陥れようとする者もきっと出てくるはずです。ご注意なさいますように」。国王は深くうなずいたが、大臣の心配は的中してしまう。人質として国を離れている間に、国王に大臣を貶める噂を囁く者は少なくなかった。人質の任務を終えて、帰国しても、大臣は国王に二度と会うことはできなかった。
ガバナンスは自ら情報収集することで機能する
人の心理はもろい。冷静に考えれば、起こりそうもないことでも、簡単に心を乱されてしまう。組織のリーダーも例外ではない。側近の言い分を鵜呑みにしていては真実を見誤り、組織のガバナンスはおかしな方向に向かう。そうした罠に陥らないためにも、多方面から情報を収集し、事実を見定める基本姿勢を忘れてはいけない。
(月・水・金連載、#32に続く)