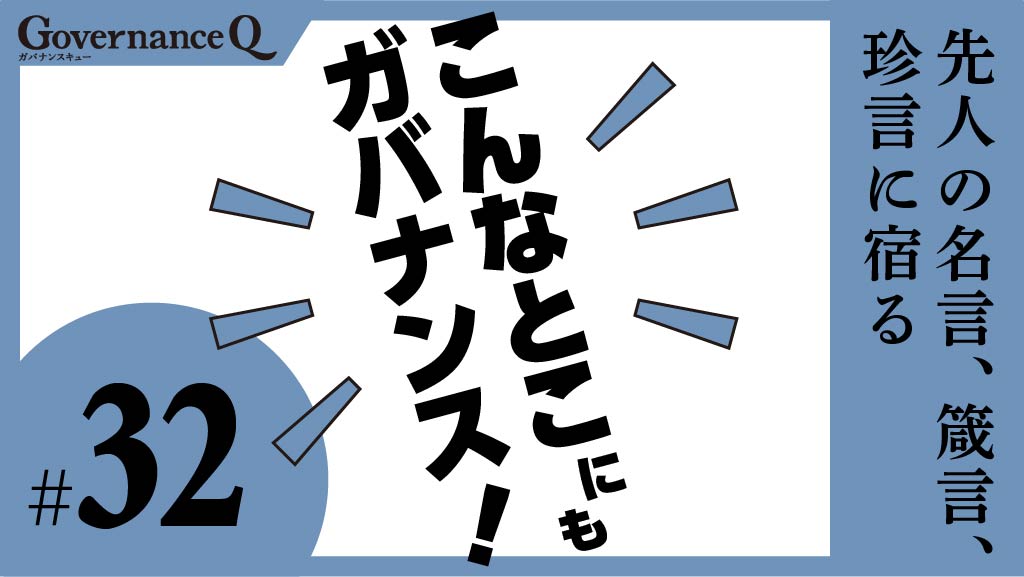栗下直也:コラムニスト
「こんなとこにもガバナンス!」とは(連載概要ページ)
「盛衰朽隆は人生の常である」
高橋是清(たかはし・これきよ、政治家)1854~1936年。政治家・財政家。仙台藩士高橋是忠の養子。米国に留学後、森有礼の書生となる。文部省、農商務省、日本銀行に勤める。1911年、日銀総裁。蔵相、政友会総裁、首相などの要職を歴任するが1936年の二・二六事件で暗殺された。
波乱万丈だった「ダルマさん」の人生
「順境はいつまでも続くものではなく、逆境も心の持ちよう一つで、これを転じて順境たらしめることも出来る。境遇の順逆は、心の構え方一つでどうにでも変化するものである」と続く。
「ピンチはチャンス」という言葉もあるが、人生は心の持ち方次第だ。それは是清の人生が物語っている。上記の略歴からみるとピカピカのエリートだが「波乱万丈」「一寸先は闇」という言葉が彼ほど似合う偉人は少ない。
13歳の時、藩の留学生に選ばれ、米国に渡る。本人は留学するつもりで渡米したものの学びの場は一向に得られず、意味も分からず契約書にサインしたところ、50ドルで農園主に奴隷として売られてしまう。関係者の尽力もあり、翌年、逃げるように帰国する。
語学力を買われ、15歳で大学南校(現東京大学)の教授手伝いの職を得るが、若ければ遊んでしまう。酒と芸者遊びにおぼれ、学校を退職し、芸者の箱屋になる。
その後、唐津での英語教師、翻訳業、予備校教師を経て、役人に転身する。順調に出世するがなぜかペルーの銀山の経営に当たろうとして、詐欺にひっかかる。日本に戻ってきても福島での農場経営や上州(今の群馬県)での鉱山開発に立て続けに失敗し、破産。日銀に要職とはいえない資材係でもぐりこむ。このとき、37歳。首相どころか日銀総裁になる気配も皆無だが、ここから是清のサクセスストーリーは始まる。
自分の幸運を信じて努力すれば花開く
是清は楽天家を自称していた。幼い頃から養家の祖母から「おまえはしあわせ者だ、運のいい子だ」と聞かせられていたこともあり、「どんな失敗をしても、窮地に陥っても、自分にはいつかよい運が転換して来るものだと、一心になって努力した」と自伝にも記している。
組織運営がうまくいくか、いかないかはときの運もある。どれだけ心血を注いだところで、環境ひとつで機能しないことは少なくない。もちろん、「何もせずに運任せ」は言語道断だが、やることをやったら、「どうにかなる」と考え、くよくよ心配しない胆力もリーダーにはときに必要だろう。
(月・水・金連載、#33に続く)