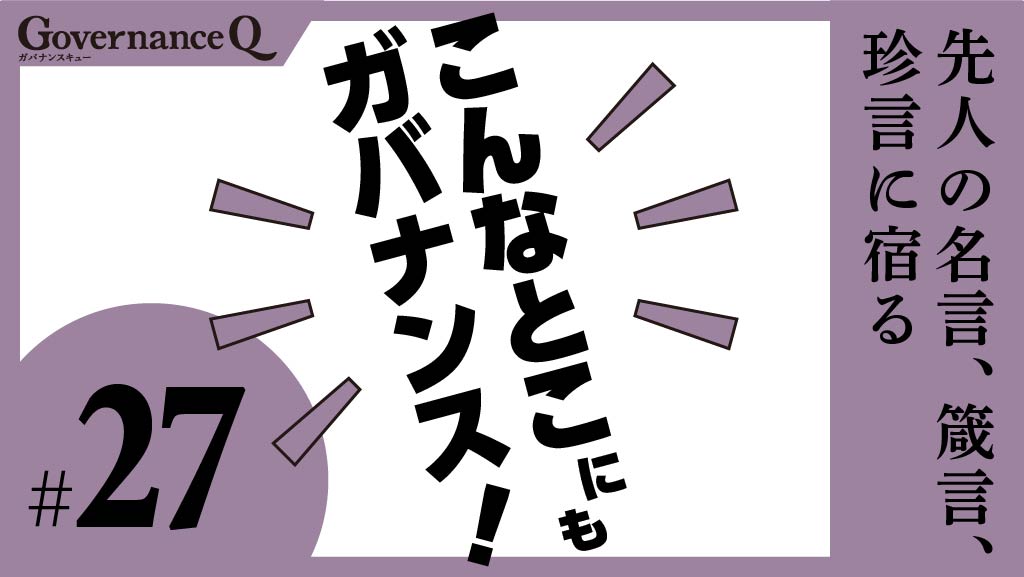栗下直也:コラムニスト
「こんなとこにもガバナンス!」とは(連載概要ページ)
「何をするにもその日限りだと思えば、自然と覚悟が決まって最善の選択ができるようになる」
藤堂高虎(とうどう・たかとら、戦国時代の武将)1556~1630年。近江の戦国大名浅井長政(織田信長の義弟)、豊臣秀吉の弟羽柴秀長に仕え軍功を立てた。のちに秀吉に招かれ、秀吉没後は徳川家康に接近し、関ケ原の戦いでは東軍に属した。大坂夏の陣では真田幸村に苦戦していた家康を助け、伊勢津藩の初代となる。
卑賤の出身でも最終的に32万石の大名に大出世
冒頭の言葉は、高虎の遺訓。「寝屋を出るよりその日を死番と心得るべし。かように覚悟極まるゆえに物に動ずることなし。これ本意となすべし」の現代語訳だ。
藤堂高虎はその功績よりも、生涯で7回主君を変えたことで後世に名を残す。“変節漢”と罵られることがあるものの、自分を評価してくれる「職場」を、周りの声に惑わされずに自分で考え、選び続けたとも言える。最終的に32万石の大大名になっていることから分かるように、その判断に狂いはなかった。
高虎は「その日を死番と心得るべし」を日々実践した。
象徴的なエピソードがある。
豊臣秀吉が朝鮮に侵攻した文禄・慶長の役は明国本土への侵攻ができず、膠着状態に陥っていた。秀吉の死で撤退を決めた日本軍は、秀吉の死を隠したまま14万軍の撤退を決めたが、敵が海上封鎖を敷いているため、簡単には帰国できない。ただでさえ撤退戦は簡単ではないが、しかも異国の地。指揮を誰がとるか。
「言われたら超スピードでやる」家康も舌を巻いた行動力
家康の屋敷で高虎に朝鮮半島への渡航命令が伝えられたその日、家康は夕暮れになってから言い忘れていたことを思い出す。家康はすぐに使者を高虎の屋敷に送り、「近日中に出帆するとは思うが、言い残したことがあるので、今日か、明朝に再度ご来訪いただきたい」と伝えた。
選ばれたのが高虎だった。
ところが、高虎の家臣は「我が殿は、貴館を退出した後、大急ぎで軍陣を整え、すでに朝鮮へ出立いたしました」と答えた。
家康はこれを聞いて感心した。
「高虎はその昔、与右衛門と名乗る卑賤の身だったが、太閤(豊臣秀吉)の引き立てを受け、次第に立身を重ねた士なれば、尋常の者ではない。働き盛りの若輩は高虎のような行動ぶりを聞き覚えて後々の手本とせねばならぬ」と側近を諭した。
ガバナンスも、時に熟慮も重要だが、それは方針を決めるまで。方針が決まったら、実行する。先延ばしにして良いことは何もない。
(月・水・金連載、#28に続く)