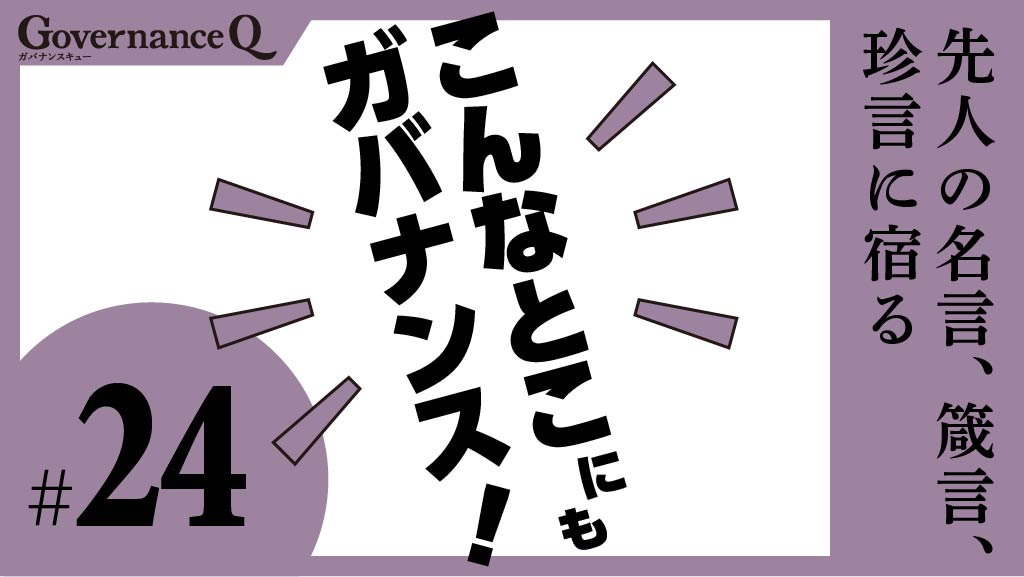栗下直也:コラムニスト
「こんなとこにもガバナンス!」とは(連載概要ページ)
「自分より賢い人間を自分の周りに置く」
アンドリュー・カーネギー(米国の経営者)1835~1919年。スコットランドの貧しい織工の家に生まれ、一家とともに渡米。製鋼業で成功し、「鉄鋼王」と呼ばれた。1901年モルガン商会に事業を売却し、それから亡くなるまでの18年間は「天は自ら助くる者を助く」という考えのもと、ニューヨークのカーネギー・ホール、財団、カーネギー工科大学(CIT、現在はカーネギーメロン大学の一部)などを設立し、慈善事業に専念した。
スコットランドの貧民街から鉄鋼王に登りつめたカーネギー
アンドリュー・カーネギーはアメリカン・ドリームの体現者である。極貧の家庭に育ちながら、アメリカでも有数の大富豪となった。
カーネギーは父親が事業に失敗したため、13歳でピッツバーグの蒸気織物工場でボイラー焚きとして働き始める。やがて電信局へと転職し、独力でモールス信号を覚えた。次に、ペンシルバニア鉄道に就職する。真面目な働きぶりから地区の責任者までに抜擢されるが、そこで満足しなかった。鉄道建設が急速に進む有り様を目の当たりに見て、鉄道経営よりも鉄道建設資材の供給に関心を持った。
「19世紀後半に文明の進歩を支えるのは鉄である」と確信したカーネギーは、投資でまとまった財産を手にしていたこともあり、それを元手に鉄鋼事業に進出した。歴史はまさにカーネギーの予想通りに進んだ。
冒頭の言葉は、正確には「自分より賢い人間を自分の周りに置く方法を知っていた者ここに眠る」。カーネギーの墓碑銘(ニューヨーク州)に刻まれている。
篤志家として巨万の富を社会に還元
アメリカの立身出世物語の典型的な人物として知られるが、カーネギーは13歳から働いたため、まともに学校には行っていない。財界人の中には彼の学歴の無さを馬鹿にする者もいたが、「私は学がないが、どんなことでも5分あれば最適な人物から話を聞ける」とやり返した。
カーネギーは周囲の人間を大事にした。「大金を家族に遺すのは恥だ」と資産4億ドルのうち、3億5000万ドルを図書館や劇場など公共のために、2000万ドルを平和基金に寄付した。残りの3000万ドルも、使用人や友人たちを支援するために使った。家族にはわずかな信託基金を遺しただけだった。
経営者は権力を握ると、我を通しがちだが、周りの言うことを聞かずに、自分の考えを押し通せば現場が混乱する。精神論に聞こえるかもしれないが、カーネギーのような謙虚な精神はガバナンスには欠かせない。
(月・水・金連載、#25に続く)