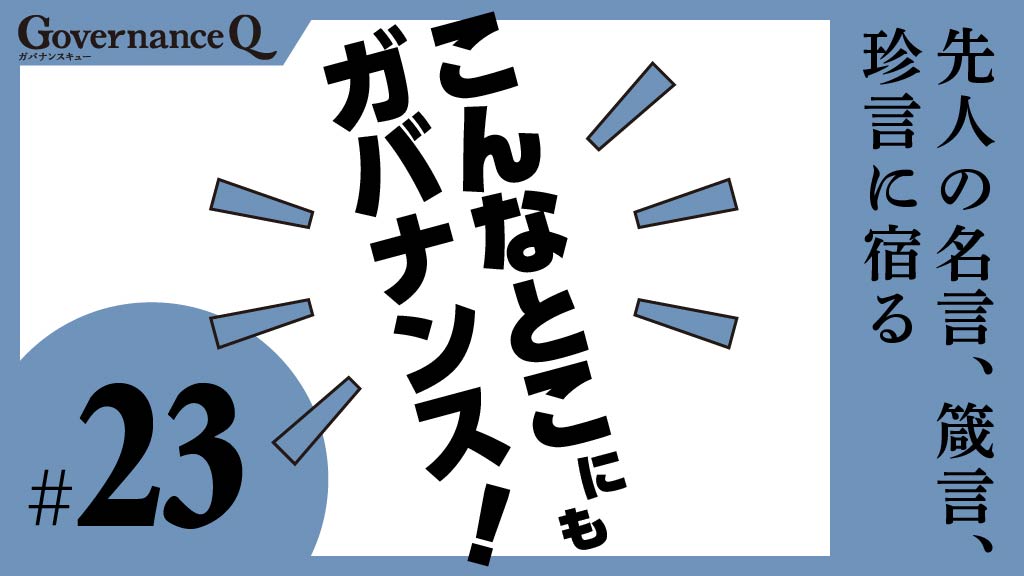栗下直也:コラムニスト
「こんなとこにもガバナンス!」とは(連載概要ページ)
「急ぐ事はゆっくり書け」
小早川隆景(こばやかわ・たかかげ、戦国時代の武将)1533~97年。戦国時代を代表する中国地方の大大名、毛利元就の三男。「三本の矢」の1人で、義を重んじる知将として知られる。隆景は1544年、竹原小早川家の養子となる。やがて本家の沼田小早川家も継ぎ、小早川両家を統一した。豊臣政権になると秀吉の絶大な信頼を受け、その義理の甥である羽柴秀俊を養子としてもらい受けた。秀俊こそ、のちの小早川秀秋である。95年には長年の功績から徳川家康、前田利家らと並ぶ五大老に任じられたが、秀吉死去前年の97年に病没した。
物事はすぐに決断してはいけない
小早川隆景は勇猛な武将と知られるが、猪突猛進なタイプではなく、かなり慎重な人物だったという。何かを決断するときはじっくり考え抜き、選択肢を数多く用意した。
人生においては、急ぐ時ほど焦らず熟考しなければいけないという教えを周囲にも徹底させた。当時、身分の高い武将は手紙を書記に口述筆記させるのが一般的だったが、「急ぐ内容の手紙ほど、書記のことも考えてゆっくり話せ」と隆景は繰り返していた。
隆景といえば、やはり「三本の矢」だ。1557年、毛利元就は長男の毛利隆元、次男の吉川元春、三男の隆景に三子教訓状を送り、兄弟の結束を訴えた。これが後に、1本では折れやすい矢も3本束ねれば強くなる――という逸話の基になったとされている。
だが、有名なこの言葉には別の真意があるとも言われている。この逸話の影響で兄弟3人の仲は良さそうに見えるが、実態は逆だった。元就は隆景の力量が本家毛利家をしのぎ始めていることに気づき、隆景を戒めるために書いたとの見方がある。
元就は内紛を禁じ、吉川家の養子となっていた元春と、小早川家を継いだ隆景はその教えを守った。長兄隆元と父元就が亡くなり、隆元の長男、輝元が毛利家を継いでも本家を支え続けた。
目先の利益よりも「義」を重んじる
隆景が義を重んじる武将として後世に名を残すのは、それだけではない。
82年に毛利家は、織田信長の命を受けた羽柴(のちの豊臣)秀吉の中国攻めを受ける。しかし、その最中に本能寺の変が勃発。秀吉は急いで毛利側と和睦を結び、退却する。次兄元春は秀吉の追撃を主張したが、隆景は交わした約束を守る信義の大切さを説いた。結果、秀吉は中国大返しを果たし、信長の後継争いを勝ち抜き、天下人となっていく。
隆景は小早川家の繁栄よりも毛利家の発展に尽くした。さながら子会社が親会社を支えるかのように、毛利家を存続へと導いた。じっくり何が重要かを考える。目先の利益よりも義を重んじる――。それは令和のコーポレートガバナンスを考える上でも忘れてはいけない基本姿勢だろう。
(月・水・金連載、#24に続く)