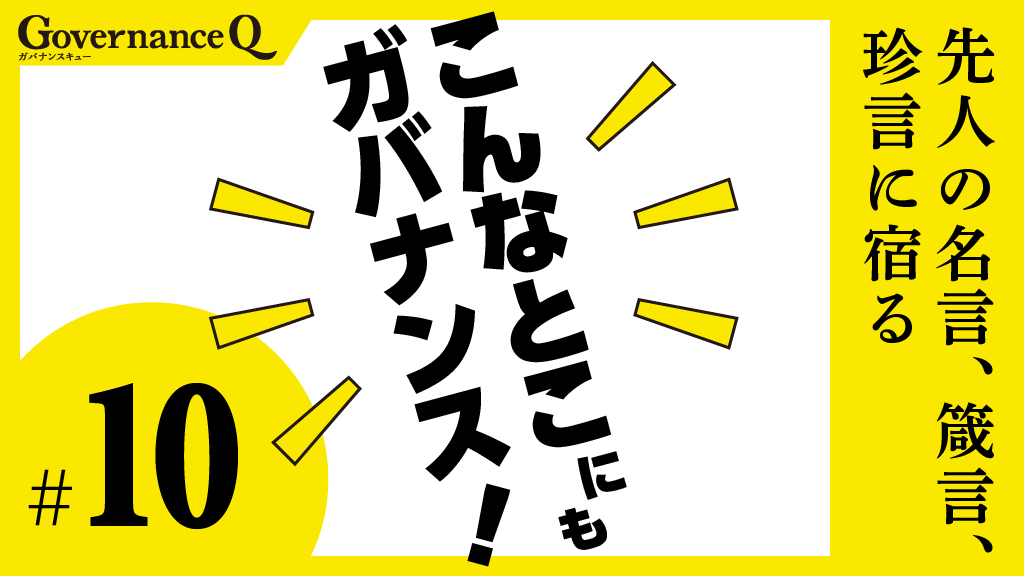栗下直也:コラムニスト
「こんなとこにもガバナンス!」とは(連載概要ページ)
「政治を軽蔑するものは、軽蔑すべき政治しか持つことが出来ない」
トーマス・マン(ドイツの作家)
1875~1955年。火災保険会社で働きながら、1894年に『転落』で作家デビューする。1901年に自身の一族を描いた『ブデンブローク家の人々』の成功で作家活動に専念する。29年に『魔の山』でノーベル文学賞を受賞する。
ナチズムに反対し米国に亡命したトーマス・マン
トーマス・マンはデビュー当初は政治と距離をとったが、第一次世界大戦後に民主主義擁護に積極的に転じ、1933年に成立したナチス政権に反対し、スイスを経てアメリカに移住する。ヒューマニズムの立場からナチズムを攻撃した。ちなみに、兄のハインリッヒも作家で、ナチス時代にフランス・米国に亡命し反ナチズム闘争を展開している。
冒頭の言葉は代表作の『魔の山』の一節だ。
おそらく、みなさんの部署にもいるはずだ。会議などで常にとりあえず反対する人が……。提案した人の意見の粗を探し、「それではダメだ」と指摘する。
提案者からしたら「評論家であるまいし、代案を出してください」となる。一昔前は代案が出せないのを見越して、自分の主張を押し通すこともできたが、最近は「代案がないから反対できないということはなく、ダメなものダメだ」と再反論する人も少なくない。議論はただただ停滞する。
間違っていることを指摘することは比較的やさしい。ところが、どのようにしたらいいのかを提案することは簡単ではない。
“論破”で組織は回せない
会社の部単位の会議ですらこうした有り様なのだから、組織全体や国単位なると、決まるものも決まらない。そうした現実を目の当たりにした多くの人は「結局、誰がどうやろうと変わらない」と諦めモードになりがちだ。ただ、汚職や腐敗に呆れて、軽蔑するだけでは、それこそ永遠に何も変わらない。相手を軽蔑し、罵っても溜飲が下がるだけだ。
重要なのは否定するだけでなく、具体的にどう変えるかを考えること。組織運営の目的は議論で相手を打ち負かすことでもなければ、モラルを説くことでもないのだから。
(月・水・金連載、#11に続く)