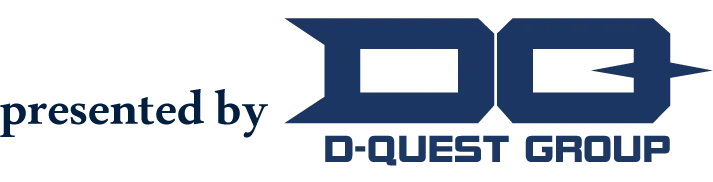栗下直也:コラムニスト
「こんなとこにもガバナンス!」とは(連載概要ページ)
「今すべてが一変してはならぬという法は、ないではないか」
ドストエフスキー『罪と罰』(1866年)
『罪と罰』は1866年発表のフョードル・ドストエフスキー(1821~1881年)の長編小説で、世界文学の最高傑作のひとつと言っても言い過ぎではない。青年ラスコーリニコフが新たな道徳を樹立するためには、あらゆる手段が許されるという思想に取りつかれ、質屋の老婆とその妹を斧で撲殺して金品を奪う。警察の心理的追及もあり、罪の意識にさいなまれた彼は、自己犠牲に生きる娼婦ソーニャのすすめで自首し、シベリアで懲役刑に服する。
世界文学の最高傑作だけど、世界観がさっぱり理解できず
思春期には誰もが一度は読もうと思う同書を私も高校生の時に手に取った。老婆と妹を惨殺するところまでは推理小説にも似た迫真力で引きつけられたが、正直、それ以降の世界は当時の私には理解できなかった。
だが、老婆の撲殺はほんの序章で、物語の主題は、事件のあとの主人公と彼を取り巻く人たちの間で繰り広げられる心理劇にある。売春婦に身を堕としてもなお無垢な魂を持つソーニャにラスコーリニコフは魂を洗われ、それまでの苦しい隔絶観から解放され、人間として回復し始めるのだが、キリスト教的愛の思想がさっぱりわからない当時の私には複雑な世界感がさっぱり理解できなかった。
ちなみに、『謎解き『罪と罰』』(新潮選書、江川卓=たく=ロシア文学者、元巨人軍の江川卓ではない)によると、『罪と罰』の「罪」には「神のおきてに背く行為」を、「罰」には「神は愛する者をこそ罰し給う」を含意させているという。「『罪と罰』ってタイトルは単純すぎないか」と感じていたが、深いのだ。
また、「そもそも斧で殺すか」とも思っていたが、同書によるとラスコーリニコフという姓にはロシア語の割裂く(ラスコローチ)という意味を持たせていて、老婆の脳天を斧で「割裂く」運命を暗示している。知れば知るほど、過去の自分が罪深くなってくる。恥ずかし過ぎて、まさに今すべてを一変させたい。
個人も組織も「変わる」ことに理由はいらない
冒頭の言葉は監獄で他の囚人との関係の変化からラスコーリニコフが発した言葉だ。
頭では理解していても、人間は変化に臆病だ。何かを変えるのには理由を欲しがるが、変えるのに理由はいらない。変わろうと思うことこそ動機なのだ。もちろん、個人はもちろん、ビジネスの世界でも当てはまる。環境は日々変わっているわけだから、組織が変わらない理由はないのだ。
(月・水・金連載、#5に続く)