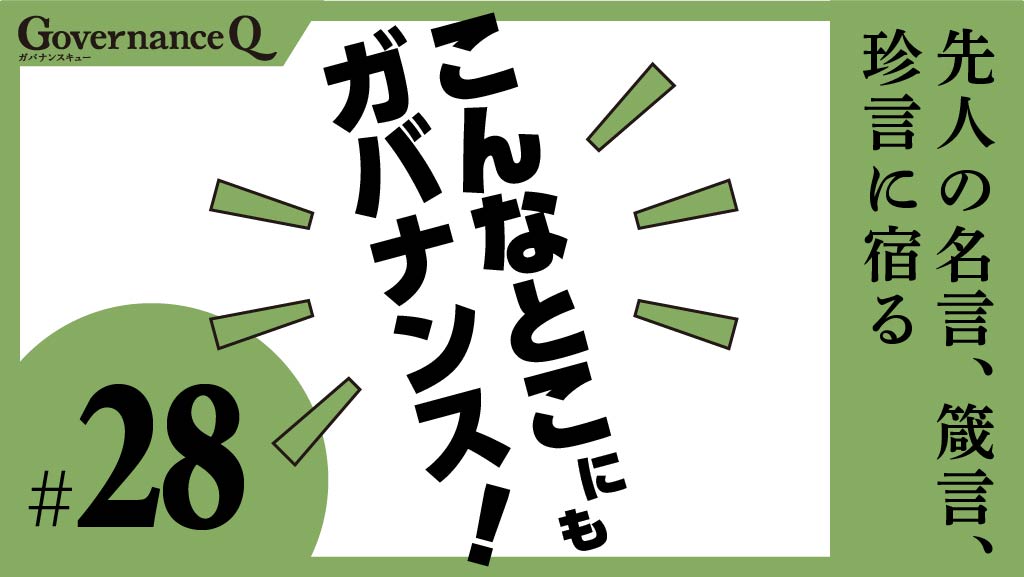「九転び十起き」
浅野総一郎(あさの・そういちろう、日本の経営者)
1848~1930年。越中(富山県)出身。少年時代より各種の商業を営んだが失敗し、1871年に東京へ出奔する。やがて薪炭、石炭などの商売から渋沢栄一と知り合い、84年渋沢の助力により官営深川セメント工場の払下げに成功し、浅野セメント(後の日本セメント、現太平洋セメント)を発展させた。さらに1913年に鶴見、川崎沿岸の約500万平方メートルの埋め立て事業に着手し、昭和初期までに完工させ、現在の京浜工業地帯の生みの親となる。同郷の安田善次郎の資金援助を受けて海運、鉱山、造船、鉄鋼、電力など多角的に事業を展開。一代で浅野財閥を築き上げた。
根っからの商売人だった「セメント王」
苦労は人を育てるとはいうが、浅野総一郎ほどその言葉が似合う経営者はいないかもしれない。
浅野は商才があった。だが、才能があることは時に人を不幸にする。父親が亡くなり、母と妹を抱えた15歳の浅野は一念発起し、自分で事業を興す。醤油の醸造などに手を出すがうまくいかない。17歳の時に地元ではあまり普及していなかった稲扱器(今の脱穀機)の貸し付けを思いつき、親族や知人から250両をかき集め、稲扱器を買い占めるが、凶作だったため、借金だけが残った。
窮地に陥った浅野だったが、彼の事業への姿勢を買っていた地元の名士の紹介で大地主の養子になる。生活には困らなかったが、事業欲は抑えられない。養父にカネを借り、卸の仕事を始める。順調だったが、富山地方での凶作を見込んで、米の買い占めに動き、大勝負に出たら、仕込んだ米が不良品で会社は倒産する。
養子縁組を解消されるが、それでも事業欲は衰えない。全然、懲りない。高利貸しからカネを借り、自分でムシロや畳表などの卸業を始めたが、高利には勝てなかった。借金は500両以上に膨らんでいて、高利貸しの取り立てを恐れた浅野は東京に逃げる。24歳だった。
一文無しの浅野はそこで商売の基本に立ち返る。安く仕入れて確実に高く売る。仕事がなかったので、水を汲んで砂糖を入れ、日本橋あたりに出掛けて「ヒヤッコイ、ヒヤッコイ」と呼び掛けると、商売になった。次に、横浜へ出て竹の皮を売った。味噌や寿司を包む竹が高く売れることに気づいたからだ。砂糖水で儲けたお金で千葉の知人から竹の皮を仕入れて横浜で売った。1両の仕入れで35貫(130キロ余)もの竹の皮が買える。これが横浜では3貫目1両で売れる。計算するまでもないが、千葉で仕入れた1両分の竹の皮が横浜では10両以上に化けた。
もちろん、竹の皮売りで人生を終えるつもりはなかった。薪炭、石炭へと事業を拡げ上京から約2年で横浜の石炭商として名も知られるようになっていた。
一生懸命働けば貧乏で困ることはない
ここから一気に大実業家への階段を上りそうだが、試練は続く。
強盗に入られ、有り金を全部巻き上げられ、その翌年には火事で家が全焼して3万円(現在の約3億円)を失う。「なんだか、いけるかも?」と思うと、転んでしまう。それでも、起きる。家が全焼した2年後の1877年に西南戦争の勃発で石炭相場が暴騰し、大儲けする。そして、1881年にはコレラの大流行をいち早く察知して、コールタールをタダ同然で横浜市から払い下げて、コレラの消毒に使う石炭酸水をつくって、またまた巨利を得た。
そこからは今までの苦難がうそのように手掛ける事業が成功し、とんとん拍子で浅野財閥へと発展させた。
浅野の支援者となったのが渋沢栄一であり、安田善次郎だった。安田や渋沢は「事業は人である」とよく口にしていたが、浅野は苦労した分、彼らに愛された。強靭な精神力と忍耐力が浅野の信用の裏付けになった。事業も組織の整備も毎日の地道な積み重ねに勝るものはない。
浅野は一分一秒を惜しみ、働いた。勉強を怠らなかった。「稼ぐに追いつく貧乏なし」「1日に4時間以上寝るとばかになる」という言葉も残している。
(月・水・金連載、#29に続く)