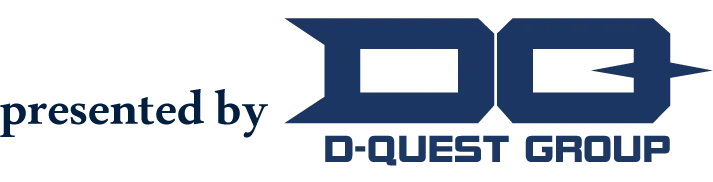最大の問題点は、指針等が掲げる要件のうち何をどこまで満たすべきかを事前に明確に予測できないだけでなく、利用する企業側の行動を正当化するために用いられてしまう危険があるという点だ。
公正M&A指針は、「MBO(経営陣買収)や支配株主による従属会社の買収」において、公正な取引条件を設定するために講じることが求められる「公正性担保措置のうち、一般に有効性が高いと考えられる典型的な措置」として、①独立した特別委員会の設置、②マーケット・チェック(他の潜在的な買収者による対抗的な買収提案が行われる機会の確保)、③マジョリティ・オブ・マイノリティ(少数株主の過半数)、④強圧性排除――などを掲げている。
しかし、これらの公正性担保措置は、「公正な取引条件を実現するための必要条件ではなく、常に全ての公正性担保措置を講じなければならない」わけではなく、「個別のM&Aにおける具体的状況に応じて、いかなる措置をどの程度講じるべきかが検討されるべきものであり、また、講じられる措置を全体として見て取引条件の公正さを担保するための手続として十分かどうかが評価されるべきもの」とされているのだ(公正M&A指針54頁)。
これでは、公正性担保措置として具体的に何をどこまで講じなければならないかが明らかでなく、予測可能性は確保されない。結局、企業が自主的に判断する他ないが、企業が誠実、あるいは、保守的に公正性担保措置を講じるとは限らない。実際のM&Aで採られる公正性担保措置のうちで、最も重要と考えられるマーケット・チェックが実施される割合は極めて低い。
また、マジョリティ・オブ・マイノリティについては、買収防衛策の導入・発動のような、「『機関権限の分配秩序』に関わる事項」、すなわち、株主構成の変更、ひいては経営支配権の移転に関わる事項は、取締役会ではなく、株主が決定することが必要であるというのが判例・裁判例の考え方である。そのため、買収防衛策の導入・発動の局面において非利害関係者(マイノリティ)か否かの判断を、取締役会の構成員でもある社外取締役から構成される特別委員会(独立委員会)に委ねることは、恣意的な判断となるリスクがある。
それにもかかわらず、社外取をメンバーとする特別委員会を設置する事例が少なくない。要するに、公正M&A指針が掲げる公正性担保措置は、実際にM&Aを主導的に行う企業にとって都合のよい“緩い指針”として使われているのだ。
これら以外にも、05年の買収防衛指針、19年の公正M&A指針、23年の買収行動指針がそれぞれどのような関係にあるのかが必ずしも明確になっていないという問題点もある。
例えば、公正M&A指針とその4年後の買収行動指針とを比較すると、買収行動指針は「上場会社における買収一般」が対象とされているため、同指針の適用対象を文言どおり読むと、公正M&A指針が対象とする「構造的な利益相反関係にあるM&A取引」(MBO・上場子会社の完全子会社化)も対象に含まれることになる。
しかし両指針は、原則や視点などで一致しておらず、その場合の優先順位等も後発の買収行動指針には書かれていない。そのため、MBO案件は、公正M&A指針の適用だけを考えればよいのか、買収行動指針も考慮することが必要なのか、真面目に取り組もうとする企業ほど困惑するような事態になりかねない。