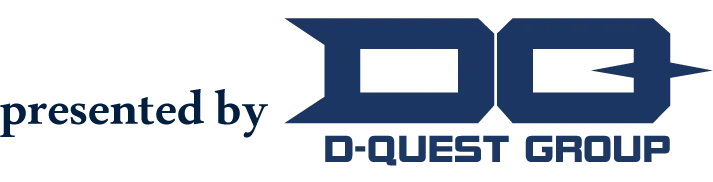練達の法曹も悩ます「それでも判例に多様な解釈や選択肢が生じる場合」
もっとも、上記のプロトコルにより、最高裁判決にさまざまな解釈の余地や選択肢が生じることを完全に防止できているかというと、実際はそうなっていない。最高裁判例の解釈や適用範囲(どのような事案についてその最高裁判決の判断枠組みが適用されるか)などについては、研究者の見解や下級審裁判例でまちまちな状況が出現しているのだ。
なぜ、このような事態が生じているかというと、いくつかの理由が考えられる。
第1に、最高裁判例(判決理由を含む)のうちで、どの部分に拘束力があるのかを見極めることが難しい場合があるということが大きな理由だ。最高裁判例のうち拘束力のある部分を「レイシオ・デシデンダイ」という。
その判決理由中では、法律判断の結論を正当化するための理論的説明や法制度、法規の趣旨の一般的解説、法解釈の一般的指針など、当該事案の法的論点とは関係しない法律論のようなものも述べられており、それらは拘束力が生じない“傍論”に過ぎない(これを「オバイター・ディクタム」という)。ただ、最高裁判決のどの部分が拘束力のあるレイシオ・デシデンダイに当たり、逆にどの部分が拘束力のないオバイター・ディクタムに当たるのかを線引きすることは、練達な裁判官や研究者にとっても難しい場合があるといわれている。
なぜなら、レイシオ・デシデンダイに当たるのは、基本的には判決理由中の当該事案の法的論点に対する結論を示した命題の部分であり、法的論点に対する結論を導くための理由付けとして用いられているロジックの役割を果たしている命題の部分(理由付け命題)は判例ではないと解する見解が強い一方、このような理由付け命題も判例となり得るという有力な見解もあるからだ。
また、結論を示した命題は、結論にとって意味のある事実である「重要な事実」(material facts)だけを残して、他の同種の事件にも適用できる程度に抽象化した命題を指すが、どこまでがmaterial factsなのかについては明確には線引きできない。これも線引きを難しくしている理由だ。
第2に、最高裁判例は民集・刑集と呼ばれる公式判例集に掲載される重要な判例ばかりではなく、“それ以外”の最高裁判例もある。“それ以外”の最高裁判例については、前項で説明した重層的な①~⑤のプロトコルは履践されない。
それでも、判例集には掲載されない判例の中で、事例として他の事例にとっても参考になるような判例は「最高裁判所裁判集民事」(集民)に掲載され、その最高裁判決の主要なものについては①~③の解説までは公表されることが多いが、その場合でも、④⑤のような最高裁調査官による正式な解説は書かれないままである。
第3に、集民に掲載され、事例判決に過ぎないにもかかわらず、それを研究者・実務家ともに評価を誤り、あたかも民集掲載の最高裁判例であるかのように取り上げてしまうケースもないではない。
特に、複数の著名な研究者が概説書や判例研究などで、事例判決に過ぎない最高裁判決を拘束力がある判例のように取り扱ったため、中堅の研究者や下級審裁判所の裁判官もその見解を踏襲してしまったという苦々しいケースも実際に生じている。
裁判官・検察官・弁護士などの法曹実務家にとっても、判例の趣旨・意図を正確に理解することが必ずしも容易であるとは限らないということを告白するとは、名誉なこととは思えない。
それでも、法的安定性・予測可能性の確保のために判例の趣旨・意図を精確に把握することは、法律実務家にとって“一丁目一番地”である。私自身もそのことと肝に命じ、自らの研鑽のため、実務の傍ら、複数の研究会に参加して、毎年いくつかの判例報告をし、判例研究・評釈を法律雑誌や大学の紀要などに寄稿することを長年続けている。