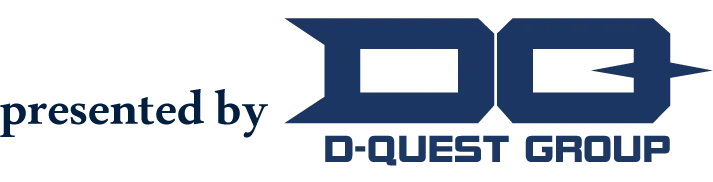「今日の痛み」を避けて「明日の破滅」を選ぶ心理
恋愛ゲーム理論に、ひとつの典型的な悲劇がある。
関係が完全に冷めきっているのに別れ話を切り出せない。「今日、この話をすれば激しく揉めるだろう」という、“今日の摩擦”を避けるために結論を先延ばしする。しかし、時間は解決策を与えてはくれない。むしろ決断を遅らせれば遅らせるほど状況は深刻化し、やがて修復不能な破局を迎える。
行動経済学はこれを「損失回避性」や「現在バイアス」という概念で説明する。目の前の小さな痛み(マイナス5)を避けるために、将来の大きな損失(マイナス50)を無意識に選んでしまう。
これは人間心理としては極めて自然な、いわば“業”のようなものだ。しかし、この心理的メカニズムが、高度な公共性を有する企業組織の意思決定に持ち込まれたとき、それは「個人の悲劇」ではなく「社会的な害悪」へと変質する。
企業組織における決定的な非対称性
企業組織における意思決定が、個人の恋愛と決定的に異なるのは、その「波及範囲」と「責任の非対称性」である。二人の間の私的な関係であれば、別れ話を先延ばしにした代償を払うのは当事者二人だ。しかし、大企業、中でもインフラを担うような巨大組織における意思決定には、地域住民、規制当局、従業員、株主、金融機関、さらには将来世代に至るまで、多層的なステークホルダーが紐付いている。
ここで深刻な非対称性が生じる。「今日のマイナス5(工程の遅延やコスト増)」を避ける判断を下すのは、空調の効いた会議室に座る一部の経営層だ。しかし、その“先延ばし”の結果として数年後に顕在化する「マイナス50(信頼崩壊や事故リスク)」の代償を払わされるのは、その判断に関与しなかった無数の第三者である。
とりわけ公共財を預かる事業者が、「組織内の空気」や「短期的なKPI(重要業績評価指標)」を優先して真実を歪めることは、単なる経営判断のミスではない。それは、社会がその事業を許容している前提条件――制度全体の信頼――を内側から損ない、意思決定に関与しない多数の第三者に損失やリスクを転嫁する、広範な「負の外部性」を社会全体に転嫁する行為にほかならない。
そう、中部電力の浜岡原子力発電所(静岡・御前崎市)をめぐる問題のことである。
思考実験として想像する「中部電力の会議室」
さる(2026年)1月5日、中部電は浜岡原発の耐震設計に関わる地震動評価で不適切な「代表波」の選定があった疑いを認め、第三者委員会を設置して調査と再発防止に取り組むと発表した。
地盤調査データのうち、都合の良いものだけを選んで地震の揺れを過小評価していた可能性があり、原子力規制委員会は「審査データのねつ造」として審査を白紙に戻す方針という極めて異例な方針を示し、また、1月14日には、今後、規制委による立入り検査も進められると報じられている。
ここでは、報道された事象を“経営学的な思考実験の素材”として活用し、あらゆる組織に潜む構造的問題――なぜ組織が集団として、これほど致命的な「都合の良い判断」へと傾いてしまったのか、その力学の解明を試みたい。
この問題は、原発事業特有の問題ではない。品質偽装、粉飾決算、不祥事の隠蔽……。安全、品質、法令遵守といった「本来は最優先されるべき価値」が、コストやスケジュール、「組織内の暗黙の了解」によって、いつの間にか、脇に追いやられていくプロセスは、いくつもの不祥事事例から学んだはずの“失敗の構図”と共通している。
では、こうした“先延ばし”は組織内でどう進行するのか。会議室の光景を想像してほしい。
技術担当役員は資料に目を落とし、言葉を選ぶ。「このデータを採用すれば、基準地震動は大幅に上がります。現在の耐震補強計画では到底足りず、再稼働計画はさらに数年遅れ、投資額も数千億円単位で膨らみます……」。沈黙ののち、誰かが口を開く。「もう少し、データを『精査』できないか」。
その一言は、露骨な「改ざん命令」ではない。しかし、そのわずか30秒の沈黙と曖昧な提案が、現場に対して「空気を読め」という強烈な呪いをかける。そして5年後、10年後の破局は、その瞬間に静かに決定づけられる。
「事業適格性」という見えない資産の崩壊
現代の原発運営は、社会からの圧倒的な信頼に基づく「事業正統性(Legitimacy)」があって初めて成立する、許認可ビジネスの最高峰である。山中伸介・規制委委員長の「審査の白紙化」という発言は、単なる手続きの遅延ではなく、事業者の適格性が根底から否定されることを意味する(1月14日の定例会合で白紙化が正式決定)。
経営の時間感覚で見れば、審査の遅延は多くの場合「回復可能なリスク」である。追加説明や補正という「費用」と「時間」で取り戻すことができる。しかし、データ不正疑惑が突きつけているのは、カネや時間では解決できない信頼の欠如であり、より正確に言えば、「この組織に高リスクな原子炉を担う資格があるか」という根源的な問いである。
通常の規制違反であれば、罰金や業務停止といった、損益計算書や事業計画の中で対処可能な「管理コスト」として処理できる。しかし、適格性の否定はそれとは性質が異なる。「この主体(事業者)にはもはや信任を与えられない」という評価であり、その影響は即座に数値には表われないが、一度下されれば、後からいかに是正措置を積み重ねても二度と回復できない“断絶”を含んでいる。
技術判断の「独立性」――“科学への敬意”という遮断壁
中部電の問題で最も深刻なのは、技術判断への「経営的介入」が疑われる点だ。耐震設計や安全評価は、本来「科学的事実の積み上げ」という極めてドライなプロセスであるべきで、観測されたデータが示すリスクの大きさが、経営の都合(予算、工期、株主への説明等)で変動してはならない。
しかし、報道された「都合の良いデータの抽出」が事実であれば、それは科学への介入、あるいは経営への過度な忖度を意味する。ここで問われるのは、経営陣の「科学への敬意」である。健全なガバナンス下では、CEO(最高経営責任者)は「技術的真実を曲げずに示せ。その結果生じるコストや株主への説明は経営の責任だ」と宣言し、専門領域を保護する。
しかし、技術部門と経営部門の間に存在すべき“遮断壁”が破れている組織では、「もう少し、何とかならないか」というプレッシャーが霧のように組織を包み込む。「空気を読む」文化が、「技術者の矜持」を静かに侵食し、組織は「嘘の上に築かれた城」へと変貌していく。

なぜ組織は「バレるリスク」を選ぶのか
ここで、冒頭の「別れ話を切り出せない心理」に戻ろう。なぜ冷静なはずの経営パーソンが、将来的に「バレる」確率が極めて高い不正を選択してしまうのか。そこには複数の認知バイアスが複合的に作用している。
ひとつが「正常性バイアス」だ。「これまでも多少の調整はしてきたが、大きな事故は起きなかった。今回も大丈夫だろう」という根拠のない過信が、リスクの感度を麻痺させる。
もうひとつに「段階的コミットメント」がある。最初はほんの小さなデータの丸め込みだったものが、回を重ねるうちに「もう引き返せない」という心理的拘束を生む。集団意思決定の場では、さらに「集団浅慮(グループシンク)」と「責任の分散」が加わる。「役員会全員で決めた方針だ」という感覚が、個人の倫理的ブレーキを解除してしまう。
これらのバイアスは、個人の意志では対抗できない。だからこそ、組織として「構造的な遮断装置」を設計する必要がある。
取締役会が問うべき論点:浜岡から学ぶ
この組織的な沈黙の連鎖を断ち切り、実務として何を問うべきか。取締役会で検討すべき論点は次のようなものが考えられる。
A. データ・プロセスの検証体制(客観性)
基準データの選定プロセスに、経営層の意向を排除した「第三者の目」が入っているか。経営層に届く「要約された資料」の背後にある「生データ」に対し、独立したチェックが機能する設計になっているか。
B. 心理的安全性の実態(不都合な真実の評価)
「計画を根底から覆す不都合な事実」が持ち込まれたとき、組織はどう反応したか。過去3年のうち、社内で「悪いニュースを早期に上げて評価された」事例はあるか。
C. 技術判断の独立性の担保(科学的良心の死守)
技術トップ(CTO=最高技術責任者等)が、CEOの方針に対して「科学的にノー」を突きつける権限を明文化しているか。その独立性を守るために、社外取締役がそのプロセスに関与しているか。
D. 長期リスクの可視化
「適格性喪失」「免許剥奪」のシナリオを、財務インパクトとして試算しているか。コンプライアンス違反を「罰金リスク」ではなく、「事業免許の喪失・市場退出」という最悪のシナリオとして、短期KPIと同じダッシュボードで見ているか。
これらは、法律論ではなく、また、コンプライアンス部門に丸投げする話でもない。取締役会で、経営陣自らが事業の「存立基盤」を守るために問い続けなければならない事項である。
喪失した「ガバナンス&ロー」という2つの土台
報道された浜岡原発の事案は、仮にそれが事実であれば、2つの土台を同時に揺るがす。
ひとつは、ガバナンスの土台としての技術判断の独立性である。科学への敬意がなければ、どれだけ立派なコンプライアンス体制を整えても空文化する。もうひとつは、規制制度の実効性を支える、規制当局と事業者間の信頼関係の維持という土台。データ不正が致命的なのは、結果として危険が顕在化したか否か以前に、事業者の誠実な情報提供を前提として設計された法制度そのものを成立不能にする点にある。
議事録に残らない「沈黙」の行方
恋愛の別れ話では、先送りの代償を払うのは当事者二人だ。しかし、組織の意思決定は違う。取締役会で交わされる沈黙や曖昧模糊とした合意の帰結は、会議室の外に広がっていく。そして、判断に関与していない無数の人々が、その結果を引き受ける。そこに、組織意思決定の“重さ”がある。
取締役会の判断には、常に明確な正解があるわけではない。だが、後から必ず問われる軸がある。それは、その取締役会の判断は、「社会からこの事業を任せてよい主体か」という問いを、正面から引き受け、検討した上での判断だったのか――ということである。
その問いを避け、目先の「マイナス5」から逃げた沈黙は、公式の議事録には残らないかもしれない。しかし、その空白は、組織の未来に、そして社会の記憶に、確実に刻まれていく。
だが、逆もまた真なり。いや、そこに活路があるはずだ。
「不都合な真実」という名の別れ話を、最も痛みの少ない初期段階で切り出せる組織文化を築くこと。それは単なる守りのガバナンスではない。不確実性が常態化した現代において、堅実な「組織の存続基盤(レジリエンス)」となりうる。
間違いを隠蔽するコストをゼロにし、早期の軌道修正を「称賛されるべき決断」へと書き換える。その困難ではあるものの、誠実なプロセスを積み重ねることが、組織運営に血を通わせる。サンクコスト(埋没費用)への執着を捨て、今日この瞬間に「不都合な真実」と向き合えるか。その摩擦を恐れず、むしろ健全な対立の火種として歓迎する組織へと変革すること。
それこそが、経営の中核を担う役職員が、組織の土台を再構築するために成すべき、最もシンプルにして、最も戦略的な投資なのだ。
(次回は2026年2月5日配信予定)