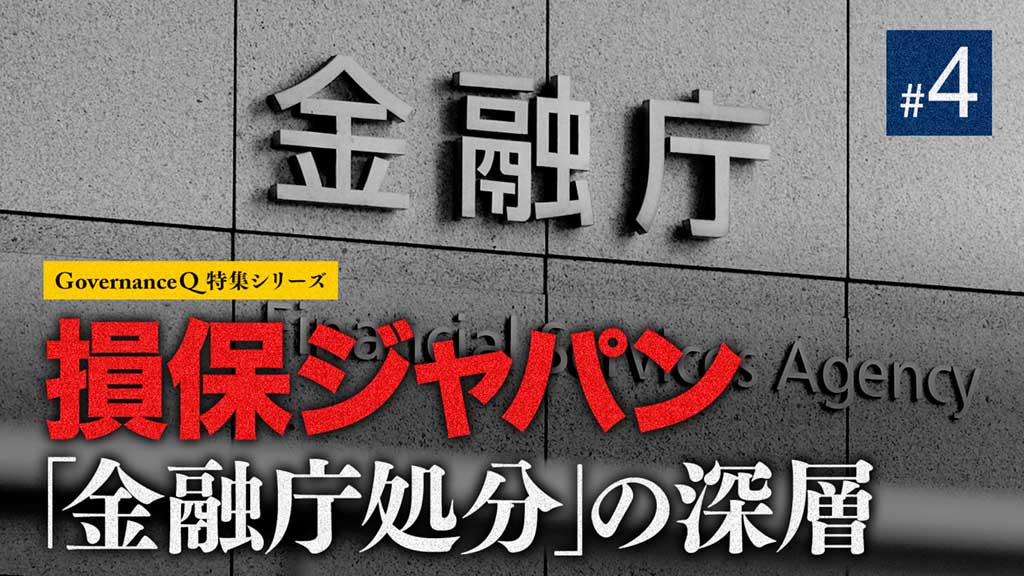(#3から続く)中古車販売大手のビッグモーターによる保険金不正請求問題をめぐって、金融庁は1月25日、損害保険ジャパンおよび親会社のSOMPOホールディングス(HD)に業務改善命令を出した。子会社の事業会社と親会社である持株会社がともに金融庁処分を受けたわけだが、SOMPOHDの子会社の監視・監督義務は一般の持株会社よりもより重い。#4では#3に続き、損保ジャパンでリスク管理担当役員を務め、現在は日本経営倫理学会常任理事の井上泉氏(ジャパンリスクソリューション社長)が、SOMPOHDの経営責任を検証する――。
SOMPOHDとはいかなる「持ち株会社」なのか
前記事では、親会社の取締役が負っているとされる子会社監督責任の内容と範囲については、各企業の個別性によって判断が分かれることをお伝えしましたが、そこで、ここではSOMPOHDの責任のあり方を考える時に、SOMPOHDの性格と同社と子会社の損保ジャパンとの関係性がどのようなものであったかを考えてみましょう。
SOMPOHDは持株会社ですが、持株会社とは、他の会社を支配する目的で、その会社の株式を保有する会社のことです。持株会社には2種類あります。通常よく見られるのは、自らも生産・販売等の事業を営みながら、子会社を設立し、その会社の事業活動を支配する目的で株式を保有するケースです。これは「事業持株会社」と呼ばれます。一方、自らは事業を行わず、他の会社の事業活動を支配する目的で、その会社の株式を保有する「純粋持株会社」があり、SOMPOHDは「純粋持株会社」です。
SOMPOHDは子会社管理専門の会社である
SOMPOHDの定款第2条には、会社の目的として「損害保険会社、生命保険会社その他の保険業法の規定により子会社等とした会社の経営管理」を掲げています。つまり、他の営利事業は行わず、子会社群を管理・監督することだけを使命としている会社(純粋持株会社)なのです。純粋持株会社であるSOMPOHDの下には22の連結子会社と多数の関連会社がぶら下がっています。
SOMPOHDはこれらの子会社等からの株式配当と子会社から徴収する業務指導料(手数料)が収入の原資となります。このような性格を持った純粋持株会社の子会社に対する責任が、他の事業持株会社とまったく同じということはあり得ないでしょう。
SOMPOHDは「保険持株会社」である
保険会社を子会社とする持株会社は、保険業法で規定される「保険持株会社」と呼ばれます。保険会社の高い公共性に鑑み、保険持株会社の設立には、内閣総理大臣の認可を受けなければなりません。そして、保険業法では、保険持株会社は、その業務を営むに当たっては、「その子会社である保険会社の業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない」(同法271条の21第3項)とあり、格別の義務を保険持株会社に課しています。
損保ジャパンはSOMPOHDを構成する22の連結子会社の中にあって、“最大最強”と言ってよい存在です。下記の表は、SOMPOHDの事業セグメント別に収益、純利益、従業員数を示しています。異なった事業分野での決算数値の比較は単純にはできないのですが、それでも大体のイメージは掴むことができます。国内損害保険事業のほとんどが損保ジャパンの数字ですから、いかに損保ジャパンがグループ内で大きな地位を占めているかがわかります。
SOMPOHDの事業セグメント別業績(2022年度)
| 事業セグメント | 収益 | 純利益 | 従業員数 |
| ① 国内損害保険事業 | 正味収入保険料 2兆2,905億円 | 550億円 | 2万3,500人 |
| ② 海外保険事業 | 正味保険料 1兆3,801億円 | 480億円 | 7,467人 |
| ③ 国内生保事業 | 生命保険料 3,108億円 | 10億円 | 2,636人 |
| ④ 介護・シニア事業 | 経常収益 1,516億円 | 7億円 | 13,840人 |
保険事業には強い規律が必要
以上をまとめると、次のように言えるでしょう。
① SOMPOHDの会社の性格、法的に課せられた義務から、親会社たるSOMPOHDは、子会社損保ジャパンの業務が健全かつ適切に運営されているか監督する義務がある。そして、その責任の度合いは、一般の「事業持株会社」に求められるものよりもはるかに高いレベルであるべき。
② とりわけグループ内で影響力の大きい損保ジャパンに対しては、特段の注意をもって、その業務運営を見守る責任があった。
③ SOMPOHDは損保ジャパンの業務執行に関し、その主体性は尊重しながらも、契約者保護やコンプライアンス上の問題が発生しないよう普段から積極的に監視を行い、もしそのような兆候が観察された場合は、損保ジャパン任せにせず、ただちに是正の努力を主体的に行うべきであった。
このような観点から親会社責任を考察すると、SOMPOHDが、これまで損保ジャパンに示してきたガバナンスに関する対応は、保険事業の社会性・公共性(契約者保護、コンプライアンス重視)を考慮したとき、あまりに消極的に過ぎ、是認されないということになります。
(#5に続く)
【前回シリーズ】「ビッグモーター×損保会社」問題の核心(全6回)