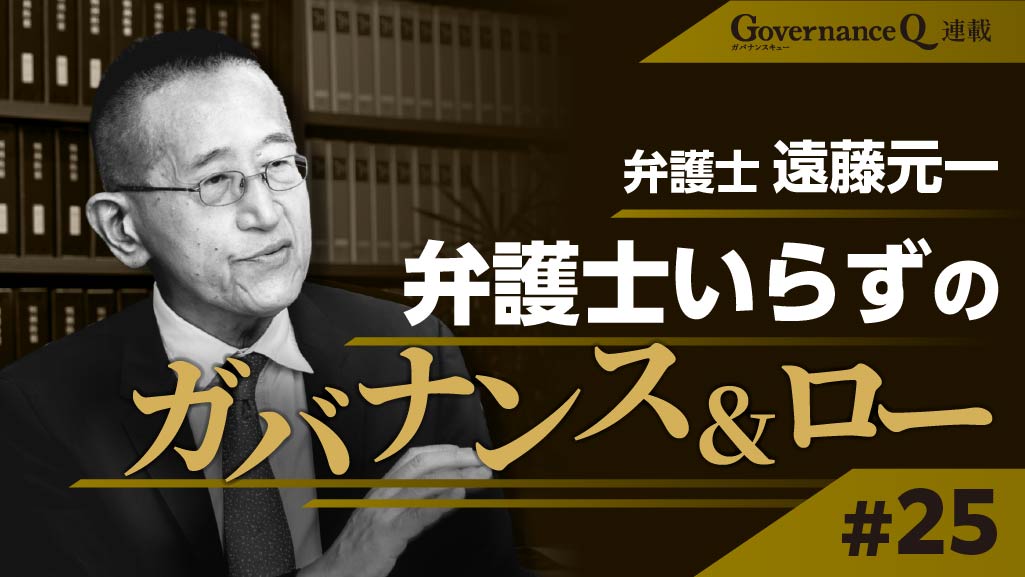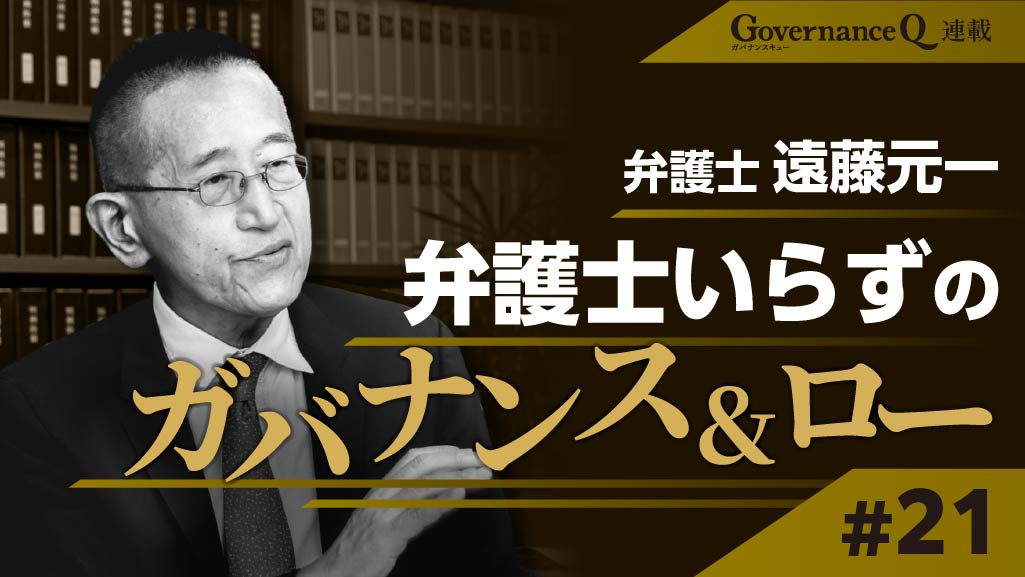夏祭りの露店と言えば、「金魚すくい」が真っ先に思い起こされる。筆者の自宅がある横浜のあちらこちらの商店街でも、子どもに限らず、大人も金魚すくいを楽しんでいるシーンが目に付くようになってきた。最近は、自分ではなく、他人が金魚すくいをしている姿を夏の風物詩として鑑賞するのが楽しみだ。
ところで、金魚をすくう円形の枠に和紙を貼った道具を「ポイ」というらしい。和紙は濡れると時間の経過とともに強度が落ち、金魚が飛び跳ねようものなら、すぐに破れてしまう。水に濡らす時間を短くし、金魚の泳ぎにあわせて和紙に負担がなるべくかからないようにポイをうまく捌くのがポイントだ。
そんなポイの動きを見ていて、日本版スチュワードシップ・コードの第3次改訂のことを思い出してしまった。
日本版スチュワードシップ・コードの5年ぶりの改訂
今年6月26日、5年ぶりに金融庁の「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」(以下、改訂検討会)から、日本版スチュワードシップ・コード(同、SSコード)の第3次改訂(同、改訂SSコード)が公表された。
SSコードの改訂方針は、「スチュワードシップ・コード及びコーポレート ガバナンス・コードのフォローアップ会議」が昨年6月7日に公表した「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム2024」(同、意見書)において、「…(省略)…建設的な目的を持った対話に資する協働エンゲージメントの促進や、実質株主の透明性確保に向けて、スチュワードシップ・コードを見直すべきである」と記されていたことを受けてのこと。
結果、協働エンゲージメントの促進と実質株主の透明性確保に関する条項がSSコードに追加された。つまり、5年ぶりの改訂の目的は、協働エンゲージメントの一層の推進、エンゲージメントに際して投資先の会社へ株式保有状況を説明することである(その他、策定・改訂時から一定期間が経過し実務への浸透が進んだ箇所等を削除・統合・簡略化するなど、コードのスリム化を図ることも目的のひとつとされている)。
実質株主の透明性の確保
先に「実質株主の透明性確保」について説明しよう。機関投資家が保有する株式は、通常、信託会社に保管を委託しており、信託が名義人となっている。株主総会議案に関する議決権は名義人が行使するが、機関投資家が名義人に賛否を指図することとなっていて、こうした議決権行使を指図する権限を有する者を「実質株主」という。
わが国の上場会社の側からは、株主名簿で確認できるのは名義人までで、実質株主を正確に把握することは難しい。機関投資家からエンゲージメント(対話)を求められる場合、当然ながら、上場会社としては、その機関投資家がどれだけの議決権(株式)を保有しているのか――は重要な関心事項である。
しかし、株式保有数を知らせることは運用戦略を窺わせる場合もあるため、機関投資家によっては保有株式数を知らせないことも少なからずある。実際、これまでのSSコードでは、「どの程度投資先企業の株式を保有しているかについて企業に対して説明することが望ましい場合もある」(注15)との注釈にとどまっていた。
ところが、今回の改訂においては、指針に格上げして、「どの程度投資先企業の株式を保有しているかについて企業に対して説明すべきであり、投資先企業から求めがあった場合の対応方針についてあらかじめ公表すべきである」(指針4-2)とした。
協働エンゲージメント
もうひとつが「協働エンゲージメント」である。協働エンゲージメントとは、投資先の会社との建設的な目的を持った対話を、複数の機関投資家が協働で行うことを意味している。協働エンゲージメントは、単独では限定的な影響力しか及ぼせない機関投資家が、より強い影響力を行使して投資先企業に働きかける目的で用いられる手法である。
協働エンゲージメントについて、現行コードは「有益な場合もあり得る」(指針4-5)としていたが、改訂によって「重要な選択肢である」と改められ、かつ「対話のあり方を検討する際には、投資先企業の持続的成長に資する建設的な対応となるかを念頭に置くべきである」(指針4-6)との一文が追加された。
SSコードに賛同して参加している機関投資家等は、改訂コード公表から遅くとも6カ月後(今年12月末)までに、改訂内容に対応した公表項目の更新(および更新した旨の公表と金融庁への通知)を行うことが期待されている。
改訂SSコードは狙い通りの効果を発揮できるか
では、改訂SSコードがその狙い通りの役割を発揮するかというと、残念ながら、あまり期待できないのではないかと、筆者は推測している。そう考える理由は次の通りだ。
特に焦点になるのは、改訂SSコード指針4-2で実質株主の透明性が確保されるかという点だが、改訂SSコードも、これまでと同様、「コンプライ・オア・エクスプレイン」(原則を遵守するか、そうでない場合はその理由を説明するか)の手法を採用している。したがって、理由があれば(“それらしい理由”を掲げれば)株式保有の状況を説明しなくてもよいとの結論に変わりはない。
もちろん、実質株主の透明性確保は会社法改正の対象として法務省法制審議会(株式・株主総会等関係)で審議中であり、上場会社としては、機関投資家(さらにはアクティビスト=物言う株主)の株式保有状況を確認できる規定の新設が期待される。もっともそれでも、実質株主の状況を把握できるのは発行会社(上場会社)が念頭に置かれていて、資本市場に対して明らかにすることは想定されていないようだ。
しかし、実質株主の開示は、①資金の出し手と名義株主との乖離が著しく、資本市場の透明性の低さを解消し、一般投資家の投資判断を支える情報開示を充実することが本来の目的である。その実現のためには、上場会社だけでなく、資本市場に対して実質株主を「見える化」することが求められるだろう。
また、②経営に影響を及ぼす実質株主の属性を開示し、さらに開示義務違反(情報提供請求に応じないという法的構成を採用する国もある)に対して株主権行使の制限を含む民事・刑事上のエンフォースメント(法執行)を課すことは、コーポレートガバナンスの健全性の確保のため、また、そうした制度を有する欧州市場とのイコールフッティングさせた資本市場の整備のためにも必要であろう。
ところが、改訂SSコードに上記①と②を期待することは、プリンシプル(原理原則)ベースの性質上、期待できず、また、会社法改正についての法制審議会での議論でも期待することは難しいと想定される。
改訂SSコードを受入れるか否かはあくまで任意
以上の通り、SSコードの受け入れを表明している機関投資家との関係でも、実質株主の透明性を確保することは期待できない。
そもそも、機関投資家がSSコードを受け入れるかどうかは任意であり、受け入れを表明していない機関投資家(機関投資家と称するアクティビストを含む)にとっては、改訂SSコードは何ら考慮する必要がないという根本的な問題もある。
確かに、SSコードの受け入れを表明する機関投資家の数は確実に増加しつつあり、今年3月31日時点で340機関にも上る。しかし、SSコードの受け入れを機関投資家の自主的判断に委ねる限り、日本国内に本店・支社・支店を有せず、金融庁や東証に忖度する必要がない海外の機関投資家に、(改訂)SSコードの自発的な受け入れを期待することは難しい。
しかし、米国の1934年証券取引所法2条4項が明記している通り、資本市場は、資本が支配する熾烈な場であり、信頼できる市場の基盤を整備するには多様なエンフォースメント手段を備えることが必要であることは資本市場の歴史に照らし、自明の理といってよかろう。
信頼できる市場の基盤を整備するには、SSコードをハードロー化して国内外の機関投資家に強制的に適用するか、すべての機関投資家、特に金融庁や東証に何ら忖度する必要がない海外の機関投資家にも改正SSコードの受入れを表明するように仕向ける合理的なインセンティブを設定する必要があり、そこまで徹底して制度設計を行うことが求められるのではなかろうか。

株式市場の“金魚”を総ざらいするには
夏祭りの金魚すくいの話に戻ろう。
さまざまな夜店や屋台がひしめき合い、たくさんの人々が行き交う夏祭り会場の一角にある金魚すくいの会場で、金魚をすくおうとしても、慣れている人でない限り、一匹の金魚をすくうことすら容易ではない。特に幼い子どもなどは大抵、金魚を無理にすくおうとして途端に和紙が破け、ゲームオーバーの事態となる。
金魚が飛び跳ねては和紙が破れる光景が繰り返されるのを見ながら、SSコードと機関投資家の関係を思った。
ポイの和紙(SSコード)を破って(受け入れず)、水槽を自由気ままに泳ぎ回る金魚(SSコードに沿った行動をしない機関投資家)。水に濡らしても強度が落ちず、簡単には破れないような和紙をポイに用いて(コードを受け入れるように誘因するインセンティブを設定した仕組みで)、水槽を泳ぎ回る金魚(機関投資家)をすべてすくえたら、さぞ爽快な気分になるだろう。いや、それでも、和紙を破って水槽を泳ぎ回る金魚は必ずいるかもしれない……。では、ポイに網を張ればいいのか……。
とはいえ、本当の金魚すくいはポイの和紙が破れてしまうことにハラハラするからこそ、楽しいのは言うまでもない。
(本連載は今回で一度休載のうえ、今年10月以降の再開を予定しています)