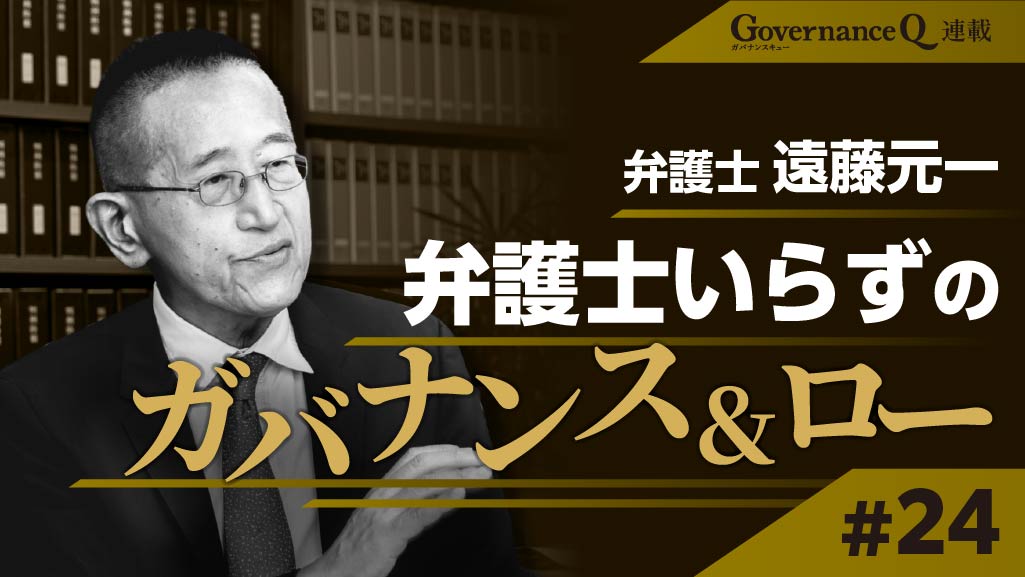天空を埋め尽くして輝く長岡の花火を見て感じたこと
先週土曜日(8月2日)、日本屈指の花火大会といわれる新潟・長岡の花火を見てきた。
長岡駅から30分くらい歩いて信濃川の会場に着くと、目の前には、長生橋のたもとから約250メートル、長岡大手大橋からは約50メートルに位置する広大な河川敷が広がっていた。それだけに、花火の打ち上げ場所も相当広く確保できるため、長岡花火は、多種多様な大型スターマイン(いくつもの花火玉を組み合わせる連発花火)を数多く打ち上げることができるのだそうだ。
直径650メートルの大輪の華が空に広がる「正三尺玉」や、幅2キロにわたる「フェニックス」、大絵巻のストーリーを描くかのようにさまざまな花火が繰り出される「天地人」などが次々に打ち上げられ、あっという間に2時間余が経過した。
いうまでもないが、花火が天空を埋め尽くして輝くのは、短時間、ほんの一瞬の時間。だからこそ、その瞬間にだけ描かれる花火は見る人の心に大きな感動を刻み込むのだと思う。
しかし、資本市場の上場企業は花火とは異なり、上場はゴールではなく、新たなスタートに過ぎない。上場後、如何に成長ストーリーを実現して企業価値を高めるか真価が問われる。つまり、上場を果たした後短期間で資本市場から退出することは、公開企業のとるべき選択肢ではないはずだ。
ところが、この選択肢でないはずの途を選択せざるを得ない企業がときどき市場に登場することがある。
オルツ事件とは
直近、にわかに注目されているのは、AI(人工知能)開発のスタートアップで、東証グロース市場に上場しているオルツの粉飾事案だ。
2024年10月の上場直後には、日本初のAIベンチャーとして1兆円の価値を目指すなどと宣言していたオルツ。しかし、7月28日に公表された第三者委員会の調査報告書によると、オルツは広告宣伝費として広告代理店4社に約138億円、研究開発費として事業者2社に約16億円を支出。その後、広告代理店を経由してスーパーパートナー(SP)と呼ばれる販売業者から架空の売上代金を回収するという循環取引を繰り返していた。オルツの売上高の過大計上による影響額は約119億円に上り、実に売り上げの約9割が架空だったという。
7月30日、オルツは東京地裁に民事再生手続開始申立てをし、あくまで事業継続を模索する姿勢を示しているが、売り上げが約1割の実体しかない事業では、市場で競争力がある事業なのか甚だ疑わしく、スポンサー探しも困難を極めることは確実だ。
株価も調査報告書の公表後、値幅制限の下限(ストップ安水準)まで下げた後、8月1日には一時20円近くまで値を下げ、新規上場時には約190億円だったオルツの時価総額は8億円以下にまで目減りした。
オルツの一連の粉飾スキャンダルは、監査法人やVC(ベンチャーキャピタル)も、主幹事証券会社も、取引所も、オルツの会計不正を見逃していたということになる。つまり、資本市場のゲートキーパー(門番)としての役割を発揮できずに、このような会社を上場させ、個人株主を中心とした投資家に大きな損失を被らせたのみならず、AI業界やスタートアップ全体に対する信頼に悪影響を与え、新興市場の上場審査の信頼性を大きく揺るがせている。