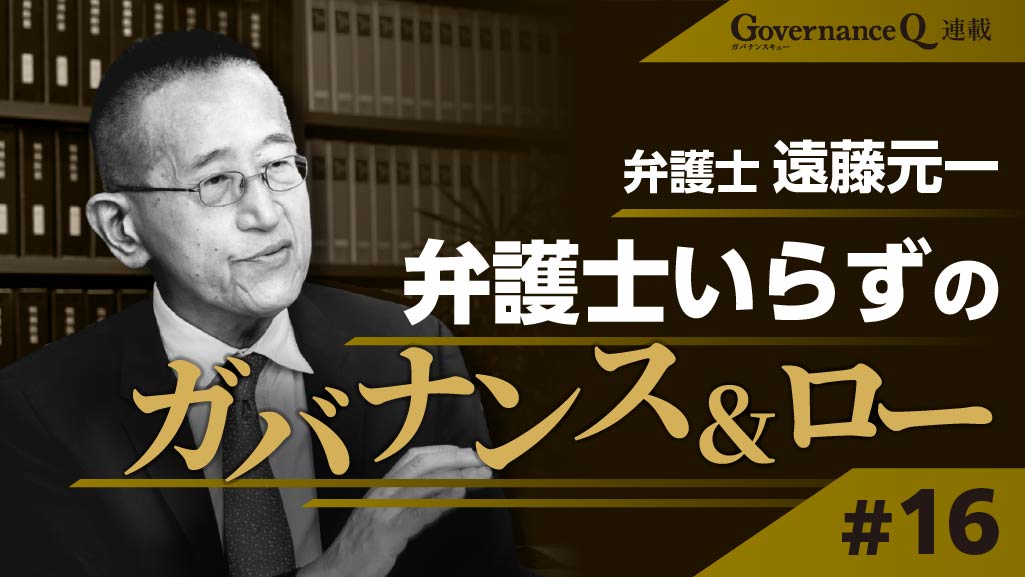社会科学などで多用される「三層構造モデル」
直近数回ほど、個別事案に触れたものが続いたが、今回はやや概念的ながら、「内部統制システム」について取り上げたい。
社会科学の領域を中心として、「三層構造」を用いた分析手法が浸透して久しい。古くは精神分析学の領域で、ジークムント・フロイトが「心の三層構造モデル(構造モデル)」を提唱したことが有名だ。
フロイトは、心の構造をさまざまな欲求が無秩序に存在する「イド:Id」(無意識の領域)、「エゴ:Ego」(自我の領域)、イドとエゴを律する“良心”というべき「スーパーエゴ:Superego」(上位自我)という3つの構成要素に分けて考える。
また、歴史学の領域では、フェルナン・ブローデルが歴史の三層構造を提唱した。ブローデルは、歴史を「短期波動」(短期的な事件で、中期的な社会状況に影響されて発生)、「中期波動」(中期的な社会状況で、長期間変化しない構造を土台に形成)、「長期波動」(長期的に持続する構造で、すべての土台となる)の3つの構造で捉える。
さらに最近では、「Web三層構造(アーキテクチャ)」という概念も登場している。機能や役割を「プレゼンテーション層」「アプリケーション層」「データベース層」の3つの層に分けて管理し、Webアプリを開発・構築する際の基本的な構造として利用されている。
論理的に物事を考えるとき、3つくらいに分けて考えることは、三段論法などで馴染みがあり、社会科学、自然科学などの分野でも使われている。今回のテーマ、会社法の内部統制体制(システム)についても同様で、(会社法研究者や法曹実務家にも十分には認識されていないけれども)30年前に裁判所で初めて認められた当初から、実は三層構造で語られていたのだ。