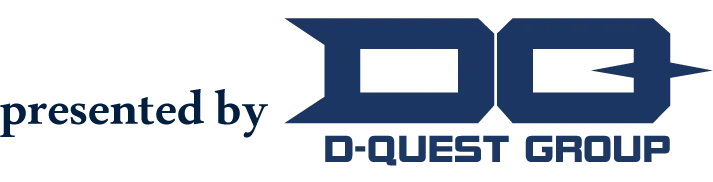夕暮れ時、古い工場の敷地に立つと、時折、機械の低い唸りが風に混じって聞こえてくる。油と金属が長年にわたって染み込んだ、わずかに甘く、重たい匂いが、冷え始めた空気の中に漂っている。生産量が急増するわけでもなく、株価を押し上げるニュースがあるわけでもない。それでも、その音と匂いには、何十年にもわたり地域の雇用と技術を支えてきた時間の堆積が刻み込まれている。市場の取引画面には映らないが、企業の現場には、確かに流れている時間がある。
企業には、市場の時計とは異なる速度で流れる「時間」がある。この当たり前の事実が、近年の日本の資本市場では、しばしば見失われがちになっているように思われる。
市場が捉えるのは、常に「いま」の断面である。一方、企業の意思決定は、過去に引き受けた時間と、将来にわたって背負う時間のあいだで行われる。そのズレが、評価の緊張を生む。
ノーベル経済学賞を受賞した心理学者ダニエル・カーネマンは、その著書である『ファスト&スロー(Thinking, Fast and Slow)』で、人間の判断を「速い思考」(システム1)と「遅い思考」(システム2)に分けて説明した。直感的で即断的、パターン認識に優れた前者と、論理的で熟慮を要する後者。どちらが優れているという話ではなく、状況に応じて両者を使い分けることが、人間の合理性を支えている。
この枠組みを、日本の資本市場、とりわけ2015年以降に本格化したコーポレートガバナンス改革に重ねてみると、ある偏りが浮かび上がる。現在の市場は、制度的にも心理的にも、「速い思考」に極めて親和的な構造を獲得した。その一方で、企業が長年かけて形成してきた「遅い時間」を、どのように評価し、どのように市場と共有するのかという問いは、なお十分に整理されていない。
米欧のモノサシで解像度を上げるという選択
コーポレートガバナンス・コード(15年)およびスチュワードシップ・コード(14年)の導入は、日本企業の統治構造に大きな転換をもたらした。その背景にあったのは、日本経済の長期停滞と、グローバルにあふれる投資資金の存在である。
世界には余剰資本が存在する。しかし、それは無差別に流れ込むわけではない。資金は、「理解できる市場」「比較可能な市場」を選ぶ。ガバナンス構造が不透明で、企業行動の合理性が読み取れない市場に、長期資金は定着しない。
日本のガバナンス改革は、端的に言えば、日本企業を米国・欧州の投資家が理解できる言語に翻訳する試みであった。社外取締役の独立性、委員会設置、ROE(自己資本利益率)やROIC(投下資本利益率)といった資本効率指標、エンゲージメントを前提とした対話の制度化……。これらはいずれも、日本企業の内部構造を「外から測れる形」に変換する――とりわけ、グローバルな投資家のモノサシに尺度を合わせ、日本企業の解像度を上げる装置である。
この方向性自体を否定することはできない。閉鎖的で、説明を欠き、内部留保を積み上げること自体が目的化していた日本型経営が、国際資本から評価されなかったのは事実である。改革は、日本市場の解像度を引き上げ、一定の資金流入を実現した。その意味で、この改革は明確に「成功」した側面を持つことは否定できない事実であろう。
PER、PBR……指標が語り始めるとき
しかし、翻訳は常に、原文の一部を切り落とす、あるいは脚色する作業が伴う。
近年、その象徴として浮上しているのが、PER(株価収益率)やPBR(株価純資産倍率)といった株価指標の扱われ方である。指標が前面に出るとき、市場は企業に語りかける。「あなたは、なぜこの数値なのか」と。
23年、東京証券取引所が「PBR1倍割れ企業」に対して改善策の開示を求めたことは、市場に極めて明確なメッセージを送った。すなわち、「評価されていない理由を説明せよ」という要請である。
ここで市場の「速い思考」は、即座に作動する。PER1倍未満=利益は出ているが、将来の成長が期待されていない。PBR1倍割れ=資本が効率的に使われていない――。こうした判断は分かりやすく、比較可能で、投資判断にも用いやすい。だが同時に、その背後には、多くの前提が暗黙のうちに置かれている。
そもそもPBRは、帳簿上の純資産と市場評価を比較する指標に過ぎない。日本企業の貸借対照表には、取得原価主義や減損ルール、歴史的な資産構成といった制度的制約が折り重なっている。帳簿価額と事業価値との乖離は、経営判断の誤りではなく、制度の帰結として生じている場合も少なくない。
「遅い企業」が抱える構造的制約
鉄鋼、化学、造船、海運といった装置産業は、巨額の初期投資と長期にわたる償却を前提とする。景気循環の谷では利益が圧縮され、PERは容易に1倍を下回る。しかし、それは経営の失敗を意味するわけではない。むしろ、事業継続を前提とする限り、合理的な資本構成である場合も多い。
地域金融機関や不動産開発も同様である。地域経済の下支え、雇用の維持、取引関係の継続といった役割は、四半期決算や単年度の利益指標にはほとんど反映されない。それでも、これらの企業は、地域社会の“時間”を引き受けることで存在意義を保ってきた。
PERやPBRという一枚のラベルは、こうした企業の「遅い時間」を切り取ってその断面を見せることはない。むしろ切り捨ててしまう。その結果、「解体」「縮小」「即時の還元」といった選択肢だけが過度に強調される。
ガバナンス改革の静かな逆説
ここに、ガバナンス改革が孕む逆説がある。改革は本来、「中長期的な企業価値向上」を掲げていた。理念の水準では、明らかに「遅い思考」を市場に埋め込もうとしていたのである。
しかし実務の現場では、制度はしばしば「速い評価」で回収されてしまう。社外取締役の人数、独立委員会の設置有無、ESGスコア、資本効率指標……。これらは測定可能で、説明しやすく、比較にも適している。その結果、ガバナンスは、企業の時間を守る緩衝材ではなく、市場の速度を企業に伝える増幅器として機能し始めている。
つまり、制度は洗練されたが、語られない価値が増えた。その空白をどう埋めるかが、次の課題となる。
取締役会で感じる「時間の緊張」
法曹実務家のバックグラウンドを有する取締役として取締役会に関与していると、この緊張は抽象論ではなく、具体的な空気として立ち現れる。研究開発投資や人材育成は、短期的には指標を悪化させる。しかし、そこに手を付けなければ、数年後の競争力は失われる。経営判断とは、つねに時間軸の選択を伴う行為である。
それにもかかわらず、取締役会で頻繁に問われるのは、「市場はどう反応するか」「株価にどう響くか」という即時的な評価である。企業が持つ「遅い時間」の価値を、市場に向けて翻訳する言語は、なお十分に共有されていない。

「ナラティブ」という回復の回路
この断絶を埋める手がかりは、近年ようやく姿を見せ始めている。統合報告書や人的資本開示は、単なる情報量の増加ではない。それは、企業が自らの価値創造を、時間軸を含んだ物語(ナラティブ)として語るための制度的空間である。
PER1倍未満という数値の背後には、必ず固有の文脈がある。景気循環のボトムにある装置産業、構造転換の途上にある地域金融機関、長期的な研究開発に資源を振り向ける製造業――。これらの企業が直面しているのは、同じ「1倍未満」という数値でも、その意味はまったく異なる。しかし、指標だけを見る市場の目には、その違いは映らない。
ナラティブとは、この文脈を回復させる試みである。なぜこの投資を選んだのか。どのような時間軸で価値を創造しようとしているのか。何を守り、何を変えようとしているのか。こうした問いに対して言葉を紡ぐことは、単なるIR(投資家向け広報)活動ではない。それは、企業が自らの時間を市場の言語に翻訳し、理解可能な形で提示する、ガバナンスの中核的な営みである。
カーネマンの枠組みに立ち返れば、ナラティブとは「遅い思考」を市場に届けるための装置だと言える。数値は速い判断を可能にするが、物語は熟慮を促す。両者は対立するものではなく、補完し合うべきものだ。
速い測定と遅い理解。その2つを対立させるのではなく、どう調律するか。そこに、これからのガバナンスの知恵がある。
「時間を説明する責任」というガバナンス
もうひとつ見落とされがちな論点がある。それは、「遅い時間」を生きること自体が、もはや暗黙の了解として許容されなくなっているという現実である。かつては、長期雇用や設備投資、取引関係の継続といった日本企業の行動様式は、それ自体が説明不要の前提として共有されていた。しかし現在、その前提は失われた。市場が変わった以上、企業は「時間をかける理由」を語らなければならない立場に置かれている。
これは、企業にとって不利な条件であると同時に、機会でもある。なぜなら、語ることを通じて初めて、企業の時間は市場の時間と接続されるからだ。時間をかけることは、もはや黙示的な正当性ではなく、説明責任の対象となった。その説明を、数値だけで行うことはできない。ここに、ナラティブと対話の必然性がある。
企業は時間とともに生きる
市場の時計は正確で、時に無慈悲だ。しかし、企業は時計だけで生きているわけではない。PERやPBRが示す瞬間の像と、企業が歩んできた長い時間。その両方を同時に見る視線を、市場はまだ十分に獲得していない。
PER1倍未満、PBR1倍割れの企業が突きつけているのは、怠慢への批判ではなく、時間の扱い方そのものへの問いである。企業の価値は、決算短信や指標の中だけに存在しているわけではない。
取締役会で交わされる逡巡、現場で積み重ねられる判断、そして語られないまま引き受けられてきた時間の重み――そうしたものの総体が、企業という存在を形づくっている。
ガバナンスとは、ルールを整えることでも、指標を満たすことでもない。異なる時間軸を生きる市場と企業のあいだで、何を急ぎ、何を待つのかを選び続けるための、ひとつの知恵の体系である。
PER1倍未満というラベルの向こう側に、どのような時間が流れているのか。その問いに耳を澄ませ、急がず、しかし立ち止まり過ぎずに考えること。そこから始まるガバナンスは、必ずしも弁護士の言葉を必要としない。
必要なのは、制度を守ることではなく、時間を理解しようとする姿勢である。その姿勢さえあれば、ガバナンスとローは、現場の言葉で語り直すことができる――。「弁護士いらずのガバナンス&ロー」は、2026年も、静かに続いていく。
(次回は2026年1月22日配信予定)