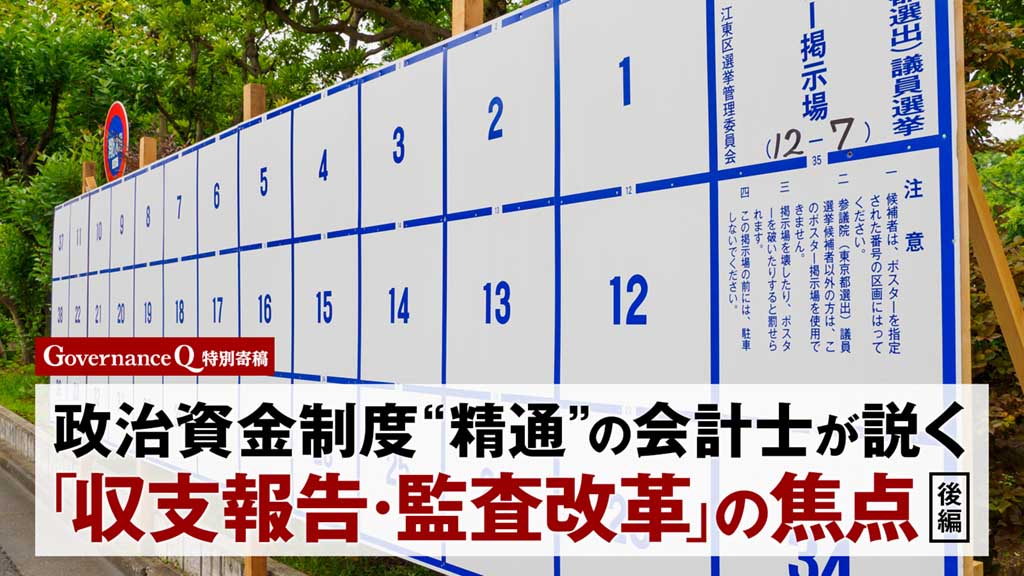1.実効性ある改革に向けて考慮すべき急所
国会議員事務所のガバナンス――「究極の個人商店」
(前編から続く)かように多くの問題点を抱える収支報告書の開示と監査であるが、今後の改革を論じるにあたっては、永田町のリアル、国会議員事務所のガバナンスの実態を考慮に入れる必要がある。
程度の差はあれ、国会議員の事務所は、国民に選ばれた議員本人を頂点とする“究極の個人商店”である。そこにある内部統制は、ひとえに統制環境、即ち、議員本人の姿勢や倫理観(Tone of the top)にかかっており、それ以上でも以下でもない。昭和~平成~令和と、秘書や事務所職員のワークライフバランスも随分と改善されたではあろうが、多くの事務所ではリソースも潤沢ではなく、複式簿記の論点ひとつをとってしても、身分の安定した多くの公務員を抱える役所に導入するのとでは勝手が違う点に留意を要する。
「細則主義」と「原則主義」
「正すべきは正す」は当然として、いかにルールを細分化したとて、悪の会計リテラシーを持つ人物であれば、その裏をかくことは容易となる。21世紀初頭、リスクマネジメントの超優良企業の名をほしいままにした米エネルギー企業のエンロンが、細則主義(Rule Based)の会計基準をすり抜けるボックス・チェックの手法により巧妙に粉飾決算を企てたことは、今なお記憶に新しいところである。企業会計の世界においても、国際会計基準(IFRS)やサステナブル開示など、原則主義(Principle Based)はその主流となりつつある。
また、巨額の国費を投じて選任・維持される国会議員に、企業の新入社員同様の経費申請のイロハをルール化して課すよりも、本来は大人の節度ある常識を持った対応で臨んで欲しいところである。
悪しき選民思想からの脱却――果たして会計は些末なものか?
プライベートな問題を除けば、国会議員に関する不祥事の大半にはカネの問題がついて回る。したがって政治資金の問題は、議員本人にとっての“生死”をも左右する重要なものであるにもかかわらず、収支報告書のディスクロージャーに関しては、多忙を極める国会議員に「帳簿記入という些末な雑務に携わせることのないように」という悪しき選民思想、ひいては会計を一歩下に見るというかつての日本人の価値観が根底に存在するようにや感じる。
よって、ひとたび問題が生ずると、その責めは「会計責任者へ」という抗弁になるが、そこには議論のすり替えがあり、日常の実務はともかく、「会計説明責任」(accountability)は、本来、事務所の代表者たる議員本人が負うべきで筋合いであると考える。
今回の議論では、議員本人と会計責任者の間で交わされる「確認書」も争点となっているが、議員本人が会計責任者となり、担当者の任命・監督責任に緊張感を持たせるのも一考であろう。なお、上場企業の監査における「経営者確認書」とは、財務諸表の作成責任や内部統制の構築責任が経営者にあり、監査に必要なすべての書類を提供したことを宣誓するものである。前述のとおり、本来筆者は永田町に企業会計・監査のロジックを安易に持ち込むことには慎重であるが、この点は、原則主義の徹底の観点からも参考になるのではないか。