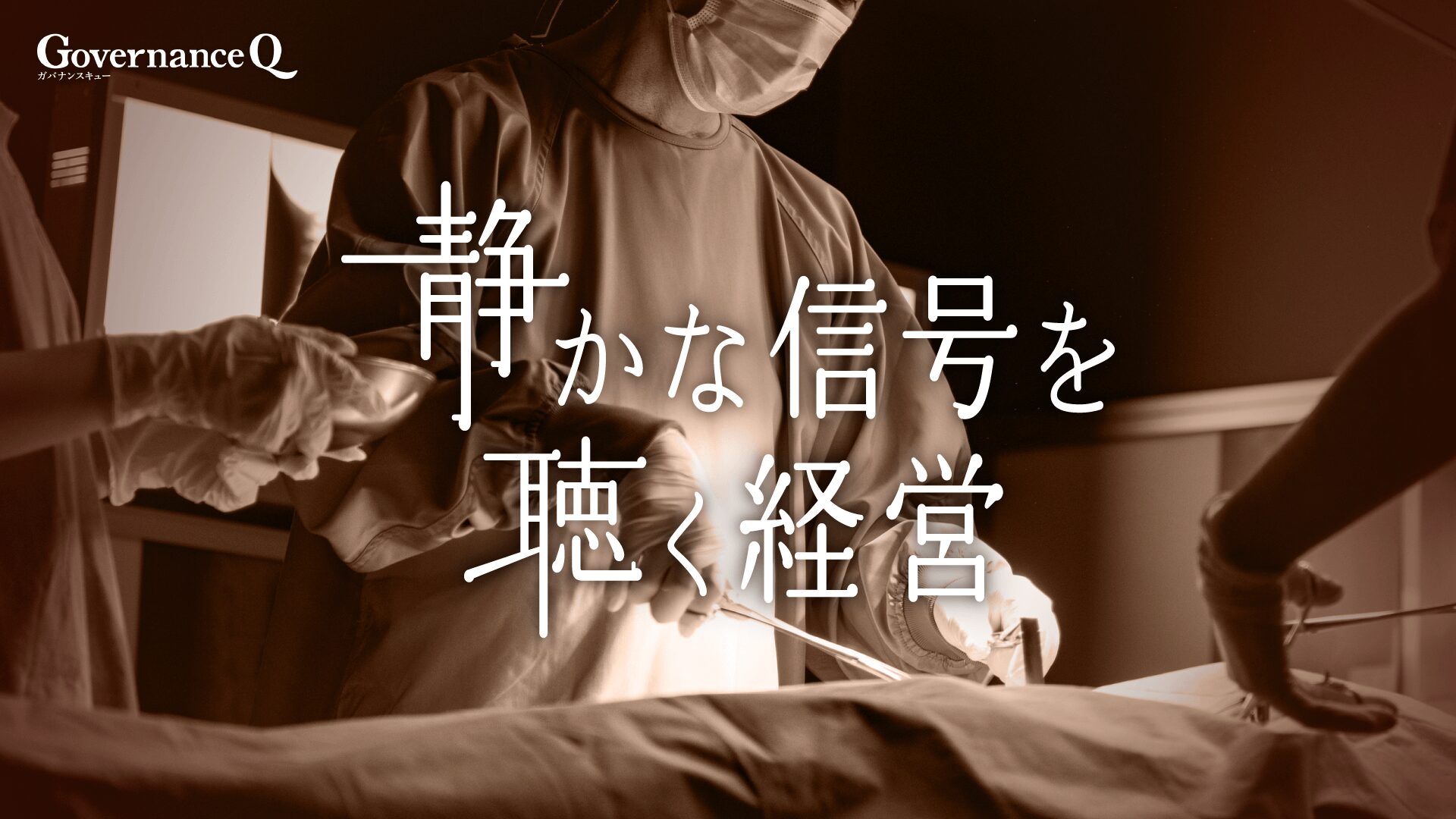遠藤元一:弁護士(東京霞ヶ関法律事務所)
自社の不正を検知する仕組みとして、ますます注目を集める企業の内部通報制度。果たして、日本企業は同制度が本来持つ“潜在力”を引き出せているであろうか――。本シリーズでは、ガバナンスと企業法務に精通する遠藤元一弁護士が、内部通報担当者のみならず、経営層に向けて、内部通報システムを企業の中核資産に転換する試みを各フェーズで提案する。題して「静かな信号を聴く経営」。
企業経営において、内部通報制度は、長らく法令対応やコンプライアンス部門の「備品」として扱われてきた。しかし本質はそこにはない。
通報制度は現場からの一次情報を拾い上げ、兆候を捉え、意思決定の質を底上げする経営装置である。経営幹部がこの装置を使いこなす時、通報制度は企業価値を生み続ける中核資産へと変わる。内部通報制度を「企業価値の源泉」として視点転換を図り、通報制度の制度設計の見直し・再構築に着手することは経営者が取り組むべき喫緊の課題である。
企業の意思決定とは、限られた時間の中で不確定かつ不完全な情報を統合し、未来の不確実性に挑む行為にほかならない。その過程で最も価値を持つのは、現場から上がる「違和感」や「兆し」である。これらはKPI(重要業績評価指標)や財務指標には表れないものの、組織の歪みやリスクの萌芽を最も早く知らせる信号であり、経営層にとって不可欠な非定量情報である。
こうした現場の声や兆候が通報制度を通じて経営層に届けば、リスクの初期検知や組織の健全性の把握が可能となる。その結果、企業は環境変化に柔軟に対応し、持続的な価値創造を実現できる。
したがって、通報制度は、現場で生じる微細な信号を経営判断に直結させる「センサー(感覚器官)」として設計されるべきである。財務指標や市場データと並び、現場の違和感を拾い上げる制度設計こそが、組織のしなやかさと持続可能性を支える鍵となる。
「見えなかった経営課題」をあぶり出す気象レーダーへ
これまでの内部通報制度は「火災報知器」のように、問題が顕在化した後に警告を発する装置にとどまってきた。これからは「気象レーダー」として、兆候を先取りし、進路を予測し、備えを促す存在であるべきだ。単発ではノイズにしか見えない情報も、複数が同じ方向を指す時、構造的な問題の兆候となる。通報制度は、経営が手を打つべき優先順位を示す羅針盤として機能する必要がある。
社長が通報起点の改善事例を月次会議で紹介し続けた結果、通報件数は著しく増加し、重大事故や不正事象が激減した企業を筆者は知っている。逆に、通報制度があっても、通報の阻害要因、窓口や体制の不備・限界などの欠陥が原因で、通報してもフィードバックがなく、現場が声を上げても無駄と感じれば、通報制度はワークせず、組織風土は淀み、悪化していく。残念ながら、そうした企業も目にしてきた。
内部通報制度が形骸化した組織では、問題は水面下で拡大し、外部からの指摘や事故・事件によって初めて表面化する。その時の衝撃、そして損害は、通報制度が機能していた場合の数倍、時には数十倍に膨れ上がる。
ESG経営、人権デューデリジェンス、各種規制……高まるレピュテーションリスク
近年の外部環境は、この制度の再構築を強く促している。公益通報者保護法の改正により、従業員300名超の企業は実効的な体制整備が義務化され、行政指導や企業名公表のリスクが現実のものとなった。資本市場ではESG(環境・社会・ガバナンス)や人的資本の開示内容が精査され、特に海外投資家は制度の有無だけでなく、その運用実績や改善事例まで求める。制度が形骸化している企業は、資本調達において明確な不利益を被る時代が到来した。
さらに、人権デューディリジェンス対応や贈収賄規制、環境規制など国際的な規制と社会的監視がサプライチェーン(供給連鎖)全体に及び、1社の問題が取引先にまで波及するケースが激増している。自社だけでなく子会社や委託先、合弁先での問題を早期に発見・対処できない企業は、外部から予期せぬ形で問題が公に晒される事態に遭遇する。
こうなると、もはや自発的な危機対応ができずに著しくレピテーション(評判)を毀損し、監督官庁、取引所、会計監査人、取引先などの様々な利害関係者との対応に忙殺され、行政処分や刑事罰、株主代表訴訟といった多重のリスクが同時に引き起こされる可能性もある。
企業の説明責任は「事後の釈明」から「事前の予防と学習」へと重心を移し、問題が発覚してから「知りませんでした」「制度はありました」ではもはや通用しない。ステークホルダーが求めるのは、予兆を掴み、学習し、改善し続ける企業である。
「ノイズにしか見えない単発の通報」を点から線、そして面へ
このような環境下で求められるのは、守りの制度から学習する制度への設計変更である。先述の通り、従来の内部通報制度は火の手が上がってから警報を鳴らす火災報知器だったが、これからは嵐の兆しを遠くから捉え、進路を予測し、備えを促す気象レーダーでなければならない。
通報は火の手の報告だけではない。日々の小さな摩擦音、現場の違和感、数値の裏側に潜む歪みが、ばらばらの形で上がってくる。製造現場からの「最近、材料の品質にばらつきを感じる」という声、営業部門からの「「自社製品が不当に値引きされているようだ」という情報、人事部門への「管理職のマネジメントスタイルが従来と変わってきた」という相談……。
単発では“点”にしか見えない内部通報だが、複数の情報が同じ方向を示す時、それは”線”となり、さらに増えれば”面”、つまり構造的問題の兆候となる。品質問題の背景には調達のコストダウン圧力があるかもしれない。価格競争の激化は業界構造の変化を示唆しているかもしれない。マネジメントスタイルの変化は、人事制度や評価基準の歪みを反映しているかもしれない……というわけだ。
内部通報制度の価値は、従来、「経営層に見えていなかった経営課題」をあぶり出し、経営が手を打つべき優先順位を示すことにある。通報制度が、部門の箱ではなく、経営直轄のセンサーとして設計され、機能しなければならない理由はここにある。
社長による改善事例の紹介で「通報件数が倍増」
トップが繰り返し意義を語り、自らが通報を積極的に拾い上げ、改善事例を全社に返す企業では、組織の風通しが良くなり、役職員の心理的安全性も高まる。それにより通報制度の活性化をもたらし、声が集まり、学習が回り、意思決定は現場に根を張る。
先に触れた通り、製造業のある企業では、社長が月次経営会議で必ず内部通報起点の改善事例を紹介し、改善に貢献した部門を表彰している。結果として通報件数は増加し(レポートラインの活性化と相まって)、重大インシデントは激減し、改善提案数は倍増した。制度は告発装置から改善エンジンへと進化しているのだ。
一方、内部通報制度を掲げながら通報しても反応が遅く、フィードバックがなく、現場が「何を通報しても無駄」と学習してしまった企業では、制度は形骸化し、情報は枯渇する。
消費者庁アンケート等に見え隠れする通報制度の“静かな枯死”
2024年度の消費者庁実施など、通報制度に関する各種アンケートには、通報窓口を設置して何年が経過するが、年間通報件数は10件未満。現場からは「以前に通報したが、何も変わらなかった」「むしろ面倒事のような扱いを受けた」、それどころか、「人事や待遇で不利益な扱いを受けた」という声が漏れている。制度は存在しても誰も信用していない。通報制度の“静かな枯死”こそ企業経営にとって最大のリスクである。

(東京・霞ケ関の消費者庁)
現代の企業経営において、最大の制約要因は資本でも人材でもなく、「情報の非対称性」である。経営層が意思決定を行う際には、財務指標や市場データと同様に、現場の声や兆候といった非定量情報が不可欠だ。これらは、数値では捉えられない組織の歪みやリスクの兆しを、最も早く知らせる信号である。
「内部通報=告発=ネガティブ」という固定観念
内部通報制度は、設計や運用次第でこの非定量情報を経営判断に直結させる“神経回路”として機能する。しかし、現場との情報ギャップが生じると、経営層は過去の成功体験に依存し、変化への感度を鈍らせるバイアスに陥る。その結果、意思決定は“過去の勝ちパターン”に縛られ、戦略は現場に届かず、現場の声も経営に届かない。こうして組織は空転し、施策は空振りし、機会は失われる。
このような情報の非対称性を解消する最も直接的かつ効果的な手段が、内部通報制度なのである。これは、経営と現場をつなぎ、組織の変化感度を高め、意思決定の精度と柔軟性を支える重要なツールであり、持続的な価値創造のための知的インフラとなり得る。
しかし、多くの企業は「内部通報=告発=ネガティブ」という固定観念に縛られ、制度の持つ積極的価値を見落としている。実際には、通報制度を通じて得られる情報の大半は、懲戒や告発に直結するものではなく、むしろ業務改善や制度見直し、研修強化といった前向きな変化のきっかけとなる「気づき」である。
ある金融機関の分析では、年間200件の通報のうち懲戒処分に至ったのはわずか5件であり、残りの195件は改善や学習の契機となった。制度は「犯人探し装置」ではなく「改善発見装置」として機能していたわけだ。
経営者が「内部通報制度」を使いこなす覚悟と矜持
内部通報制度を、単なるコンプライアンスの枠を超えた経営戦略ツールとして再定義し、パラダイムシフトを起こすこと――これこそが、今、経営者に最も求められる出発点である。
通報を歓迎し、通報者を評価し、通報を契機とした改善を称える組織文化を築くことで、企業は競合より一歩先んじた鋭敏な情報収集力とレジリエント(弾力的)な適応力を手に入れる。通報制度は、経営の意思決定を支えるセンサーであり、現場の声を未来の競争力へと変換する戦略的インフラである。
とはいえ、経営幹部がこの制度を“使う側”に回る重要性は理解できても、「具体的に何をどうすればよいのか」が示されなければ、納得と行動にはつながらない。確かに“万能の解”は存在しないであろう。しかし本稿ではあえて、その解を提示するという挑戦に踏み込み、実践的な指針を示したい。
続くⅡでは、内部通報制度が機能しなかった事例を解剖し、「何が欠けていたのか」を抽出する。そして「どう設計すれば防げたのか」という視点から、制度を機能させるための要件を検証する。その上でⅢ以下では、通報制度を経営の武器へと進化させるための設計原則、運用プロセス、そして文化醸成の方法論を具体的に提示していく。
内部通報制度は、法令対応やコンプライアンス部門の「部品」から始まるのかもしれない。また、これから展開する内容は、自社やグループ会社の通報制度の制度設計や運用状況等から見れば、要求水準が高すぎるのではないか、さらには理想論に過ぎないのではないかとすら感じる読者がいるかもしれない。
しかし、そこにとどまるか、経営の中核資産にまで高めるかは、経営幹部の強い意思と設計次第である。制度を「守りの盾」から「攻めの羅針盤」へと変革する第一歩は、経営者自らがこの装置を握り、使いこなす覚悟と矜持を持つことから始まる。しばしお付き合いいただきたい。
(パートⅡにつづく)