「内部通報は、最終的には“社員を守る仕組み”だと考えています」
事業所向け通販大手のアスクルは2025年4月、内部通報制度「アスクルホットライン」を大きく拡充した。その狙いを、内部通報を管掌するコーポレート本部コーポレートコミュニケーション統括部長の小和田有花氏はこう語る。新たな内部通報システムは、単なる法令遵守にとどまらない、アスクルの企業文化に深く根差した独自のコンプライアンス機能の強化へと進もうとしている。
「これまでの通報件数でよいのか?」という疑問
1993年に事務用品メーカー、プラスの通販事業部門として創業したアスクルは、BtoBのEC(電子商取引)事業「ASKUL(アスクル)」「ソロエルアリーナ」を中核にする東証プライム上場の総合EC企業。
2012年にはヤフー(現LINEヤフー)との業務・資本提携を契機にBtoC事業にも参入、日用品ECサービス「LOHACO(ロハコ)」などを通じて一般家庭にも広く浸透している。さらには、ペット・ガーデニング用品EC大手のcharm(チャーム)、ASKUL LOGIST(アスクルロジスト)などの企業向けロジスティクス事業、四阿山(群馬・長野)の雪融け水を原料としたナチュラルミネラルウォーターの製造販売を手掛ける嬬恋銘水などを傘下に抱え、小売りから物流、製造まで事業範囲は多岐にわたっている。
結果、本体とグループ各社、正社員から派遣社員、海外からの技能実習生まで含む多様な雇用形態の連結従業員は3687名(24年5月現在)。今後もグループ全体として企業規模、事業領域ともに成長が見込まれる中、アスクル社内では、従来の内部通報制度について「このままでいいのか?」といった疑問が共有されるようになっていったという。
「これまでもコーポレートガバナンスや内部統制を検証する際の基礎データとして、取締役会などで窓口に寄せられた内部通報の件数を報告してきました。その際、『この件数は果たして妥当なのか?』という根本的な疑問が経営陣、通報窓口を運営する私たち現場の間で持ち上がりました」(小和田氏)
確かに、経済メディアが発表する通報件数ランキングなどを見ると、特に巨大製造業企業では従業員数に比例する格好で通報の絶対数は当然多くなる。アスクルも従業員1人当たりの通報件数で比較すると、決して少なくはないのだが、やはり絶対数としては……。こうした認識が背景にあったという。
そもそも、アスクル本体の従来の内部通報制度は、郵送などのチャネルもあるが、基本的には小和田氏をはじめ社内の従事者7名(監査役含む)が個人の電話やメールアドレスで通報を受け付ける仕組み。グループ会社の従業員については、各社で通報窓口を設けながら、アスクル本体でも受け付ける二段構えで、社外では顧問弁護士事務所への通報ルートも用意していた。
「従事者には守秘義務があるとはいえ、“社員から社員へ通報する”という制度設計がメインになっていることが、グループ全体を含めた従業員の通報を躊躇させているのではないか。また、外部といっても、会社の顧問弁護士なので、その点も社員・従業員の心理的ハードルが高いのではということで、数年前からシステムの見直しを始めたのです」(小和田氏)
さらに近年、わが国で企業不祥事が相次いでいる状況を受け、内部通報制度が企業の自浄作用として機能することの重要性が強く認識されるようになっている。そんな社会的な背景も、単なる法令遵守を指向した形式的なコンプライアンス対応ではなく、実質的に機能する制度構築を目指すアスクルの動きを後押しした。
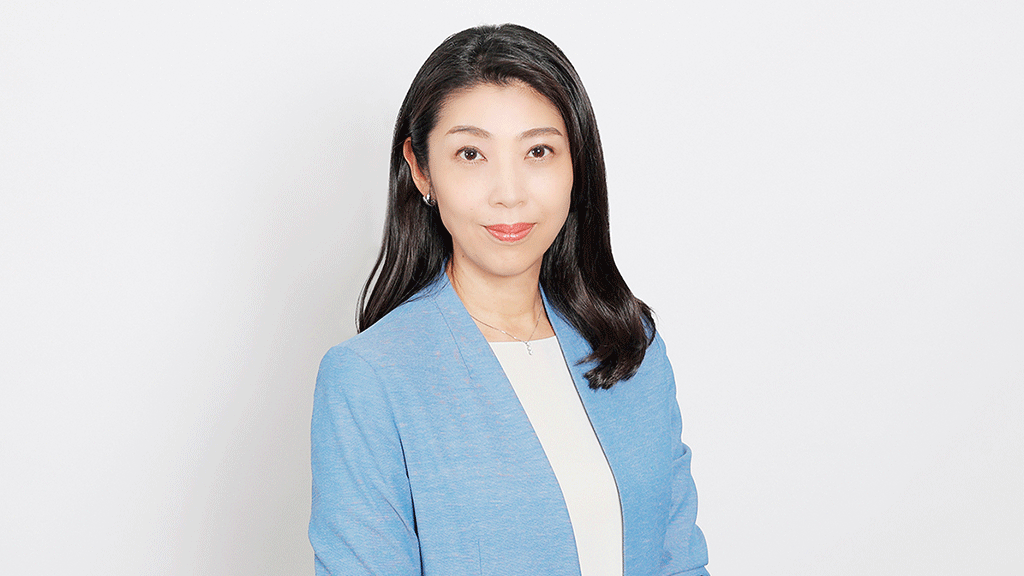
アスクルの新内部通報システム“3つの特徴”
こうして拡充についての検討が始まったアスクルの内部通報制度。役員レベルからの継続的な問題提起に加え、グループ全体でのガバナンス強化を図る中、24年夏、ディー・クエストが提供する外部システム「DQヘルプライン」の導入を決定、25年春に新制度がスタートした。その特徴は主に①通報受付対象の拡大、②多言語対応、③利用しやすい制度設計の3点にある。
①通報受付対象を「取引先」にまで拡大
アスクルの新内部通報制度の特徴のひとつは、通報を受け付ける対象範囲をグループ従業員だけでなく、パートナーである取引先にまで拡大したこと。
アスクルは最大の強みとして「共創」を掲げているが、実際、提供する商品やサービスは、メーカー・サプライヤー、配送キャリア、コールセンターパートナー、そして「エージェント」と呼ばれる担当販売店といった、さまざまな企業の協力で成り立っている。こうした取引先からの声を内部通報制度でも掬い上げようというのが、今回の大きな試みだ。
取引先への受け付け対象拡大ついては、社内で内部通報担当者から各事業部門の責任者に新制度の詳細を説明することから始まった。
「対象を拡大する以上、取引先から通報が多く寄せられるようになる可能性があります。ですので、アスクルとして内部通報制度を拡充していくのだということを各本部長に納得してもらうよう、まずは社内のコミュニケーションから徹底しました」(小和田氏)
社内で合意を形成したうえで、プレスリリースの発表にとどまらず、真に取引先に制度への理解が浸透することを重視。サプライヤー向けの専用イントラネットでの告知、エージェント向けの告知、そして各事業部門から取引先への直接的な周知など、多層的なアプローチを展開した。
②多言語対応
つづく改良点が、通報窓口の多言語対応だった。
アスクルグループでは近年、技能実習生をはじめとする外国人労働者が増加。グループ企業である嬬恋銘水のミネラルウォーターの製造現場や、ASKUL LOGISTの物流センターなどにおいてインドネシアやベトナムの出身者を採用し、専用の寮を新設するほど、従業員の多国籍化が進展している。
外国人労働者にとって内部通報制度は、言語の壁や文化の違いを超えて安心して働ける環境を保証する「最後のセーフティーネット」(小和田氏)というべき仕組み。そのため、内部通報システムの拡充に当たって多言語対応機能は必須要件と想定していたが、今回の刷新で英語、インドネシア語、ベトナム語でも通報が行えるようにした。
③利用しやすい制度設計
アスクルが新たに導入した新内部通報システムは、匿名性を保ちながら双方向コミュニケーションを可能にするものだが、従来の匿名通報の場合、通報者と継続した連絡が取れないといったケースも時として発生していた。
新システムでは、外部のシステムを経由させることで、通報者は自ら名乗ることなく、従事者と私書箱的な機能を通じて継続的なコミュニケーションを行うことができる。これによって詳細な事実確認や調査結果のフィードバックが可能となり、これまで以上に通報者の納得感を高めていくことが期待される。
中でも特筆すべきは、利用者の心理的ハードルを極限まで下げた設計にある。いくら匿名であっても内部通報する際、最低限、共通IDの入力などを求める企業が多い中、同社はフリーアクセスを選択。何らの認証なしに誰もが窓口システムに通報することができる。
その方針について、小和田氏は次のように語る。
「アスクルホットラインはもちろん内部通報制度ではありますが、その根底には『どのような些細なことでもいいので、私たちに声を届けてほしい』という思いがあります。むしろ、声が届かないことこそ、会社がもっとも警戒すべきこと。ですから、公益通報制度が想定する不正などの情報とは多少内容を異にするものが入ってきても、本質的な問題ではないと考えています」
取引先への通報対象拡大といい、窓口へのフリーアクセスといい、アスクルには「とにかく使いやすい制度にする」という明確な方針があるわけだが、大手企業をはじめ、雑多な内容の通報を忌避しようとする企業が少なくいなのも事実(アスクルでは内部通報窓口とは別にハラスメント相談窓口を設けている)。
しかし、アスクルには“開かれた内部通報制度”を構築しようとする企業文化が根付いているという。


