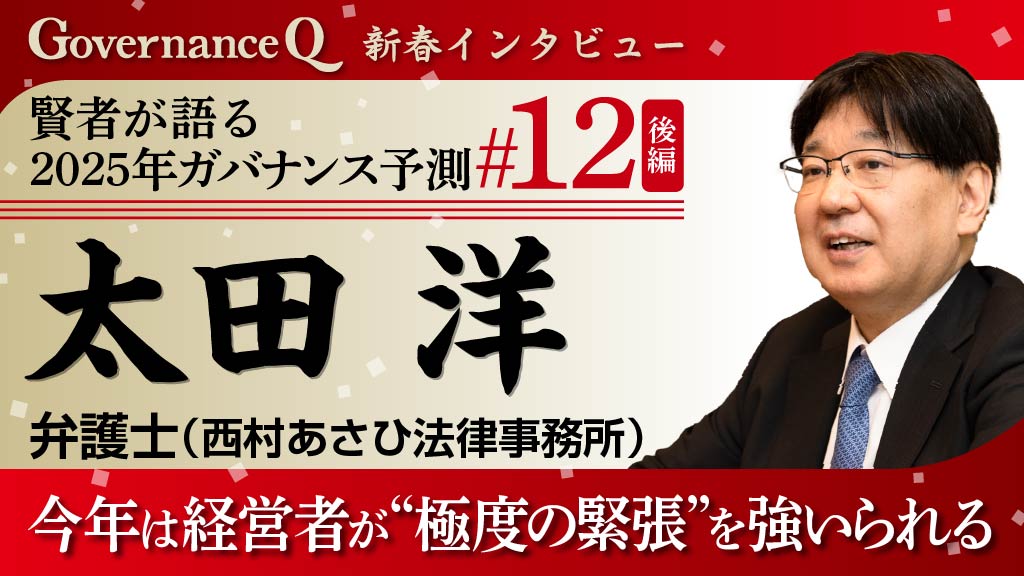(前編から続く)日本経済新聞「弁護士ランキング」で3年連続首位(企業法務全般)となった西村あさひ法律事務所の太田洋弁護士インタビュー後編。太田弁護士は、2024年はアクティビスト(物言う株主)と「同意なき買収」が活発化した1年だったが、今年は、上場企業経営者がさらに緊張を強いられる年になると予測する。その心は――。
大事なのは“中長期保有株主”の支持をいかに得るか
前編でお話した通り(前編参照)、2024年はダイドーリミテッド株をめぐってアクティビスト(物言う株主)、ストラテジックキャピタルの全株売り抜けで、アクティビズムの問題点
が浮き彫りになった年でした。それでは、アクティビズムに対して、発行体企業の経営者はどう対峙すればいいのか。
これは基本的には穏健な、言い換えれば、中長期的な株式保有を志向する機関投資家の支持をいかに得るか――ということに尽きると思います。逆に言えば、機関投資家からの支持すら得られないような施策を行う経営者は、退場を迫られるということです。
中長期的な利益という点では、通常株主の利益とステークホルダーの利益が一致するものですので、だからこそ、コーポレートガバナンス・コード(CGコード)のキーワードも「会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上」となっている。穏健な株主たちの支持さえきちんと得ていれば、たとえ株主総会でいろいろな株主提案があったとしても、勝ち切ることができます。
要は、経営者が中長期保有の株主の支持をいかに集めるかが重要という視点で考えるべきで、個々のアクティビストがどう言っているのかは、実は二次的な問題なのです。
もっとも、アクティビストの要求が、仮に一般の中長期保有の機関投資家も同じく経営者にやってほしい施策と考えていることだったら、アクティビスト側に軍配が上がります。例えば、配当性向が10~20%程度の企業が、せめて東証プライム上場企業の平均40%ぐらいの配当性向にしてほしいという場合、アクティビストから株主提案が出ると、発行体企業側が負ける。こんな具合です。
これはすなわち、中長期保有の機関投資家がしてほしいことをきちんと行っていれば、アクティビストの主張がどうであれ、特に問題にするようなことはない、経営者は“強気”でいていいということです。
アクティビストからは政策保有株、いわゆる「持ち合い」についての問題が往々にして指摘されますが、政策保有は日本では過剰に“悪”とされている面があると思っています。かつての政策保有が“ガチガチ”といった昭和や平成中期までの時代は、さまざまな弊害があったのも事実です。
ところが、現状はかなりの程度、政策保有株はなくなっています。仮に政策保有株が多少残っていても、一般の多くの株主からそっぽを向かれるような施策を行っていると、経営者は株主提案で取締役選任が否決される。今はそんな時代になっているわけですし、そういう意味では政策保有株式の弊害は現在では概ね解消していると思います。
だから、政策保有株式を本当にゼロにしなければいけないのかというと、必ずしもそうではないように思います。何らかの理由があって保有を続けているケースがほとんどです。商社であれば、取引先の株式を一定程度持たなければならないだとか、資本・業務提携のような緩やかな形で保有しているだとか、これが政策保有の現実でしょう。
そもそも、アクティビストが主張するように政策保有株をゼロにして、“砂”のような流動性の株主だけになった場合、上場企業は資本の論理の荒波に揉みくちゃになる危険性があります。そのような状況でCGコードが謳う「会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上」が果たして実現されるでしょうか。