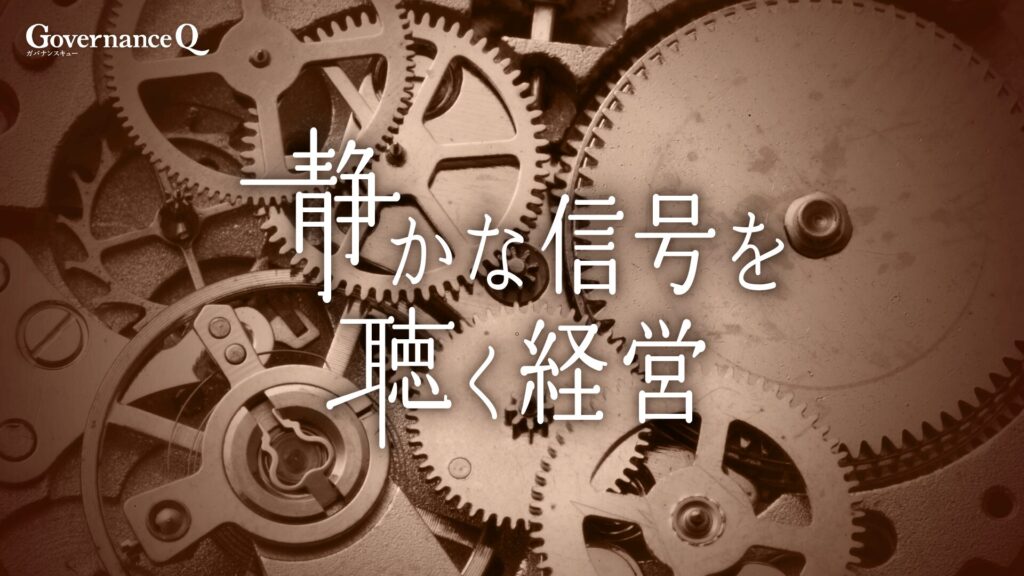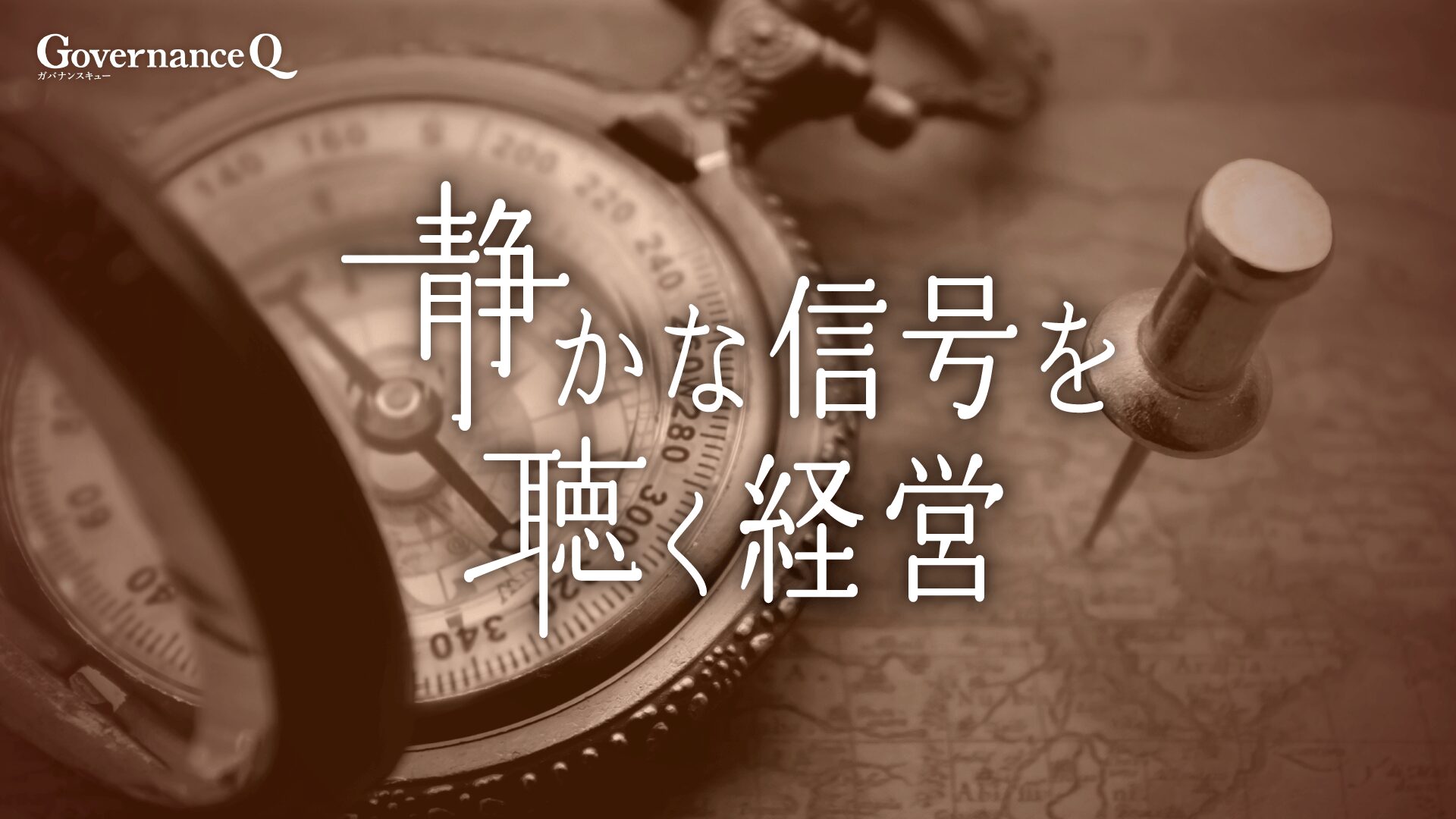遠藤元一:弁護士(東京霞ヶ関法律事務所)
内部通報制度は、設計図だけでは動かない。真に息づかせるには、日々の運用に細やかなルールと習慣を組み込み、経営と現場の間で情報と行動が循環する状態を築くことが欠かせない。そうしたものがないのであれば、自らつくる必要がある。以下では、制度を「止まらない装置」として稼働させるためのプロトコル(手続き)原則を提示したい。
①入口設計
内部通報制度の入口設計は、「まず受け取る」ことが原則である。通報受付の段階で「これは対象外」「まずは上司に相談を」と門前払いをすると、現場は制度の利用を避けるようになる。受付拒否をせず、案件の優先度に応じた三層処理(緊急対応・通常対応・モニタリング)を明確にし、内部通報担当者の間で未処理案件をダッシュボードで可視化することによって、制度の受容力と柔軟性を高める。
②通報経路
通報経路は、通報者の心理状態や立場、案件の性質に応じて選択できるよう、WEB・電話・郵送・面談・外部機関など、多様な手段を整備する。匿名・実名、社内・外部、日本語・外国語といった選択肢を組み合わせ、制度のアクセシビリティと信頼性を担保する。
③対応時間と進捗状況
内部通報制度への信頼は、時間の扱い方に左右される。例えば、受付確認は24時間以内、初動判断は72時間以内、調査計画は7日以内、是正実施は30日以内、効果検証は90日以内――といった具合に時間を明文化し、例外は経営トップの判断に限ると設定する。時間を守る姿勢そのものが、制度への信頼を支える。
進捗状況は担当者間でリアルタイムに把握できるようにし、遅延が発生した場合は自動アラートで上位管理者に通知する。通報者への進捗報告も時限化し、調査開始時・中間報告時・完了時の3回を最低限とし、複雑な案件では週次報告を行う。
④通報案件に応じた時限設計
すべての案件を同一時限で処理するのではなく、緊急度と重要度に応じた階層的な時限設定を行う。たとえば、人命や重大な法令違反に関わる最重要案件は6時間以内に着手し、安全やコンプライアンスに関わる重要案件は24時間以内、業務や人事に関わる通常案件は72時間以内、提案や改善に関わる軽微案件は1週間以内に着手する。判定基準はマニュアル化し、担当者の主観的判断の余地を最小限に抑える。
⑤専門性の装備
通報内容は多岐にわたるため、テーマごとの専門性を装備することが不可欠である。品質不正は品質保証部門、ハラスメントは人事・労務、財務問題は経理・監査といったように、専門的なバックグラウンドを持つ社員の知見を、正常化バイアスや当該部門からの影響が及ばないように法務・内部通報担当部門が常時モニタリングしながら、活用しつつ一次対応に当たる体制を構築する。社内で対応困難な案件については、法律事務所や技術コンサルタントなど外部専門家と連携し、迅速かつ的確な対応を可能にする。
⑥ヒトによる通報データの定量・定性分析
通報内容や傾向はダッシュボードで分析できるが、数字だけでは現場のニュアンスは掴めない。定量分析と定性分析を併用し、統計的傾向と個別事情の両方を把握する。AI(人工知能)による自動分析は類似案件の検索や重要度の予測などの支援機能にとどめ、最終判断は必ず人間が行う。

⑦通報制度とKPI設計サイクルの接続
営業目標や生産KPI(重要業績評価指標)が過剰なプレッシャーとなり、現場の不正や逸脱を誘発しかねないことは再三繰り返してきた通りだが、内部通報制度をKPI設計サイクルに接続し、通報から得られた示唆を目標設定の見直しに反映させる。新たなKPI設定時には現場への事前ヒアリングを制度化し、実現可能性やリスクを詳細に検証する。
⑧「構造的問題の兆候」のパターンを自動検知
これも各パートで繰り返し述べてきたが、個別の通報を“点”で捉えるのではなく、複数の通報を“線”で結び、構造的問題を“面”で把握する必要がある。同一部署での類似通報、同一時期の関連通報、同一テーマの連続通報などのパターンを自動検知し、構造的問題の兆候として早期警戒する。地理的・時間的クラスター分析も活用し、偶然ではない偏りを検知する。
⑨「報復ゼロ」を実現する追跡調査
内部通報行為に起因する人事・待遇的な「報復ゼロ」を実現するには、単なる宣言ではなく、実績の積み上げが必要である。報復申し立て件数、認定件数、是正措置、処分実績、再発率を定期的に開示し、制度の実効性を証明する。通報者の人事情報を通報の前と後で追跡し、統計的に異常な変化がないかを検証する。
⑩「透明性」の段階的向上
内部通報制度の透明性は一度に達成するものではなく、段階的に向上させるべきである。初期段階では通報件数や平均処理時間などの基本統計を開示し、制度への信頼が高まるにつれて、改善事例の詳細や制度運用の課題と改善計画まで開示範囲を拡張する。
⑪部門長の評価項目に「通報起点の改善実績」
(通報ルートの1つとしての)部門長の役割は、通報を上に上げることから、通報を起点に部門内改善を実行することへと転換すべきである。通報は上司の失敗ではなく、改善の機会として位置づけ直す。部門長の評価項目に「通報起点改善」を追加し、改善実績や水平展開の成果を査定する。
⑫利害関係者を組み込んだ設計
現代の企業は単独では存在しえず、サプライヤー、委託先のみならず、顧客、地域社会など多様な利害関係者の関係の中で事業を展開している。内部通報制度も企業の境界を越えて、これらの外部利害関係者の一部を組み込んだ設計が必要である。特に協業先については、契約書や約款に外部通報窓口を明記する一方、取引先自体の通報制度の整備状況を評価項目に含める。
⑬組織学習の定期的な実施
組織学習を偶発的な出来事に依存させず、定期的な“イベント”として制度化する。四半期ごとに「トップ10教訓」を匿名サマリーで全社に共有し、各部門に適用と対策を報告させる。年次の「学習成果発表会」では、通報起点の改善で成果を上げた部門が事例発表を行い、成功事例だけでなく失敗事例からの学習も共有する。
⑭通報制度のPDCAサイクル構築
通報制度は一度つくって終わりではなく、生き物のように進化させ続ける必要がある。年次レビューで経路、閾値、KPI、評価連動、開示方針を見直し、環境変化や過去の教訓を反映させる。制度改善のPDCA(計画・実行・評価・改善)サイクルを確立し、各フェーズの責任者と期限を明確化することで、改善活動の実効性を担保する。
(パートⅥにつづく)