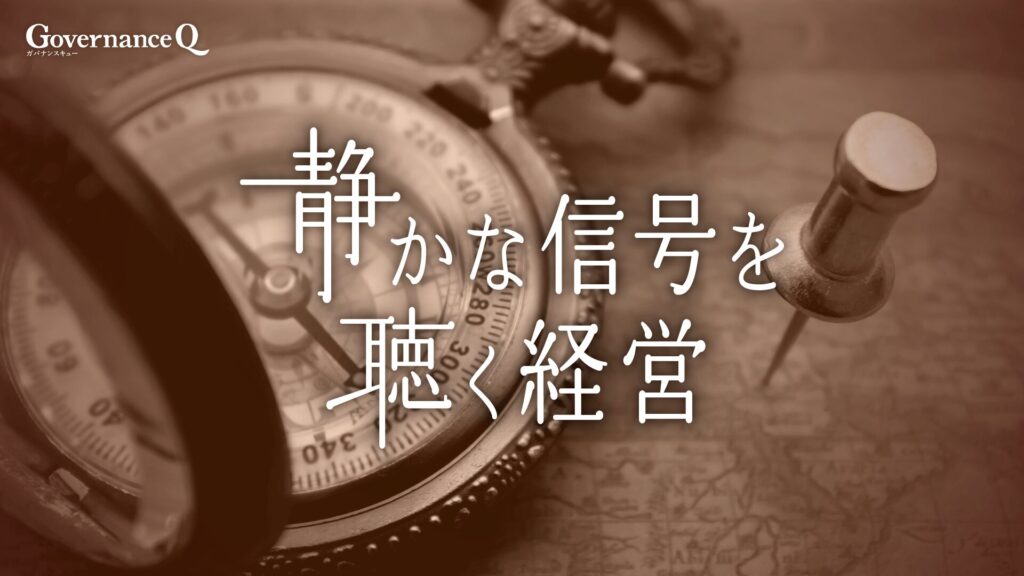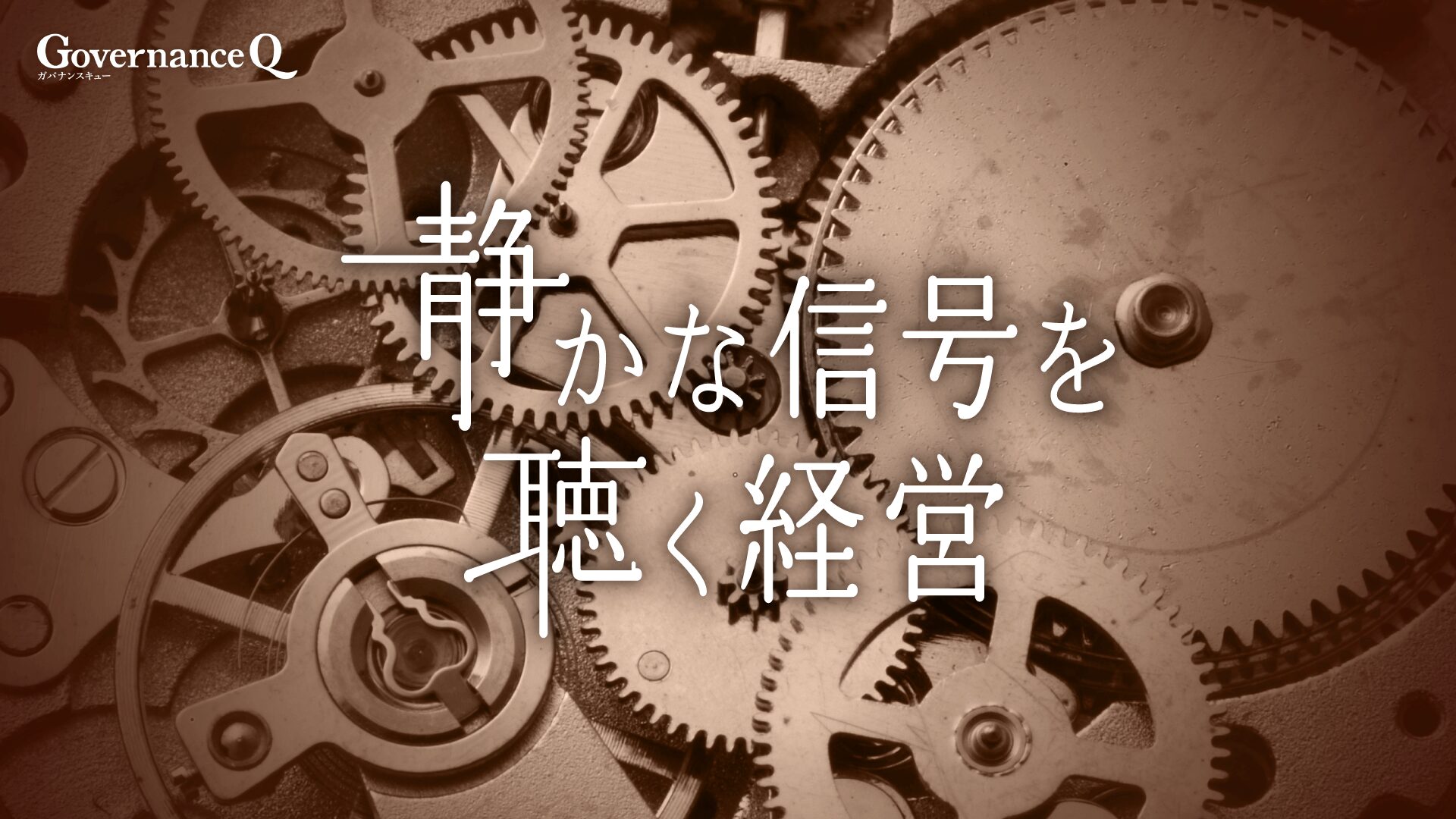遠藤元一:弁護士(東京霞ヶ関法律事務所)
経営幹部自らが内部通報制度を能動的に使う“先頭走者”となることが肝要である。制度がどれだけ精緻に設計されても、それを動かす主体がいなければ機能しない。通報制度の生命力は、設計や運用の巧拙ではなく、それを日々動かす経営幹部の姿勢と行動によって決まる。
ここでは、その経営幹部が果たすべき4つの役割として、①旗振り役、②保証人、③意思決定者、④統合者の側面を明示し、それぞれの行動原則を具体的に示したい。
①内部通報制度の「旗振り役」
第1の役割は「旗振り役」である。内部通報制度の意義と成果を語るのは、経営幹部の責務である。通報制度は現場にとって「使ってよいもの」ではなく、「使うべきもの」であるというメッセージを、トップが機会のあるごとに持続的かつ継続的に発信し続けていかなければならない。
ただし、現場に内部通報制度の利用を促すだけでは足りない。通報起点の改善事例を月次会議や社内報で紹介し、通報制度が企業価値向上に貢献していることを具体的に示す。失敗事例も率直に共有して改善姿勢を明示することで、制度への信頼と心理的安全性を醸成する。社内外への発信、つまりイントラネット、投資家説明会、メディア対応などを通じて、内部通報制度の存在と実効性を可視化することが重要である。
②内部通報制度の「保証人」
第2の役割は「保証人」である。内部通報制度の信頼性は、「報復ゼロ」の実績によって支えられる。公益通報者保護法で定められているとはいえ、単に「報復は禁止」と宣言するだけでは足りない。違反時には必ず処分を行い、その事実を社内に共有する必要がある。
報復の定義は広く設定し、配置転換や評価変更などのグレーゾーンも含めて監視対象とする。通報者の人事情報を通報の前と後で継続的に追跡し、統計的に異常な変化がないかを検証する。通報者への積極的支援、すなわち、産業医面談、休暇取得、職場復帰支援などを提供することで、通報制度利用者の安心感を高める。
加えて、第三者機関による報復防止監査も定期的に実施し、外部の客観的評価によって制度の透明性を担保する。通報者に対して通報を理由とした不利益取り扱いや報復を禁止することは、心理的安全性を確保するためにも不可欠な条件であり、第三者機関による評価・定期的監査は、不利益取り扱いや報復の禁止を徹底できていることを、透明性があり、かつ検証可能な形で自社の役職員に示すことの選択肢のひとつと考えられる。また、通報が人事評価に影響を与えないような制度とし、それを役職員に知らせて、心理的安全性を担保する。
③内部通報制度の「意思決定者」
第3の役割は「意思決定者」である。通報情報は、単なる事実確認にとどまらず、経営判断に反映されなければ意味がない。
複数の通報から特定のKPI(重要業績評価指標)が現場に過剰な負荷を与えていることが判明した場合、そのKPIの見直しや目標値の修正を即座に決断する。通報傾向は月次で経営会議に報告し、重要案件については臨時会議を招集する。
意思決定の基準、すなわち、同種の通報が複数件、法的リスク、顧客影響、メディア露出リスクなどを事前に明確化し、重要な情報が見落とされるリスクを最小化する。通報から明らかになった問題の解決には、追加的な経営資源の投入が必要となることもある。短期的なコスト負担を恐れず、中長期的な企業価値向上の観点から判断する姿勢が求められる。
改善策が期待した効果を得られなかった場合でも、失敗を隠さず、素早く修正する姿勢を示すことは、現場に「完璧(な不正事案)でなくても声を上げて良い」というメッセージを送り、役職員の心理的安全性を高めることにもつながる。
④内部通報制度の「統合者」
第4の役割は「統合者」である。内部通報制度は、単独で存在していても効果は限定的である。採用、昇進、配置、研修などの経営プロセスと有機的に結びつけることで、制度は初めて全社的な影響力を持つ。
新入社員研修に制度説明を組み込み、採用面接では「職場で気になることがあったら、どうするか?」という質問を追加する。昇進・昇格の判定では、部下からの通報への適切な対応を評価項目に含める。監査・内部統制・リスクマネジメントとも連携し、通報傾向を監査計画やリスクマップに反映させる。
契約・調達では、外部通報窓口の案内を契約書に明記する一方、取引先自体の通報制度整備の状況を評価項目に加える。経営企画では、通報データから抽出された課題を中期経営計画に反映し、広報・IR(投資家向け広報)では制度の運用実績と改善事例を投資家向け資料に記載し、開示する。

また、当然のことながら、経営者不正も通報対象となる。経営者不正を対象とする通報制度では、社内窓口では対処が困難なため、社外監査役や監査等委員など経営から独立した役員、あるいは外部専門機関を通報窓口とすることが不可欠である。
通報者の匿名性を技術的・運用的に確保することが制度の前提条件となる。その上で、経営陣自らが通報に対して適正に対応する姿勢をあらかじめ明示的にコミットしておくことで、通報制度への信頼性が大きく高まる。通報者保護の方針を明文化し、全社的に周知することも重要である。調査プロセスの透明化と、通報後のフィードバック体制を整えることにより、通報制度が実効的に機能する。
この4つの役割は、どれかひとつでも欠ければ内部通報制度の力を削ぐ。旗振り役がいなければ現場は制度を忘れ、保証人がいなければ声は上がらず、意思決定者がいなければ通報情報は活かされず、統合者がいなければ制度は孤立する。
逆に、4役すべてが揃えば、内部通報制度は企業の免疫力と学習能力を飛躍的に高める。制度は「設計するもの」ではなく、「動かすもの」である。
とはいえ、問題なのは「では、どうやって内部通報制度を動かすのか」であろう。次のパートⅤでは、通報制度を「止まらない装置」として稼働させるための運用原則を提示する。
(パートⅤにつづく)