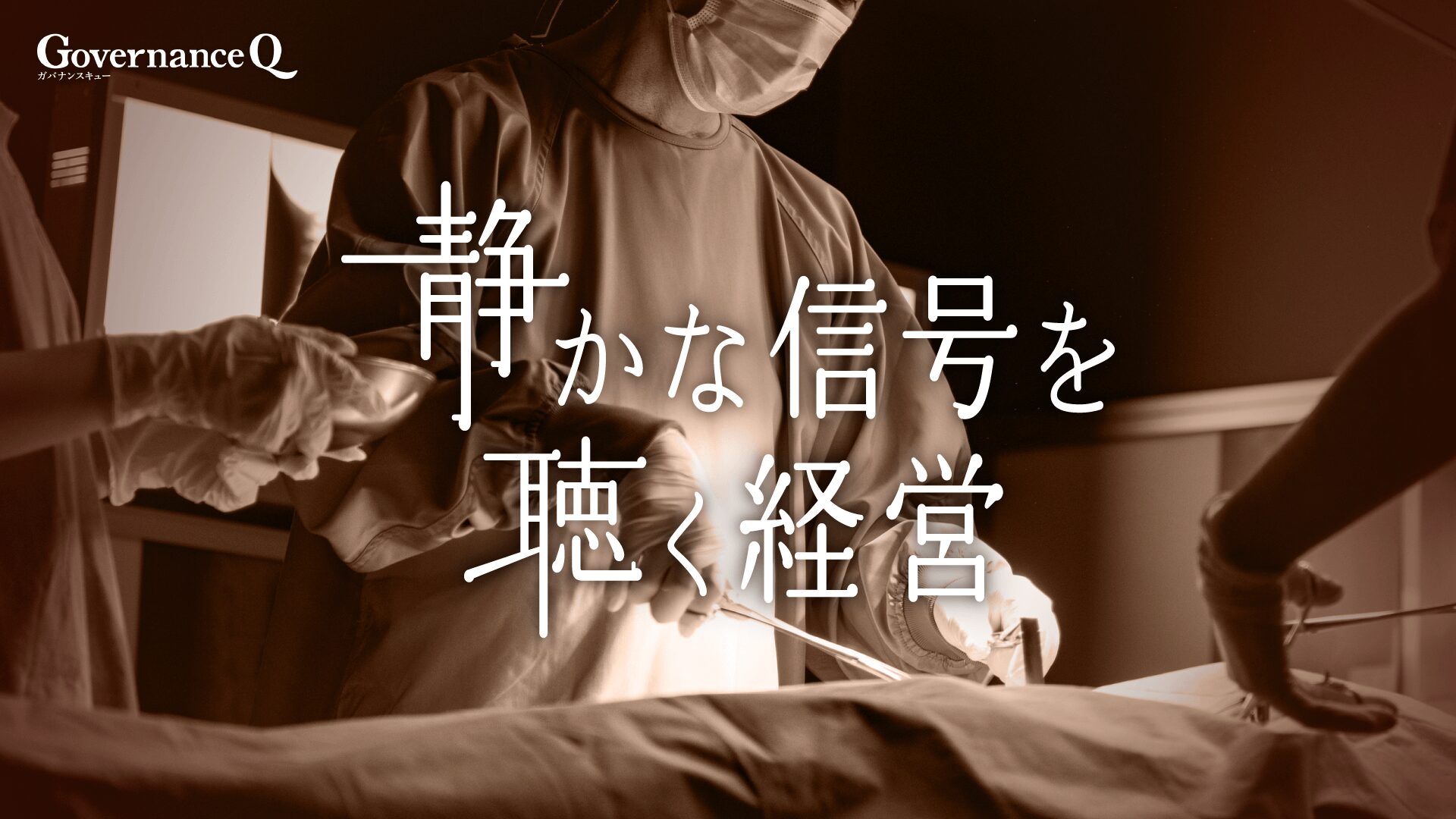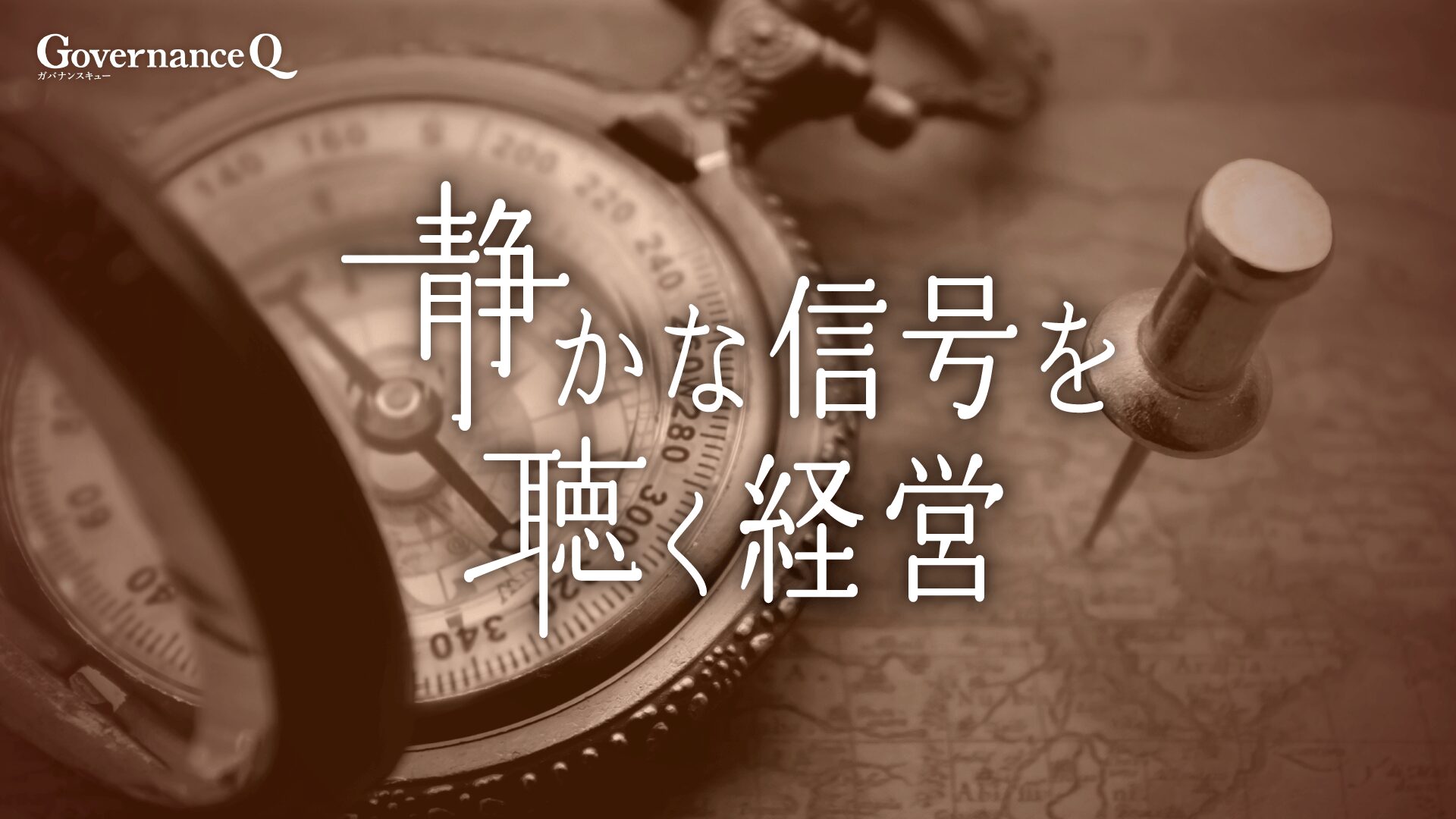遠藤元一:弁護士(東京霞ヶ関法律事務所)
内部通報制度は、単なる告発窓口ではない。企業の免疫力と学習能力を高める「経営装置」であることはパートIとパートⅡで繰り返し述べてきた。真に機能させるためには、内部通報を「問題の報告」ではなく「改善の起点」として捉え直し、経営判断に資する情報源として活かす構造が求められる。
以下では、通報制度に備えるべき4つの機能を指摘する。それは①改善、②学習、③提案、④予防の機能である。
①「改善」装置としての内部通報
第1に、内部通報制度は“改善と革新の源泉”として機能すべきである。通報制度を「告発専用」にしてしまうと、現場は通報制度の利用を避けるようになる。利用低下は、経営層への重要情報の到達を阻み、判断の質を損なう事態をもたらす。
通報制度が使われるためには、改善提案や小さな気づきも受け入れる設計が不可欠である。窓口は共通としても、受け付けた後は「通報」と「提案」は明確に区別し、それぞれに適した処理プロセスを設ける。実名提案には評価や表彰を紐づけ、匿名提案についても採用時に社内へ広く告知することで、制度の利用促進につなげる。
一方、提案の質を高めるためには、現場向けの改善提案研修やテンプレートの提供が有効である。さらに、四半期ごとに「通報・提案で変えたこと」をトップが全社に共有することで、通報制度の成果を可視化し、現場の信頼を醸成する。
②「学習」装置としての内部通報
第2に、組織知識の蓄積と活用を促す学習装置の機能を内部通報制度に担わせることも重要である。通報案件は単発の是正で終わらせず、案件ごとに「匿名要約・論点・対応・教訓」をテンプレート化し、全社的な知識として蓄積する。
教訓の抽出では、「発生理由」「早期発見できなかった理由」「拡大理由」の3点を分析し、再発防止策を設計変更として提示する。禁止や注意喚起の一辺倒ではなく、業務プロセスや制度設計の変更によってリスクを根本から除去しようとする姿勢が重要である。
AI(人工知能)ベースの類似案件検索を導入することによって初動対応の質とスピードを向上させることができる。通報レポートは取締役会の定例アジェンダに固定化し、戦略策定に反映させることで、制度を経営判断の支援装置として位置づける。
③KPI等の見直しにつながる「提案」装置としての内部通報
第3に内部通報制度は、現場から経営が設定した目標の見直し・修正を促す提案装置として機能する。営業目標や生産KPI(重要目標達成指標)が過剰なプレッシャーとなり、不正や逸脱を誘発することは珍しくない。東芝の不正会計事件(2015年)の真因は、まさにここにあった。
通報制度をKPI設計サイクルに接続し、通報から得られた現場の示唆を目標設定の見直しに反映させ、新たなKPI設定時には現場への事前ヒアリングを制度化し、実現可能性や必要なリソース、想定されるリスクを詳細に検証する。
設定後も初期段階での通報動向を注意深く観察し、異常な兆候があれば即座に見直しを行う。目標設定プロセスに「通報制度チェック」を組み込み、過去の通報データから類似の問題が発生していないか、新たな目標が不正や逸脱を誘発する可能性がないかを事前評価する。

④「予防」装置としての内部通報
最後は、予防装置としての機能である。内部通報制度によって構造的問題の早期発見を可能にすることで、不正や逸脱を誘発しかねない要因を取り除き、リスクを事前に予防することができる。これは極めて重要だ。
個別の通報を“点”ではなく“線”で捉え、さらに“面”として構造的問題を把握するという考え方だが、同一部署での類似通報、同一時期の関連通報、同一テーマの連続通報などのパターンを自動検知し、構造的問題の兆候として早期警戒する。地理的・時間的クラスター分析も活用し、特定の地域や時間帯に通報が集中する傾向があれば、それを偶然ではなく、何らかの構造的要因の存在として捉える。
*
これら4つの機能を制度に組み込むことで、内部通報制度は単なる窓口から脱却し、経営の意思決定を支える装置へと進化する。制度は「使われること」で価値を持ち、「使った結果」で評価される。次のパートⅣでは、制度を動かす主体としての経営幹部の役割と行動原則を明示する。
(パートⅣにつづく)