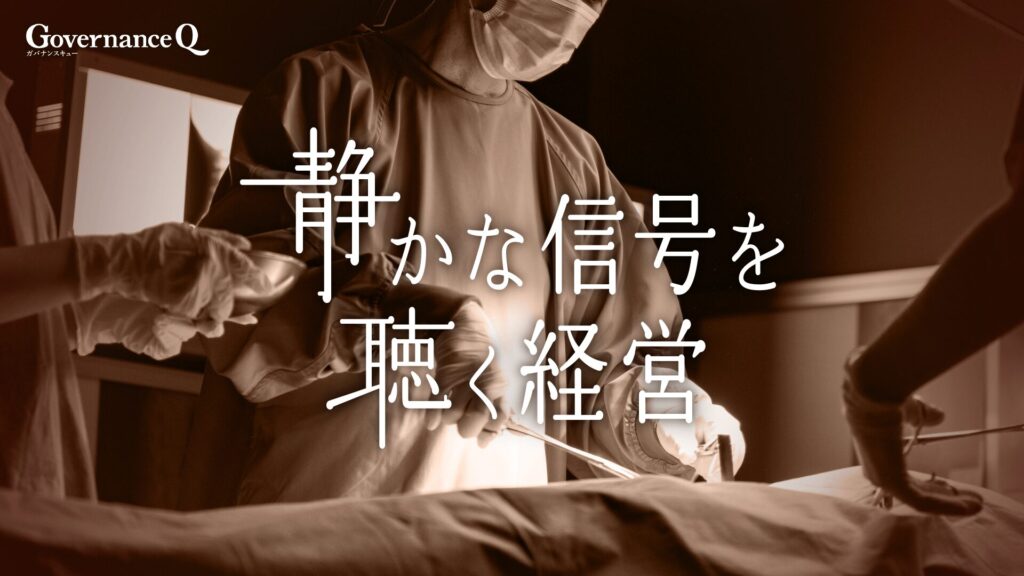遠藤元一:弁護士(東京霞ヶ関法律事務所)
企業不祥事は、突如として生起し、爆発するものではない。その前段階には必ず、現場や関係者の間で小さな兆候が現れ、それが見過ごされ、常態化していくプロセスがある。内部通報制度が機能していれば拾えたはずの「違和感」や「兆し」が、制度の不全によって腐敗し、やがて企業価値を揺るがす事態へと成長・発展する。
ここでは、通報制度が機能しなかった事例をもとに、別の制度設計あるいは運用であれば異なる結論に至った可能性を検証し、改善策に落とし込むためのブレーンストーミングを試みたい。
これまでの企業不祥事例における「内部通報制度」の機能不全
オリンパス事件(2011年):メディア報道起点の不祥事発覚
オリンパス事件では、巨額の損失隠しが簿外処理と不透明なM&A(合併・買収)によって拡大し、最終的に数千億円の時価総額が消失した。起点は雑誌メディアでの報道だった。
一方、同社の内部通報制度はコンプライアンス室(当時)の下にあり、社外取締役や社外監査役を含め外部への直通経路が存在しなかった。財務担当者が疑義を感じても、安全に報告する手段がなく、組織内で情報が遮断された。制度の物理的な「経路設計」が欠ければ、誠実な声も届かず、真実は組織の壁に吸収されてしまう。もし社外取締役直通の匿名通報ルートが設計されていれば、メディアの特報で損失隠しが糾弾される以前に問題が発覚していた可能性は高い。
大王製紙「元会長特別背任」事件(2011年):絶対的権力者による不正
大王製紙の特別背任事件では、創業家出身の会長が子会社などから160億円以上を私的流用した。
同社の内部通報窓口は法務・広報課長(が開封権限を持つメールアドレス)で、最終的な報告対象は社長だった。横断的な情報共有システムがなく、全体像を把握できるのは絶対的権力者である会長のみという構造的欠陥が存在した。権力の源泉が通報制度を支配すれば、制度は自浄機能を失い、沈黙の温床となる。仮に、高額資金移動の自動通報ルールと、社外取締役・外部法律事務所への直通経路があれば、異常は早期に検知できた可能性がある。
米ウェルズ・ファーゴ「不正口座開設」事件(2016年):営業文化に埋没した内部通報
米国大手銀行ウェルズ・ファーゴでは、従業員が過大な販売ノルマを達成するため、顧客の同意を得ずに数百万件の口座やクレジットカードを開設するという不正が長期間にわたり行われていた。
同社には内部通報制度が存在し、多数の従業員が不正を指摘していた。しかし、通報は「営業現場の一部に見られる文化的問題」として経営陣に軽視され、組織的な不正として認識されることはなかった。通報ルートが経営層の判断に依存していたため、制度は形骸化し、結果として「声を上げても無駄」という沈黙の文化が醸成された。
制度が存在しても、経営陣が真剣に受け止めなければ自浄機能は働かない。仮に、通報内容を監査委員会や社外取締役に直接エスカレーションできる仕組みや、営業成績と不正リスクを自動的にモニタリングするシステムが整備されていれば、不正は早期に顕在化した可能性が高い。

(写真は本社所在地サンフランシスコの風景)
川崎重工業・子会社「検査不正」(2022年):子会社における内部通報制度の機能不全
川崎重工の子会社において、一部の「吸収式冷凍機」をめぐって出荷前試験の実測を省略して架空データを検査成績書に記載し、計測器の目盛りを操作して性能を偽装するなどの手口で顧客や官公庁に虚偽の性能を報告していた。
形式上は子会社独自とグループ全体の2つの経路で内部通報が可能な体制が整っていたものの、現場には「性能に実害がなければ問題ない」という慣行と、通報が組織内で不利益を生むとの恐れが根強くあったため、制度は形骸化していた。匿名かつ社外直通(グループ全体)の通報経路が実質的に機能し、検査成績書の虚偽記載が増加し始めた時点で現場から警告が伝わっていれば、不正は「性能試験短縮」の段階で食い止められ、長期化・制度化する前に是正された可能性が高い。
制度設計の巧拙が経営層の「意思決定の質」に直結する
これらの事例に共通するのは、「内部通報制度が存在していたが、機能していなかった」という構造的欠陥である。通報制度が経営幹部に接続されていなければ、現場の声は届かず、制度はワークせず、形骸化し、確実に組織の免疫力を失う。
制度設計においては、通報経路の複線化、匿名性の担保、専門性の装備、経営判断への接続、外部機関との連携といった要素を「付帯機能」としてではなく、企業の持続的価値創造に不可欠な「戦略的インフラ」として組み込む必要がある。
通報制度は「存在するか否か」ではなく、「使えるかどうか」がすべてである。使える通報制度とは、現場にとって「頼れる」、経営にとって「判断材料となる」、そして自社のガバナンスの健全性を社会に対して「説明・検証可能な」制度である。その設計の巧拙が、企業のレピュテーション、コンプライアンス体制、さらには経営層の意思決定の質に直結する。
繰り返すが、内部通報制度設計とは、単なるルール整備ではなく、企業の神経系を構築する営みである。通報制度が機能不全に陥れば、現場の声は経営に届かず、リスクは潜在化し、経営層はリスクを認識できない中での意思決定を余儀なくされる。逆に、制度が有機的に機能すれば、現場の兆候は経営の知覚となり、判断は的確さを増し、企業は環境変化にしなやかに対応できる。
(パートⅢにつづく)