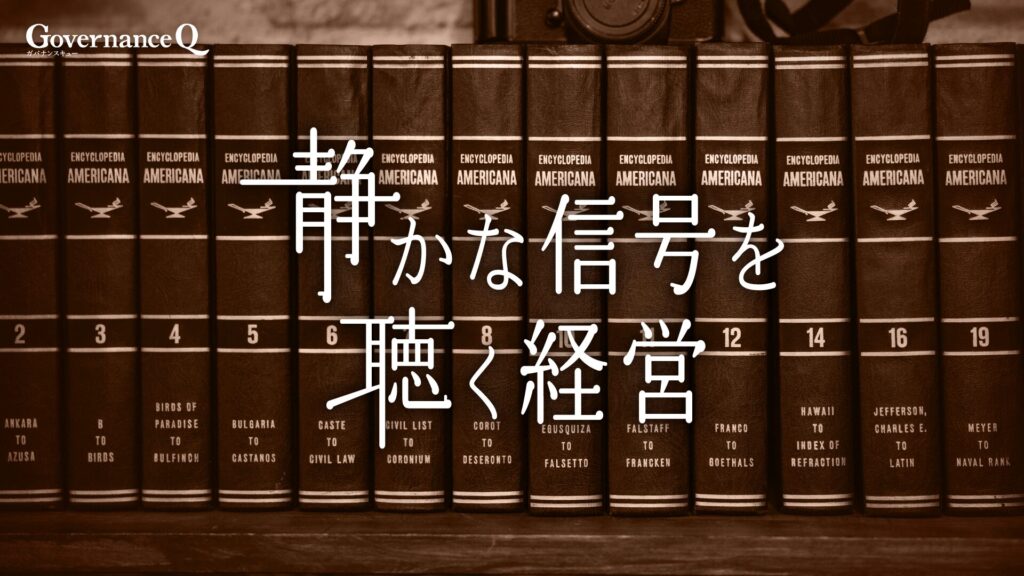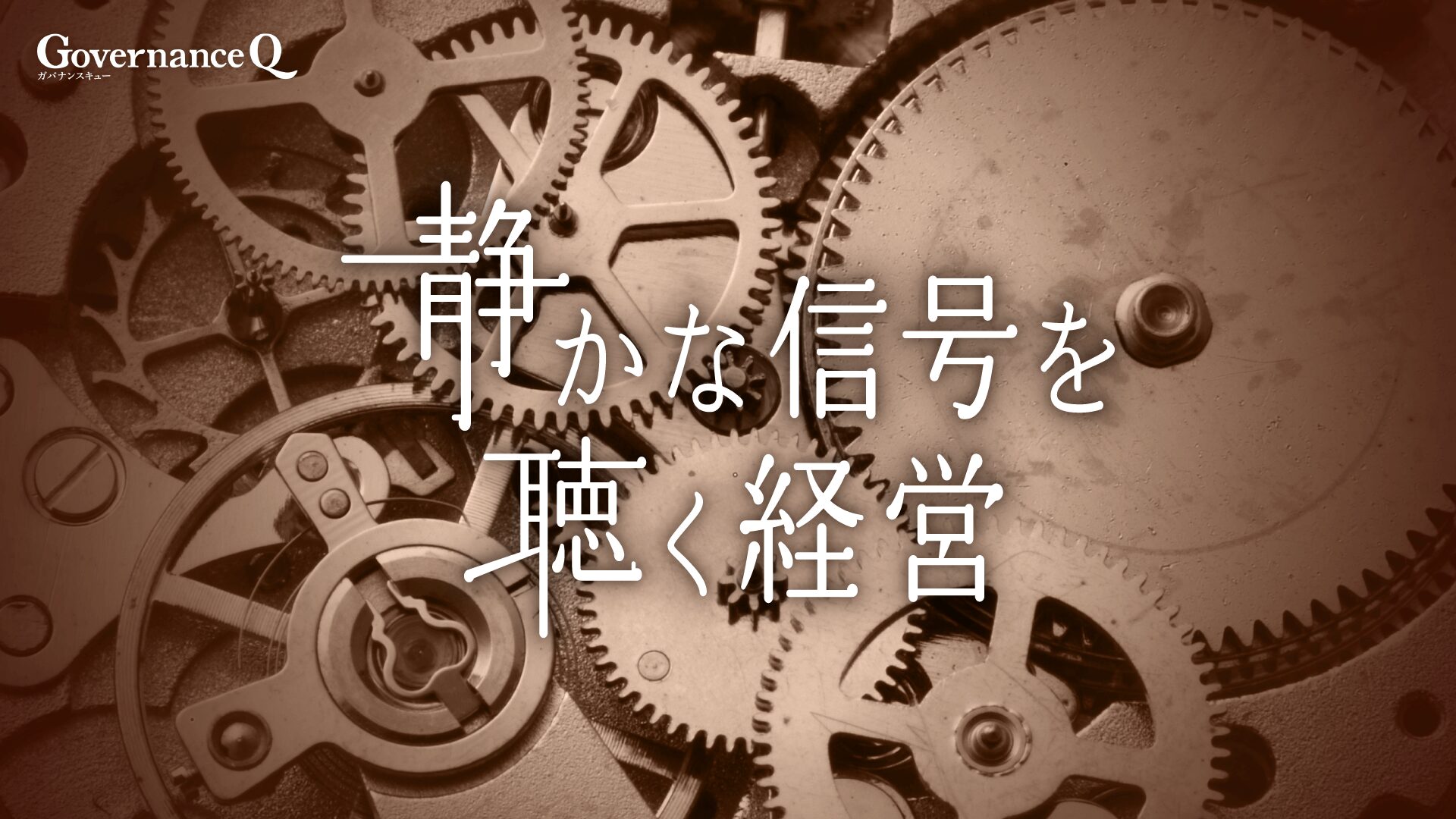遠藤元一:弁護士(東京霞ヶ関法律事務所)
内部通報制度の成功は、印象や雰囲気では測れない。客観的なデータに基づいてこそ、その実効性は確かめられる。通報制度が「使われているか」「機能しているか」「価値を生んでいるか」を可視化することで、経営幹部は制度への投資判断と改善方針を合理的に導くことができる。
以下では制度成果の多元的指標設計と、継続的改善のメカニズムを提示する。
多元的指標設計
まず、内部通報制度の成果は1つの指標では測れない。従来よく用いられてきた「通報件数」は、制度の活性度を示す1つの要素ではあるが、それ自体が成功・失敗を決定するものではない。通報件数の増加が制度の成熟を意味する場合もあれば、職場環境の悪化を示す場合もある。したがって、制度の評価には複数の指標を併用し、例えば、①量的指標、②質的指標、③プロセス指標、④アウトカム指標の4つのカテゴリーを用いる必要がある。
①量的指標
量的指標には、通報受理件数、分野別件数、緊急度別件数、匿名・実名比率、外部経路利用率などが含まれる。これらは内部通報制度の利用状況を示すが、単独では評価できない。
②質的指標
質的指標では、通報内容の具体性(5段階評価)、問題の重要度(3段階評価)、改善可能性(4段階評価)を専門家が評価する。抽象的な不満ではなく、具体的で建設的な通報が増加することが、制度の成熟を示す。
③プロセス指標
プロセス指標は、初動時間(受理から着手まで)、調査期間(着手から完了まで)、是正期間(完了から改善実施まで)、フィードバック時間(完了から通報者への報告まで)を測定する。これらの時間短縮は、制度への信頼向上に直結する。
④アウトカム指標
アウトカム指標では、改善実施率(調査完了案件のうち何らかの改善を実施した比率)、改善効果(定量的な効果測定)、再発防止率(同種問題の再発防止効果)、通報者満足度(事後アンケート結果)を評価する。
これら4つの指標には個社の重要度に応じた重み付けを設定し、総合評価スコアを算出する。重み付けは業界特性、企業規模、事業環境を考慮して決定する。
たとえば、製造業では品質・安全に関する指標、金融業では法令遵守に関する指標、IT業では情報セキュリティに関する指標の重みを高く設定する。成長企業では改善効果の指標、成熟企業では再発防止の指標に重点を置くといった具合だ。総合評価は100点満点で表示し、90点以上を「優秀」、80〜89点を「良好」、70〜79点を「普通」、60〜69点を「改善要」、60点未満を「再設計要」として5段階評価する。
制度の客観的評価をさらに高めるためには、業界横断的なベンチマーキングが有効である。同業他社や他業界の内部通報制度運用の優秀企業との比較を通じて、自社の制度の位置づけと改善余地を明確にする。業界団体、学術機関、専門コンサルタントと連携し、匿名化されたデータによる比較分析を行う。ベンチマーク項目は、通報件数/従業員数、初動時間平均値、改善実施率、通報者満足度、制度運営コスト/売上高比率などを中心とし、業界上位25%に入ることを目標とする。

継続的改善のメカニズム
内部通報制度を進化させ続けるには、PDCAサイクルを制度に組み込むことが不可欠である。Plan(計画)段階では前年度の成果分析と課題抽出を行い、改善計画を策定する。Do(実行)段階では改善施策を実施し、進捗管理を徹底する。Check(評価)段階では改善効果を定量・定性の両面から評価し、Action(改善)段階では成功施策の標準化と失敗施策の修正を行う。各段階の責任者、期限、成果物を明確に定義し、改善活動の実効性を担保する。
さらに、内部通報制度に関わるすべてのステークホルダーからのフィードバックを定期的に収集し、改善に活用する。通報者アンケートでは対応満足度、改善提案、制度利用の意向を確認し、調査担当者からは業務負荷や効率化提案を聴取する。部門長からは制度運用の課題や現場への影響、改善アイデアを収集する。外部ステークホルダー、すなわち、顧客、取引先、地域社会、投資家などからの声も重要な改善情報源として活用し、年次のステークホルダーダイアログで制度に対する期待と評価を確認する。
内部通報制度は「使った結果」で評価される。その結果を可視化し、改善に活かすことで制度は進化し続け、組織の資産となる。最終回Ⅶでは、通報制度を経営の中核資産として位置づけるための最終的な視座と、経営幹部への問いかけを提示する。
(最終回パートⅦにつづく)