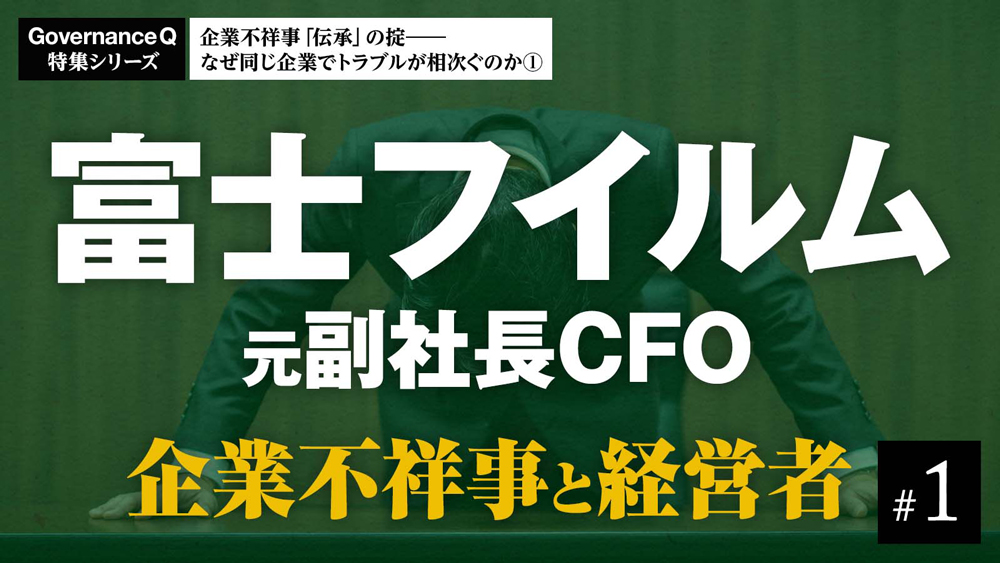日本企業の不祥事・不正が後を絶たない。それどころか、同じ企業が何度も問題を繰り返すケースが相次ぐ。そんなモラルハザードの核心には何があるのか――。制度なのか、その運用なのか。問題はそればかりではない。経営者のその資質にこそ、不祥事発生の萌芽が隠されている。富士写真フイルム(現・富士フイルム)代表取締役副社長・CFO(最高財務責任者)を務め、企業倫理のあるべき姿について積極的な提言を発信している今井祐氏が、不祥事企業の語られざる“病巣”を抉る。
不祥事が起こっても問われない「経営者の資質」
私は以前から、コーポレートガバナンスだけでなく、企業不正・不祥事防止の実効性向上のためには「制度とその運用と経営者資質の“三位一体”の改革・改善」が必須条件だと主張してきました。詳細は追って説明しますが、私の分析では近年、日本企業が引き起こした約60の不祥事のうち、実に70%近くが「経営者の資質」に問題があるケースに該当しているのです。しかも、何度も不祥事を繰り返している企業が後を絶たない。この観点から、企業はいかに不正・不祥事を防ぐかにとどまらず、仮に問題を起こしたとしても、それを繰り返さないようにする手立てを考えてみたいと思います。
これまで不正・不祥事防止をめぐる議論の多くは、制度とその運用の2点だけで終わる傾向があり、経営者資質には踏み込まなかった。なぜかと言うと、経営者に対して、その資質そのものを問うことは憚られてきたからです。つまり、「あなたには経営トップである資質がない」「社長の任に堪えない」とは誰も言えなかった。だから、不祥事を引き起こした企業が第三者委員会を設置しても、第三者委は経営者資質にまで切り込まないケースが多かったのです。不祥事の発生や防止において、経営者資質は盲点だったわけです。しかし、経営者資質を改革・改善の対象から外したままでは不祥事の再発は根本的には防げません。
その際、キーワードとなるのが「経営者資質と企業文化の醸成」です。企業文化を形づくるのが経営者資質だと言ってもいいでしょう。経営者資質とは、誠実性(Integrity=インテグリティ)と倫理的価値観を持ち合わせることです。これは内部統制のグローバル・スタンダードと言われる米国COSO(米国トレッドウェイ委員会支援組織委員会、1985年に米国で設立された金融業界の不正報告を抑止するための団体)が掲げている言葉です。本来、誠実性は倫理的価値観のひとつですが、COSOの考え方は倫理的価値観の中でも誠実性を最も重要視し、あえて倫理的価値観と並べて特記しているわけです。誠実性以外の倫理的価値観は各々の企業や経営者によって違ってもよいが、誠実性だけは外せないという考え方に基づいています。
企業体が持つべき価値観の重要度を表すイメージとしては、一番大きな概念として、パーパス(企業の存在意義)、ミッション(使命)、ビジョン、コアバリュー(中核的価値観)といった倫理的価値観があり、その内部にコーポレートガバナンスという制度、意思決定のフレームワークがあります。さらに、コーポレートガバナンスの内側にコンプライアンスがあります。企業不祥事はコンプライアンスに背いた問題事象です。ただし、コンプライアンスは単に法令順守にとどまらず、そこには社会通念や社会道徳も含まれる。倫理的価値観とは、そうした枠組みを超越して全体を包み込む概念だということです。倫理的価値観を抜きにしてコーポレートガバナンス、コンプライアンスがあっても何ら意味をなさないのです。
経営者資質と言われると、生まれながらの資質と思われるかもしれませんが、先天的なものと後天的なものとの2種類があり、後天的なものは経験や教育、研修によって形成されていきます。しかし、日本企業において残念なのは、今の経営者に対する教育や研修には“座学”が圧倒的に多いことです。コーポレートガバナンスとは何か、会社法とは何かを学ぶのが経営者教育・研修だと思われていますが、それは大きな間違いです。
端的に言うと、ハーバード大学のマイケル・サンデル教授が行っている白熱教室のような討論形式が理想です。簡単には答えの出せないような現代社会の難問をテーマにして、参加者全員で議論するといったアプローチが、経営者資質を養ううえで効果的と言えるでしょう。