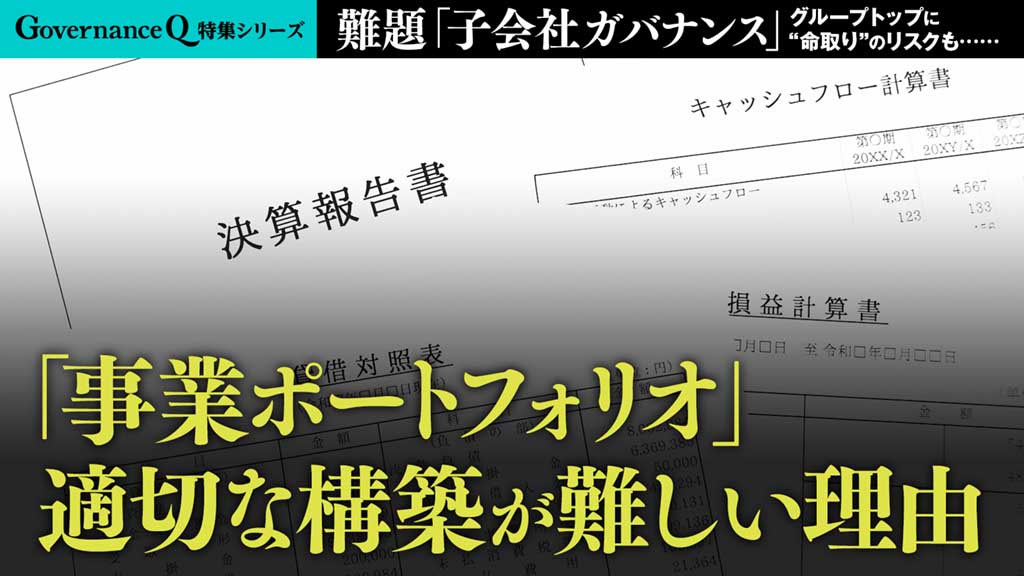#1では大手企業の不動産子会社を例に、子会社のガバナンス不全があわや不祥事を生み出しかねない危険性を伝えた。続く#2では、新設子会社、あるいは新規事業をグループ全体の中でどのように位置づけるかについて、コーポレートガバナンスの現状を追う。トップの恣意的なポートフォリオが罷り通るケースがある一方、子会社の撤退や売却については、決定がままならないケースもあるという。
グループ決算優先で歪な新規事業の位置づけ
企業は、子会社を設立して新規事業を始め、子会社を清算または売却し、子会社を再編する。子会社の機動的・有機的な運営はグループ経営を行ううえで必須の課題だが、事業ポートフォリオの構築を合理的に進めることは、実は難しい。
ある外資系不動産コンサルタントが批判するのは、以下のケースだ。
IT企業として成長し、金融事業に進出したA社が、今度は不動産事業を始めた。その際、A社本体に担当部を新設するのでもなく、かと言って、新たに子会社を設立するのでもなく、クレジットカード事業を行っている既存子会社に準備室を設置し、外部から人材を採用、10名弱の不動産事業部を立ち上げた。不動産事業部の目的は、土地を購入して宿泊施設を建設する他に、再開発、不動産投資事業も予定した。
「クレジットカード子会社の中に設置したのは、決算対策を優先させたためです」
外資系不動産コンサルタントはこう指摘する。
当時、A社は本業のIT事業は堅調だったが、別の子会社が業績不振で、連結決算で3期連続の赤字を計上した。取引銀行による融資は難しくなり、堂々と新規事業を立ち上げることのできる状況ではなかった。
ただ、クレジットカード子会社は好調で、キャッシュも積み上がっていた。不動産事業は先行投資が必要なうえに、回収までの期間が長く、比較的リスクが高い。クレジットカード子会社に設置すれば、当初見込まれる不動産事業の赤字を吸収できるため、決算は傷が付かないという考えだ。しかも、投資資金は借り入れをせず、クレジットカード子会社が持つキャッシュを投じる計画だった。
しかし、クレジットカード事業と不動産事業はまったく別物だ。
「クレジットカード事業を行ってきた子会社の経営陣が、不動産事業をマネジメントできるはずはありません。しかし新設した『不動産事業部』の責任者に、権限を全面的に委譲したわけでもなく、A社の不動産事業は中途半端に見えました」(コンサルタント)
クレジットカード子会社内に新設された不動産事業部は、宿泊施設運営の経験がある人材を外部から招聘して部長に据え、部員は人材募集をかけた。
「募集要項を見ると、年収は400万~700万円台。子会社の経営陣が、この程度の条件しか承諾しなかったのでしょう。しかしこれでは、他の不動産会社で燻っている中堅社員程度しか採用できません。不動産に限らず、新規事業の立ち上げには人事と採用が大きく影響しますが、責任者にその権限がなければ、結果を出すのは難しいでしょう」(同)
実は、A社の創業社長はワンマンで、細かい点まで指示することで知られる。それを考えれば、不動産事業を始める際にクレジットカード子会社の中に新設する案は、創業社長の一声だったと思われる。ワンマン経営者の場合、合理性に欠けた判断が行われても、それを止める術はないことが多い。
余談になるが、大手飲食店チェーンを経営する企業の会長が詐欺に遭って、軽く億を超える資金を失った。この企業では、社長以下、幹部の全員が詐欺だと確信していたというが、会長を止めることはできず、カネの振り込み手続きは社員が行っていた。