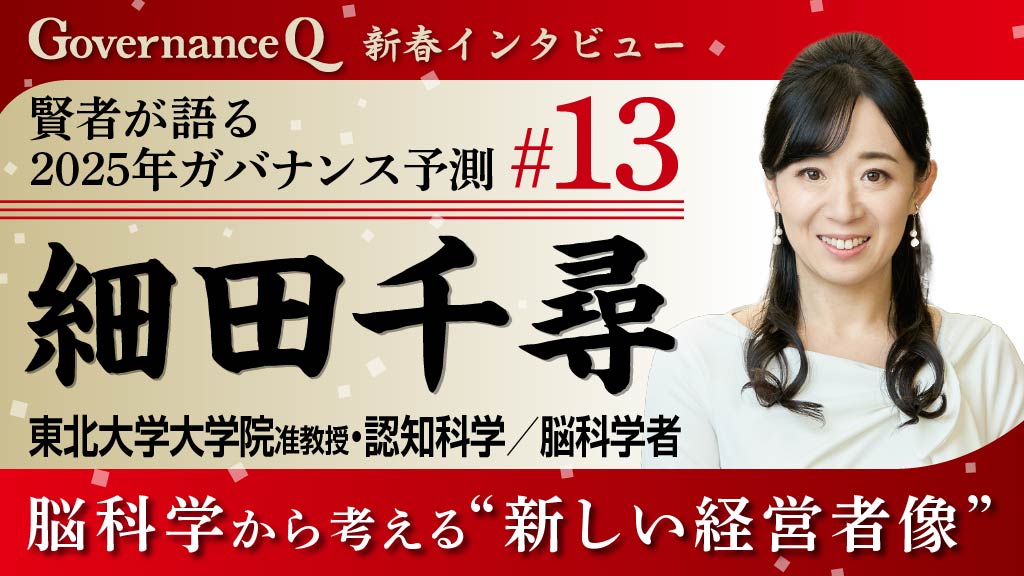「Governance Q」新春インタビュー最終回の13回は、東北大学大学院准教授で脳科学者の細田千尋氏。自身も3人の子どもを持つ母親である細田氏は、脳科学の観点から女性活躍、子育て中のキャリア形成のためのテクノロジー、そして、子育てにおける新たな価値創造の研究もしている。「ソーシャルウェルビーイング」という考え方のもと、細田氏が考える、昭和や平成と異なる“新しい経営者”の在り方とは――。
経営者と従業員の最適解を導く「ソーシャルウェルビーイング」の考え方
私の専門は「脳科学」「認知科学」と言われる、ヒトを対象とした研究領域になります。
多岐にわたる研究テーマに取り組んでいますが、そのうちのひとつは、「人はどのように学び、成長し続けるのか?」です。個々人の認知特性や脳情報の特徴をマッピングすることで、個人や集団のパフォーマンスを向上させるなど、パフォーマンスと「ウェルビーイング」(well-being)の最適解を導くことを目指しています。
一般的には性格や脳、非認知能力、それこそ、企業経営者が備えるべきリーダーシップなどの部分に目が行きがちですが、私たちの研究ではこれらに加え、「注意(アテンション)の個人差」にも着目しています。みなが同じ空間で会話をしている場合、それぞれの視野は決まっているのですが、その会話中、どこにどのくらい注意を払うかによって習得できる情報量は全然違ってきます。
それは物理的に見えているということだけでなく、いろいろな意識的に向けられた注意がどのように分配されているかによって、まったく違ってくるのです。
結果として同じ時間・場所にいて、同じ会話をしていても獲得する情報が多い人と少ない人、学びが多い人と少ない人が出てきます。そういった知覚特性や脳特徴も含めて、多角的な情報を使いながら個人の特性をマップしていきます。
その上で、「この人がこういうパフォーマンスをあげたいなら、こういう方法が良いですよ」という提案をエビデンス(証拠)ベースで出来るようになることを目指しています。
例えば、経営者が業績を向上させるため、社員に新しいことを学んでほしいと考えたとします。本人が学びたいと思っているのなら問題はありませんが、学びたくないと思っていた時にどうするのか……。こういうことは企業をはじめ、社会では往々にして発生する問題です。
そうした“個人の意思”と”集団の意思”との最適解はどこにあるのかと問われた時、「ウェルビーイング」という概念に行き着くわけです。ただし、個人と集団のウェルビーイングは必ずしも一致しません。特に同じ時間スケールで一致することは難しい。
ところが、ある程度の時間幅の中でそれぞれのウェルビーイングが成立するためには、どういうふうに重ね合わせていけばいいか。そこには「互酬性の規範」が必要になってくるのではないかと思います。互酬性の規範は、一方が何かを与えた際に、他方が何らかの形でそれに応えるべきだという期待を指します。
この規範は、協力、信頼、および社会的結束を促進するのに役立つ基本的な社会的原則と言われています。つまり、自分のウェルビーイングだけを考えるのではなく、双方が双方のウェルビーイングのために機能する、という信頼があることが前提になるわけです。
人との関わりを自分の資産として捉える考え方は昨今、「社会関係資本(ソーシャルキャピタル)」という言い方がされますが、この互酬性の規範は、社会関係資本の重要な要素です。そういった目に見えない非財務的な価値を捉えながら、それらをどのように経営に取り込み、個人の能力を向上させていくかということも、私の現在の研究領域です。