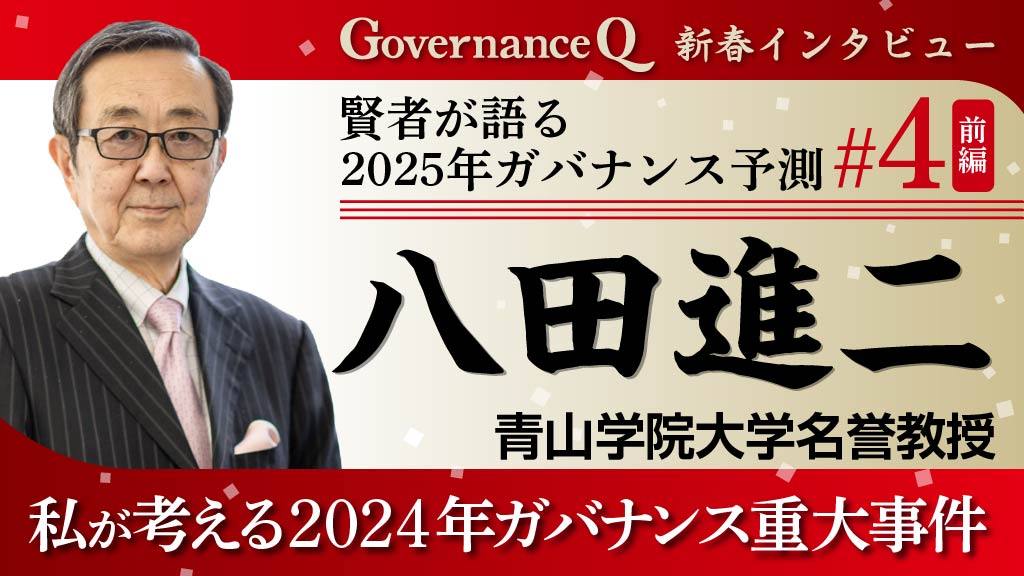新春インタビュー晦日の第4弾は、本誌「Governance Q」でもお馴染みの八田進二・青山学院大学名誉教授。2024年も新聞、テレビなどで数多のガバナンス問題を厳しく論じる一方、不正対策のエキスパートが参集する日本公認不正検査士協会(ACFE JAPAN)でも評議員会会長を務める八田教授が選ぶ「2024年のガバナンス重大事件」とは――。新春インタビュー前編。
2024年もガバナンスをめぐる問題が多く企業、各種組織を問わず発生し、実際、私もさまざまなメディアから取材を受けることになった。同年について言うと、具体的には次の5つの大きな事例が挙げられるだろう。
① 自民党の裏金、政治とカネの問題
② 損保ジャパンの問題(保険大手カルテル、ビッグモーター事件)
③ トヨタグループ認証不正問題
④ 小林製薬「紅麹」問題
⑤ 東京女子医科大学理事長の「一強独裁」問題
これらの諸問題をもとに、まずは24年のガバナンスの現在地を考えてみたい。
永田町のガバナンス不全を示した「自民党裏金問題」
最初の①の自民党の裏金問題については、発生から1年以上が経つ現在もなお、終わりが見えていない。これは自民党ならびに日本の政治家の政治資金の管理をめぐってガバナンスが効いていないことを示している。
会計的な視点で見れば、公的な組織における資金の流れは収入であれ支出であれ、入出金すべての取引について総額計上し開示することで、初めて説明責任が果たされたといえるのである。
ところが、政治資金規正法では収入についてはザルのまま、支出についても帳尻が合うように記載すれば良しとするという発想が抜けていない。ゆえに政治資金の議論も、「企業団体献金を禁じるか否か」といった小手先の議論に終始している。
会計的発想のない議論を見ている限り、当分、政治資金の問題はくすぶり続けるのではないだろうか。
持ち株会社のガバナンスが指弾された「損保ジャパン問題」
②の損保ジャパンの問題では、2023年から尾を引いている中古車販売大手、旧ビッグモーター(現在は新会社WECARSと存続会社BALMに分割)の保険不正の問題と、大手損保会社のカルテルの2つが重なった。現場のコンプライアンス意識の欠如は度し難いものがあるが、同様に問われるべきは持ち株会社の責任である。
損保ジャパンをはじめ事業子会社群を抱えるSOMPOホールディング(HD)は、自らは事業を行わず、SOMPOHD株価の維持とグループ各社の戦略策定や指導といった経営管理を担っている。
SOMPOHD自体は500名ほどの従業員を抱えており、その多くは事業会社出身の社員で構成されているであろうが、持ち株会社は基本的に現場を抱えてはいない。一方でグループ各社の人事権を握っており、当然ながら、子会社の事業に対する責任を有している。
ところが、ビッグモーター問題発生当初はトカゲのしっぽ切りの如く、子会社や現場の処分だけで済まそうとしたものの、損保ジャパンの社長だけでなく、最終的には24年3月、SOMPOHDの桜田謙悟会長兼グループCEO(最高経営責任者)がその職を退かざるを得なくなった(桜田氏本人は「結果責任」を強調し、引責辞任を否定する格好だったが……)。
グループトップの辞任は当然の対応ではあるが、持ち株会社を頂点とするホールディングカンパニーのグループガバナンスとは何かを考えさせられる事例であった。