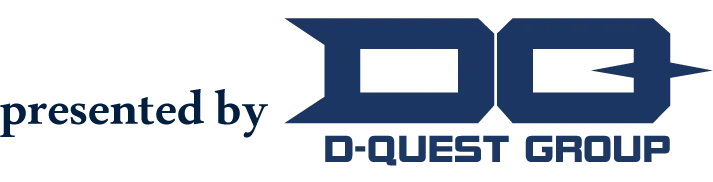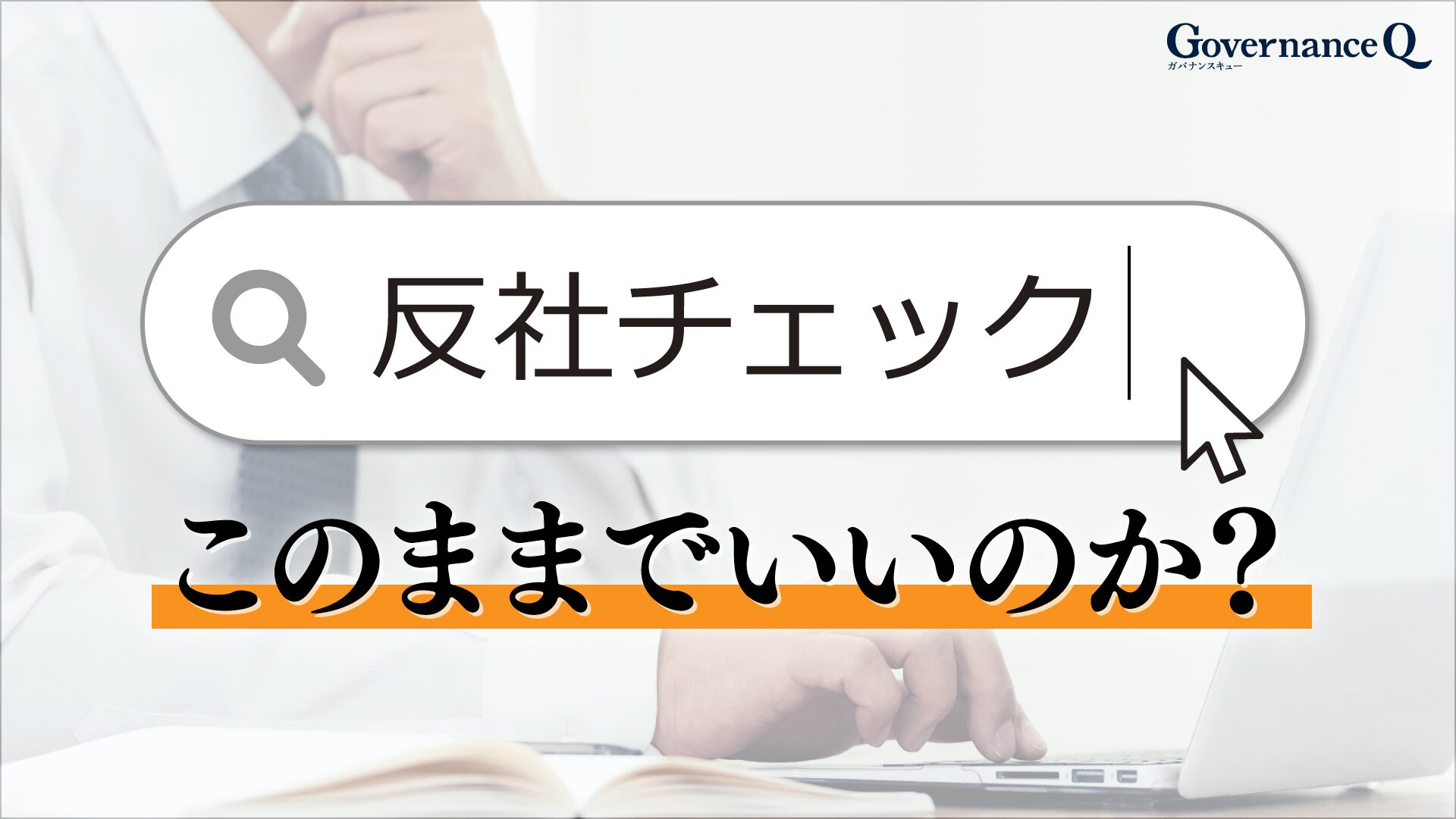コンプライアンスチェック、実は根拠がない?
「契約書に暴排条項を入れている」から反社チェックは要らない?
反社チェックに代表されるコンプライアンスチェック。ところが、「なぜ実施しなければならないのか?」と問われると、意外にも、答えに困ってしまうものです。
「新規取引先や採用候補者のリスクをあらかじめ除去しておきたいから」という回答は模範的としても、「社内の業務フロー上、そうなっているから」「同業他社も実施しているから」「IPO(新規株主上場)の際、主幹事証券会社などに指摘を受けたから」といった受け身的な動機というケースも少なくありません。
考え方はともかく、コンプライアンスチェックを実施している企業がある一方、実施していない企業もあります。
「(実施しなくても)罰則がないから」
「別に法律・法令で義務化されていないから」
「契約書段階で暴排条項を入れているから」……
コンプライアンスチェックを実施していない企業にその理由を聞くと、このような反応が返ってきます。ただ、これまた意外なことに、こうした考え方が間違っているかというと、必ずしもそうとは言い切れない実態があるのです。
反社チェックの“根拠”とされる「暴排条例」の中身
コンプライアンスチェック、特に反社チェックの“根拠”として、サービス提供会社がよく取り上げるものに以下のような関連法規等があります。
1. 企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針(政府指針、2007年)
2. 暴力団排除条例(全都道府県が施行、10~11年)
3. 会社法(取締役の善管注意義務)
4. 東京証券取引所・上場審査等に関するガイドライン
ところが、これらは企業等にコンプライアンスチェックの実施を義務化・明文化したものではありません。端的に言うと、反社チェックサービス提供会社が「チェックしていないと、関連法規に引っ掛かりますよ」式のホラーストーリー(恐怖訴求)を展開する材料になっている側面もあるのです。
とはいえ、その中でも3の暴排条例がもっともコンプライアンスチェックの根拠に近いものとされています。それでも、内容は次のようなものに過ぎないのです。東京都の暴排条例(概要)を例にとると、《事業者の契約時における措置》として
〈契約時に相手方が暴力団でないことを確認〉
〈契約時に、相手方が暴力団関係者と判明した場合、催告なく契約を解除できる旨の特約を定めるよう努めること〉
と記載があるだけで、しかも、それは「都民等の役割(努力義務)」という位置づけでしかありません。
【参照】東京都暴排条例の概要ページ(警視庁のサイトに移動します)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/tsuiho/haijo_seitei/haijo_jourei.files/gaiyo.pdf
そういう意味では、コンプライアンスチェックを「法令の義務ではないから実施しない」という考え方は、あながち根拠のないものではないのです。
トクリュウ、半グレ…「準暴力団」の暗躍
一方、以前の記事でもお伝えしたとおり、暴力団の構成員・準構成員は年々減少し、1991年に合計で9万人超だったのが、24年時点で同2万人を割り込む状況になっています。これは暴力団組織そのものが衰退していることを如実に示すデータと言えそうです。
その反面、暴力団に協力する「共生者」、不良集団「半グレ」や「匿名・流動型犯罪グループ(トクリュウ)」といった特定の組織に明示的に属さない一群が現れ、暗躍しているのは周知のとおりです。
必ずしも暴力団系とは言えない、この種の反社会的勢力(警察は半グレ、トクリュウ両者を「準暴力団」と定義)は、当局もその実態を把握しきれていないのが現状と言います。当局ですらそうである以上、対象者・対象法人の“前歴”を追うという従来型の反社チェックで、そうした準暴力団を完全に排除することは、残念ながら、不可能と言わざるを得ません。
当局も把握できない、過去の報道記事をたどっても反社に該当しない……。こうなると、「コンプライアンスチェックなんて、実施しても意味がない」となってしまいそうですが、果たして、そうでしょうか。
反社のマフィア化で高まる接触リスク
むしろ、反社勢力がマフィア化しているため、役員・職員個人のみならず、企業自体も知らず知らずのうちに、反社と何らかの関係を持ってしまうリスクは減少するどころか、高まっているというのが現状です。
先にコンプライアンスチェックを実施しない理由として、「契約書段階で暴排条項を入れているから」というものがありました。これは暴排条例上の努力義務となっており、確かに必要かつ効果的な反社対策ではあります。
しかし、意図せざる形、予測不可能な形とはいえ、実際に反社、あるいはコンプライアンス上不適切な相手との関係が浮上してそのことが発覚した場合、企業側が「そんな相手とは知らなかった。暴排条項を入れていたので、契約を打ち切った。ウチは被害者」というだけで済むものでしょうか。
会社のコンプライアンス体制で制裁を判断する米国

現在のコンプライアンスをめぐる社会的な共通認識を考えると、暴排条項による解約は”当たり前の措置”でしかありません。そのため、「なぜコンプライアンス上問題のある相手と見抜けなかったのか」といった批判、場合によっては「実際には水面下で交際があるのではないか」といった社会的な疑念や指弾を受ける危険性は強まっていると言えるのです。故意の交際は言語道断ですが、過失的な接触であっても、社会から厳しい眼差しが向けられることは避けられません。
「コンプライアンスプログラム」の実効性
ところで、近年、日本企業においても「コンプライアンスプログラム」を策定する動きが強まっています。主に従業員にコンプライアンスを遵守させるためのガイドラインや教育・研修制度、罰則規定などを含む一連の制度・運営設計のことです。
さらに米国ではコンプライアンスプログラムについて、司法当局がその有効性を評価・反映するという流れが進展しています。企業が不祥事を発生させた場合、米司法省(DOJ)は、その企業におけるプログラムの設計、運用、機能などを評価したうえで、制裁の内容を判断する方針としているのです。
言い換えれば、適切なプログラムが実効性をもって日常的に機能していれば、仮に企業で不正事案が起きたとしても、DOJは訴追を見送ったり、制裁金を減額したりするといった判断を下すことがあり得るというわけです。もちろん、プログラムの未設定は言うに及ばず、その有効性に疑いが持たれる企業が同種の不祥事を引き起こした場合には、厳しい対応が待っているということになります。
もっとも、日本ではこうした量刑判断の制度が明示的に採用されているわけではありません。しかし、企業が抱えるリスクは日増しに予見困難になっています。リスクを根絶できない以上、それを検知・回避しようという予防的な制度が誠実に設計・運用されていれば、不祥事を発生させたとしても、その分、当局、そして世論から “情状酌量”を 引き出すことができるでしょう。
つまり、コンプライアンスチェックを行っていない企業において不適切な者との関係が発覚するのと、コンプライアンスチェックを行っている企業において同様の事案が発覚するのでは、質的にまったく異るわけです。しかも、世界的なコンプライアンスをめぐる動向を考えれば、両者の違いは今後、厳しく区別される流れにあります。
法令で義務化されていないから――。コンプライアンスにおいて、このような考え方が通用する時代ではなくなりつつあることだけは間違いありません。こうした視点も含めて、改めてコンプライアンスチェックの在り様を検討されることをお勧めします。
「反社チェック」の現状をより詳しく知るために
弊社ディー・クエストでは2025年11月、コンプライアンスチェック担当者、特に新任の方を対象にウェビナーを開催、現在、アーカイブ配信を行っております。
無料でご視聴いただけますので、コンプライアンスチェックについて詳しく知りたい方は、以下のバナーより登録のうえ、ぜひともご覧ください。
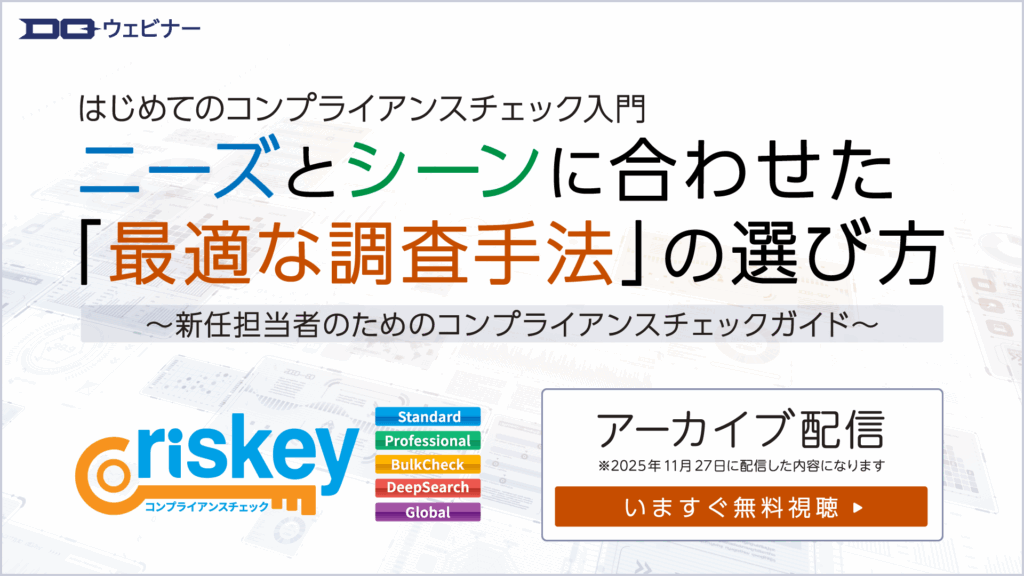
ニーズとシーンに合わせた「最適な調査手法」の選び方