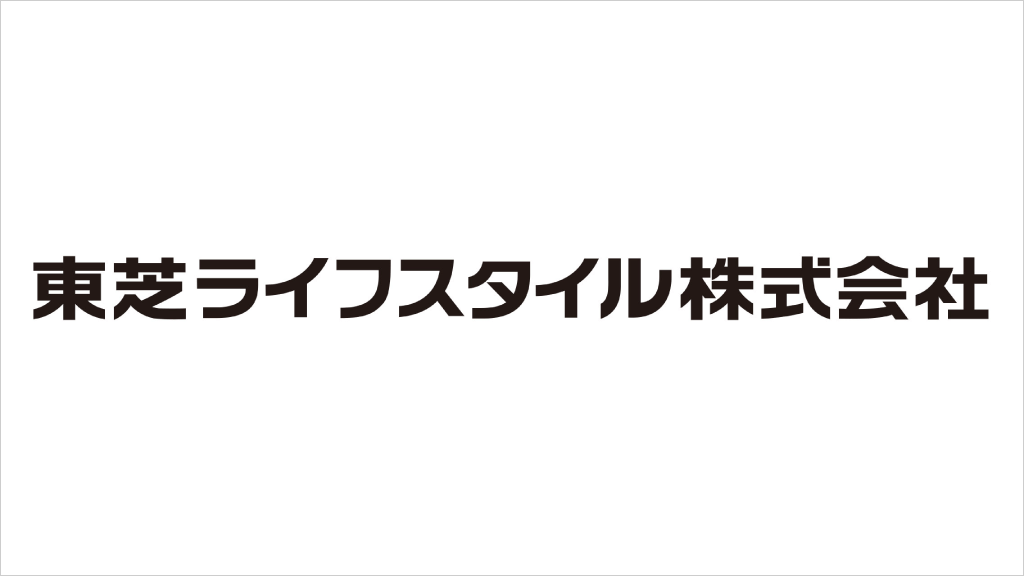「お客さまの体験価値を高めるには、社員のエンゲージメントが大事」
これは、東芝ブランドで主に白物家電の製造・販売を手掛ける東芝ライフスタイル(川崎市)の経営メッセージだ。お客さまそれぞれにとってのステキな暮らしを届けるためには、社員が明るく元気に活力に溢れ、経営目標の達成に向けて前向きに取り組んでいることが大前提である。だからこそ、阻害要因は芽が小さいうちに摘み取りたい。内部通報とハラスメント対応はその最たるものだと同社は位置づける。
2024年DQヘルプライン導入
きっかけは「より社員が相談しやすくするには何ができるのか?」という疑問
きっかけは「より社員が相談しやすくするには何ができるのか?」という疑問
企業理念は「人々に素敵なくらしを」。ブランドステートメントは「タイセツを、カタチに。」――。グループ社員数1万2000人を擁するグローバル企業の東芝ライフスタイルは、東芝が家電事業を分社化した東芝家電製造株式会社を経て2014年に設立された。16年には中国の世界的家電メーカー、美的集団(Midea)グループの一員となった。
東芝ライフスタイルのグループ会社には、炊飯器等の製造を担う東芝ホームテクノ株式会社(新潟・加茂市)、電池の製造を担う東芝電池株式会社(群馬・安中市)、販売・修理の東芝コンシューママーケティング株式会社、BtoB事業の東芝エルイーソリューション株式会社、音響機器などの輸入販売を行う東芝エルイートレーディング株式会社などの国内に加え、中国、タイ、ベトナムなど海外でもグローバルに展開。その数は15社に上る。

「内部通報制度は会社発足時からありましたが、担当している内部監査の観点から23年頃から社内における内部通報制度をより強化していく必要性を感じていました」と語るのは、内部通報制度を管轄する法務部・監査担当グループ長の野々山一郎氏だ。
当時、東芝ライフスタイルは内部通報制度として、主に不正に関する通報を受け付ける「リスク相談ホットライン」(法務部が所管)と、ハラスメントについて相談できる「グループハラスメント相談メール」(人事総務部が所管)の2つの窓口を運用していた。ところが、2つの相談窓口にはそれぞれに懸念点があったという。
まず、リスク相談ホットライン。メール、郵便、社内便、電話と複数の経路で受け付け、匿名での通報も可能にしていたが、ホットラインもハラスメント相談メールも、受付件数は少ないものであった。これを受け、法務部と人事総務部では、様々な経営革新に取り組んでいるときこそ、阻害要因をしっかりと取り除き、お客さまに向かってリソースを集中させる必要があるが、果たして、潜在的な阻害要因も含めて、対処できているのだろうか、と考え始めた。
「通報件数が多いから良い、少ないから悪いとは一概には言えません。ただ、より社員の声を聴きやすくするアプローチはないかと考えました」と野々山氏は当時を振り返る。
ハラスメント相談についてはメールのみの受け付けであり、個人が特定できてしまう懸念もあり、時代性や世相も踏まえた、対応を検討し始めた。そのような中で、中立的な社外窓口であること、業務時間外でも相談しやすい受付体制の有効性を感じた。
さらに、通報窓口に携わるスタッフは、法務部では野々山氏の他に一人、ハラスメント相談は人事総務部 人事部長の松浦大海氏がグループ全体を見ながら、規模の大きいグループ会社には必要に応じて松浦氏が担当者を割り振るという方法を取っていた。当の松浦氏が話す。
「少ない人数で対応していましたが、中立性・匿名性に加えて通報者や相談者の心理的負担を考えると、専門業者が運営する外部窓口を新たに設置することも必要ではないか、と考えました」
そこで選定条件として挙げたのが、①電話およびメールで対応が可能、②ひとつの窓口で内部通報もハラスメント相談も行えるワンストップサービス、③親会社が中国企業であることから中国語が母国語の社員も安心して相談可能――の大きく3つ。そして、それらの条件を満たしているということから、2024年にディー・クエストが提供する外部システム「DQヘルプライン」の導入を開始した。
導入から約1年が経過した現在、東芝ライフスタイルの内部通報をめぐる状況はどうなっているのか。
「DQヘルプライン経由での通報・相談は導入前と比べると年間2件程度増えました。ただし、DQヘルプライン導入によって件数が増えたかと言うと、まだ、“有意なデータとは言えない”と思っています。また、DQヘルプライン経由で通報も相談も、電話経由がないというのが意外でした」(野々山氏)
「確かに、2023年に民間企業が行った《電話業務に関する実態調査》では、20~30代の7割以上が〈電話業務が苦手〉という調査結果が出ている。その背景にはSNSやチャットといったメッセージ機能が普及したことが考えられる」と、ハラスメント相談窓口を管掌する松浦氏が語る。
「一般的なお客さまセンターやコールセンターなど、電話対応のみの場合、今はそのこと自体がクレームの対象になると聞きます。他方で、ハラスメント相談などは込み入った内容になることもあるので、電話でないと詳細が掴みきれないケースも出てきます。そういった意味で、現時点では電話での通報・相談はありませんが、選択肢が複数ある方が担当者も利用者も安心できると考えています」