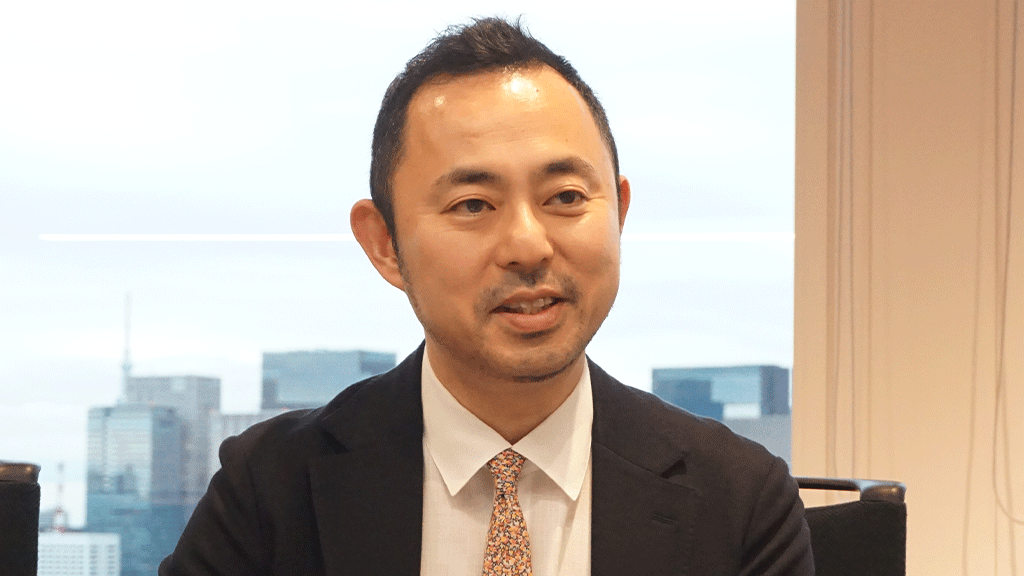平時からの「データガバナンス」の重要性
上場企業を中心に重大な問題事象が起きると、第三者委員会や特別調査委員会など(以下、「調査委員会」と総称します。)を組成し外部の調査委員の目を通して真相究明を行い、再発防止策を策定するという流れが、不祥事対応のスタンダードになってきています。実際、私自身、これまで調査委員会の委員長・委員を多数経験してきました。
そのような経験から、企業のみならず、一般にも広く認識していただきたいことは、「調査委員会は強制力を持っていない」という調査委員会の大前提についてです。
調査委員会を立ち上げることになった企業・組織は、非常に重大かつ深刻な局面にあって、徹底した調査が行われ、その結果が受け入れられるのか、それとも受け入れられずに事態がさらに悪化してしまうのかといった、大きな岐路に立たされています。外部において調査を担う立場としては、調査を充実させて信頼性のあるものにしなければいけない。でも、強制力を持った調査ではない――。ここにジレンマがあります。
この強制力のない真相究明に当たって前提条件となるのが、「平時のデータガバナンス」と、「調査委員会調査に対する経営トップの信頼と覚悟」の2点です。両者の有無によって調査のあり方は大きく変わることになります。
まず、データガバナンスについて。失敗例から説明しますと、例えば企業で何らかの不正・不祥事案が起きたとします。その際、社内のどこにどのようなデータがあるか、誰と誰が何を知っていて、どのようなやり取りをしていたかを正確に把握しなければなりません。
そのためのメールを含む関係資料をデジタル・フォレンジックの手法等を駆使して調査するわけですが、これには相当な時間とコストがかかります。誰を対象にどの期間についてデータを集めるか。収集したデータをどういう発想のもとに抽出して分析してレビューするのか。デジタル・フォレンジック調査を実施している間も、いろいろなキーパーソンからヒアリングし、デジタル以外の資料も分析して、全体像を見通しながら調査を進めていきます。
その後、デジタル・フォレンジック調査の結果が出て、その結果をもとに再度ヒアリングを行うと、当初の調査結果とは違う話が出てきたり、より重要な情報が出てきたりすることがあります。そうなると、当初の計画とは異なって調査範囲が膨らんだり、調査期間を延長せざるを得なくなったりするなど、予期しないさまざまな問題に直面することになります。
こういった想定変更が相次ぐと、調査費用も膨らんでいき、調査の予定期間等を開示している場合には変更も開示を余儀なくされ、企業価値毀損が継続・拡大してしまいます。
だから、企業にとっては平時からのデータガバナンスが重要なのです。日頃からデータやメールなど、社内コミュニケーションの管理・整理がなされていて、問題が起きたときにそれらのデータが不足なく調査の対象に挙げられるようになっているか否か。
こうした態勢が平時から整備されていれば、社内でのリスク管理や内部統制が機能していることになりますし、不正の事前予防や早期発見にもつながります。仮に不祥事に発展しても、より的確かつスピーディに対応できる。しかし実際には、データガバナンスが機能していないため、第三者による調査の段階でも困難を伴うケースが多いのも実情です。