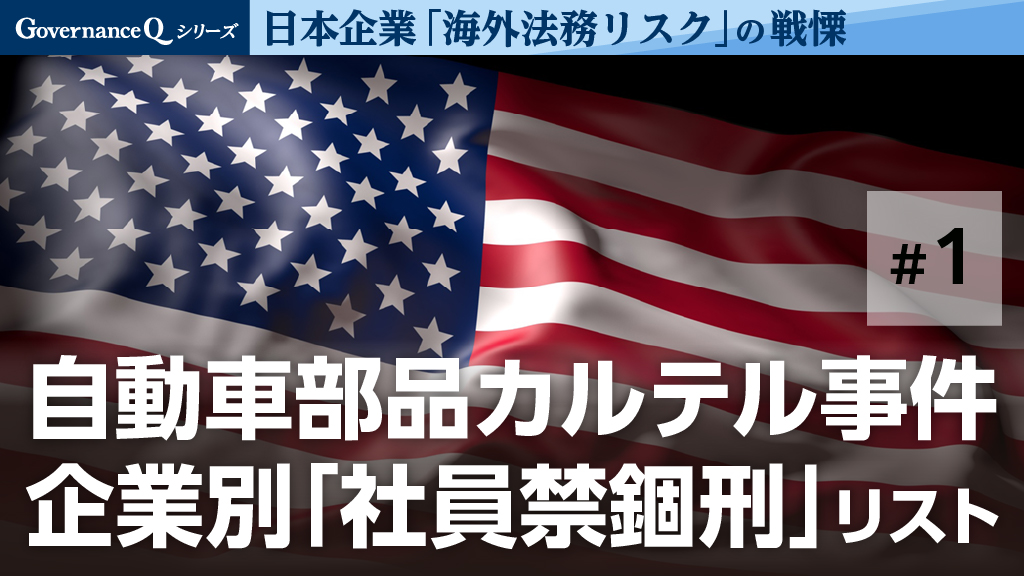グローバル化の進展に伴い、日本企業が直面する国際法務リスクが近年、一段と高まっている。米国では2010年代に反トラスト法(独占禁止法)違反などで多数の日本企業、日本人ビジネスマンが摘発され、多額の罰金や禁錮刑を科されたことが記憶に新しい。
企業も個人も、国内でのコンプライアンス(法令・社会規範の順守)対応だけでは不十分だ。海外の法規制や法務リスクにも視野を広げた「グローバルコンプライアンス」を意識して身を律しなければ、過酷な結末に直面する恐れがある。
本シリーズでは、米国や欧州諸国といった先進国のみならず、中国など新興国における法務リスクについて、日本企業および日本人ビジネスマンの立場から概説する。
猛威を振るった反トラスト法
2010年2月、日米欧などの競争当局が自動車部品メーカーに一斉に立ち入り検査を実施した。国際的な「自動車部品カルテル事件」の始まりを告げる号砲となった。
日本メーカーを中心に多数の企業が摘発の対象となったが、特に苛烈な取り締まりを行ったのが米司法省だった。
2011年9月、古河電気工業が主要部品であるワイヤーハーネス(自動車用組電線)をめぐるカルテルで有罪を認め、2億ドルの罰金を支払うことに同意。米司法省は自動車部品カルテル事件での「初の摘発事案」と誇った。
最終的に、古河電工を含む46社が米司法省に摘発され、45社が司法取引に応じて罰金を支払った。このうちほぼ9割を日本企業が占めた。罰金総額は29億ドル超に及んだ。
最大の罰金を支払ったのは矢崎総業で4億7000万ドル(2012年1月)。当時の為替レート(1ドル=約77円)換算で約360億円。現在、同じ額の罰金を科されたと仮定すると、円安が進んでいるため実に約700億円にもなる。
企業は巨額罰金を納めても、本業に邁進して利益を出せば埋め合わせはまだ可能だ。しかし個人の場合、数字では表せない過酷な状況に追い込まれる。
自動車部品カルテル事件では米司法省に計66人が摘発され、うち32人が有罪答弁に応じて実刑を科され、米連邦刑務所で服役した。刑期は1~2年だ。
米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手の元通訳、水原一平被告が今年6月、米連邦地裁で銀行詐欺などの罪を認めた。その有罪答弁が斟酌され、処罰は大幅に軽減される公算が大きいものの、5年前後の禁錮刑は免れないとみられている。
詐欺や反トラスト法違反はホワイトカラー犯罪と呼ばれるが、司法取引に応じてもなお一定期間、米刑務所行きになるのが一般的なのだ。
次ページで企業別の処分・制裁リストを公開する。