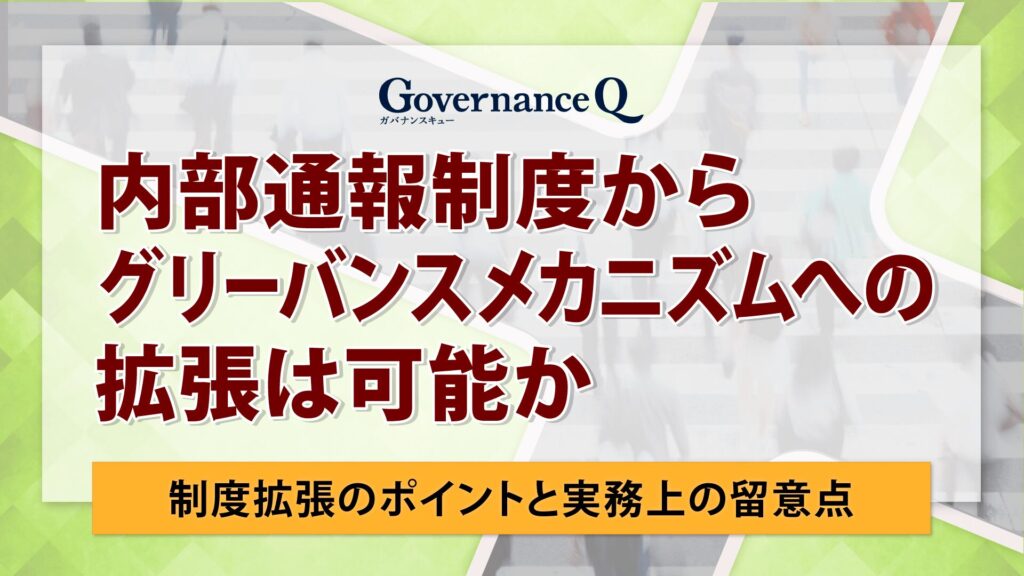株式会社ディー・クエスト 取締役(公認不正検査士) 福山 隆秋
「ビジネスと人権」への対応が求められる中、グリーバンスメカニズム(苦情処理メカニズム)の導入は日本企業にとって悩ましい問題です。そうした中で、既存の内部通報制度を苦情処理メカニズムに機能拡張しようという動きも広がっています。今回は、国内外の内部通報体制の構築・運用コンサルティングに長年携わってきた弊社ディー・クエスト取締役の福山隆秋が、その可能性と課題をお伝えします。
はじめに:ウェビナーのご質問から
2025年9月25日、「人権デューデリジェンスと内部通報制度の交差点 ──企業が直面するリスクと対応策」と題したウェビナー (株式会社Drop様との共催)を担当しました。当日は多くの企業実務担当者の方々にご参加いただき、内部通報制度とグリーバンスメカニズム(苦情処理メカニズム)について非常に実践的な質問が多数寄せられました。
*現在、無料アーカイブ配信中です。下の記事から視聴お申し込みください。
特に「既存の内部通報制度をグリーバンスメカニズムにどう応用するのか」「その際のリスクや注意点は何か」という点への関心が際立っていました。しかし、限られた時間内ですべてに十分にお答えすることができなかったため、本稿では、ウェビナーの論点を改めて整理し、寄せられたご質問について解説させていただきます。
ご承知の通り、国際的な要請や社会の変化を背景に、グリーバンスメカニズム(以下GM)を導入しないことのリスクは年々高まっています。ビジネスと人権に関する国連指導原則(UNGP)やESG・サステナビリティ関連の規制により、企業にはサプライチェーン全体での人権リスク対応が強く求められています。また、消費者やステークホルダーの視線も厳しくなり、人権侵害が顕在化すれば、ブランド価値や取引継続に深刻な影響を及ぼすおそれがあります。
こうしたなかで理想を言えば、内部通報制度とGMはそれぞれ制度の趣旨・目的が異なるため、体系も体制も別建てで設計・運用できるに越したことはありません。なぜなら、その方が“声を上げる側(従業員、外部ステークホルダーやライツホルダー等)”も、“受ける側(企業・組織)”も、それぞれの制度の趣旨に応じた適格な対応や救済を受けやすくなるからです。
しかし、多くの日本企業においてはこうした理想的なGMの体制整備に投じられる人員・リソースに限りがあるのも実情でしょう。一方、従前の内部通報制度とGMには「声を上げた人に不利益がないようにする」「一定の事実調査やフィードバックが行われる」などの機能的な類似点も存在します。
こうした背景からも、既存の内部通報制度を拡張し、GMとして機能させることは現実的な対応策であると同時に、リスク管理と信頼確保の両面で重要な経営課題といえます。実際、GMの運用部署が内部通報制度の担当部署に割り振られるケースが多くなっています(その是非についてもご担当の方々からお伺いしたことがありますが、こちらではいったん置いておきます)。
ウェビナーで類似の質問が相次いだのも、こうした背景が反映されていると考えられ、各企業ともに種々の制約がある中で試行錯誤し模索段階の現場が多い、ということだと推察します。
本稿では、両制度の共通点・相違点を踏まえつつ、「なぜ内部通報制度をGMにそのまま転用できないのか=なぜ拡張せざるを得ない場面が多いのか」「拡張時に現場で気をつけるべきことは何か」について、実務視点から整理し、具体的な制度設計・運用拡張を解説します。
内部通報制度とグリーバンスメカニズムの違い
両制度は、組織内外の「声」に応える仕組みという点では共通していますが、目的と救済対象が根本的に異なります。
内部通報制度の目的
企業内で発生する不正・法令違反などの早期発見と是正を目的とするものです。主な利用対象は自社(自グループ)の従業員・役員であり、通報内容も不正からの組織保護を念頭に置いたものとなっています。
グリーバンスメカニズムの目的
GMは、事業活動による人権侵害から幅広いステークホルダー(従業員だけでなく、地域住民や消費者、サプライヤーの従業員等)を救済することが目的です。たとえば、組織の活動が地域社会にもたらす差別や環境破壊、名誉毀損なども対象になります。
このように、内部通報制度は主に「組織の健全性維持」を、GMは「個人や第三者の権利救済」を目指す制度設計です。そのため、単なる制度の名称の違いだけではなく、救済対象・通報内容、そして実施体制に本質的な違いがあります。
制度拡張前に検討すべきポイント
では、GMの枠組みを既存の内部通報制度に盛り込むにはどうすればいいのでしょうか。まずは、下記のような実務的な論点を検証する必要があります。
規程上の位置づけと運用シミュレーション
GMを内部通報規程に組み込む場合、現状の規程で救済対象や受付フローをどう整理できるのかといったシミュレーションが重要です。「誰が」「どのような事案を」「どのチャネルで」申し立てできるのか。既存の規程が利用対象者を自社(グループ会社を含む)の従業員等に限定していたり、通報の対象となる内容を自社に関することに限っていたりしたら、ステークホルダー全体に門戸を広げる必要があります。
事務局・運用担当者の体制見直し
GMは外部の人権団体や専門家による知見・支援が求められる場合があります。制度拡張前に内部通報の担当者だけでGMの運用を担うのが適切かを必ず検討し、場合によっては外部委託や専門家の参加も検討する必要があります。そのため、どのプロセスで両制度の運用が分岐するのかもあらかじめシミュレーションしておくべきです。
調査と対応のプロセス設計
内部通報では法令違反や不正行為の事実確認を主眼としますが、GMでは事実認定のみならず解決や対話による納得形成も重視されます。従来通りの調査フローで十分かどうか、納得できない場合の再申し立てや外部機関との連携も念頭に置くべきです。
受付窓口・周知文面の拡張性
受付窓口の案内が「従業員向け」になっている場合は、外部ステークホルダー向けに新規に別途案内を作成「します。周知・告知の文面も「どなたでも利用できる」ことを明記する必要があります。また、GMの実効性を高めるためにも周知・告知の文面を多言語対応することも検討します。
国連「ビジネスと人権指導原則」が求める8つの要件
GMには国際的な要件が定められています。国連のビジネスと人権に関する指導原則(UNGP)が示す「有効なグリーバンスメカニズムの8つの要件」は、制度運用のチェックリストとして不可欠です。
| 正当性 | 公正かつ信頼される運営体制 |
|---|---|
| 利用可能性 | 全ステークホルダーに認知・利用しやすい設計 |
| 予測可能性 | 手続きの所要時間など具体的な見通しの提示 |
| 公平性 | 十分な情報と平等な取り扱い5 透明性 経過・結果の説明、制度の情報公開 |
| 権利適合性 | 国際人権基準に適合した救済の提供 |
| 継続的学習源 | 運用状況から制度改良・再発防止への活用 |
| 対話重視 | ステークホルダーとの協議・対話による解決 |
この8要件は、単なる苦情受付ではなく、「人権を守るための合理的な制度設計」を要求するものです。たとえば、外部専門家へのアクセスや調停の機会を設けること、匿名性や報復防止策の充実、結果や対応方針の通知など、小さな配慮・工夫が実効性の違いを生みます。
内部通報制度にGMの機能を盛り込む場合、8要件のどの部分は既存の内部通報制度を活用できるのか、もしくはできないのかを確認しておく必要があります。
内部通報制度へのGM拡張:現実的なシナリオ
実務的には、既存の内部通報制度の機能(匿名性・公正性・透明性を担保したコミュニケーションとしての機能)を活用したGM導入には、次の二つの設計パターンがあります。
制度の二層化(内部通報×人権通報)
規程や受付窓口を整理し、一般的な不正・法令違反通報と人権侵害通報について適切なタイミングでフローを分岐できるようにします。人権事案は外部の専門家と連携できるようにし、通報者には両メカニズムを利用できる選択肢を提供することで利便性と信頼性を確保します。
チャネル柔軟化・拡張による段階的運用
通報窓口を多言語対応・匿名化(ウェブフォーム、電話、ポスト設置等)し、利用者の声が届きやすい設計にする。周知の方法も社内外ポスターやウェブ公開などを工夫する。これにより、自社従業員以外の声も届く受付体制が可能となります。
このシナリオは、あくまでも異なる制度を運用するという前提で、内部通報制度の機能面を活用することを主眼にします。
担当者が押さえるべき注意事項
GMの内部通報制度への拡張・統合にあたっては、以下の点も事前に確認することをお勧めします。
内部通報制度の担当者のみで運用する場合のリスク
専門性不足の懸念があれば、外部専門家と連携できるようにします。
既存調査対応との違い・限界
GMでは和解や対話型の解決(説明会、意見聴取会など)が求められる場合が多い。調査一辺倒の運用では不満が残る可能性もあるため、事案の性質ごとに最適な対応方法を検討します。
窓口・周知文言は拡張必須
受付窓口の告知・利用案内が従来通り「従業員限定」なら、対象ステークホルダーに利用可能である旨を明記し、問い合わせ方法も多様化する必要があります。
国連要件クリアの定期点検
8つの要件を自社制度が満たしているか、外部評価やセルフチェックを定期的に実施します。学習源としての制度運用、PDCAサイクルによる改善も不可欠です。
まとめ:両制度の本質を踏まえた上で現実的な拡張を
本来、内部通報制度とGMはその趣旨や対象も異なるため、制度設計も別建てにすることが「理想」だと考えます。しかし、企業や組織における人的リソースや業務の実態に鑑みると、内部通報制度をベースとしてうまく拡張し、GMとしての役割を担わせるということも考慮する必要があります。
ただし、「既存の窓口にGMを足せば良い」という安易な考え方では、社内外の信頼や実効性を棄損しかねません。上述した観点(規程設計・担当体制・プロセス設計・国際要件への適合)をクリアし、「意図を持った制度運用」を実現することが企業・組織の責務として重要です。
本稿の発端になったウェビナーで寄せられた現場の悩みの多くは「業務の現実と制度設計のギャップ」に端を発しています。制度拡張の具体的事例や、外部の運営ツールの活用、専門家参加のプロセス等、実務の知恵を積極的に取り入れながら、PDCAサイクルに取り入れていかれることをお勧めします。
企業のコンプライアンス強化、人権尊重経営への取り組みがますます重要性を増す中、グリーバンスメカニズムの導入や制度の進化についても多くの企業で検討が進められています。それぞれの現場に即した声の受け皿が整備されていくことで、持続可能な経営基盤の実現に近づくものと考えられます。